 サイトマップ
サイトマップ



 書評 自閉症当事者――4.『30 歳からの社会人デビュー』
書評 自閉症当事者――4.『30 歳からの社会人デビュー』


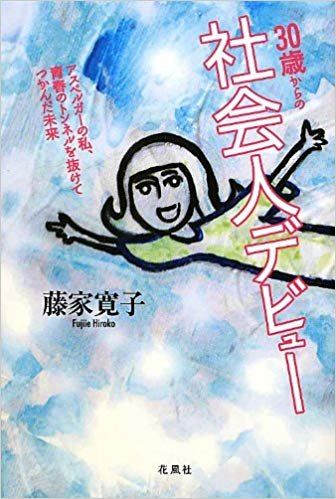
『30 歳からの社会人デビュー――アスペルガーの私、青春のトンネルを抜けてつかんだ未来』(花風社、2012/10/1 刊行)
藤家寛子(著)
四六判、286 ページ
![]()
今世紀に入ったあたりから、多くの自閉症当事者が伝記や手記を出版するようになりましたが、ここでとりあげる作品の著者であり、アスペルガー症候群と診断されている藤家寛子さんは、2004 年に最初の著書『他の誰かになりたかった』(花風社)を書いています。ちなみに、この本の副題は、「多重人格から目覚めた自閉の少女の手記」となっていますが、ドナ・ウィリアムズさんを筆頭に、別人格をかなり自覚的に利用していた〔いる〕自閉症者と比べると、著者の「多重人格」は、その間の記憶が大幅に消えているということなので、通常の多重人格性障害のものにむしろ近いという印象を受けます。その8年後の 2012 年に出版された本書(『30 歳からの社会人デビュー』)は、「決して人のせいにせず、障害のせいにもせず、できるようになりたいことにはストイックに取り組ん」できたことによって(190 ページ)さまざまな側面で成長を続けてきた著者が、いよいよ「大人の女性」として社会に出るまでの経過を記した非常に貴重な記録です。
一歩踏み込んだ主張をすることになる本レビューでは、なるべく著者の言葉をそのまま使うことで、正確な記述を期したいと思います。ただ、あまり詳しく書きすぎると、本書がかえって売れなくなってしまうおそれもないとは言えません。それでは当方の本意に反することになるので、やはり自分で読んでみないとわからないものだということを、ここに強調しておきたいと思います。
著者の特徴は、主として社会の側の受け入れ態勢を変えることに情熱を注いだらしき山岸さんや森口さんと違って、「現実を受け入れる強さを持つこと」と「誰のせいにもしないこと」(96-97 ページ)という姿勢を高らかに宣言していることです。「こちらから定型発達の方に歩み寄ることは、屈するということなのだろうか。/どうしてそう思えてしまうのか、私には不思議だ。/でも、確かにそういう考えを持つ人はいるらしい」(20 ページ)、「思い違いをしてはいけないのは、定型発達の人も日々、努力して生きている」(221 ページ)というわけです。さらには、「世間には、根強く修行否定派の皆さんがいらっしゃる。/医者の中にだって、頑張る必要がないと説く人が多い(191 ページ)」と、堂々と専門家の批判までしています。これは、経験に基づく真の自信のなせる業なのでしょう。そして、「私たちにも社会生活を送る権利がある。/しかし、日々の努力なくして権利を訴えることはフェアじゃないと思った」(22 ページ)として、次のように明言するのです。
人生を好転させるためには、自分から動いていかなくてはいけない。/自分から、社会に寄り添っていかなければいけないのだ。/そのためには、恨み言ばかりの生活から離れたほうがいい。/自分の人生に起こっていることは、社会のせいではない。/運に見放されていたり、どんなに努力しても報われなかったり。/だけど、そういうことは、ままあることだ。/誰かのせいにしたい気持ちは分からなくもないが、それでは幸せから遠ざかる。/大切なのは、現実と向き合うことだ。(217 ページ)
オポチュニティーの神の寓話は、まさにそのことを言っているわけですが、自分から積極的に向かって行かなければ、真の意味での幸福をつかむことはできないものなのです。著者はさらに続けます。
「できないことが当たり前」を受け入れてくれるほど、世の中は甘くない。/だから、そういう一部の人々は、結局のところ、自滅していくしかないのだろう」(10 ページ)。
「努力なく、障害に抱え込まれて生きていく人生に、多分出口はない。/ただ同じところをグルグルと、同じ景色を見ながら、ひたすらまわり続ける人生は、安全だけれども、何の喜びもなく、つまらない人生だろう。(223 ページ)
誤解を恐れずに言えば、“定型発達” をしている圧倒的多数の人たち[註1]が中心になって世の中を動かしているのは、進化の歴史を考えれば明らかであり、それを否定することは、数百万年にも及ぶ人類の歴史を否定するようなものです。もちろん、ヒューマニタリアニズムや人類愛と呼ばれるものが昔からあったのは事実ですが、現代ほどではなかったはずですし、そうした余裕のない国や文化圏が今なお存在するのもまちがいないところです。ついでに言えば、ハンス・アスペルガー先生は、まさにそうした全体主義国家の中で、絶滅させられる運命にあった自閉症児を含む障害児たちを、可能な限り救いたかったということなのでしょう。
ところで、著者は、もとは「頑張るという言葉が大嫌いな子どもだった」(12 ページ)そうです。「修行の意味に気付いたのは、大人になってから」のことで、しかも「発達障害だという診断をもらってから」のことだ(102 ページ)というのです。そうなると、やはり診断には意味があることになります。「頑張ることのできなかった子ども時代とがらりと変わり、今の私にとって頑張るというのは、生きることそのものだ。/頑張ることを厳密にいうなら、『現状に甘んじないで生きていくこと』を表している。〔中略〕頑張ることは、挑戦し続けるということでもある」(16 ページ)。そして、「いつかは親元を離れ、自立しなければいけないことは分かっていた」(19 ページ)そうです。
したがって、著者の考える「一本立ちは、親からの完全独立」(103 ページ)なのでした。それは、経済的に独立することと、心理的に独立することのふたつを兼ね備えたものでなければなりません。親からすれば、子どもが自立しない限り育児が完了したことにならないため、「障害児をもつ母親は、みんな心の奥深く死ぬに死ねない思いを抱いて、この世を去っていく」のではないか(久保、1999年、206 ページ)と思わざるをえませんが、逆に、人に迷惑をかけることなくそれができてさえいれば、多少の障害や症状が残っていても、大きな問題にはならないはずです。
ついでながら、子どもに対する親の、あるべき基本的姿勢にふれておくと、「虎はわが子を千尋の谷に突き落とす」と言われるように、子どもには自立に向けて厳しく接する必要があります。それが、親の愛情というものです。たとえば、振り込め詐欺にだまされる親たちは、自分の不安をなだめるために子どもを助けようとするから罠にかかるのであって、本来の親であれば、息子を装った犯人から電話を受け、わが子だと勘違いしてしまったとしても、不祥事の後始末を求めてくるわけですから、「自分で責任をとりなさい」と突き放さなければならないのです。それができないからこそだまされてしまうわけです。その結果、大きな損害が発生するだけではすまず、当の息子から、「俺がそんなことをしたと、どうして思ったのか。俺を信用していないのか」と責められることにもなってしまうのです。
話を戻すと、著者は、長年の精進の結果として、一種の悟りにも似た境地にすら到達しています。専門家は “気づき” ということを重視しますが、実際には、気づき自体に力はありません。それは現実に変化が起こった結果として意識にのぼるものなのであって、それが、次のような “発見” になってくるのです。これは、人に教わってわかることではなく、心の底から自然に出てくるものです。これがさらに進んだ境地が、一般に悟りと呼ばれるものなのでしょう。
「現状に満足し、しばし平凡な日常を味わうことも大事なこと」ではあるが、「人間はそれに甘んじてしまったら、成長しなくなる生き物である。/それは、定型発達の人も発達障害の人も同じ。/だから精進が必要なのだ。(23 ページ)
生きていれば、理不尽な出来事にぶつかることもある。/悔しい思いをしたり、残酷な仕打ちを受けたりするだろう。/障害を抱えていれば、なおさらそういう機会は多い。/しかし、考えようによっては、だからこそ、学ぶものも多いといえる。(218 ページ)
どんなに心地が悪くても、我慢しなければいけないときがある。/気持ちの悪さを押し殺して、仕事をしなければいけないこともある。/それが、社会のルールに従って生きていくということなのだと思う。(207 ページ)
先が決まっていない道のりを歩いていくのは、時に不安を感じることもある。/でも、それこそが生きる醍醐味であることに、最近、私は気付いた。(71 ページ)
乗り越えてきたものが多ければ多いほど、人生の厚みは増す。/それって、豊かなことではないだろうか。(218 ページ)
そして、現実に起こった変化について、著者は次のように具体的に語っています。
私はお酒は一切飲めなかった。/でも、食べられるものが増え、食欲が出てきた頃を境に、酎ハイくらいならお酒を飲めるようになったのだ。/今ではお祝い事があると必ずお酒を飲む。旅行に行ったときも飲む。(138 ページ)
人と関わりすぎると、姿をくらましたくなっていた私。/そのせいで壊れた関係がいくつかあった。/昔は人と関わることで生まれてくる感情を処理しきれなかった。〔中略〕そんな私が、普通に恋をしている。/周囲の人は、そのことに驚き、そして喜ぶ。(188 ページ)
以前なら、何かトラブルが発生すると、頭がいっぱいになって、すぐさま結論を出そうと必死になっていた。そうしなければ、具合が悪かった。/ひとつのことしか考えられず、一方向からしか物事を見れなかった。/今回のことだったら、すぐに店をやめる、としか思いつかなかっただろう。/人に意見を求めることもしなかったし、そういう手段があると思いつけなかった。/頭の回線がすぐパンクして、通信不能になっていた感じだった。
ところが今はどうだろう。/今回はまず、親や友達に相談をした。/仕事を続けるか、辞めるとしても転職を考えるか、どちらにしてももっと情報が必要だと感じた。/すぐさま答えを導き出さなくても、ゆっくり考えようと思うことができた。じっくり考えた方がいい結果が出ることは経験から学んでいた。/なんだかビックリだ。/今までなかった神経回路が生えたみたいだった。頭の中で考えた情報が、きちんと脳に伝達されている。/これまでだったら、何かを考えても、神経が、もつれた刺繍糸みたいになって、うまくつたわっていかなかったのに。/どうなっているんだろう。/でも、とにかく、いい傾向だ。(202-203 ページ)
〔仕事先から〕帰ったら、バタンキューすることもなく、ちゃんとお風呂に入った。/湯船の中で鼻歌を歌いながら、私はニヤニヤしていた。/これって、まるで「社会人」だ! ドラマに出てくる、「大人の女性」みたいだ!(121 ページ)
そうなると、自閉症は、少なくともかなりの程度まで回復可能であることになりますが、そればかりではありません。脳の機能異常とされているものも、現実には回復可能であることになるのです。このことは、発達障害者のみならず、器質性とされるそれ以外の障害を抱えている人たちの多くにとっても、大変な朗報のはずです[註2]。
かくして、自分を救った著者は、その経験を他者と分かち合うことを考えるようになります。
どんなにどん底からでも、這い上がりさえすれば、キラキラと輝く太陽の下で生活できることを伝える。/それが、私に与えられた新しい使命ではないかと考えるようになった。/私が回復したのは、それを多くの人に伝えるためかもしれないのだ。(152 ページ)
〔ドラグストアで働くようになって1ヵ月半が過ぎたころから〕これまですこぶる調子よくすすんでいた日々。それが、少しずつ狂い始めた。/まず、就寝前の薬がよく効かなくなった。入眠までに時間がかかり、夜中の三時過ぎに目が覚める。/寝ては醒めを繰り返すので、熟睡ができなくなった。この悪循環の影響は、仕事に差し支えた。/眠りの質が低下したせいで、頭がボーっとして、うまく集中できなくなった。そして、メニエールの発作にも似ためまいが、私を襲うようになった。(192 ページ)
著者は、「本当は、こんなによくなったことが不安でたまらなかった」(191 ページ)と書いていますが、人間は一般に、自分が望んでいることがいざ現実になると、それを素直に喜ばないものなのです。そして、その時に、その幸福に水を注すような工作を、いわゆる無意識のうちに行なうことになるのです。その時には、心身症的な症状をはじめ、さまざまな “異常” が起こります。ただしそれは、いずれ “ほとぼり” が冷めると消えるので、一過性のものにすぎません。そして、全体の経過を遠目で眺めると、いい方向にしか進んでいないことがわかるわけです。知らない間に、私の人生は、いい方向にばかり進むようになった。/あんなに不遇だった二十数年間が嘘のようだ。/一体何がよかったのだろう。/私はどうやって人生を立て直したのだろう。(213 ページ)
これは、グニラ・ガーランドさんが自著『ずっと「普通」になりたかった』(273 ページ)に書いているのとまったく同じ疑問ですが、別にふしぎなことではありません。一流のスポーツ選手などが語ることと根は同じなのですが、要するに、難しい課題や選択肢をいつも選んで進んで行けば、いわゆる舵取りの必要なく、自分が望んでいる方向へ自然に進むようになっているのです。それは、ネガティヴィズムから脱却して、真の意味で素直になるということでもあります。このあたりについては、経験的に知ることしかできないのですが、このことは、自閉症スペクトラム障害とは無関係に、人間であれば誰にでも当てはまる大原則と言えるでしょう。自閉症の本質がわかっていないのは、ひとつには、“正常” とされる人たちの心の動きがほとんど理解されていないためです。逆に言えば、自閉症の本質――正確に言うと、脳の病変や機能異常という側面ではなく、精神病理学的な角度から見た自閉症の本質――が明らかになれば、それにつれて、正常とは何かという、心理学や精神医学では実際に扱われることがまずない、人間にとってきわめて重要な疑問も並行して解決に向かうはずなのです[註3]。
本書は、自閉症の人たちと “定型発達” とされる人たちが、根本から異質なわけではないどころか、両者は実は地続きであることを教えてくれる、きわめて重要な資料と言えるでしょう。
[註1]小林秀雄さんの親友でもあった、昭和初期の詩人、中原中也が、軽蔑と畏敬の念の双方を込めて創案した言葉を借用すれば。「芸術派」に対する「生活派」。
[註2]かつてわが国の失語症研究を主導していた井村恒郎先生は、日中戦争中に内地へ送還された失語症傷病兵の症状が、自然治癒することに注目していました。それまでの定説とは相いれない所見が観察されたということです。国立下総療養所での 1941 年頃の経験です。「最初に感じたことはいろんな局在症状が治ってる。当たり前のことですがね。戦傷者は年齢の若い頭部外傷者でしょう。〔中略〕戦場で負傷してそれから野戦病院とか兵站病院とかいろんな病院をめぐって、病床日誌と共に内地まで戻ってくる。だから一年から二年もかかるんです。病床日誌は野戦病院のときから始まってますが、〔中略〕内地でわれわれが診たときにはもうないんですね。〔中略〕クライストなんかの本を読んでみると、本に地図が描いてあってここは言語、ここは認識とかなんとか書いてありまして、そしてその前に学生の頃教わった観念として、神経細胞は再生しないという観念が頭にありますから、長く残っていると思ってましたでしょう。ところが診たらね、これはと思う場所に傷があるんだけれども症状がない。あれはずいぶん当てがはずれました」(井村、1983年、170-171ページ)。この問題については、たとえば、大阪大学医学系研究科の山下俊英らによる、マウスを使った実験的研究の報告(Ueno et al,, 2012)を参照してください。
[註3]この点については、千住淳『自閉症スペクトラムとは何か: ひとの「関わり」の謎に挑む』(ちくま新書)を参照してください。


