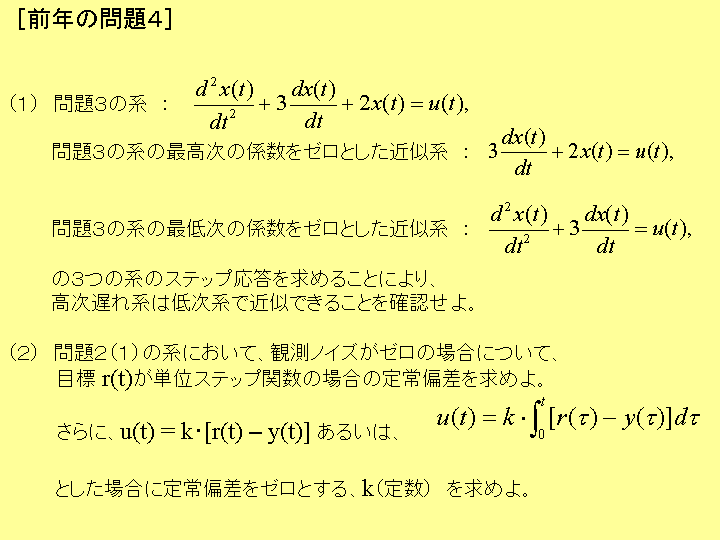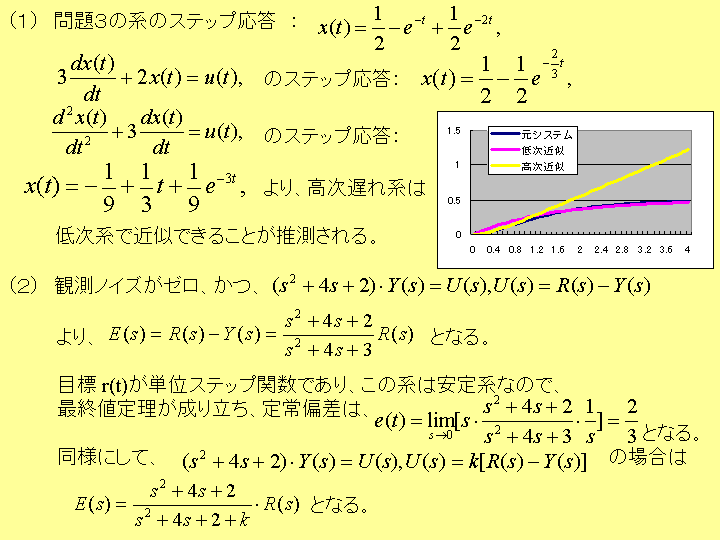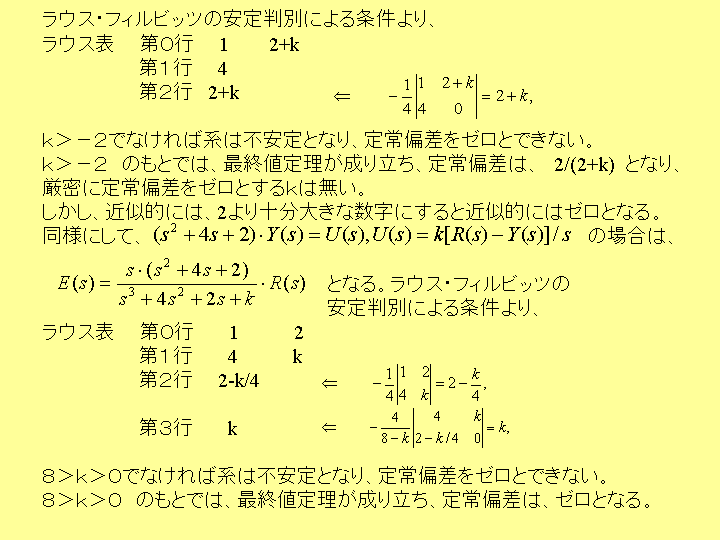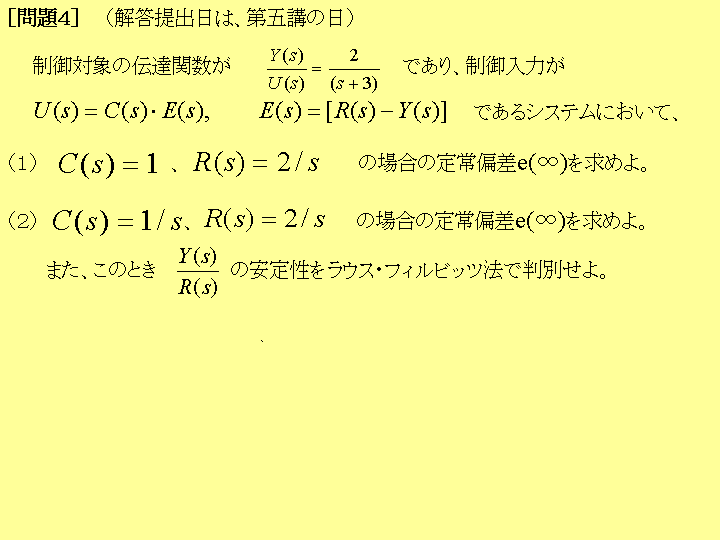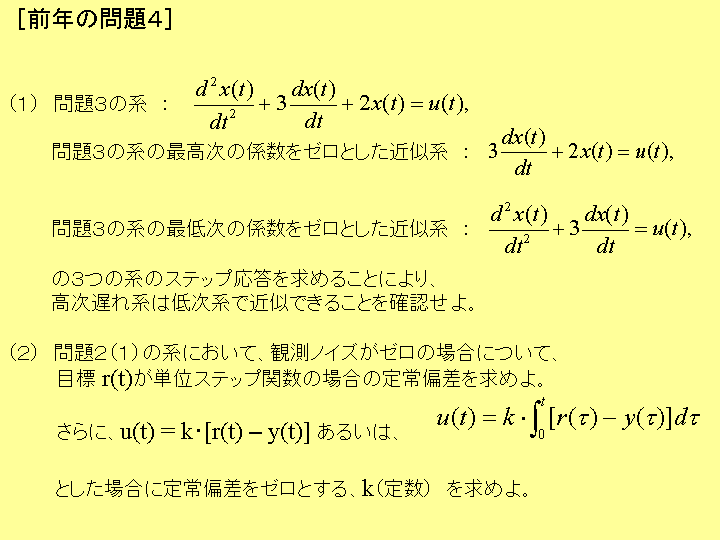
第四講 : 古典制御:システム解析2
あなた
は、今日の講義を受けると、代表的な入力信号に対するシステムの時間応答解析方法についての知見が得られます。
(講義内容一覧)
◆制御系の時間応答特性:一次
遅れ系・二次遅れ系のステップ応答、過渡・定常特性、定
常偏差、行き過ぎ量
◆定
常偏差は目標関数と制御システムのタイプで決まる
◆高
次遅れ系は低次系で近似・代用されることが多い
◆ラ
ウスやフィルビッツの安定判別法
◆数値シ
ミュレーション
コーヒーブ
レイク(休憩室)
数式ばかりでは、感覚的あるいはイメージ的に納得しにくいので、極端な時間遅れ系に対
する制御の例について紹介をします。
例えば、通
信するのに十数分もするような距離が存在する場合、あなたは、どのように制御すればよいと思いますか?
実例として
は、火星と地球との間、電波が伝播するのに十数分かかります。だから、米国の火星探査ロボットであるソジャーナを遠隔操作することが困難であることは、想
像に難くないですよね。(例えば自動車で、ハンドルやアクセルやブレーキを操作して十数分後に応答されても、運転は不可能に近く、事故ばかり起こしそうで
すよね。実用に耐えない位、低速で走ることにすれば、運転は可能かもしれませんが、・・・)
実際には、
次のような制御が採用されました。
シミュレー
ションベースの操作方式:ソジャーナに搭載されたレーザースキャナが送信してくる火星表面の三次元形状に基づいて作られる近傍の概略の地形モデルが使われ
る。そのモデルを用いて、管制室側でロボットの動きをシミュレートしようというわけである。その世界をどう動かしてほしいかを命令列としてプログラムし、
バーチャルナソジャーナをシミュレーションの上で動かしてみる。うまくいくようであれば、大体一日分くらいの行動計画をソジャーナに送信し、受け取ったソ
ジャーナは、一日分の命令を自律的に実行し、火星表面で活躍する。