 �T�C�g�}�b�v�@
�T�C�g�}�b�v�@



 ��������ƈ���
��������ƈ���
�@�̂���A�u����͒B�҂ŗ��炪�悢�v�ƌ����Ă��܂����B�a�C�ɂȂ�����ʓ|�����Ȃ���Ȃ炸��ςȂ̂ŁA�v�ɂ͌��C�ł��Ă����Ȃ��ƍ��邪�A���Ȃ��Ƃ����Ԃ͉Ƃɂ��Ȃ��łق����A�������Ă��炦��A�ȂƂ��Ă͈��S���Đ������邱�Ƃ��ł���A�Ƃ������Ƃł��B�Ƃ��낪�A���炭�O����A���̂悤�ɂ̂�т�ƍ\���Ă����Ȃ������������A�ǂ���炩�Ȃ葝�����Ă��Ă���̂ł��B���̗\���́A����30�N�قǑO�ɂ͋C�Â���Ă��܂����i���Ƃ��A�w�T������x1981�N11��26�����j���A���݂ł́A��N��̕v�Ɗ��˂����킹�ĕ邷���Ƃɑ��āA�s���ǂ��납���|��������Ȃ��A���Ȃ�̐��ɂ̂ڂ�悤�ɂȂ����̂ł��B���ɂ́A�v�ɎE�ӂ�����A���̂��Ƃ�v�Ɍ������Č�������Ȃ��炢�邻���ł��i�w�T������x2010�N3��6�����u�v�ɑ�������łق����Ȃ����v�j�B
�@�u�v�w�̂��Ƃ͑��l�ɂ͂킩��Ȃ��v�ƌ�������̂́A���̂悤�Ȃ��Ƃ�������̂́A�Ȃ��Ȃ̂ł��傤���B����́A�{���Ɉ���������������ʂȂ̂ł��傤���B����Ƃ��A�����ʂ̗��R������̂ł��傤���B�{���ł́A���̖��ɂ��Č������܂��B
�@���̍��́A�g�g���h��g�ƕ��h���d�v�ȗv�f�ɂȂ��Ă������Ƃ������āA�l���m�̌����Ƃ������́A�Ɠ��m�̌����̂悤�ȑ��ʂ�����܂����B�܂��A�����̑��ɂ͌o�ϓI�����̎�i���قƂ�ǂȂ��������߂�����A��قǂ̂��Ƃ��Ȃ�����A�����Ƃ����I�����͂���܂���ł����B�s�����������Ƃ��Ă��A��������ɂ�����A�s���Ɉڂ����肷��̂́A�����ꂴ��g�킪�܂܁h�ł���A���܂�̂�������܂��������Ƃ������Ƃł��B���邢�́A�g��l�h�ɑ��āg�Ŏ�����h����̂����R�ł����āA���܂Ă���Ƃ������o����Ȃ�������������܂���B�j�����ڂƂ������j�I�w�i�̒��ŁA�g�ƕ������h�Ƃ������x���������Ă������Ƃ���`���āA�قƂ�ǂ̏ꍇ�A�����̑����A����I�Ȍ��g��������ꂽ�킯�ł��m���Q�n�B�����̂킪���ł́A�����Ƃ͂܂��Ɂu�����������́v�������̂ł��B���݂ł��A���E�e�n�����킽���A�C�X���������͂��߁A��������͈ˑR�Ƃ��Đe�����߁A���̖{�l�����͌����������ɏ��߂Ċ�����킹��Ƃ�����������n����A�����ď��Ȃ��Ȃ��悤�ł��B
�@���̖��剻�̒��ŁA���������́A�S�g�Ƃ��Ɏ���ɋ��������܂����Ȃ�܂������A�����Ɋւ�����K�I�ȍl�������͂��قǕς�炸�A�������Ƃ������K���A��r�I�ŋ߂܂Ŏc���Ă��܂����B�I���܂��Ȃ����ɐ��܂ꂽ�������̐���ł́A�l�N����w�𑲋Ƃ��Ă���ƂɏA�E���邱�ƂȂ��A���̂܂܁g�ԉŏC�Ɓh�ɓ����������������A�܂��ꕔ�ɂ����̂ł��B�����āA���̂قƂ�ǂ͌�������ʂ��Č������܂����B�܂��A�A�E�������������̏ꍇ���A�����鍘�������x�̂��̂ŁA�����̂��߂Q�A�R�N�̂����ɑސE����䗦�����ɍ������A�������r�I�ŋ߂܂ő����܂����B���̂��߁A��w���̏����Ј��ł����Ă��A�g�E��̉ԁh�I�Ȉ������A�G�p�I�Ȏd�������^�����Ȃ����Ƃ������A���̂��Ƃ������̎Љ�I�n�ʂ����コ����ۂ̏�Q�ɂȂ�Ƃ��āA��莋����Ă����킯�ł��B
�@�����̎Љ�ʔO�Ƃ��āA������30�܂łɌ���������̂Ƃ���Ă������߁A����܂ł͐e�ʂ�ߏ��̐��b�D���Ȃ��������A�������̘b�����X�Ƃ����Ă���̂ł����A�����R�O���߂���ƁA���͂�g�����K����h���킵���Ƃ݂Ȃ���A����ɂ���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ����������悤�ł��B
�@���̌�A�킪���ł́A�����́g�Љ�i�o�h��������ɂȂ�A�o�ϓI�Ɏ������鏗�������������Ȃ�ɂ�āA�����ɑ���l������������ɕς���Ă��܂����B�����āA�������Ȃ��Ƃ����I�������Ƃ鏗�������������Ă���ƁA�����Ƃ����T�O��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A�����̕��ϔN��K�R�I�ɏオ���Ă����̂ł��B������Ӎ������ۂł��B�j���̏ꍇ���A�d�����i���قƂ�ǂȂ������̂Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قǁA�Ǝ��S�ʂ��e�ՂɂȂ������Ƃ������āA�������Ȃ��Ɛg�����������đI������l��������������o�Ă��܂����B����ƕ��s���āA�̂ӂ��̌�������ʂ��Č�������l�����̐����A�}�����Ă��܂����̂ł��B
�@�����ɂ��Ă��A������x�̊��ԁA���ۂ𑱂��Č����Ɏ���Ƃ����̂ӂ��̃p�^�[�����������A���N�P�ʂ��炢�Ŏ��X�Ƒ����ւ��A�Ȃ��Ȃ��������悤�Ƃ��Ȃ��j�����������Ă��܂����B����ƂƂ��ɁA�����͕K�������K���ɂȂ���Ȃ��A�ƍl����l��������������o�Ă����̂ł��i���Ƃ��A�[�V�A2009�j�B�܂��A�̂̓����W�Ƃ͎��I�ɈႤ�̂ł����A�������Ă������͂��o���Ȃ��l������A�������Ă��A���X�ɕʋ��◣���Ɏ���l������A�g�n�N�����h��g�n�N�č��h������l�����̐��������Ă����̂ł��B�����āA�ꂠ���Ƃ͕ʂɁA��Ƃ��ĒZ���I�Ȉ��l�����l���������Ȃ��炸�o�Ă����̂��܂������Ȃ������Ȃ̂ŁA�����ɂ��āA�×��̓����Ƃ����ϔN�̎�������ꋓ�ɉ�����ꂽ�Ƃ������ʂ����邱�Ƃ́A���Ȃ����ے�ł��Ȃ��ł��傤�B
�@�Ƃ���ŁA�ƒ�ɓ��������������́A���Ɏq�ǂ���ł���}���Ɂg���т��݁h�A�����Ƃ������́g������h�Ƃ����Ăт������ӂ��킵�����e�ɕς���Ă��������̂ł����B���l�������A�����������̂��Ƃ��āA���ɋC�ɂ��邱�Ƃ��Ȃ������悤�ł��B���ꂪ�A�����炭10�N�قǑO����}���ɕς��n�߁A���ł́A�قƂ�ǂ̊��������������A�q�ǂ��������Ă��Ă��A�������́A���N��̖��������ƂقƂ�Ǖς��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă��܂��B�̂Ɣ�ׂ�ƁA�S�����ʂ��āA�j���Ƃ����S�g�Ƃ��Ɏ�Ԃ�A���C�ɂȂ��Ă����Ƃ��������[���ω������邱�Ƃ��A���̔w�i�Ƃ��Č��̂����Ȃ��_�ł��傤�B
�@�������̂悤�ȁA�I�풼��ɐ��܂ꂽ�A������c��̐���́A���Ƃ��ΐ��l���̎ʐ^������Ƃ킩��܂����A����̊��o���炷��A�j���Ƃ��ɂ��Ȃ�ӂ��Č����܂����B�܂��A�����̂S�O��̒j���́A�ɒ[�Ɍ�������60�キ�炢�Ɍ������悤�Ɏv���܂��B���ł́A100���z���Ă��Ă��A�M���������قnj��C�Ȑl���o�Ă��Ă��܂��B�ǂ̂悤�Ȍ����ɂ����̂��͂Ƃ������Ƃ��āA�������ƕ��s���ċN���������̕ω��́A�l�ގj�I�Ɍ��Ă���߂ďd�v�ȈӖ��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@���̍��ɂ͊��ɁA���҂Ƃ�������ɑ���g����h�������Ă��Ă��܂��B���Ȃ��Ƃ��A���Ԉ�ʂɂ͂����l�����Ă���悤�ł����A���́A�����ɑ傫�Ȗ�肪�Ђ���ł���̂ł��B���������ł���A�������������ɗ��҂ɂ������̂́A����Ƃ������́A��������ł��B�u�����������ځv�ƌ�����悤�ɁA��������Ƃ́A����ɑ��邠������ɋ߂����̂ƍl����킩��₷���ł��傤�B���̂悤�ɁA��������Ɩ{���̈���́A���Ĕ�Ȃ���̂Ȃ̂ł����A���̂ӂ�����ʂ����Ɏg���l�������������߁A�������N����₷���̂ł��B���̐S���Ö@���Ă��������Ǝ�w�́A�������������������������Ȃ������̂ɁA���ꂪ�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����ƒQ���Ă��܂������A�ނ��낻��́A�N����ׂ����ċN����K�R�I�Ȍo�߂Ȃ̂ł��B���̂��Ƃ́A����I���x���ł́A�����炭�قƂ�ǂ̐l���m���Ă��܂��B����́A�t�̗������Ƃ悭�킩��͂��ł��B���Ɉ��p����̂́A�ْ��ɏЉ�����Ƃ̂���A���ɋ����[������ł��B
�@���鎞�A���@���ɐS���Ö@���Ă�����\��̏������A�S���Ö@���ɓ����ė���Ȃ�A�����ɂ��������Ƃ����\��ŁA���̂悤�Șb�����Ă��ꂽ�B�����̌\��̊����҂̂Ƃ���ɁA�����̂悤�ɂ��̕v���ʉ�ɗ��Ă��邪�A���@���ɂ��܂��܂��̏������a�������}�����B����ƕv�́A�Ȃւ̃v���[���g�����Q���A�a���̃x�b�h�ɍ����Ă���Ȃ̑O�ɂ�������₤�₵�������o���āA�x�b�h�ɎO�w�����Ȃ���A�u���a�����A���߂łƂ��������܂��B���ꂩ�����낵�����肢���܂��v�ƌ����ƁA����ɑ��čȂ��A�u���肪�Ƃ��������܂��B����Ƃ���낵�����肢���܂��v�ƁA�������O�w�����ĉ������Ƃ����̂ł���B����ɂ́A�����̎O�l�̖�����������l�Ɉ��R�Ƃ��A�v�킸��������킹���Ƃ����B��͂�S���Ö@���Ă����ʂ̂ЂƂ���A���̎��̖͗l����͂�����̕\��ōČ����Ă��ꂽ�̂ŁA���̒ʂ�̂��Ƃ��������̂͊m���Ȃ̂ł��낤�i�}���A2005�N�160-161�y�[�W�j�B
�@�����ォ�Ȃ�̔N�����o�Ă���A���̂悤�ɁA�S���I�����̉����A���������l�ԊW�������ĂȂ��l�������ꕔ�ɂ��܂��m���R�n�B���̂悤�Ȑl�����̏ꍇ�A����ɕs���s������������Ƃ��Ȃ���A�v�w�����������Ƃ��Ȃ��A�݂��ɂ���߂Ă₳�����ԓx���Ƃ邱�Ƃ������̂ł��B�ꂠ�������@���Ă���ꍇ�ɂ́A�����ɕa�@�ɗ������A����̊�����Ă����Ђɏo���A�ގЌ�͕a�@�֒��s���āA�ʉ�Ԃ��I���܂ňꏏ�ɉ߂����A��x���A���A�Ƃ������Ƃ���ۂɂ��Ă����l������قǂł��i�Ƃ͂����A�q�ǂ�������ꍇ�ɂ́A���̊ԁA�q�ǂ��͕��u����Ă��܂��j�B���������W�𗝑z�̕v�w�̂悤�ɍl����l������ł��傤���A����́A�S���I�������������߂Ɂ\�\��������A���l�s�V�̂��߂Ɂ\�\���ނ܂���������ɂ����Ȃ��W���A�{���̈Ӗ��ň���̐[���W�ƍ��o���Ă���Ƃ������Ƃł��B
�@�����ł̃|�C���g�́A�����������Ƃ̂Ȃ��Ⴂ���������ł��A��������ƕv�w�̈���Ƃ͍��{�I�ɈႤ�Ƃ������Ƃ��A����I���x���ł͐捏���m���Ă���Ƃ��������ł��B���N�A��Y�����v�w���A���̂悤�ȁg���l�s�V�h�ȑԓx���Ƃ�̂��݂�ƁA�ǂ����Ă���a�����o����������Ȃ��킯�ł��B�������A���N�ȏ�̒j���ł��A�V���ɒm�荇�����ꍇ�ł���A�Ⴂ�l�����̗�������Ɠ����̂��̂��N����̂ŁA�݂��ɂ₳�������邱�Ƃ͓�Ȃ��ł��邵�A����͉����ӂ����Ȃ��Ƃł͂Ȃ��̂ł����A�ꏏ�ɕ�炷���Ԃ������Ȃ�ƁA�����������ɔ����ƂƂ��ɁA����ɋC������Ȃ��Ȃ�A�������Ȃ��Ȃ�܂��B
�@���̒i�K�ɂȂ�ƁA�j���̏ꍇ�ɂ́A���܂�b�����Ȃ��Ȃ�����A�����̕����ɂ������Ď�⓹�y�ɂӂ�������A�ʂĂ͖\�͓I�ɂȂ����肷��킯�ł��B�܂��A�����̏ꍇ�ɂ́A�����p�ŕ��������������A���\�Ȍ����Řb������A�v�ɑ��Đ₦���������������肷��悤�ɂȂ�ł��傤�B�����āA���I�ȈӖ�����ł͂Ȃ��A�݂��ɐg�̓I�ȐڐG�������悤�ɂȂ邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��͂��ł��B�������A����́A�������ƂƂ������́A���Ɋj�Ƒ������Ă���Љ�ł́A�m�̓������킸�A���R�Ȍo�߂ƍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��傤�B
�@��������ƁA�����錑�ӊ��Ƃ́A����܂ł�������������Ƃ������A����ɑ��邠�����ꂪ�قڏ�����\�\�܂�A�u�����͂����v�ɂȂ�\�\�����ɂ�����ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B�ł́A���̌�͂ǂ��Ȃ�̂ł��傤���B�ӂ���́A����̂Ȃ��A�P�Ȃ铯���l�ɂȂ��Ă��܂��̂ł��傤���B���̐���l����q���g�ɂȂ�̂́A���Ƃ��Ȃƈ��l�̔�r�ł��B�Ȃƈ��l�Ƃ�����j�����A��ʎ��̂�]�����ŐQ������ɂȂ����Ƃ��܂��B��������ƁA���̒j������삷��̂͂ǂ���ł��傤���B�ӎ��ł́A���̒j���́A�Ȃ������l�̂ق��ɂ͂邩�g����h�������Ă���͂��ł��B
�@�����ł͂����肵�Ă���̂́A��قǓ���Ȏ���ł��Ȃ�����A���l���Ȃ������u���ĉ�삷�邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B����́A���A�̑��݂�����Ƃ��A���̋`�����Ȃ����߂Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A���������ԕ��\�\�@�I�ȈӖ��ł͂Ȃ��A�S���I�ȈӖ��ł̊ԕ��\�\�ɂȂ�����ł��傤�B���N�������Ă���ꍇ��ʂɂ���A���l�Ƃ́A�Ȃƈ���ĕ\�ʓI�ȊW�ɂ������A�u�J�~���Ēn�ł܂�v�Ƃ����o�߂����x�ƂȂ��J�肩�����Ă����悤�ȁA�e���Ȋԕ��ł͂Ȃ��̂ł��m���S�n�B�ł́A�Ȃ́A�P�Ȃ�`���ӎ��⑹�����肩��A��������������v�̉������Ԃ��Ԃ���̂ł��傤���B
�@���̐l�����́A�������ɂЂ��������Ă���킯�ł͂Ȃ��A�ӂ��̎Љ���𑗂��Ă��āA�E��ł̑ΐl�W�܂Ŕ����Ă���킯�ł͂���܂���B�������A���̒��x�͂��܂��܂ŁA���Ƃ��A�E��̓����ƌl�I�Ȃ����������邱�Ƃɂ��A����ȊO�̗F�l����邱�Ƃɂ���R�͂Ȃ����A������x���z���Đe�����Ȃ邱�Ƃɂ͒�R������Ƃ����l�������������ŁA�F�l����邱�Ƃ͂��Ƃ��A�E��̖Y�N���Ԉ����s�ɎQ������̂������قǂ̐l���������܂��B�E��̒��ōs�Ȃ���s���Ƃ͂����A���̒��ł͌��I�Ȋ�������Ă��邾���ł͂��܂��A�l�I�ȑ��ʂ��ǂ����Ă��o�Ă��܂����߂ɁA���̎Q�������₪��Ƃ������Ƃł��B
�@��قǂӂ�Ă������A�����̑����Z���Ԃ̂����Ɏ��X�Ƒւ��Ă䂭�l�����̂قƂ�ǂ��A�����炭���̔��e�ɓ���܂��B�V����C���^�[�l�b�g�̐l�����k���ɂ́A���̐l��������̑��k��������ڂ��Ă��܂��B���ۑ���Ɖ�O�ɋ����Ƃ��߂��Ȃ��Ȃ����̂́A����Ȃ��Ȃ��������Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ��A���肪���܂���������Ȃ��Ȃ�A�₽���Ȃ����̂ŁA�ǂ�������悢�̂��킩��Ȃ��Ƃ��A���߂đ���Ƃ����Ă��܂����̂ŁA�����I���Ȃ̂ł͂Ȃ����A�Ƃ��������̂ł��B�����āA����܂ł̑���ƕʂ�A���̑���ƌ��ۂ��n�߂�ƁA�܂��V�N�ȊW�����܂�A���Ȃ��Ƃ����̐������͈��ׂȏ�Ԃ������킯�ł��B���̐l�����́A��������ِ̈��ƌ��ۂł���̂�����A������x�ȏ�e�����Ȃ�Ȃ����Ƃō����Ă���l�����Ƃ͈Ⴄ�悤�Ɍ����邩������܂���B�������A�{�l�̍����Ă���|�C���g�����X�قȂ邾���ŁA�{���͑S�������ł��B
�@���鏗�q�吶�́A�S�N���ɂȂ��Ă��A�܂���x���������������Ƃ�����܂���ł����B�D���ɂȂ����j���͂��Ă��A�l�I�Ȍ��ۂɂ܂Ŕ��W�������Ƃ́A��x�Ƃ��ĂȂ������̂ł��B�{�l�͂�����A�����ɏ����Ƃ��Ă̖��͂��Ȃ��A���ׂ����邽�߂ɈႢ�Ȃ��Ƃ��Ď�����ӂ߁A���̂��ƂŁg���h������Ă��܂����B�F�l�����́A���X�Ɨ����̑����ւ��A�g�����o���h���܂��܂��L�x�ɂȂ��Ă䂫�܂��B���������F�l�����́A�{�l�ɓ���̌��ۑ��肪�ł��Ȃ����Ƃ��ӂ�������A�S�z���Ă���Ă��������ł��B�Ƃ��낪����Ƃ��A���̗��͎v�����݂ɂ����Ȃ��������Ƃ������Ă����o�������N����܂��B
�@���̏��q�吶�́A���N�̒j�����D���ɂȂ�A�v���]���āA���̂��Ƃ����Ǝ�������u�����v����̂ł����A���̒j������́A�u�����l�������Ăق����v�ƌ����܂��B���̌�A���̒j���́A�Ԏ������Ȃ��܂܁A�{�l�ɂ������������Ă��炢�������Ȃ��Ԃ���A�{�l�̎��ӂŌJ�肩���������܂��B�������A�ْ��̂��߁A����ȏ㑊��ɐڋ߂ł��Ȃ��{�l�́A���ɑI�������Ȃ��܂ܐÊς𑱂��܂��B���炭���āA�҂�����Ȃ��Ȃ����{�l�̂��ƂցA�悤�₭����̕Ԏ������[���œ͂��܂��B�Ƃ��낪�����ɂ́A�u�Y����Ȃ��l������̂ŁA�����������Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ə�����Ă����̂ł��B
�@���̕ԐM��ǂ{�l�́A�����������ƂŃV���b�N���܂����B�S���Ö@�̒��ł��A���R�̂��ƂȂ���A���́g�V���b�N�h�����ɂȂ�܂����B����́A�����������Ƃɂ��ʏ�̒Ɏ�ł���̂��A����Ƃ��A���̐S���Ö@�Ō��������\�\�܂�A�K���ے�ɋN������Ǐ�\�\�ł���̂��A�Ƃ������Ƃł��B�����A���ꂪ�ӂ��̒Ɏ�ł���A�S���Ö@�̑Ώۂɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ŁA���R�ɉ���̂����Ԃ������đ҂�������܂���B����ɑ��āA�������ꂪ�g�����h�ł���A�ǂ��Ɋ�т��������̂����͂����肳���A�u�����ɂ��V���b�N�v�Ƃ����`������Ă���A���̏Ǐ�����������邱�Ƃ��\�ɂȂ�̂ł��B
�@���̐�ɐV���ȓW�J���Ȃ�����A�����������Ƃ��̂��͎̂����Ȃ̂ŁA����͏펯�I�ɂ͔��ɕs�K�Ȃ��Ƃł���A�����ɍK�����Ȃǂ��낤�͂�������܂���B�Ƃ��낪�A�l�Ԃ̖{���͂����Ɛ[���Ƃ���ɂ���A�����ɐ^�̈Ӗ��ł̍K���S���B����Ă��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��̂ł��B�����ł܂��A���́g�V���b�N�h���ǂ̂悤�Ȃ��̂����A���̐S���Ö@�ŏ�p���Ă���A�g����̉��Z�h�Ƃ������@�Ŋm�F���邱�Ƃɂ��܂����B��������ƁA��͂�Ƃ����ׂ�������́A�ʏ�̒Ɏ�ł͂Ȃ��A�ǂ����g�����h�炵�����Ƃ��킩�����̂ł��m���T�n�B
�@�����āA����ɖ��炩�ɂȂ����̂́A���肪�����̂��Ƃ��A�V�ъ��o�ł������y������Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�^���Ȍ��ۂ̑ΏۂƂ��čl���Ă���Ă������Ƃ��A���̕ԐM�����Ă͂����芴����ꂽ�A�Ƃ����S�I�����ł����B����������̂��Ƃ�^���ɍl���Ă��������łȂ��A������A�����̂��Ƃ�^���ɍl���A�v���Y��ł������ƂɋC�Â����ꂽ�A�Ƃ������Ƃł��B���̂��Ƃ��킩�����i�K�Ŗ{�l�́A�{���ɍD���Ȃ킯�ł��Ȃ��ِ��ƋC�y�ɂ������ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ����M�O���A�S�̒�ɂ����Ă������ƂɎv������܂��B����ƂƂ��ɁA���̂悤�Ȃ��ƂɎ��R�ɋC�Â����ꂽ�̂ł����B
�@�ِ��ƊȒP�Ɍ��ۂ��n�߂���l�����̏ꍇ�ɂ́A�݂��ɂ���قǍD���ȑ���ł͂Ȃ����炱���A���������R���Ȃ��A�C�y�Ɍ��ۂ��n�߂���Ƃ������ƂȂ̂ł͂Ȃ����A���̂��߁A���ۂ�������x�����Ĉ���[�܂�i�K�ɂȂ�ƁA�����Œ�R���N�����āA����Ăĉ�������Ƃ������ƂȂ̂ł͂Ȃ����B���������āA��������X�Ƒւ��Ă䂭�悤�ȁA�g�����o���h���L�x�Ȑl�����ł����Ă���͂�A�{���ɍD���ȑ���Ƃ́A���ۂ��n�߂邱�Ǝ��̂�����̂ł͂Ȃ����B
�@�{���ɍD���ȑ���ɑ��ẮA���ꂱ���m�̓������킸�A���������邱�Ƃ������Ȃ���̂ł��B���{�l�Ɣ�ׂĂ͂邩�ɗz�C�Ŋy�ϓI�Ȃ͂��̃A�����J�l��Ώۂɍs�Ȃ�ꂽ���钲���ł��A���̉҂̂قƂ�ǂ��A�{���ɍD���ȑ���ɐ��������悤�Ƃ���ƁA�u�ӂ邦����A���Ȃ�����A�Ԃ��Ȃ�����A���ׂĂɋC��ɂȂ�����A�ǂ����悤���Ȃ����a�ɂȂ�����A�ǂ������肵�āA������{�I�Ȕ\�͂�Z�p�������ڂ��Ȃ��Ȃ�v�Ɠ����Ă��邻���ł��i�t�B�b�V���[�A1993�34�y�[�W�j�B�܂��A28�̃A�����J�l�j���́A���������̒��ŁA���̂悤�Ȕ��������Ă��܂��B
�@�����ǂ����Ȃ肻���Ȃ��炢�A�����ǂ��ǂ����Ă���B����ɏo�āA���������̊ϋq�̑O�ł������Ă��܂����݂����Ȋ������B�h�A�̃x����炻���Ƃ���Ǝ肪�ӂ邦��B�ޏ��ɓd�b��������Ƃ��ȂA�ǂ���ǂ���Ƃ����ۓ����d�b�̌Ăяo���������傫�����̂Ȃ��ŋ�����B�i�����A34�y�[�W�j
�@���ꂪ�A�{���ɍD���ȑ���ɐڋ߂��悤�Ƃ���Ƃ��ɋN����A���ՓI�Ȕ����Ȃ̂ł��傤�B�����̌l��������Ƃ͂����A���̂悤�ȁg�n�[�h���h���������Ȃ������Ƃ���A���̑���́A����قǍD���ł͂Ȃ��A��R�Ȃ��C�y�ɂ������鑊��Ƃ������ƂɂȂ�͂��ł��B�{�l���A����̒j���ɐڋ߂��悤�Ƃ���Ƃ��ɁA����Ɠ����悤�Ȑg�̔������N�����Ă��܂������A�E�C���Ă�������z���Ă����̂ł��B���̓_�ɂ��ẮA����̒j���������ł����B�����Ɏ����āA���̏��q�吶�́A����܂ł̎����̗��́A�P�Ȃ�v�����݂ɂ����Ȃ��������Ƃ�F�߂�������Ȃ��Ȃ�ƂƂ��ɁA�����Ƃ��Ă̎��M�����߂Ĉӎ��ɕ����яオ�����̂ł����B
�@���̐}�́A�A�����J�̏����l�ފw�҂��A�U�Q�̍��E�n��E�����̗����̃s�[�N�ׁA������O���t�ɂ������̂ł��B���������ƁA��������l�����̂قƂ�ǂ́A�ǂ���猋����S�N�܂ł̊Ԃɗ������Ă��܂��A���̃s�[�N�͂S�N�ڂɂ��邱�Ƃ��A�͂�����ƌ��Ď��܂��B�܂�A��������l�����̈��|�I�����́A�܂��Ɍ��ӊ��ɓ���O��܂łɗ������Ă��܂��Ƃ������Ƃł��B���̂悤�ȗ������悢���������͂Ƃ������A���ӊ��ɓ��鍠�܂łɗ�������l�����ƁA����ȍ~�܂Ō��������𑱂���l�����Ƃł́A���������܂��Ɍ����A��������̑I�т������̂��̂�����Ă���̂�������܂���B�܂�A�O�҂́A�C�y�Ɍ��ۂ��n�߂āA�Ȃ�䂫�̂܂܌��������O���[�v�ł���A��҂́A�{���ɍD���ȑ���ƁA�݂��ɒ�R�����z�����������O���[�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃł��B
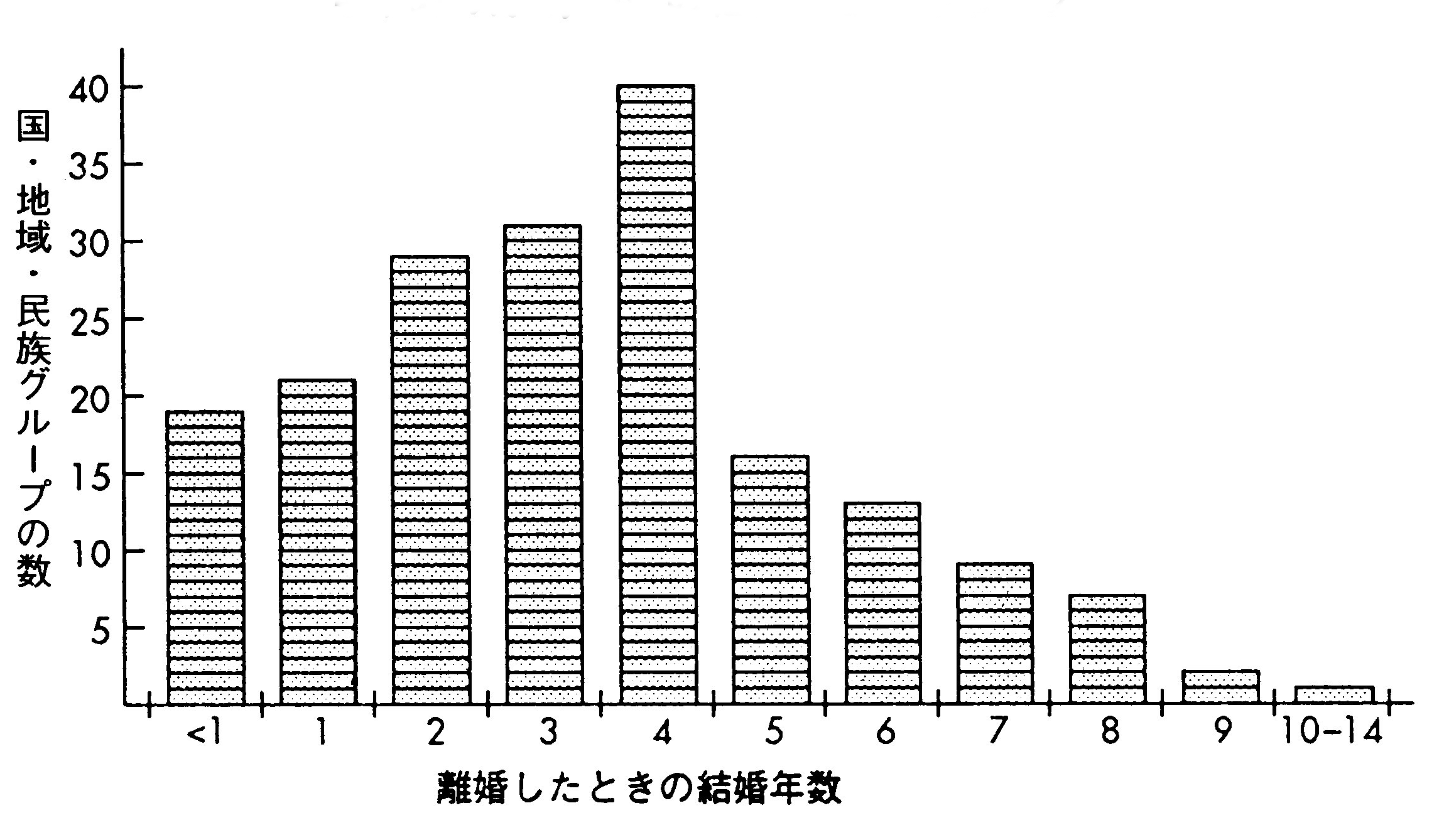
�}�P�@���E62�̍��E�n��E�����W�c�ɂ�����A1947-89�N�̊Ԃ̂���N�x�̗����̃s�[�N188����W�v�������́B���E�S�̂Ō���ƁA�����Q�N�ڂ���S�N�ڂ܂ł̕v�w�������Ɏ���ꍇ���ł������A���̃s�[�N�͂S�N�ڂɂȂ��Ă���i�t�B�b�V���[�A1993�N�107�y�[�W���Čf�BFisher, 1992, pp. 358-62�j�B
|
�@�����Ő�������ƁA�ȏ�̌������疾�炩�ɂȂ����̂́A���̂Q�_�ł��B
���ӊ��ƌĂ���Ԃ́A��������Ƃ����������ꂪ���������A�^�̈���[�܂��Ă䂭�i�K�ɂ����邱�ƁB 
��R�i���̏ꍇ�́A����̔ے�j�̋����l�����̏ꍇ�A�{���ɍD���ȑ���Ɨ����⌋��������͔̂��ɓ�����߁A�����⌋��������邩�A�����Ȃ���A����قǍD���Ȃ킯�ł͂Ȃ�������ǂ����Ă��I�т₷���Ȃ邱�ƁB
�@�����܂ł���ƁA��قǂ̋^��ɓ����邱�Ƃ��ł������ł��B�Ȃƈ��l������ꍇ�A�ӂ���̈���͂ǂ����ǂ��Ⴄ�̂��A�v���|�ꂽ�ꍇ�A���l�ł͂Ȃ��Ȃ����̉�������̂́A�P�Ȃ�`���ӎ��⑹������̂��߂ɂ����Ȃ��̂��A�Ƃ������ł����B����ɑ��ẮA�v�ւ̍Ȃ̊�������^�̈Ӗ��ł̈���ł���A���l�Ƃ̊ԂɌ�����A��������Ƃ����A���瑊�Ȋ���ł͂Ȃ��A�[������Ȃ���Ƃ��Ă��������Ȃ������A�Ȃ́i�ӎ��ł́A�����ꏭ�Ȃ��ꌙ���┽�����ɂ������Ȃ���ł����Ă��j�����邱�Ƃ��ł���A�Ɠ����邱�Ƃ��ł���ł��傤�m���U�n�B�Ō�ɁA�v�̒�N��ɋN���邳�܂��܂Ȗ��ɂ��Č������܂����A�����܂ł���A����������肪�N���闝�R���A�͂�����킩��͂��ł��B
�@���N�O�ɍs�Ȃ�ꂽ���钲���ɂ��A�c��̐���̒j����85�p�[�Z���g���������̒�N���y���݂ɂ��Ă����̂ɑ��āA�Ȃ�40�p�[�Z���g�͕v�̒�N���u�J���v�Ɋ����Ă����A�Ƃ������ʂ��o�Ă��܂��i���G���_�[�r�W�l�X���i���A2004�N�j�B�܂��A�v�̏ꍇ�ɂ́A�v�w�ňꏏ�ɓ������Ƃ����Ċy�������Ǝv���Ă���䗦��47.4�p�[�Z���g�ƁA�S�̂̔����߂����߂��̂ɑ��āA�Ȃ̏ꍇ�ɂ́A33.3�p�[�Z���g�ƑS�̂̂R���̂P��������܂���ł����B�v�́A�����Ȃƈꏏ�ɂ���������Ȃɂ��čs�������邾���Ȃ̂ł����A�Ȃ̂ق��́A�܂��ɂ���������Ƃ�����������킯�ł��B���̌��ʁA�v�́A�Ȃ̑ԓx�ɓ��f�◎�_���o����̂ɑ��āA�Ȃ́A�v�̑ԓx�����ĕs�����⋰�|��������̂ł��B�����ł��A���҂̊ԂɁA�ʼn߂ł��Ȃ��قǂ̑Η��������Ă��邱�Ƃ��킩��܂��m���V�n�B
�@������x���܂�ς�����Ƃ�����A�܂����̂ꂠ���ƌ������������ǂ�����q�˂��A���P�[�g�����̌��ʂ��A�V����G���ɍڂ��Ă���̂��A���x�������������Ƃ�����܂��B���̂悤�Ȏ���ɑ��Ă��A�v�ƍȂ̉́A���R�̂��ƂȂ���傫���H���Ⴂ�܂��B�v�̑����́A���Ȃ��Ƃ����ׂ����A���̍ȂƂ܂������������Ɖ���̂ł����A�Ȃ́A�ނ��낻��������X���ɂ���킯�ł��B���Ȃ�̔䗦�̕v���A�Ȃ���ԍD�����Ǝv���Ă���̂ɑ��āA�v����ԍD�����Ǝv���Ă���Ȃ̔䗦�́A����قǍ����Ȃ��̂ł��i�����V���A2009�N12��27�����j�B���̂��Ƃ́A��N��̕v�������Ȃ��������錴���ƂȂ����Ă���͂��ł��B�ł́A���̌����͂ǂ��ɂ���̂ł��傤���B
�@��N��ł͂���܂��A���Ȃ�[���Ȏ�����A�����̌o�߂̒��ŁA�����I�ɕ��������Ƃ�����܂��B�U�O��̌����̉�Ќo�c�҂́A�ӂ���̖������ɉƂ��o�Ă������߁A�ȂƂӂ��肾���Ő������Ă����̂ł����A���鎞�A�A�����A�قƂ�ǂ̉ƍ�����ƂƂ��ɁA�Ȃ��p�������Ă����̂ł��B���f�ʼnƂ��o�Ă��܂��Ă����̂ł����B�݂̂Ȃ炸�A����ɂ�����������ʒ��⊔�����A�S�������o����Ă��܂����B�ʒ��Ɗ����͖��`�ύX����Ă������Ƃ��A��ł킩��܂��B�܂��Ɏ����Ȍv��Ɋ�Â����s���ł����B���̒j���́A�ƒ�̂��Ƃ͍ȂɔC������ɂ��Ă������߁A�����ǂ��ɂ��邩����킩�炸�A�ˑR�ɂЂƂ��炵�𔗂��āA���ɍ������Ƃ������Ƃł��B��e�̐g����ȍs���ɂ�����ʂāA���e��S�z���������́A�x���ɂȂ�Ǝ��Ƃɍs���āA���e�̐��b�����Ă��������ł��B�Ƃ͂����A���̎���ł́A�������Əo��P���������Ȃ������ɁA�Ȃ͕v�Ɣ��肪���̗��s�ɏo������悤�ɂȂ�܂����B�����āA����ɂ���߂��A10�N�߂������������̂́A���ǂ͍Ăѓ������n�߂Ă��܂��B
�@��N��̕v�ɂ��āA�l���������ł����낵���̂ŁA���̕v���|�ǂ����������Ƃ��ĐS���Ö@���n�߂��������A���̂Ƃ��낾���ł����l�����܂��B����܂ŕv�́A�����̑O����A������ӂ܂Ŏp�������Ă���Ă����̂ŁA���S���ĕ�炷���Ƃ��ł������A��N��́A���Ɏq�ǂ��������������āA�v�Ƃӂ��肾���ɂȂ��Ă���ꍇ�ɂ́A�Ƃ̒��ŕv�Ƃ������˂����킹�Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA���̂��Ƃ��l����ƁA���낵���Ė������Ȃ��Ƃ����킯�ł��B�����̍Ȃ́A�u�v�����̋C�����킩���Ă���Ȃ��v���Ƃ�A�u�₳�������Ă���Ȃ��v���Ƃ��A���̗��R�ɂ�����悤�ł��B�Ƃ��낪�t�ɁA�u�����̕v�́A���̌������Ƃ����ł������Ă���āA�₳��������̂����₾�v�Ƒi����Ȃ�����̂ł��B
�@�ł́A�Ȃ����̂܂܂̐S����ԂŎ��Ԃ��o�߂��A���ۂɕv����N���}���Ă��܂����ꍇ�ɂ́A�ǂ̂悤�ȓW�J�ɂȂ�̂ł��傤���B�ȂƂ��ẮA���Ԃ͋ɗ́A�������o������悤�ɂ��邩�A�t�ɁA�v�ɊO�ʼn߂����Ă��炤�悤���߂邱�ƂɂȂ�܂��B���̂悤�ɂ��āA�Ȃ�ׂ��v�Ɗ�����킹�Ȃ��悤�ɂ���킯�ł��B�������o������ꍇ�ɂ́A�K�����Ƃ��n�߂���A��̃T�[�N����{�����e�B�A�����ɎQ��������A���Ԃ̉Ƃ�n���������A������ӂ܂ʼn�����̃X�|�[�c�N���u�ɓ���Z������A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�v���O�o������ꍇ�ɂ́A�A���o�C�g����̃O���[�v�����������āA�����ʂ킹����A�Ђǂ��ꍇ�ɂ́A�ٓ����������āA���邢�́A�������������ɁA������[���܂Œǂ��o�����肷�邱�Ƃ�����܂��B
�@�����́A�Ƃ��ǂ����H���Ƃ��Ă����a�H�̓X�ɁA�Ћ��œX��v�w�ɘb�������Ȃ���A������@���œ��{��������ł���V�O��̒j�������܂����B�X��̘b�ł́A���O�ɗ��Ė�ɂȂ�܂ł����Ƃ���̂������ł��B�������A�����͂��Ă����̂ŏ����ɂ͂Ȃ���̂́A�悭�m���Ă���ߏ��̐l�ł��邽�ߒf�肫�ꂸ�A���̋q�̑̂͐S�z�ɂȂ邵�X�̕��͋C�͈����Ȃ邵�ŁA�����Ă���Ƃ������Ƃł����B���̒j�����A�Ƃɂ���ꂸ�A����Ƃđ��ɍs���Ƃ��낪�Ȃ����߂ɁA���̓X�ɋ������Ă���Ƃ������Ƃ̂悤�ł����B
�@�R�~���j�e�B�E�Z���^�[�ɋ߂�A50��㔼�̂��鏗���́A���̂��ƂɊ֘A����A���ɋ����[���b�����Ă���܂����B�S�ق��g���C�x���g���\�肳��Ă������̒��̂��Ƃł��B�����̃T�[�N���ɏ�������j���O���[�v���A���̓��ɕ������g���Ȃ����Ƃ����O�������߂��A�����̗j�����Ƃ������ƂŁA�Z���^�[�ɂ���ė��܂����B���������̏������A�����͊ق����p�ł��Ȃ����Ƃ�`����ƁA�j�������݂͌��Ɋ�������킹�A�u�����ɂ͋A��Ȃ��v�ƌ����āA�[���ȕ\��ɂȂ�܂����B���̗l�q���������̏����́A�����Ɏ�����@���ē���A���Ƃ��H�ʂ��ĕ�����p�ӂ����̂������ł��B���̃O���[�v�̂悤�ɁA�������A�Ȃ̗v���ɉ����ĂЂƂ��щƂ��o����A�[���ɂȂ�܂ŋA��ł����A�ǂ����Ŏ��Ԃ��Ԃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��j�������́A�����炭����قǒ������Ȃ��Ǝv���܂��B
�@��ʂɂ́A�����̏Ǐ�́A�g�X�g���X�h�ɂ����̂ƍl�����Ă��܂��B�Ƃ��������A����ȊO�̍l�������́A�����㑶�݂��Ȃ��̂ł��B���̂��߁A���̂悤�Ȍ`�ŏǏo��A����́A�v���X�g���X���ɂȂ��Ă��邽�߂��A�ƒf�肳��Ă��܂��킯�ł��B���������X�g���X���_��PTSD���_�̖��_�ɂ��ẮA���z�[���y�[�W�́u�X�g���X���_�ɑ���ᔻ�v��uPTSD���_�̐�������₤�v�̃y�[�W���Q�Ƃ��Ă����������Ƃɂ��āA�����ł́A�S�����̏Ǐ�͌����Ƃ��čK���ے�ɂ���ċN������̂Ƃ��āA�b��i�߂܂��B��������ƁA�����̂ق����A�ꂠ����ƒ됶����厖�ɂ��Ă���A�����ɍK����������₷�����߂ɁA����ɑ���ے�������Ȃ�A���̌��ʂƂ��āA�v�Ƃӂ���ʼn߂����ŐS�g�ǏN����₷���Ȃ�A�Ƃ����\���������яオ���Ă��܂��B
�@�{�N�R���A����T�����ɁA�u�v�ɑ�������łق����Ȃ����v�Ƃ����L�����f�ڂ���܂����B���̒��ɁA���̖����������邤���Ńq���g�ƂȂ鋻���[�����Ⴊ�ڂ��Ă��܂��B��N��ڑO�ɂ����j�����A����܂Ŏd���ɐ�S���Ă��ĉƒ���ڂ݂Ȃ��������ƂȂ��A�ސE��́A�Ȃ�ׂ��Ȃƈꏏ�ɍs�����A�ӂ���ʼn߂������Ԃ��ɂ��悤�ƍl���A���̋C���𗦒��ɍȂɑł������܂��B�Ƃ��낪�A�Ȃ́A�u��N��͂��O�̍K����D�悵�����v�Ƃ����v�̌��t�����Ƃ���ɁA�{�肪�ꋓ�ɂ��ݏグ�Ă��āA�v�Ɍ������āA���̂悤�Ȕl�|�𗁂т����Ƃ����̂ł��B
�@�Ȃɂ����܂���g���O�̍K���h��I�@���̂���܂ł̐l���͂��Ȃ��ɂނ��Ⴍ����ɂ���Ă����̂�I�@�{���Ɏ��̍K�����v���Ȃ�A���܂�������ł��ꂽ�ق������ɂƂ��Ă͍K����I
�@��������v�́A���f���A�Ȃ����ׂ��Ȃ��ق荞��ł��܂��������ł��B���ꂪ�{���ɂ������Ƃ���̂��ƂȂ̂��ǂ����͂킩��܂��A�������Ƃ��Ă��������ӂ����ł͂Ȃ��b�ł��B�v�����f�����̂��A�ނ�͂���܂���B����܂ł̍Ȃ̓w�͂ɕ悤�Ƃ��āA��N��́A�u���O�̍K����D�悵�����v�ƁA�����Ɍ�肩�����̂ɑ��āA�\���Ƃ͐����̔������Ԃ��Ă�������ł��B�������A��������Ȃ���A�Ȃ��{��o�����Ƃ͂Ȃ������ł��傤����A�Ȃ�����悤�Ƃ���v�̌��t���A�Ȃ����{�������Ƃ����l�����Ȃ��ł��傤�B���̐S�̓����́A�f�C���E�y���U�[���A���E�I�x�X�g�Z���[�ƂȂ��������w�gIt�h�ƌĂꂽ�q�x�ɏ����Ă���A�w�Z�̒S�C����e�Ɉ��Ă��{�l���]����莆���A��e�Ɍ������Ƃ��̔����ƉZ�ӂ��ł��B���̈ꌏ����A��e�̓y���U�[������gIt�h�ƌĂԂ悤�ɂȂ����̂ł����B
�@�ڂ��͗L���V�ɂȂ��āA������葬�������ĕꂳ��̉ƂɋA�����B�ł��A�\�z���Ă����Ƃ���A�K���͒��Â����Ȃ������B���̏��͕�����j���Ď莆���J���A�����Ɩڂ�ʂ��ƁA����������B
�@�u�ց[���A�W�[�O���[�搶�́A���܂����w�Z�V���̖��O����������ւ�Ɏv���Ă����������Ă��B����ɂ��܂��̓N���X�ł��D�G�Ȑ��k�̂ЂƂ肾���āB�ӂ���A�����h�Ȃ̂˂��H�v
�@�ꂳ��͕X�̂悤�ɗ₽�����ɂȂ�A�ڂ��̊���w�ł��Â����B
�@�u���ꂾ���͂������蓪�ɂ���������ł����Ȃ����A���̂���Y�I�@���܂���������������āA�������ɂ悭�v���邱�ƂȂȂ��́I�@�킩�����H�@���܂��Ȃǂ������Ă����I�@���܂��Ȃ�āwIT�x��I�@���Ȃ��̂Ƃ��������I�@�����̎q����Ȃ���I�@���˂����̂�I�@���ˁI�@�����������H�@���܂��I�v
�@�ꂳ��͎莆���т�т�ׂ��������ƁA������ނ��Ă܂��e���r�����͂��߂��B�ڂ��͂��̏�ɓ˂��������܂܁A�����Ƃɐ�̂悤�ɎU������莆�̎c�[�����߂��B
�@���܂ł����āA�����悤�Ȃ��Ƃ͉��x������Ԃ������Ă�������ǁA����̇�IT���Ƃ������t�قǎc���Ȍ��t�͂Ȃ������B�i�y���U�[�A1998�N�158-159�y�[�W�j
�@���������o�߂�����ƁA��e�̑ԓx�̗��s�s���Ƃ������A���ُ̈퐫���͂�����킩��͂��ł��B�K���ے�Ƃ����l���������炷��A���̗��s�s�����傫����Α傫���قǁA��e�́A�{�S�ł͎q�ǂ��̍K�������ł��邱�ƂɂȂ�܂��B�������A����͎����̈ӎ����犮�S�ɉB����Ă��܂��A�ُ�s���ƂȂ��Č����邱�ƂɂȂ�킯�ł��B���̂��߁A��e���g���A�ӎ��̏�ł́A�S�����R���킩��Ȃ��܂܁A���̏u�Ԃ���s������{�肪�Ђ����狭�����ݏグ�Ă���̂ł��B�������A���̎��ɁA�S�g�Ǐo�邱�Ƃ��悭����܂��B���̂悤�Ȍo�߂��炵�Ă��A�S�g�Ǐo������A�����ɃX�g���X������Ƃ����_���ɂ́A���͐��������Ȃ����Ƃ��͂�����킩��ł��傤�B
�@��قǂ̏T�����Ɍf�ڂ���Ă����v�w�̎���ł́A�u���܂�������ł��ꂽ�ق������ɂƂ��Ă͍K����v�Ƃ����Ȃ̌��t���ǂ���Ɏ��A�Ȃ̖{���ƌ��Ȃ��������ŋL����������Ă��܂��B�������A���̂悤�ȏ펯�I�Ȍ������������̂ł́A�^�̈Ӗ��ł��̖����������邱�Ƃ͂ł��܂��A���̂悤�Ȏ���̐������ł��܂���B
�@30�㔼�̂��鏗�����畷�����b�ł��B���̏����i�����j�́A���Ƃ��痣��ĂЂƂ�ŕ�炷�悤�ɂȂ�܂ŁA������e���珬���������A�炢�v�������Ă��������ł��B���̏��������Ƃ𗣂�Ă���́A��e�̍U���̖���́A���e�Ɍ�������悤�ɂȂ�܂����B���̂悤�ȏ̒��ŁA�O�o���̕��e���|��A�~�}�Ԃŕa�@�ɉ^���Ƃ����o�������N�������̂ł��B���̂��Ƃ�m�炳�ꂽ��e�́A�p�j�b�N�̂悤�ɂȂ��ĕa�@�ɋ삯���܂����B�K���Ȃ��ƂɁA���ƂȂ����̂ł����A���̒����́A�ʂ̈Ӗ��ŋ������ꂽ�̂ł��B�������X�����ɕ��e�ɏ��������������Ă����e���A���e���~�}�Ԃʼn^�ꂽ���Ƃ��ƁA�Ȃ���������Ăĕa�@�ɋ삯����̂����A�S�������ł��Ȃ������̂ł����B����Ƃ�����́A���e�ɖ�����̂��Ƃ�����ƁA�����̐������낤���Ȃ邱�Ƃ����ꂽ���߁A�ƍl����ׂ����ƂȂ̂ł��傤���B
�@���̎���ł́A��O�҂������Ă��A����قǂт����肵�Ȃ���������܂��A���̎���́A�����ł͂���܂���B40��̂���j���i���j�j���畷��������ł��B��e�́A���ɕ��e�̒�N��ɂ́A���������A����݂��Ƃe�ɂԂ��Ă��āA���e�͂�����A�������������āA���_�������ɖق��ĕ����Ă��������ł��B���q���猩�Ă��A��e�̌��t�͕����ꂵ�����̂ł����B�Ƃ��낪�A����Ƃ��A���̕��e���]�쌌�œ|�ꂽ�̂ł��B���̌��ʁA���e�ɔ��g�s���Ǝ���ǂ��c�������߁A�ӂ��肾���̕v�w�̐����́A���{����ύX��]�V�Ȃ�����܂����B���̎��_�����e�̑ԓx�͈�ς��܂��B���݂̉��F���ł́A�v���x�u�Ƃ����A�ň��̒i�K�Ɣ��肳��Ă��邻���ł����A��e�́A�������j���炱�̘b���܂ł̏��Ȃ��Ƃ��W�N�Ԃ́A���e���{�݂ɓ��������邱�ƂȂ��A�ݑ�̂܂܂����Ɖ�삵�����Ă����̂������ł��B�w���p�[�̗͂���A�f�C�T�[�r�X�𗘗p���Ă���Ƃ͂����A�v���x�u�̘V�l���A������N�V���Ă����e���A�W�N�Ԃ����͂ʼn�삵������̂́A�������Ă��̂��Ƃł͂���܂���B
�@��̎���ƈ���āA���̎���́A�v�ɂ������̂��Ƃ�����Ǝ��������邩��A�Ƃ������R�ōݑ���𑱂����Ƃ��������͐������܂���B�|���܂ŕv�ɏ������������������Ƃ̍ߖłڂ��̂��߂ɁA�ݑ�ʼn��𑱂��Ă���Ȃǂ̉\�����A�������l�����Ȃ��ł��傤�B���̎���́A�v�ւ̐[��������邽�߂Ƃ����l�����Ȃ��̂ł��B�ł́A�|���܂ŁA�A�����������������Ă����̂͂Ȃ����Ƃ����ƁA����܂Ő������Ă����Ƃ���A���������̂Ȃ���킴�Ȃ̂ł��B���̓_�͗������ɂ����ł��傤���A�Ȃ��炷��A�����Ȃ��s���s�����Ԃ����鑊��́A�����̕v��q�ǂ��������Ȃ��Ƃ����������l����A�����킩��₷���Ȃ邩������܂���B
�@�v����̈���������邩�炱���A����ɂ���ċN���鎩���̍K���S���i������ӎ��I�Ɂj�ے肷�邽�߂ɁA�v�ɑ��邤��݂���肠����Ƃ������ƂȂ̂ŁA���̂���݂͋t����݂Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����āA�����v�ɂԂ���Ƃ��������̍s�������邱�Ƃɂ���āA�v�Ɉ���ȂǕ����Ă��Ȃ����Ƃ��A�����̈ӎ��ɏؖ����悤�Ƃ��Ă������Ƃł��B
�@�����W�ɂ��鏗����V������̏����́A�A���A���l��v�ɏ��������������邱�Ƃ͂܂��Ȃ��͂��ł����A�t�ɁA���̗��l��v���|��Ĕ��g�s���ɂȂ����Ƃ�����A�ǂ��ł��傤���B�W�N�Ԃ��ݑ�ʼn�삪����������̂ł��傤���B�������A���ɂ͂ł��������邩������܂���B����͂���Ŕ��k�ɂȂ�ł��傤���A���̏ꍇ�ɂ́A���l�Ƃ̊Ԃ́A���邢�͕v�w�̊Ԃ̐[������Ɋ�Â��s���Ƃ������́A�`���ӎ��̂悤�Ȃ��̂��A���̍���ɂ���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�ȏ�̌�������A��������ƁA�[������Ƃ́A�ǂ����ǂ̂悤�ɈႤ�̂��Ƃ������Ƃ��܂߂āA���Ĕ�Ȃ���̂ł��邱�Ƃ��A�����Ȃ�Ƃ����炩�ɂȂ����悤�Ɏv���܂��B�����܂ł͂悢�Ƃ��Ă��A�ސl���̏ꍇ�Ƃ͑傫���قȂ��Ă���A�l�Ԃ̈���̋N���́A���������ǂ��ɂ���̂ł��傤���B
�m���Q�n�@���m�̂悤�ɂ킪���ł́A���ɂȂ�܂ŏ����ɂ͎Q����������܂���ł����B���݂ł��A�����ɎQ�������Ȃ����́A�C�X����������M���ɂ���������܂��B���m�ł��A�g���R�E�����E�����h�̍��ł���͂��̃t�����X�ɂ���A����E�����1945�N�܂ŁA�X�C�X�Ɏ����Ă�1971�N�܂ŁA�����ɎQ����������܂���ł����B
�m���R�n�@���̌X���́A���ɂ���a����l�����ɂ��킾���Č�����悤�Ɏv���܂��B�������������́A�W�����Y�E�z�v�L���Y��w��w���̃L�������C���E�g�[�}�X�������A��w���⑲�ƌ�̈�t������Ώۂɂ��Ē����ɂ킽���Čv��I�ɍs�Ȃ����u�O�����v�����iThomas, 1974�j���͂��߂Ƃ��邳�܂��܂Ȍ�����ʂ��āA���v�I�Ȋp�x��������Ȃ薾�m�ɂƂ炦���Ă��܂��B
�m���S�n�@�������A��O�I�ɂ͔��ɂӂ����ȊW������܂��B�{�肩��͏��X�͂���܂����A���Ƃ��Ȃ��A������Q�҂ŋ������ׂ�����ɂ���Ƃ������ƂŁA���ƕv�̈��l�Ɛe�����Ȃ�A�݂��ɂ��������ڂ������A�ӂ���ŗ��s�ɍs���قǂ̊ԕ��ɂȂ����Ƃ���������m���Ă��܂��i���̎���ł́A���ۂɍȂ����̈��l��S���Ö@�ɂ�Ă��Ă��܂��j�B�܂��A���鏗���́A���N���ۂ��Ă����Ȏq����j���ɂ��āA���̒j�����u������ɗ₽������Ȃ�A���͋����Ȃ��v�Ɣ������Ă��܂��B���Ԃ͍L���̂ŁA�Ȃƈꏏ�ɉ�������悤�Ȉ��l�����Ȃ����Ƃ͂Ȃ��ł��傤���A�����Ƃ��Ă��A�����܂œ���ȗ�O�ł��邱�Ƃɕς��͂���܂���B
�m���T�n�@���m�Ɍ����ƁA�ʏ�̃V���b�N���Ȃ������킯�ł͂Ȃ��A����Ƃ͕ʂɁA�K���ے�Ɋ�Â��g�����h���N�����Ă���A���̂ق����ʏ�̃V���b�N�����͂邩�ɑ傫�������Ƃ������Ƃł��B
�m���U�n�@�������A�����œ����o���Ă��܂��Ȃ�����͂��ł��B�������A���̏ꍇ�ɂ��A����Ȃ����߂Ƃ������́A����̔ے�̌��ʂƍl�����ق����A�����ɋ߂��悤�Ɏv���܂��B
�m���V�n�@�c��̐���̒j���Ƃ��̍Ȃ�Ώۂɂ���2004�N�ɍs�Ȃ�ꂽ���̒����ł́A�v�̂U���O�オ�A��N��͎d������߂āA�C�܂܂ɂ̂�т肷���������A�Ɠ����Ă���̂ɑ��āA�Ȃ̑��́A�u�ł���r�W�l�X�ɂ������v���Ƃ�v�ɋ��߂�䗦��73.5�p�[�Z���g�A�u�l�Ƃ̌𗬂���ɂ��Ăق����v�ƍl����䗦��60.3�p�[�Z���g�ɂ��̂ڂ��Ă��܂��i���G���_�[�r�W�l�X���i���A2004�N�j�B�v����ɁA�v�̊�]�Ƃ͗����ɁA�v�ɂ͊O�ɂ��Ăق����Ɗ肤�Ȃ������Ƃ������Ƃł��B


