

前回は丸山狼煙場で幕営しましたので、今回はここから関ケ原を巡り、養老公園を目指します。
関ケ原は西暦1600年にいわずと知れた天下分け目の大戦(おおいくさ)が行われたところ。
遥か昔には藤古川の合戦でやはり天下の情勢を分ける戦いが繰り広げられた地でもあります。
それだけに、説明しきれないほどの名所旧跡がひしめいているところです。
また、近年は日本の大動脈である東海道線・新幹線・名神高速道路が通る交通の要衝となっています。
昔も今も日本の西と東を繋ぐ接点となっている地理上の重要なポイントなのです。
丸山狼煙場は関ケ原の戦いの時に東軍の武将である黒田長政が合戦開始の合図である狼煙を上げたところです。
ここを下ると、すぐに中田池・小栗毛池・八幡池の三つの池の周りを巡ります。
この池とその周辺は、後に出てくる関ヶ原エコミュージアムのエコフィールドになっています。
国道21号線バイパスをくぐると、広い耕地に出てきます。
その耕地の中に立つひときわ高い石碑が関ヶ原決戦地の碑です。
笹尾山を下りてきた石田三成の軍がこの地で黒田長政・細川忠興の軍と果敢に戦いましたが、あえなく敗走しました。
西軍の大将が敗走した地であるところから、決戦地となっています。
決戦地の間近にある小高い丘が石田三成が陣地を敷いた笹尾山。
笹尾山を下り国道365号を渡ったところで集落の中を進みますが、この中に島津義弘が陣を敷いた場所があります。
ルートは国道に沿って進み、関ヶ原の戦いを史実に基づいて再現した関ヶ原ウォーランドの脇を通ります。
関ヶ原エコミュージアムは関ケ原の豊かな自然をテーマにした博物館で、関ヶ原のもう一つの魅力的な素顔を楽しむことが出来ます。
二階のハイビジョンシアターでは「東海自然歩道の旅」という映像記録を見ることも出来ます。
エコミュージアムの裏手の方へ続いているルートをたどると、城山への登り口に出ます。
この山は自然豊かな山として地元の子供達の格好の遊び場になっています。
大谷吉継の陣跡、常盤御前の墓の標識を見ながら進むと東海道線をくぐって旧中仙道の関ケ原の宿場町を通ります。
国道21号線を渡るとすぐに藤古川を渡る橋に出ます。
この藤古川は古くは関の藤川といい、西暦672年の壬申の乱ではこの川を挟んで東の天武天皇(大海人皇子)軍と西の弘文天皇(大友皇子)軍が対峙しました。
関ケ原の戦いの約1000年前にも、まさに天下分け目の決戦がこの地で行われたのです。
その名残として、川の東側の地区では天武天皇を奉って井上神社が建てられており、西側では弘文天皇を氏神としています。
藤古川の合戦は天武天皇軍の勝利に終わり、弘文天皇軍は総崩れとなって大津の近くの瀬田川の合戦で壊滅しました。
この壬申の乱を制した天武天皇が乱の後にこの要衝の地に設けたのが不破の関です。
越前の愛発の関、伊勢の鈴鹿の関と共に日本の三関と称され、平城年間まで兵を派遣したり、通行人を調べたところです。
関跡には資料館が建ち、不破の関の資料が展示されると共に、芭蕉の句碑も立てられ「秋風や薮の畠も不破の関」という句が刻まれています。
新幹線をくぐり井上神社の横を通り名神高速をくぐると松尾山に登ります。
松尾山は関が原の合戦の際に小早川秀秋が陣を敷いたところです。
この地における当初西軍に組していた小早川秀秋の動向が勝敗の鍵となり、午前中は戦を傍観していた小早川軍が午後に旗を翻して西軍に攻め込み東軍を一気に勝利に導きました。
松尾山からは関ケ原が一望の下に見渡せるだけでなく、正面には伊吹山が堂々とした山容を見せてくれます。
関ケ原を下ると今須川に沿って南下し、広瀬橋を渡ったところで御幸街道に入ります。
この街道は日本武尊が東征の帰り道に通った道といわれ、また皇族が養老の滝へ通った道ともいわれています。
御幸の字は行幸から来たもののようです。
そのためか分かりませんが、桜井白鳥神社や上方白鳥神社など、雅な名前を持つ神社が沿道に立っています。
桜井白鳥神社の境内に湧く泉はその昔桜の香がしたといいます。
竜泉寺や柏尾寺はその昔かなりの隆盛を誇った寺とのことですが、織田信長の軍に焼き討ちをされて今では廃寺として跡が残るのみです。
これらの寺は多芸七坊と呼ばれた寺群の跡で、柏尾寺跡から発掘されたという千体地蔵が当時の隆盛を偲ばせます。
養老の滝は天下に聞こえた名瀑ですが、その解説は次回に譲ります。
今回は約30km10時間の道のりです。

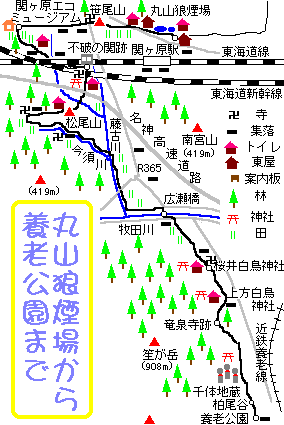

前夜は関ヶ原の町で一杯引っかけて帰ってきた後、ぐっすりと熟睡しました。
今朝もいつも通り早目の目覚ましで目覚めますが、暖かなシュラフの中で惰眠をむさぼり、結局テントを出たのは6時半頃でした。
テントを畳んで朝食を食べます。木立の間から空を見上げます。
今日もいい天気です。
朝食途中に初老の方がやってきました。
東海自然歩道を歩いておられる方です。今朝の列車でやってきたとのこと。
東から西へ向けて歩いておられるそうで、少し言葉を交わした後に先に出発なさいました。
出発は8時。丸山狼煙場の裏には中田池を始め3つの池があり、自然観察のための小屋が2つも設けられています。
朝の散歩をしていた親子連れと挨拶を交わします。
バイパスを横切って関ヶ原決戦地の碑に至ります。
周りに何もないところにぽつんと建っている様は、決戦地と名がつく割には拍子抜けの感がありますが、戦の時もかくアランという雰囲気はつかめます。
観光地というと周りにゴチャゴチャとした土産物屋や案内板が建っているという環境に僕は慣れてすぎてしまったのかもしれません。
このようにさりげなく碑だけが建っているというのも往時の雰囲気が味わえてよいのかもしれないなぁ、と感じました。
すかさず写真を一枚。
学校を回り込むようにして笹尾山の階段に至ります。
僕が笹尾山に至るのと時を同じくして一台の車が階段前の駐車場に停車し、学生らしき男二人連れが階段を登っていきました。
僕も続いて登ります。
さほど高くないにもかかわらず、頂上からは関ケ原が一望できます。
そして関ヶ原合戦陣形図が大きな看板になって建っています。
石田三成もここから味方の陣形を、そして徳川家康率いる東軍の陣形を見渡したのでしょう。
ここには石田三成陣地の碑が立っています。
先ほどの決戦地からここ笹尾山の山頂までは目と鼻の先です。
本当に戦の中に身を置いて指揮を執ったのだなぁということが実感としてしみじみ分かります。
このような場所で指揮を執るとなれば、戦国武将の武者震いもわかろうというものです。
先ほどの二人組みにお願いして関ヶ原をバックに写真を撮ってもらいます。
そして、石碑の前でも一枚。
さて、笹尾山の裏手へ降りると集落に入ります。
国道365号線を陸橋で渡るとすぐに、島津の陣地跡の標識が出てきます。
寄って行きたい気もしますが、ここはルートに従い集落の中を進みます。
集落の外れで道がよく分からなくなりますが、こういう時は地図とニラメッコして、それでも分からない時は適当に見当をつけて進みます。
ここまで歩いてくると東海自然歩道の感覚のようなものが出来てきて、適当な見当というのが結構当たるのです。
また、歩いていてもどうやらこの道はルートから外れているようだという怪しい匂いというのも何と無く分かります。
今回も適当な見当が的中し、難なく関ヶ原ウォーランドに至りました。
関ヶ原ウォーランドの中を見ていこうか、一瞬迷いましたが、テレビドラマなどで合戦模様は何度も見ていることだし、今回はパスしました。
それでもウォーランドの壁に沿って歩いていると場内の解説と言うのが風にながれて聞こえてきます。
その解説を聞くだけで入場した気分になって歩を進めました。
一旦、365号に沿った道になりますが、すぐに離れて車道に沿った道を進みます。
この車道は交通量も少なく、のんびり歩けました。
先にログハウスのような建物が見えてきました。
地図にあるビジターセンターでしょうか。
果たして建物には『エコミュージアム関ヶ原』と書いてあります。
そして建物の脇に標識がありここからルートが折れています。
名前は変わっていますが、ここがポイントの建物でしょう。
一休みするために建物に入ろうとして、ふと振返りました。
その時、雄大にそびえる伊吹山の姿が僕に迫ってきました。
僕は彦根というここから山一つ越えた地で大学時代を過ごしました。
毎日毎日、琵琶湖の上でウィンドサーフィンに明け暮れていました。
そして、琵琶湖の波に揺られながら湖を紅く染めて沈む夕日と白く輝く彦根城と雄大に聳える伊吹山をよく飽きもせず眺めたものです。
母なる琵琶湖と父なる伊吹山に育まれて過ごしたといってもよいでしょう。
その伊吹山が、こうして目の前に現れたのです。
ここまで歩いてきたんだ・・・・
懐かしい懐かしい伊吹山の姿は、あらためてここまでの遠い道のりを実感させました。
僕は伊吹山に向かって、思わず「ただいま」と呟いていました。

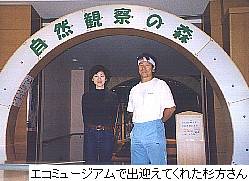 エコミュージアム到着は9:20。
とてもきれいな施設で、誰もいないせいか広々した感じです。
カウンターの中にうら若き女性が一人いました。
ひとまず荷を下ろし、カウンターに行って何があるのか物色します。
絵葉書があったので購入。
それをきっかけに、その女性・杉方さんと話が始まりました。
スタンプがあったので、それを絵葉書に押しながら、東海自然歩道を歩いてここまで来たことなどを話しました。
エコミュージアム到着は9:20。
とてもきれいな施設で、誰もいないせいか広々した感じです。
カウンターの中にうら若き女性が一人いました。
ひとまず荷を下ろし、カウンターに行って何があるのか物色します。
絵葉書があったので購入。
それをきっかけに、その女性・杉方さんと話が始まりました。
スタンプがあったので、それを絵葉書に押しながら、東海自然歩道を歩いてここまで来たことなどを話しました。
丁度パソコンが置いてあったので、そこでこの東海自然歩道膝栗毛HPにアクセスしました。
こりゃいいやということで、そこから早速弥次喜多芳名帳にアクセスし、書き込みをします。
自分のパソコン以外からここに書き込みをしたのは初めてです。
エコミュージアムはたった今開館したばかりで、まだ施設の電源も入っていないとのことでしたが、僕が来たので早速電源を入れてくれて、どうぞ中をご覧くださいということになりました。
その間に今度は彼女が弥次喜多芳名帳に書き込みをすることになりました。
展示を見終わると、今度は東海自然歩道のハイビジョン映画があるというので、二階のシアターで見せてもらうことにしました。
シアターを一人で貸し切りにしてゆっくり見せていただきました。
それから彼女が煎れてくれたお茶をすすりながら絵葉書を友人宛てに2,3通書き、すっかり仲良くなった杉方さんと写真を撮ってエコミュージアムを後にしました。
彼女の気持ちのいい応対のおかげでとても居心地がよく、すっかり長居をしました。10:20に再びスタートです。
しばらくは伊吹山を仰ぎ見ながらの道です。
頂は雲に隠れてしまいましたが、伊吹のお山だと思うと胸に迫るものがあります。
と、何やら道に落ちています。
取りあえず拾ってみると、ニッチマップの東海自然歩道の地図です。
誰が落としたものか分かりませんが、こんな処でゴミになってしまうのも惜しいので拾っていくことにしました。
今日は今までウォーカーとすれ違っていませんし(だから僕と逆行する人が落とした物ではないでしょうし)、先行する誰かが落としたとしても取りに戻ってくればすれ違うはずです。
もしかしたら、今朝丸山狼煙場で会った初老の方の落とし物かもしれません。
城山への登り口を左に見て、大谷吉継の墓の標識を右に見て、東海道本線をくぐって山中地区に出てきました。
このへんは旧中仙道の宿場町です。
国道を陸橋で渡ると、藤古川に差し掛かります。
ここの橋には、藤古川の合戦に関する解説が書いてあります。
だれしもそうだと思うのですが、壬申の乱という大乱があり、その乱に勝った天武天皇が徳政を行ったということは史実として知っていますが、その乱の雌雄を決した地がこの関ケ原にあるとは知りませんでした。
今回、出発に先駆けてルートを研究する際にその史実を知り、この藤古川もちゃんと見てこなくちゃなと思っていました。
今は何の変哲もない川ですが、この川は過去二度にわたって大乱で血に染まったのだということを思うと感慨を覚えます。
その名残が藤古川の支流に黒血川という名前で残っています。
藤古川をわたるとすぐに不破の関跡につきます。
不破の関跡資料館には入場するつもりはなかったのですが(時間の関係もありましたし)、受付の女性にハイカーが来なかったかを尋ねてみました。
先ほど拾った地図の落し主の手がかりがないか、ひょっとして資料館の中にいないかと思ったのです。
しかし、残念ながら手がかりはえられす、資料館の前で休憩をして先に進むことにしました。

不破の関跡資料館を出て、細い露地に入ります。
塀越しに関跡を覗きます。
じつは、資料館の場所に関があったわけではなく、資料館の向かいの病院の敷地内に関があったのです。
それで、出来れば病院の敷地に入って関跡を見たかったのですが、あいにく休院らしく敷地に入ることは出来ませんでした。
せめてもと思い、塀越しに覗いたわけです。
そんな僕を見て路地を挟んだ家のおじさんが庭仕事の手を休めて声をかけてくれました。
関跡も今は病院の持ち物で、開院していれば自由に見せてくれるんだがなぁと一緒に残念がってくれました。
ここを過ぎると路地は上下に分かれます。
標識がないのでしばし迷いますが、それぞれの道の様子をうかがって、どうやら下の道らしいと判断をくだし下を進みます。
この選択は合っていて、新幹線をくぐりました。
東海道本線に続いて日本の幹線をもう一つ越えたわけです。
左手に井上神社があります。
神社からは湧き水がこんこんと流れ出ています。
飲用適とあるので、水筒にたっぷり詰め込み、ついで喉を潤します。
冷たくって美味しい!
もう少し進むと、今度は名神高速道路をくぐります。
これで3つの幹線を全て越えたことになります。
折りしも高速道路は渋滞中。
車中の人の顔が見えます。
皆こちらを見ています。
重荷を背負ったトレッカーというのも珍しいのでしょう。
松尾山の登りにかかります。
道はよいのですが、ひたすら登る道です。
休みをいれずに一気に登ってしまいました。
汗をかきかき、黄色い幟のはためく山頂に到着です。
思ったより大勢のハイカーがいました。
時間も丁度お昼時。空いているベンチを見つけて昼食を作ります。
関ケ原を一望しながらのランチは美味です。
隣の高い山が南宮神社のある南宮山、霞んでいる低い山が桃配山でしょうか。
正面に目をむけると、伊吹山が山頂から霞んできてしまいました。
この山頂に独りで来ていた観光客のおばちゃんが話し掛けてきました。
歴史好きなおばちゃんで、千葉からやってきて今回は近江を中心に歴史的なポイントを回っているとのこと。
近江にはチョットうるさい僕との会話も弾みます。
湖東三山、近江八景、彦根・長浜・膳所の城等々、近江の名所を挙げれば切りがありません。
何だかんだ長話になってしまいました。
最後に、シャッターを押してもらって別れました。
12:45に再スタート。一気に平井集落まで下ります。
集落に出てからは舗装路です。
今須川に沿ってひたすら歩きます。
市町村が変わって関ヶ原町から上石津町になりました。
と、ここにも平井集落がありました。
ルートは集落の中を通ります。
橋の上に佇むお兄ちゃんがいたので挨拶をして言葉を交わします。
親戚の家に来たのだが、不在とのこと。
別れてしばらく歩くと先ほどのお兄ちゃんが車で追いぬきざま
「頑張って下さい!!!」
と大声で声援を送ってくれました。

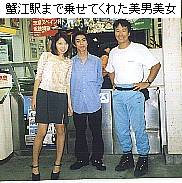 再び道は今須川沿いになり、川を見下ろす高台を進みます。
車を止めてなにやら採っている御夫婦がいます。
近づいて聞けば、崖に這っている蔦を採って飾りを作るとのこと。
蔦なら採って喜ばれることはあっても怒られることはありませんねと話すと、御夫婦揃って笑って下さいました。
この後夫婦も後ほど軽自動車で歩いている僕を追い抜く時に手を振ってくれました。
再び道は今須川沿いになり、川を見下ろす高台を進みます。
車を止めてなにやら採っている御夫婦がいます。
近づいて聞けば、崖に這っている蔦を採って飾りを作るとのこと。
蔦なら採って喜ばれることはあっても怒られることはありませんねと話すと、御夫婦揃って笑って下さいました。
この後夫婦も後ほど軽自動車で歩いている僕を追い抜く時に手を振ってくれました。
藤古川沿いに出てきます。
ここから川沿いの並木道を歩きます。
地道ならばよいのですが、ズーッと舗装路なのでいい加減足がしびれてきました。
遠くに見える名神高速を飛ばす車の恨めしいこと。
並木の下で何度も休憩をはさみながら歩きつづけました。
広瀬橋のたもとの小公園で休憩します。
ここで交通量の多い車道と合流しますので、休んでいても信号待ちで止まっている車の中からの視線を感じます。
東海自然歩道を歩いていて辛いことの一つに、交通量の多い車道を歩くということがあります。
車が気になるということもあるのですが、それよりも車に乗った人たちが僕のことを、
「大きなリュックを背負って、なんでこんなとこ歩いてんのやろ?」
という目で見るのです。この視線が何とも辛い。
ここまで歩いてきて、一人きりの幕営や料理、沿道の人に水をもらったり道を聞いたりすること、夜行列車の旅など、色々なものに慣れてきましたが、この視線だけはどうしても慣れることが出来ません。
この広瀬橋の休憩もあまり気持ちのよいものではありませんでした。
さて、好奇の目に晒されながら広瀬橋をわたります。
このまま養老まで車道歩きかなぁと思いきや、しばらくすると沢田の集落から車道をそれて山道に入っていきます。
やれやれ一安心。
しかし、今度は時間が心配です。
うかうかしていると、養老公園に着くのが夜中になってしまいます。
墓地を2箇所通って(水道が壊れて水が出しっぱなし)、集落に出てきかたと思ったら、すぐにまた山道に入ってしまいました。
ここから美濃津屋までの区間、ルートは車道と平行して通っているので比較的平坦な道かと思っていたのですが、結構なアップダウンが続きそうな気配です。
涸れ沢をわたり桜井白鳥神社に出てきたのが16:30。
ふらふらした足取りでお参りだけして鳥居の脇にある清水の横に腰を下ろします。
清水では向かいの家のおばさんが野菜を洗いに来ていました。
少し話したら、養老公園まではまだまだ距離があるとのこと。
この時点の足の状態から、明日まで歩くのはチョットきついと判断し、今日の歩行で切り上げる腹を固めました。
三重県突入は次回にお預けです。
今日切り上げるにしても、交通の便を考えると養老公園まではとにかく歩かなければなりません。
清水をペットボトルに詰め込んで出発。
上方桜井神社を経て公園の裏から再び山道です。
ここからの山道が疲れきった体にとても堪えるえげつない道でした。
細い急坂の上に岩がごろごろ転がっていて足の裏が痛くなります。
”なんのために登らせんのや!"
と文句も出てくる山道をゼイゼイハアハア息を荒げながら登ります。
登り切ったところにあったのは竜泉寺跡の看板だけ。
"なんもないやんけ!"
と行き所のない不満が言葉になって出てきます。
日吉神社に出て、暗くなった道を更に南下します。
と、暗い中に小さな山のようなものが現れました。
何だろうと薄暗い中で目をこすってよーく見ると、仏様がたくさん集まって山のようになっています。
先を急ぐ余り通り道に何があるのか忘れていましたが、これが多芸七坊の千体仏でしょう。
明るい中で見ればさぞ感慨深いのでしょうが、暗い中で見ると少々怖い感じがします。
手を合わせて先に進みました。
神明神社を経て林道に出てきました。
この地点に標識はなく、林道を登るか下るか二者択一になりました。
少しだけ登って偵察しますが、暗い中で標識も見当たらなかったので、下りに入りました。
長い林道を下って出てきたのは養老公園ならぬ養老バーベキューという店でした。
変なところに出てきちゃったなと思いましたが、相当疲れてもいたので取りあえず荷物を降ろし、犬を連れたおじさんに養老公園の在処を尋ねました。
するとまた一旦登らなければならないとのことで、先ほどの林道での二者択一は登りが正解であったとわかったのでした。
しばらく休んで意を決めて、林道ではなく舗装道路を登ることにしました。
住宅の脇を抜け養老温泉の旅館前を抜けて、ようやっと養老公園の標識に出てきました。
ここで今日はおしまいにしよう、そう決めて荷を下ろしました。
既にすっかり日が暮れて真っ暗です。
急がないと名古屋発の東京行きの最終の新幹線に間に合いません。
振返ると、上の方からRV車が下ってきました。
ダメモトで親指を立てて手を挙げると、な、なんと止まってくれたではありませんか。
とりあえず、近鉄養老駅まで乗せて欲しいというと快くOKの返事。
喜び勇んで荷を持ち込んで乗り込みます。
乗せてくれたのは名古屋の近くの蟹江まで帰るカップル。
話すうちに、蟹江まで乗せてくれることになりました。
3人でワイワイ言いながら蟹江まで同道しました。
下ろしてもらって明るい中でカップルを見ると、なかなかの美男美女。
本当に有り難うございました。
新幹線で東京に帰ってきたのは夜の11時。
今回は、大津谷公園までのヒッチハイクに始まって、蟹江までのヒッチハイクに終わった、とてもラッキーな2日間でした。

丸山狼煙場はじめ、関ヶ原の各所に行くにはJR関ヶ原駅からの歩きになります。
この一体はとても見所が多いので、歩いていても飽きませんし苦にならないでしょう。
ルート上で分かり難いところといえば、笹尾山から関ヶ原エコミュージアムへ至る間の個所でしょうか。
集落の外れで道がY字路になっています。
ここは左に進みます。ちょっと分かり難いところに標識がありますので注意して下さい。
関ヶ原ウォーランドに出て、塀に沿って進みます。
ウォーランドの入り口の方へは行かないように(もちろんウォーランドに寄っていく方は別ですが)。
突き当たりを右折してバイパスの下に出て、ここを左折して道なりに進むと車道にぽっかり出てきます。
この間、標識がとても少ないので歩いていて不安になります。
出来れば地図を片手に歩いたほうがいいかもしれません。
エコミュージアムは古い本やニッチマップの地図では「ビジターセンター」と書かれていることが多いと思います。
何時かは分かりませんが、比較的最近に建替えられて、自然観察のための施設となったのでしょう。
エコミュージアムで一息ついて杉方さんに挨拶したら、裏を通るルートを進みましょう。
このあたり、車がうち捨ててられていたり、ちょっと殺伐としたところを通りますが、山肌に沿うようになったら是非北を見て下さい。
伊吹山が雄大に聳えています。ここからの伊吹山は絶品です。
地道はすぐに舗装路になり、松尾山の麓まで続きます。
ここからは標識は少ないものの道なりに進めばよいので迷うことはないでしょう。
途中、大谷吉継の墓や常盤御前の墓などに寄って行くのも一興でしょう。
国道21号線を越え、不破の関跡で折れ、細い道に入ります。
この細い道は文中にもありますが直ぐに二手に分かれます。
左手が上に向かう道、右手が下に向かう道です。
ここは右手を進みましょう。
新幹線をくぐって井上神社に出てきます。
松尾山はなかなか急な山です。
しかし、しっかりとした登山道がついており、気持ちいい歩行が出来るはずです。
松尾山から下ると平井の集落に出ます。
ここは下りきったところのT字路で左折します。
回り込むような形で今須川沿いの太い車道に出てきます。
ここは標識がないだけに、西からやってくると分かり難いと思います。
西から来た際には右手に平井の集落が見えてきたところで、車道が今須川をわたるための立派な橋が架かっているのですが、ここの手前で右折するようにして下さい。
するとお寺(聖蓮寺)のほうに向かいます。
今須川沿いに進み、藤古川に合流したら後は川沿いの並木を進みます。
ここから広瀬橋まではずっと川沿い。
広瀬橋で川を渡ると左折して、程なく地道に入ります。
ここからは集落に出たり、また山に分け入ったりの連続です。
しかし、標識はしっかりあるので道に迷うことはないでしょう。
ニッチマップを見るとほぼ平坦な道を行くように見えますが、とてもアップダウンの激しいルートですので、それなりの覚悟をしていって下さい。
また、僕の靴にもついていたのですが、山ヒルもいるようです。
ここから養老公園までの間、いくつかの涸れ沢を川底に降りる形で渡ります。
ですから、降雨時と降雨後は渡れなくなる可能性もあります。雨の前後はご注意下さい。
関ケ原を越えると交通の便が悪くなります。
国道沿いには近鉄バスも走っているようですが、どれだけの本数があるのかは分かりません。
養老公園に出れば近鉄養老線で大垣か桑名に出るとよいでしょう。
また、宿泊施設は関ケ原に多数あるほか、養老公園周辺にも温泉旅館が多数あります。
詳しくは、名阪近鉄バス(0584-81-3328)、関ヶ原町商工観光課(0584-43-1111)、上石津町開発事業室(0584-45-3111)、養老町産業観光課(0584-32-1100)にお問い合わせ下さい。

