 �T�C�g�}�b�v�@
�T�C�g�}�b�v�@



 �@���]�\�\�R�D�w���҂ƉƑ��̂��߂̐��_�����a���_�x
�@���]�\�\�R�D�w���҂ƉƑ��̂��߂̐��_�����a���_�x


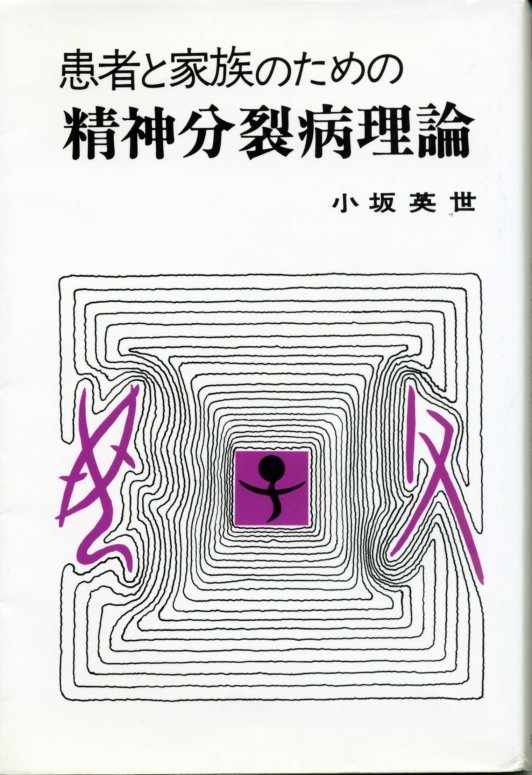
�w���҂ƉƑ��̂��߂̐��_�����a���_�x�i��^���[�A1972/4/20 ���s�j
����p���i���j
�l�Z���A293 �y�[�W

�@�Ō��͎�^�i���܁j���[�ŁA�O���i�w���_�����a�̎Љ���w���x�j�̕ҏW��S�������㓡��^�q���A��w���@����Ɨ����āA�����搼�Ђɋ������o�ŎЂł��B����܂Ō㓡�́A��w���@�����s����w�ی��w�G���x��w���Y�w�G���x�̕ҏW��S�����Ă���A���҂����̂Q���ɋL����A�ڂ��Ă������ŁA�O������і{���̏o�łɎ������̂ł��傤�B��Q���܂Ŕ��s����A��������Ă����m���P�n�̂ŁA�����̔���s���͈����Ȃ������͂��ł��B���ҁA�Ƒ���A�n��Ő��_�q�����������Ă����ی��w�m���Q�n����ȓǎ҂������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�{���́A�ʏ�̏��Ђ̔��^�i�l�Z���A�\�t�g�J�o�[�j�ł����A�܂��������p���̂悤�ɁA��ʂ̏��ЂƂ��Ă͈ٗ�̑傫���̊����i10.5�|��15�p�j�ł������Ɓi13�s�w36���j�g�܂�Ă��܂��B
�@�{���Ő�����Ă���̂́A�J�o�[�̊G�������Ă���悤�ɁA�c��e�ƕ��e�̉e�������킶��ƁA�������瓦��悤�̂Ȃ��q�ǂ��ɋy�сA���ꂪ�����ł����ꕪ���a�a����Ƃ����A���ɂ킩��₷�����_�ł��B�����ł͎����s�҂Ƃ��Ă悭�m���Ă��܂����A�����̎q�ǂ��ɑ��āA���Ȃ�ߍ��ȁA�ꍇ�ɂ���Ă͑����Ɉُ�ȑΉ�������e������̂͂܂���������܂���B�����a�̏ꍇ�������ŁA���̎���́A���N��ɏo�ł����w���_�����a�ǖ{�x�i1972�N�A���{�Ō싦��o�ʼn�j�ɂ͂������A��ɏI���ɂ킽���Ē��҂��������l�c�W�̓����̓��L�i�l�c�A2001�N�A��V�́j�ɂ��A��������Ƃ肠�����Ă��܂��B���ɂ́A�M���������قljߍ��ȋs�҂�����܂��B�Ƃ��낪�A���̊��Ҏ��g���A�e�������Ȃ���e�Ɉˑ�����Ƃ����A���҂� �g�����W�h �m���R�n�ƌĂ��L�̊W���A���̈���ő��݂���̂ł��B
�@���̒i�K�̏��◝�_�́A�����̃g���E�}���_�ƂقƂ�Ǔ����m���S�n�Ȃ̂ŁA������₷���͂��̗��_�Ȃ̂ł����A�����ɂ͂����ł͂���܂���ł����B���肪�����a�ƂȂ�ƁA������{�������Ă��邽�߂Ȃ̂ł��傤�B�N���y�����ȗ��A�]���̉��炩�ُ̈��z�肵�� �g�������h�m���T�n�Ƃ����`�e�����t����Ă��������a���A���҂̌o���Ɋ�Â����_�ɂ��A�S�����́A�������t�I�Ȏ����Ƃ������ƂɂȂ��āA�]���̂����闝�_�Ɗ��S�ɑΗ�����̂ł��m���U�n�B
�@���◝�_�̔��W�j�̒��ŁA�{���Ŕ��\���ꂽ�傫�Ȕ����́A�����������a�Ǐ�̌����ƂȂ� �g�}���h �̑��݂ł��B���̔����ɂ���āA����܂ł̎Љ���w���Ƃ��������K���Ɋ�Â����Ö@����A���◝�_�Ƃ��������a�̐S���Ö@���_�ւƑ傫������킯�ł��B���ꂾ���ł���ςȂ��ƂȂ̂ł����A���҂́A����܂Ŗ��z���ɂ���Ȃ��������@�_��̔��������Ă���̂ł��B
�@�]���̐��_��Â�S���Ö@�ł́A���ׂĂ���ϓI�Ȕ��f�Ɋ�Â��čs�Ȃ��Ă��܂����B�����ŋq�ϓI�ȕ��@���g����ȂǂƂ͒N�ЂƂ�v���Ă��Ȃ������̂ɑ��āA���҂́A�g�����h �Ƃ����q�ϓI�w�W�����݂��邱�Ƃ������̂ł��B�g�}�����ꂽ�����h ��T�钆�ŁA�g�̓I����������Ԃ��ώ@���ꂽ���ʂȂ̂ł����B����ȍ~�A���҂́A���̔�����ڈ�ɂ��� �g�}���h ���ꂽ������T��o���悤�ɂȂ�̂ł��B���҂̌����_�̓��ۂƂ͕ʂɁA�����Ƃ������ۂ����݂��邱�Ƃ͂܂���������܂���B����́A���S�ɍČ����̂��錻�ۂŁA�S���Ö@��_��Â̕��@�_��̑唭���ł��m���V�n�B�����g������ 40 �N�ȏ�ɂ킽���ē���I�Ɋώ@�������Ă����̂ŁA�����Ƃ������ۂ̑��݂�ے肷�邱�Ƃ͂��͂�s�\�ł��m���W�n�B
�@���̐S���Ö@�ɂ��ẮA���Ҏ��g���A�u�ق��Ɏ��Ɠ��������̈�t�k�́l���܂���v�i175�y�[�W�j�Ɩ������Ă��邱�Ƃ���킩��悤�ɁA�{�����o�ł��ꂽ1972�N�̎��_�ł���A���̎��×��_�𐳓��ɕ]��������Ƃ͂قƂ�ǂ��܂���ł����B�������A�{���ɓo�ꂷ����Ƃ��ЂƂ�����Ȃ��킯�ł͂���܂���B���_�̐����ɂ������͂��Ă�����Ă���Ƃ����A���҂̏I���̑��k����ł������͑����M�i�F�s�{��w�����w�����j�A���◝�_�̒ǎ����s�Ȃ����Ƃ�����������i���É���w��w�����O�q���w��������j�A���у��L�q�i���z�s�����ی��w�j�A����V�i�H��a�@�\�[�V�����E���[�J�[�A��̗�����w�����w�ȋ����B1948�|2010�N�j�̖��O���������Ă��邩��ł��B
�@���ɂ��A���҂�Ƒ��̋���̏�ł��鏬�⋳���ŏ���߂Ă���������i�������B�\�[�V�������[�J�[�j���A�{���ɂӂ��̎�����Ă��܂��B����ɂ́A�����A���̗��_�̗L�͂ȁu�����ҁv�ł������l�c�W�i�����s���_�q���Z���^�[���劲�B1926-2010�N�j���A���̗��_�ɉ��������Â��s�Ȃ������Ƃ�����A���̏��������p����Ă���̂ł��B�������Ȃ���A���Âɒ��ڂ������̂Ȃ��͑��������A���R�͂��܂��܂ł���ɂ���A��������܂��Ȃ����҂��痣��Ă��܂��܂��B�Ȃ��A�����Տ��̔��Ď҂ł������]�F�v��i�Q�n��w��w���������B1924�|1974�j�̖��O���o�Ă��܂����A���Ă̓��u�Ƃ��Ăł���A���̎��_�ł͒��҂͐����Տ���ᔻ���闧��ɂȂ��Ă��܂����i229�y�[�W�j�B
�@���̎��×��_�́A1961�N�ȗ��A�قƂ�ǁu�k��A���k�Ƃ�����i�����ʼn��Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������v����̈�t�������������ŊJ�����ꂽ�i21�y�[�W�j�ƒ��҂͏����Ă��܂����A���̒ʂ�Ȃ̂ł��傤�B�������A�w�s���̐��_�q���x�̃��r���[�ɏ����Ă������悤�ɁA���҂́A�����Ă��̂悤�Ȋ��̒��Ɏ����э��̂ł��B�ӎ��I�Ȃ��̂��ǂ����͂Ƃ������Ƃ��Ă��A�����ɂ͖��m�ȈӐ}���������͂��ł��B�{���́A��w�̒��ł́A����ƕ���ōł��傫�ȓ�ł��������_�����a�Ƃ�������̐��_�������S���I�����ɂ���ċN������̂ł��邱�Ƃ��A���̐S���Ö@���_��ʂ��āA���҂����߂Ė��炩�ɂ����m���X�n�Ƃ����_�ŁA���_��w�Ƃ�����������ɂƂǂ܂�Ȃ��A���j�I�ɏd�v�Ȓ���ł��邱�Ƃ͂܂���������܂���B
�@�{���́A�A�}�]�����u���{�̌Ö{���v�Ȃǂ�ʂ��ČÏ��Ƃ��ē��肷�邱�Ƃ͂ł��܂����A����}���قɂ��������Ȃ��قǂȂ̂ŁA�{�e�ł́A���c���Y�̎����i���c�A1998�N�A63�y�[�W�j�ɏ]���āA���e�Љ���܂߁A�Ȃ�ׂ����҂̌��t���g���ďڂ����������邱�Ƃɂ��܂��B
�@�`���ň��p����Ă��鎖��̑����́A����������b���d�v�ȃq���g�ƂȂ�A���퐶���̒��ŋN����o�����ɒ��ڂ������ʂƂ��Č@�蓖�Ă�ꂽ���̂ł��B�����̎���́A�w�s���̐��_�q���x������w���_�����a�̎Љ���w���x�̃��r���[�ɂ������Љ�Ă������̂ŁA�S�̂�����͎Q�Ƃ��Ă��������B����܂ł̒��҂́A���Ƃ��Θr���v�����čĔ��������҂ł���A�r���v���^���邱�ƂŏǏ������������ȂǁA�Ĕ���ɋ�̓I�ȉ������^����Ƃ����Ή��@���Ƃ��Ă����킯�ł����A�������������Ƃ�鎖�����ł͂Ȃ����Ƃ��A�܂��Ȃ����炩�ɂȂ�܂��B�����������邤���A���҂́A���҂�������Ĕ��Ɏ��炵�߂��o�������L�����Ă��Ȃ��Ƃ��������ɒ��ڂ���悤�ɂȂ�܂��i13�|14�y�[�W�j�B1970�N�ɓ����Ă���̂��Ƃł����B
�@�����ŁA�Y�ꋎ���Ă����o���������҂Ɏv���o�����Ă݂�ƁA���҂�Ƒ��݂̂Ȃ炸�A���Ҏ��g�������قǂ̎��Ì��ʂ�����ꂽ�̂ł��B��̓I�ȉ�����͕s�v���������ƂɂȂ�܂��m��10�n�B����́A�t���C�g���_�o�ǂ̊��҂Ŕ��������d�g�݂ƑS���������̂ł����B���̂��ߒ��҂́A���_���͂������ᔻ���闧��Ɋ��ɗ����Ă����ɂ�������炸�A�t���C�g�Ɍh�ӂ�\���A�����a�̊��҂��S���I������Y�ꋎ��d�g�݂ɁA���_���͗p��ł��� �g�}���h �Ƃ������t�Ă��̂ł����B���̎��_�ŁA�����Տ��O���[�v�Ɗ��S���Ԃ��������҂́A�u�Ĕ����Ă��}���̉������s�Ȃ��A��ʂ̃N�X�������@���s�K�v�ł���A�Ĕ��ɑ���S���I�����̂Ȃ��Ŋ��҂����炵�Ă����\�\�Ƃ��������̎��̎��Ö@�̌��^�v�ɓ��B�����̂ł��i14�y�[�W�j�B����Ԃ��ɂȂ�܂����A����́A�ЂƂ��ƂŕЂÂ��邱�Ƃ͂Ƃ��Ă��ł��Ȃ��A�܂������v���I�ȑ唭���ł����B
�@�����ЂƂv���I�������̂́A����܂ł̎��Î҂̖������A�Ƒ��⊳�Ҏ��g�ɗ^���悤�Ƃ������Ƃł��B���̂悤�Ȓ��z�́A�Y�ׂ͂Ă�̉ƂŊ��Ҏ��g���s�Ȃ� �g�����Ҍ����h �܂ŁA�����㑶�݂��܂���ł����B�������A���҂̕��@�̂ق����A�Ǐ�̌����T���ɏœ_���i���Ă���Ƃ����_�₻�̒Njy�̌������Ƃ����_�ŁA�����Ҍ������͂邩�ɂ��̂��ł��܂��B
�@���炭�̊Ԃ́A���͂��̕��@�̉��������̐ꖡ�ɐ����Ă��܂����B���҂��Y�ꋎ���Ă��܂��Ă���L�b�J�P�ƂȂ����ł����Ƃ����������Ă�̂ɂ͓�a���܂������A���̋�J�ƂĂ��A��u�ɂ��ďǏ�̏�����������m��11�n��ڑO�ɂ��ẮA�ǂ����ɔ��ł��܂��̂ł����B�k�����l
�@���̂������́A���������̐������炳�߂Ĕ��Ȃ��܂����B����ȂɊȒP�Ȏ�Â��Ȃ�A���҂̉Ƒ��ɂ��ł���͂������A��点��ׂ����\�\���������҂��Ĕ��������i�Y�ꋎ��ꂽ�j�ł����Ƃ́A�����������Ƒ��̕������A�m���Ă���͂������A�����ł��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂�����\�\���̕��@������ɐi�߂āA���Ҏ��g���ł����Ƃ�z���o���A�����Ŏ��������Âł���悤�ɂ��Ȃ���c�c�Ƃ����ӂ��ɂł��B�����ł���܂ōs�Ȃ��Ă����Ƒ�����A���ҋ���ɂ���ɗ͂�����悤�ɂȂ�܂����B�i14�|15�y�[�W�j
�@1971�N�Q���A���ɂ��܂�Ĕ��a�����Ƃ�����̎�������鏭�N���҂ɕ��������Ƃ���A���̏��N����F��ς��Ĕ�������Ƃ����o�����ɑ������܂��B���̏��N�����N�O�ɓ����悤�ȑ̌������Ă����̂������ł����A��������S�ɖY��Ă����̂ł����B�}�����N�����Ă������ƂɂȂ�܂����A�����ɂ͔��a���Ă��Ȃ������̂ł��B���̌o�����璘�҂́A���a�O�ɂ��}�����N���Ă��āA���̐ςݏd�˂������a�̔��a�ɂȂ���̂ł͂Ȃ����A�ƍl����悤�ɂȂ�܂��B�Ȃ����̏��N�́A�A���Ɍ�������̕���p���N���������߁A����ʂ𐔕��̂P�ɂ܂Ō��炳�Ȃ���Ȃ�܂���ł����B���̂��Ƃ���A�c�����ɋN�������}���̉������A���Â�i�߂邤���ő傫�ȈӖ��������Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ������z�����܂��̂ł��i16�|17�y�[�W�j�B
�@�c�����̗}���̉����ɒ��肵�A����ɐ������n�߂�Ƃ܂��Ȃ��A�V���ȋ^�₪���サ�܂����B�c�����̗}���̌��ɂ���_�̂悤�Ȃ��̂�����͂��Ȃ̂ɁA���ꂪ������Ȃ����Ƃł����B���炭���āA����� �g�e�̐S���I�ɂނ����d�ł��h �ł��邱�Ƃ��������܂����B���̌��ʁA�u�����a���҂̐e�����������Ă��� �g����炵���h �̍����v�ƁA�u���҂��e�Ɏ����G�ӂ̌���v���킩���Ă����̂ł��i17�y�[�W�j�B�Ƃ��낪�A�c�����̗}���� �g�e�̎d�ł��h �Ƃ����_�ŋ��ʂ��Ă���̂͂悢�Ƃ��Ă��A�Ĕ��̏ꍇ�̗}���ɋ��ʂ��Č����� �g��_�Ƃ�����Ղ��ł����Ɓh �Ƃǂ̂悤�ɊW���Ă���̂����͂����肵�܂���ł����B���炭���Ă킩���Ă݂�ƁA����� �g�e�̎d�ł��h �Ȃ̂ł����B���҂͍Ĕ��̒��O�ɁA�e�ɉ��������߁A���k�����m��12�n�̂ł����A�����Őe�́A�c�����̏ꍇ�Ɠ����悤�ȁu�ނ����d�ł��v�����Ă��邱�Ƃ��킩�����̂ł��i18�y�[�W�j�B�ł����Ƃ���_���A���̂��Ǝ��̂����Ȃ킯�ł͂Ȃ������Ƃ������Ƃł��B
�@���̐S���Ö@���_���A�}���̉������ŋ߂̍Ĕ�����n�߁A�����c�����̗}���ɂ܂ők��K�v������Ƃ����`�ɐ�����ꂽ�̂́A1971�N�̏��H�̂��Ƃł����i19�y�[�W�j�B�Ƃ��낪�A���_�������܂Ő������ꂽ���̍�����A���܂��܂Ȗ�肪��������悤�ɂȂ�܂����B���×��_��̓������͂��̊��҂������A�Љ�l�Ƃ��Ă͒ʗp���Ȃ�������������A���Âւ̒�R���������肷��悤�ɂȂ����̂ł��B�܂��Ȃ��A���l���̊��҂��Əo����悤�ɂȂ�܂����B�c�����̗}�����������A�e�����Q�҂ł��邱�Ƃ�m�������ł́A���͂�ꏏ�ɐ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����̂ł��B���̎咣�ɓ������ꂽ���҂́A�㌩�l��ۏؐl�Ƃ���������Ƃ�A���҂����̎����̌㉟��������悤�ɂȂ�܂��B

�@�������ĉƏo�����A���邢�͉Əo���������Ă��銳�҂����܂����Ă��邤���Ɏ��́A�������̂��ƂɋC�Â�����܂����B���ɂ�������̂́A�Љ�l�Ƃ��Ă͒ʗp���ɂ�����������������܂ł����O�ʂɏo�Ă������Ƃł��B���ɂ́A���̂悤�ȂƂ��Ɏ����Ƃ�̐ӔC�ɂ����Ă������ƁA�C�����V�C���a�ւ̓����������Ă������Ƃł��B��O�ɂ́A���ꂾ���e�݁A����ł��Ȃ���A�����ۂ��ł͐e�Ɉˑ����Ă��܂������X���������Ă������Ƃł��B��l�ɂ́A�厡��ł���A�㌩�l�A�ۏؐl�ł����鎄�̗��p�@���A�܂��Ƃɉ���ł���A�M���W�𗠐���̂��������Ƃł��B�i20�y�[�W�j
�@���̎������ɁA����Ö@�� �g���ʁh ���A����܂łƂ͎��I�ɈقȂ��Ă������Ƃ��킩��܂��B���҂��S���I������}�����Ă��邱�Ƃ���������A�}���̉��������Ö@�̒��S�ɐ��������_�ŁA���҂�����Ζ{�������킷�悤�ɂȂ����킯�ł����A����ƂƂ��ɁA�Ƒ��̑唼�����҂��痣��čs�����̂ł��m��13�n�B���̂��ƂɊ֘A���āA���҂́A�u���鎖����@��ɏ��a�l�\�Z�N�\�ꌎ�A���͐f�Ís�ׂ𒆎~���邱�Ƃɂ��܂����v�i21�y�[�W�j�Əq�ׂĂ��܂��B�����āA���҂ƉƑ��ɂ��̎��×��_�������邱�Ƃɐ�O�����t�ɂȂ�̂ł��B
�@�����ŏq�ׂ��Ă���u���鎖��v�Ƃ́A1971�N10���ɋN�������������w���Ă��܂��B���҂ւ̊m�ł���M���̂��ƂɌ`������Ă����͂��́u���������ڂ̉�v�Ƃ����Ƒ���A�s�v�c����܂�Ȃ��o�߂Œ��҂��痣�����čs�����̂ł��B���̉���炪�A����Ö@�̌��I���ʂ�ڂ̓�����ɂ��Ȃ���A�킸�����̂S������ɁA���҂��犮�S�ɗ������Ă��܂��̂ł��m��14�n�B���N�A������Ԃɂ������d�ǂ̕����a���҂ł��閅���A36 �N�O�̏o�������Q�ӂɂ킽���ĕ���������ʁA���̏�Ԃ��甲���o�����̂ł��B�������A����܂ł̍R���_�a��ł͋�������p���o��悤�ɂȂ������߁A�R�s�����ł��ނ悤�ɂȂ����Ƃ������I�Ȍo�������Ă����̂ł����i����A1971�N�j�B���̂�����̌o�߂ɂ��ẮA�w���_�����a�̎Љ���w���x�̃��r���[�̒��U�ł��ӂ�Ă������̂ŁA�S�̂�����͎Q�Ƃ��Ă��������B
�@���̂悤�ɂ��ď���f�Ï���p�~�������҂́A1971�N11���ɁA���҂ƉƑ��̋���̂��߂̏��⋳�����J�����܂��B�ŏ��́A����f�Ï��̌��������̂܂g���Ă��܂����i�{���o�ł̎��_�ł͂����ł����j���A���N�R���P���ɁA��k��S���ڂɂ���b�B�X���ɖʂ����}���V�����Ɉڂ�܂��i��}�Q�Ɓj�B1980�N���ɐ`��s���c���Ɉڂ�܂ŁA���҂͂����Ŋ��҂�Ƒ��̋���ɓ������Ă����̂ł��B
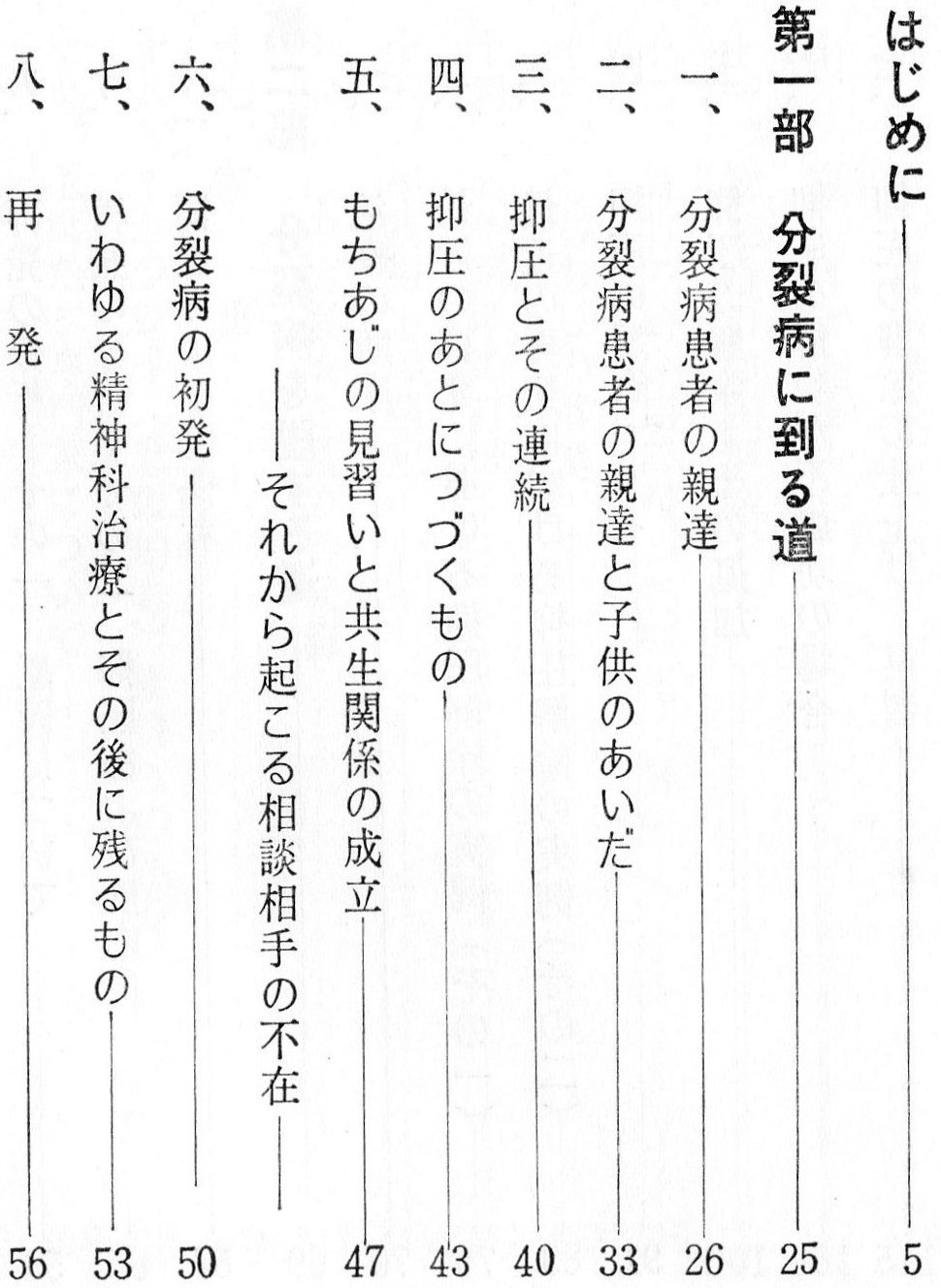 �@�ڎ�������Ƃ킩��ł��傤���A�{���́A�ȒP�Ɍ����A�u�����a�ɓ��铹�v�Ɓu�����a��E���铹�v�Ƃ����ӂ��̃Z�N�V�����𒆐S�ɓW�J����Ă���A����ɕ⑫��t�����\���ɂȂ��Ă��܂��B�S���Ö@��_��Â̂ӂ��̖{�ƈ���āA�����_���ŏ��ɒu����Ă���̂��傫�ȓ����ł��B����́A�����̂��₷���Ƃ������R�ɂ��Ƃ��������ł��傤���A������ނ��뒘�҂̎��M�̌����ƌ���ׂ��ł��傤�B���̓_�ł́A�����Ƃ��āA�e�̑Ή��������Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂�������A�����a�̐e�̓����̐�������n�܂��Ă��܂��B���̓������A��������߂Ē��҂� �g�����a���҂̐e�̂��������h �ƌĂсA�ȉ��Ɏ����悤�ɔ��ɋ�̓I�ɕ\�����Ă��܂��i29�|32�y�[�W�j�B����́A�����̉Ƒ��Ɛ[���ڐG����o�����ς܂Ȃ��ƁA�Ƃ��Ă��킩��Ȃ����̂ł��傤�B
�@�ڎ�������Ƃ킩��ł��傤���A�{���́A�ȒP�Ɍ����A�u�����a�ɓ��铹�v�Ɓu�����a��E���铹�v�Ƃ����ӂ��̃Z�N�V�����𒆐S�ɓW�J����Ă���A����ɕ⑫��t�����\���ɂȂ��Ă��܂��B�S���Ö@��_��Â̂ӂ��̖{�ƈ���āA�����_���ŏ��ɒu����Ă���̂��傫�ȓ����ł��B����́A�����̂��₷���Ƃ������R�ɂ��Ƃ��������ł��傤���A������ނ��뒘�҂̎��M�̌����ƌ���ׂ��ł��傤�B���̓_�ł́A�����Ƃ��āA�e�̑Ή��������Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂�������A�����a�̐e�̓����̐�������n�܂��Ă��܂��B���̓������A��������߂Ē��҂� �g�����a���҂̐e�̂��������h �ƌĂсA�ȉ��Ɏ����悤�ɔ��ɋ�̓I�ɕ\�����Ă��܂��i29�|32�y�[�W�j�B����́A�����̉Ƒ��Ɛ[���ڐG����o�����ς܂Ȃ��ƁA�Ƃ��Ă��킩��Ȃ����̂ł��傤�B
�@�{�߂ł́A�����a�Ɏ��铹�ɂ��āA���҂̐����ɂł�����蒉���ɐ������܂��B�K�v�ȕ��́A�{������肵�Ă��Гǂ�ł݂Ă��������B
�i�P�j�ΐl�W�̏�Ŏ�����鋤�ʂ̌X��
�@�e�̂��������́A���̂悤�Ȍ`�Ŕ�������܂��B����́A�����̎����s�҂̖��ɂ������������ȁA����߂ďd�v�Ȏw�E�ƌ�����ł��傤�B�ȉ��A���a����܂ł̊��҂��u�q�ǂ��v�ƕ\�L���܂��B
�i�P�j�e�ˎq���\�\����́A�e���q�ǂ��ɑ��āA���ڂɐS�Ȃ��A�ނ����A�₽���A����I�Ȏd�ł���������̂ł��B
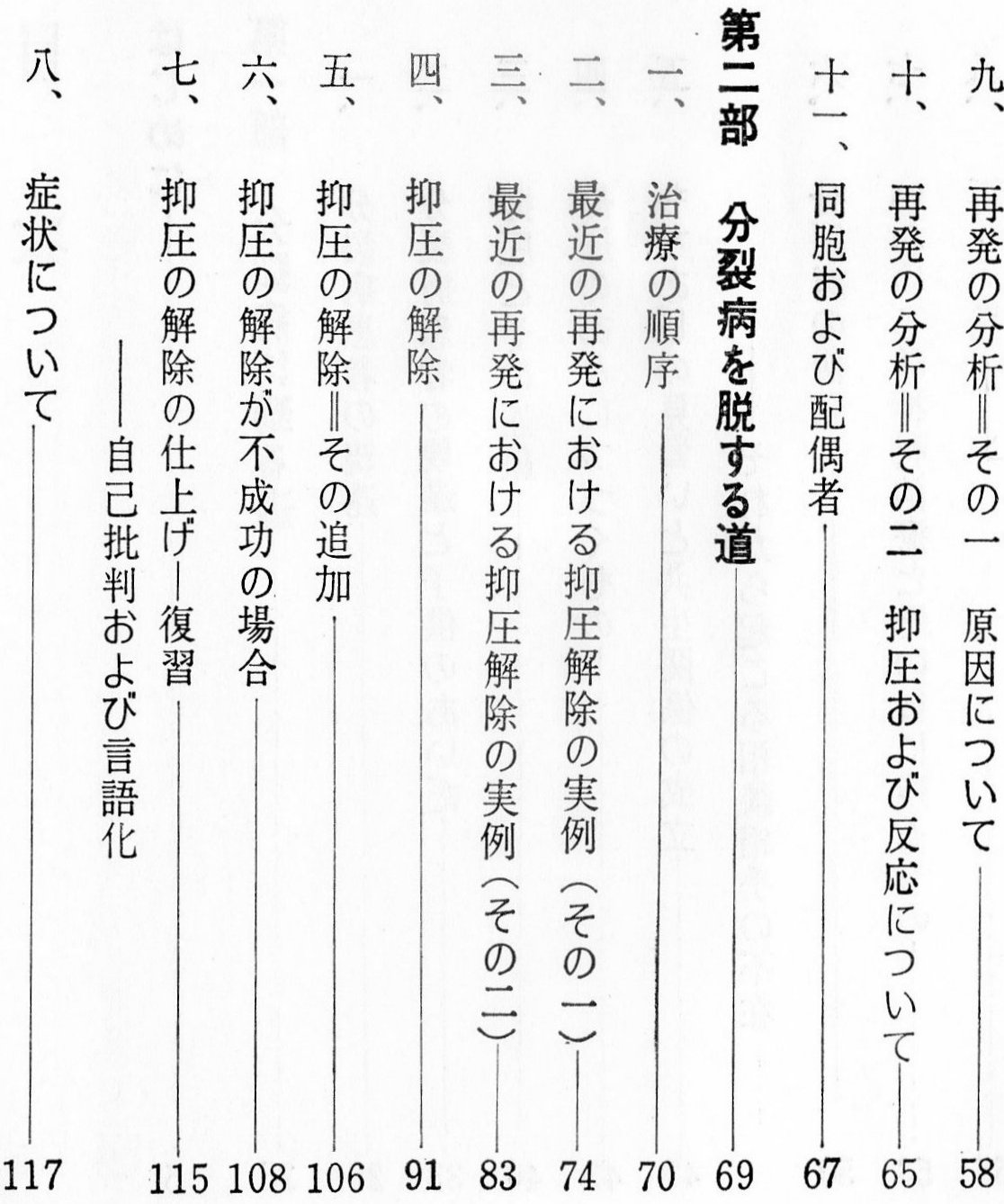 �@�������āA�c�����ɐe����Ђǂ��d�ł������q�ǂ��́A�u���̂����ɕ����Ă���ɂ͂��܂�ɂ��s�����ł���A�炢�e�̎d�ł��v��Y��Ă��܂��ȊO�ɂ���܂���B�g�ӎ����h �ɕ������߂Ă��܂��Ƃ������Ƃł��B�u�����ł����Ȃ���A�S���I�ɔj�]���������Ă��܂��v����ł��B���ꂪ�A�t���C�g�̌������}���Ƃ������ۂł��B���̗}���Ƃ����S�̎d�g�݂��A�����a�̏ꍇ�傫�Ȗ�����������̂ł��i40�|41�y�[�W�j�B
�@�������āA�c�����ɐe����Ђǂ��d�ł������q�ǂ��́A�u���̂����ɕ����Ă���ɂ͂��܂�ɂ��s�����ł���A�炢�e�̎d�ł��v��Y��Ă��܂��ȊO�ɂ���܂���B�g�ӎ����h �ɕ������߂Ă��܂��Ƃ������Ƃł��B�u�����ł����Ȃ���A�S���I�ɔj�]���������Ă��܂��v����ł��B���ꂪ�A�t���C�g�̌������}���Ƃ������ۂł��B���̗}���Ƃ����S�̎d�g�݂��A�����a�̏ꍇ�傫�Ȗ�����������̂ł��i40�|41�y�[�W�j�B
�@���̗}���́A�P��ɂƂǂ܂���̂ł͂���܂���B�e�͎q�ǂ��ɑ��āA�ނ����d�ł���e�͂Ȃ������邽�߁A�q�ǂ��̑��́A���̂Ǘ}�����邱�ƂɂȂ�킯�ł��i42�y�[�W�j�B�}���̌��ʁA��A��`�b�N�Ȃǂ̐S�g�ǓI�ȏǏ��A�_�o�ǓI�ȏǏ�A�o���i�o�Z�j���ۂȂǂ̍s����̖�肪�o�����܂��m��15�n�B�܂��A�}���́A���x���J��Ԃ��Ă���ƏK�������Ă���Ƃ��������������Ă��܂��B
�@�}���̂��߂͂����肵�����̂ł͂���܂��A�q�ǂ��͎����̐e���A���̐e�ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƍl����悤�ɂȂ�܂��B�����̎q�ǂ����A�e���w���āA�u���̐l�A���̐l�A�����̐l�v�ƌĂԂ悤�ɂȂ�̂͂��̂��߂ł��B�u��������A���ꂳ��v�ƌĂȂ��Ȃ�q�ǂ������܂��B�����āA���̂悤�Ȑe���瑁������Đ����������Ǝv���悤�ɂȂ�̂ł��i44�|45�y�[�W�j�B
�@�e���瑁�����ꂽ���Ɗ肤�q�ǂ��́A�u�Ⴂ�g��œƂ�A���̐��̍r�g���j�����邽�߂ɕK�v�Ȏ����v�����߂�悤�ɂȂ�܂��B����́A���K�I�ȗ��Â��ł���A�w���A���i�A���͂ł���A�e�e�A�X�^�C���ł��茒�S�ȓ��̂ł��B�܂��A�����₻�̑O�i�K�Ƃ��Ă̗������A�e���𗣂�邫������������Ƃ��Ďg���܂��B����͎q�ǂ��ɂƂ��ēƗ��̂��߂̋���ǂ���Ȃ̂ł����A���܂�ɑ傫�ȓq���ł����邽�߁A������͎�_�ɓ]������\�����߂Ă��܂��B���S�ȓ��̂�����ǂ���ɂ���l�����́A�c�����ɑ傫�ȕa�C�₯�����p���o�����Ă��邱�Ƃ������悤�ł��i45�|49�y�[�W�j�B�����Œ��҂́A���҂̎�_���`������錴���𐄒肵�Ă���킯�ł��B
�@��N�A���҂́A���҂ɋ��ʂ��Č����邱�������������A�g�V�����I�h �Ƃ����`�e�����g���ĕ\������悤�ɂȂ�܂��B���ׂĂ������𒆐S�ɉ���Ă���Ƃ����Ӗ��ł��B�����āA���̐[���Ȍ��ׂ������ł��������A�����a�����S�Ɏ���������Ԃ��ƍl����悤�ɂȂ�̂ł��B
�@�e����ނ����d�ł��𑱂��Ď�͔̂ߌ��ł����A���̂悤�Ȑe�Ɉ�Ă��A�Ƃ��ɐ������邤���ɁA���̐e�̂���������m�炸�m�炸�g�ɒ����Ă��܂��܂��B���ꂪ��Q�̔ߌ��ł��B���������q�ǂ������l�Ɛڂ���ƁA��a�����o���邽�߁A�����Ɠ����̐e�̂ق��ɐe�ߊ��������邱�ƂɂȂ�܂��B�e�̑����A�}���̌��ʂƂ��Ėڗ��������R�������Ȃ��q�ǂ��ɐe�ߊ�������悤�ɂȂ邽�߁A�����ɐe�q�̋����W���������܂��B���̋����W�͋����قNj��łȂ��̂ŁA���ꂪ��R�̔ߌ��ƂȂ�̂ł��i47�|49�y�[�W�j�B���ꂪ�A���҂̍l���������W�̋N���ł��B
�@���̏ꍇ�A�q�ǂ��̏�������Ă���鑶�݂��A�ە�⋳�t�A��y�A�F�l�̒����猩����悢�̂ł����A���ɐg�ɂ��Ă��܂��Ă�����������̂��߂ɁA���l���猩��ƁA�g���C�̂Ȃ��A�ʓ|�̌������̂Ȃ��A�����������̂Ȃ��h �l�ԂɂȂ��Ă��܂��B���̂��߁A���肩��h������錋�ʂɂȂ�킯�ł��B�q�ǂ��̑����A�e�Ƌ����W���������Ă��邽�߁A�e�𑊒k����ɑI�т܂��B���̌��ʂƂ��āA���l�ɒB���Ă�����A�e�ɂ��������ڂ��A���k�����������A���������߂�̂ł��B�������Ďq�ǂ��́A�l���̂����ōł��L�Ӌ`�ȗc�������A�{���̑��k���肪���Ȃ��܂܂ɂ��������ƂɂȂ�܂��B���ꂪ��S�̔ߌ��ł��i49�y�[�W�j�B
�@�����Ă��̏ꍇ�́A�v�t���ȍ~�̂��Ƃł����A�q�ǂ��h�������A�̏o�������P��������܂��B����́A���l����̂��Ƃ�����A�e����̂��Ƃ�����܂��B���̏o�����́A����ǂ���ɊW�������̂������A�q�ǂ��̂��������̂��߁A�����͓���Ȃ�܂��B�������q�ǂ��́A�e�ɑ��k�����������邱�ƂɂȂ�܂����A�e�́A��������邩����ɋC�Â��܂���B�q�ǂ��́A���ɑ��k���肪���Ȃ����ߎ���ɒǂ��߂��čs���܂��B
�@���̂��ߎq�ǂ��́A�Ƃ�ł��̋ꋫ�ɑς��A���Ƃ��蔲���悤�Ƃ��ċ���ǂ���ɂ����낤�Ƃ��܂��B�Ƃ��낪�A���������̂��߁A���������炸�A�}�����N����n�߂āA�܂��܂��s���ȏ�ԂɊׂ��čs���܂��B�����ē��ւ̑Ή�����ǂ��ł��ƂȂ�A���ɏǏ���o���܂łɂȂ�܂��B���ꂪ�����a�̏����ł��B���̂悤�ɏ����́A�o�������A�����ċN���邱�Ƃɂ���Ď���ɕa�I��Ԃɒǂ����܂��`���Ƃ�܂��B���̓_���A�ꌂ�ŕ����Ĕ��ƈقȂ�Ƃ���ł��i50�|51�y�[�W�j�B
�@������Ĕ���������ɂ͕s���芴���c��܂����A�����@�����邽�߁A����ɂ͕s�M���������Ȃ����e����̓Ɨ����}�����߁A���҂́A����ǂ���ɂ܂��܂�������悤�ɂȂ�܂��B���̂����肩�����ɒ[�Ȃ��߁A����ǂ���͘I���� �g�C�����V�T�h �Ƃ��đ��l�̖ڂɉf��悤�ɂȂ�܂����A�������ł͂���܂���B����܂ł̋���ǂ���́A�����ł��˂����Ƒ傫�����h���Ă��܂���_�ɓ]�����Ă��܂��̂ł��i55�y�[�W�j�B
�@�����̋}���Ǐ��܂��Ă��炭����ƁA�Ĕ����N����܂��B�Ĕ��̌����́A�o�����Ɗ��҂̖��_�ɉ����āA�e�̖��_���W���Ă��܂��B�Ĕ����N�����₷���o�����ɂ́A���̂悤�Ȃ��̂�����܂��B
�@�@�@�i�P�j�Ĕ��Ɋ֘A����o����
�@�o�����́A���ꂾ���ł͍Ĕ��̌����ɂ͂Ȃ�܂���B���҂̂���������傫���h���Ԃ���̂łȂ���Ȃ�Ȃ��킯�ł��B�ł�����������̂́A���҂̋���ǂ���A���Ȃ킿��_���s���˂��o�����ł��B����́A�o�����ƏǏ�o���̎��ԓI�W����A�ߋ��`�A�p���`�A�����`�A�z�N�`�̂S�^�ɕ����邱�Ƃ��ł��܂��B
�i�C�j�ߋ��`�̏o�����\�\�Ǐ�o���̐������琔���ԑO�ɋN�������o����
�@���̏ꍇ�A�}�������S�ɋN�����Ă��܂��B���e�I�ɂ́A�����Տ��Ō����Ă������̂ƂقƂ�Ǔ����ł����A�P�Ȃ锭�ǂ̂��������ł͂Ȃ��A���̗}������������ΏǏ�u�̂����ɏ�����Ƃ��Ă���_�ŁA�����Տ��Ƃ͊��S�Ɉ�����悵�Ă���킯�ł��B����ɂ́A���̂悤�Ȃ��̂�����܂��i58�|60�y�[�W�j�B
�@���̏ꍇ�A�}���̒��x�͌y���A�s���芴�͊������߂Â��ɂ�đ傫���Ȃ�܂��B���̓������Ԃ��ɒʉ߂���Ǝ��܂�܂����A�����ɂ��܂Ȃ������ꍇ�ɂ́A��]���ĉߋ��`��p���`�Ɉڍs���܂��B����͔��a�҂ɂ�����\���s���̈��ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��i61�y�[�W�j�m��16�n�B
�@���i��e�e�ɂ��Ă̂Ђ��ځA�g�̏�̑��Q�m��17�n�A�Ӎ߂ł��Ȃ��ꍇ�ȂǂŁA�}���͕s���S�ł��B������h�����ꂽ���ɂ́A��]���ĉߋ��`�ƂȂ�܂��B
�i�j�j�z�N�`�̏o�����\�\�S���̋��R����ߋ��̗}���̌�����݂��������ꍇ
�@���̏ꍇ�A�����I�ɉߋ��̗}�����������ꂽ���ƂɂȂ�܂��B�����̖��_��e�̖��_��m���Č�����{��������܂����A���������̂��߁A���͂ł͐������邱�Ƃ��ł��܂���B�܂��A�e�̂ق����A����̂��������̂��߂ɑΉ�������܂���B���̂��ߔ������N����A�����ɂ܂ō��܂��Ă��܂��킯�ł��B�i60�|62�y�[�W�j
�@�@�@�i�Q�j���҂̖��_
�@���҂̖��_�̂��߁A��L�̂悤�ȏo���������������ƂȂ��čĔ�����킯�ł����A�Ĕ��Ɏ���܂ł̏�����o�߂����炽�߂Đ�������ƁA���̂悤�ɂȂ�܂��B�i�P�j�o�������Ĕ��̂��������ƂȂ�ɂ́A���������Ƌ���ǂ���A��_���W���Ă��邱�ƁA�i�Q�j���҂͑��k����Ƃ��ĕs�K�i�Ȑe�ɁA�����W���瑊�k�����������Ă��܂����ƁA�i�R�j�����̏ꍇ�A�ЂƂ��Ƃ��ӂ����ƁA�r�n�r�Ƃ͂ƂĂ��v���Ȃ��`�Řb�����ƁA�i�S�j�ق��ɑ��k����͂��Ȃ����ƁB���̂悤�ȗv�����d�Ȃ������ʁA�}�����N����Ǐ�̍Ĕ��Ɏ���Ƃ������Ƃł��B
�@�@�@�i�R�j�e�̖��_
�@���҂͊��҂Ȃ�̋~��M�����Ă���̂ł����A�͂����肵�Ȃ����̂ł��邱�Ƃ���`���āA�e�́A�����������A����ɋC�Â��Ȃ�������A������������A���邢�͕������Ƃ��Ă��A�����̈ӌ�������������A�����Ⴂ�̐����������肵�܂��B�c�����⏉�����̏ꍇ�Ɠ����悤�ȑΉ������邱�ƂŁA���҂����]�A���_�����A�Ăї}���ւƒǂ����̂ł��B�������A�e�����Ȃ��Ƃ���ōĔ������ꍇ�ɂ́B���̎��_�œ������Ă������E��z��҂ɒu�������čl����K�v������܂��i62�|64�y�[�W�j�B
�@���̂悤�ɁA���҂͊��҂��A�����܂Őe�̔�Q�҂ƍl���Ă��܂����B���̓_�́A���Ȃ�O�ꂵ�Ă����̂ł��B�Ƃ��낪�A�����ɂ�����悤�ɁA�e�̂��Ȃ��Ƃ���ōĔ�������A��q����C�����V�C�Ĕ����N�������肵�����҂Ɛڂ���悤�ɂȂ�ƁA�������{�l�̐ӔC���d������p���ɕς���čs���̂ł��B���҂��A���҂̐ӔC�𒆐S�ɂ��������_��W�J����悤�ɂȂ�ɂ́A�������炭�̎��Ԃ��K�v�ł����B
�@�����ŁA���E��z��҂ɂ��Ăӂ�Ă����ƁA���ɔN���̓��E�̏ꍇ�ɂ́A�e�ɉ��S���Ă��邱�Ƃ������A�������Ă��珉����������⌋����ɍĔ����J��Ԃ�������̏ꍇ�ɂ́A�z��҂��e�Ǝ����������������Ă���ꍇ�������悤�ł��i67�[�W�j�B
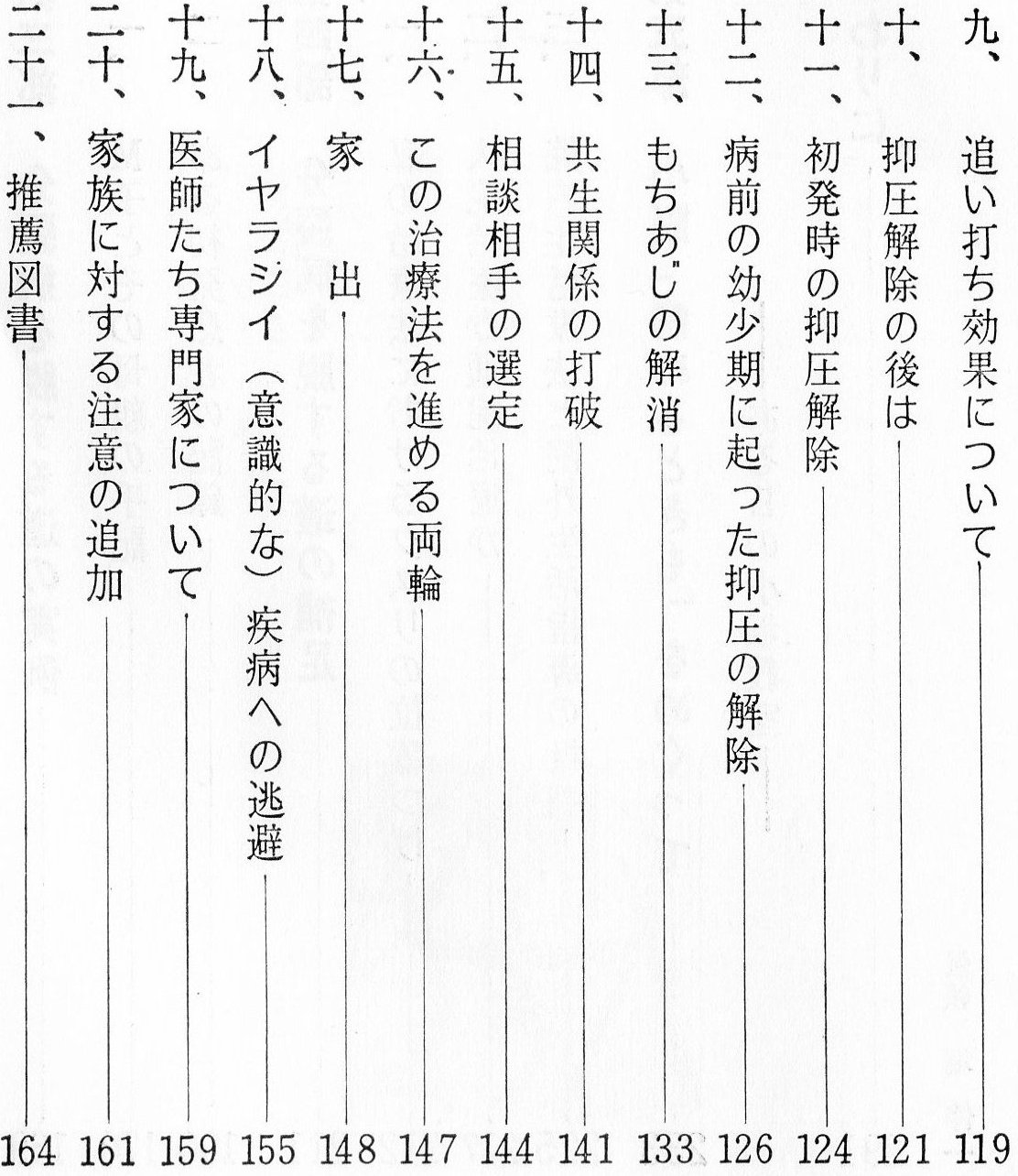 �@���҂́A�g�S���ɂ݁A�w�͂�v����h ���̂ł��邽�߁A���̎��Ö@�͖��l�����ł͂Ȃ����Ƃ����Ă��܂��i22�y�[�W�j�B�o���I�ɓ����o���ꂽ�����_�Ɋ�Â��Ă��邽�߁A�����a�Ȃ�N�ɂł����Ă͂܂�̂͂܂������Ȃ��Ƃ͂����A��ɂ����߁A����������҂ɂ͌����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�����̎��Ö@�����҂�Ƒ��ɂ�݂����ɉ�������̂ł͂Ȃ��A���炪�I�����ׂ����̂ł��邱�Ƃ�������搂��Ă���킯�ł��B������A�I���W�i���e�B�d���钘�҂��A�l�����d�����邱�Ƃ���o�����A�k��̏�ԂœƎ��ɐςݏd�˂Ă����o����ʂ��ē����A�^�̎��M�̌����ƌ��邱�Ƃ��ł���ł��傤�B
�@���҂́A�g�S���ɂ݁A�w�͂�v����h ���̂ł��邽�߁A���̎��Ö@�͖��l�����ł͂Ȃ����Ƃ����Ă��܂��i22�y�[�W�j�B�o���I�ɓ����o���ꂽ�����_�Ɋ�Â��Ă��邽�߁A�����a�Ȃ�N�ɂł����Ă͂܂�̂͂܂������Ȃ��Ƃ͂����A��ɂ����߁A����������҂ɂ͌����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�����̎��Ö@�����҂�Ƒ��ɂ�݂����ɉ�������̂ł͂Ȃ��A���炪�I�����ׂ����̂ł��邱�Ƃ�������搂��Ă���킯�ł��B������A�I���W�i���e�B�d���钘�҂��A�l�����d�����邱�Ƃ���o�����A�k��̏�ԂœƎ��ɐςݏd�˂Ă����o����ʂ��ē����A�^�̎��M�̌����ƌ��邱�Ƃ��ł���ł��傤�B
�@����Ö@�́A�i�P�j�}���̉����A�i�Q�j���������̉����A�i�R�j�����W�̑Ŕj�A�i�S�j���k����̑I��Ƃ����S�{�̒��ō\������Ă��܂��B�܂�A�}������������A���������̉������i�i�K�ŁA���Ƃ���o�Čo�ϓI�A�S���I�Ɏ�������Ƃ������Ƃł��B����ɂ���Đe�Ƃ̋����W��f�킯�ł����A���̍ۂɁA�K�ȑ��k���肪�K�v�ɂȂ�Ƃ����Ӗ��ł��B����́A���k����̗v�s�v��ʂɂ��āA�������^���B�𐋂������̎҂ł���A�����̏ꍇ�A�N�Ɍ���ꂸ�Ƃ����R�ɂł��Ă��邱�Ƃł��B�t�Ɍ����A�����܂łł���A�����a�������������ƂɂȂ�킯�ł��m��18�n�B�ȉ��A���҂̋L�q�ɏ]���āA�S�{�̒��ɂ��ď��ɐ������܂��B����́A���҂̎咣�ɏ]���ĉ���������̂Ȃ̂ŁA�S�ʓI�ɐ������Ƃ������Ƃł͂���܂��A���̐����ɏ]���ĊȒP�Ɏ��Â��ł���Ƒ��f���Ȃ��悤�ɂ��Ă��������B
�@���̎��Ö@��i�߂邽�߂ɂ́A�u�Ȃ��v�Ƃ������_���d�v�ł��B����ƂƂ��ɁA���҂ƉƑ��̑o�����A���Ȕᔻ�y�ё��ݔᔻ�ɂ���ĕϊv���čs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��i147�y�[�W�j�B
�i�C�j�Ƒ��̎Ӎ߂̑ԓx�������ꍇ
�i���j���҂̂����������e������ꍇ�⎡�肽���Ȃ��Ƃ����ꍇ
�i�n�j��t��������R���N�������Ă���ꍇ�i�ȏ�A108�|114�y�[�W�j
�@���k����́A�����m��Ȃ����Ƃ����A���̗��_�ʂ�ɂӂ�܂���f�l������A���̂ق����͂邩�ɂ悢�ł��傤�B�����ЂƂd�v�Ȃ̂́A���҂��A�����ǂ��������ɑ��k���邩�Ƃ������ł��i144�|146�y�[�W�j�B
�@���̎��Ö@�ł́A�Ƒ����痣��A�Ɨ��A�������邱�Ƃ��S�[���ɂȂ��Ă��܂��B�}������������ƁA�e�������̕a�C�̌��ł������Ƃ���������F�߂�������Ȃ��Ȃ�܂��B������Ӎ߂���Ă��A���̂���݂������邱�Ƃ͂���܂���B�e�����̑����A���ȕϊv�����Ƃ����Ă��ꎞ�I�ȏꍇ�������A�����ɒn���o�Ă��܂��B���̂��߁A�e�ƕʂ��A���̉��O�����z���邱�Ƃ��ł���̂ł��B
�@�������A���ۂɊ��҂��Əo������ƁA���̂��������͂���ɋ������������X��������܂��B����́A�����������A�u�����ŐӔC���Ƃ�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��悤�ȏ�ʂŁA����������鐫���������Ă���v�K�R�I�Ȍ��ʂł��B�������Ȃ��炻��́A�������������������邽�߂ɂ͂������čD�s���ł��B���̍ۂɏd�v�Ȗ�����������̂��A���k����Ȃ̂ł��B
�@�Əo�́A�����W��Ŕj��������ł�����܂��B�Ƃ��낪�A���ۂɉƏo�����Ă݂�ƁA�e�ɑ��邤��݂͖Y�ꋎ���A�Ƃ�����������������X��������A�����Ŏ��~�߂�������̂����k����̖����Ȃ̂ł��B
�@�Əo���������̂́A���������Ɋ�Â����ߑ��⋤���W�̍ĔR�A���k����̑I��⊈�p�̌��̂��߂ɍ��܂��A�Əo�𒆎~���Ă��܂����Ƃ�����܂��B���Ƃɖ߂�̂ł���A���Ȕᔻ�����Ă���ɂ��ׂ��ł��B���̂��Ƃ��A���������̉����⋤���W��Ŕj���邽�߂̐�D�ɋ@��ɂȂ邩��ł��B
�@���ɂ͂炳�̂��܂�A�u�C�����V�C���a�ւ̓����v��}�銳�҂��o�Ă��܂��B�l�Ԃ͐��l�ɒB������e����Ɨ�����͓̂��R�ł��B�ɂ�������炸�A�����a�ƂȂ�A���̎��Â��Ȃ���Əo�ł��Ȃ����҂�Ƒ��́A���̂��Ƃ�[�����Ȃ��Ȃ���Ȃ�܂���B�i148�|154�y�[�W�j
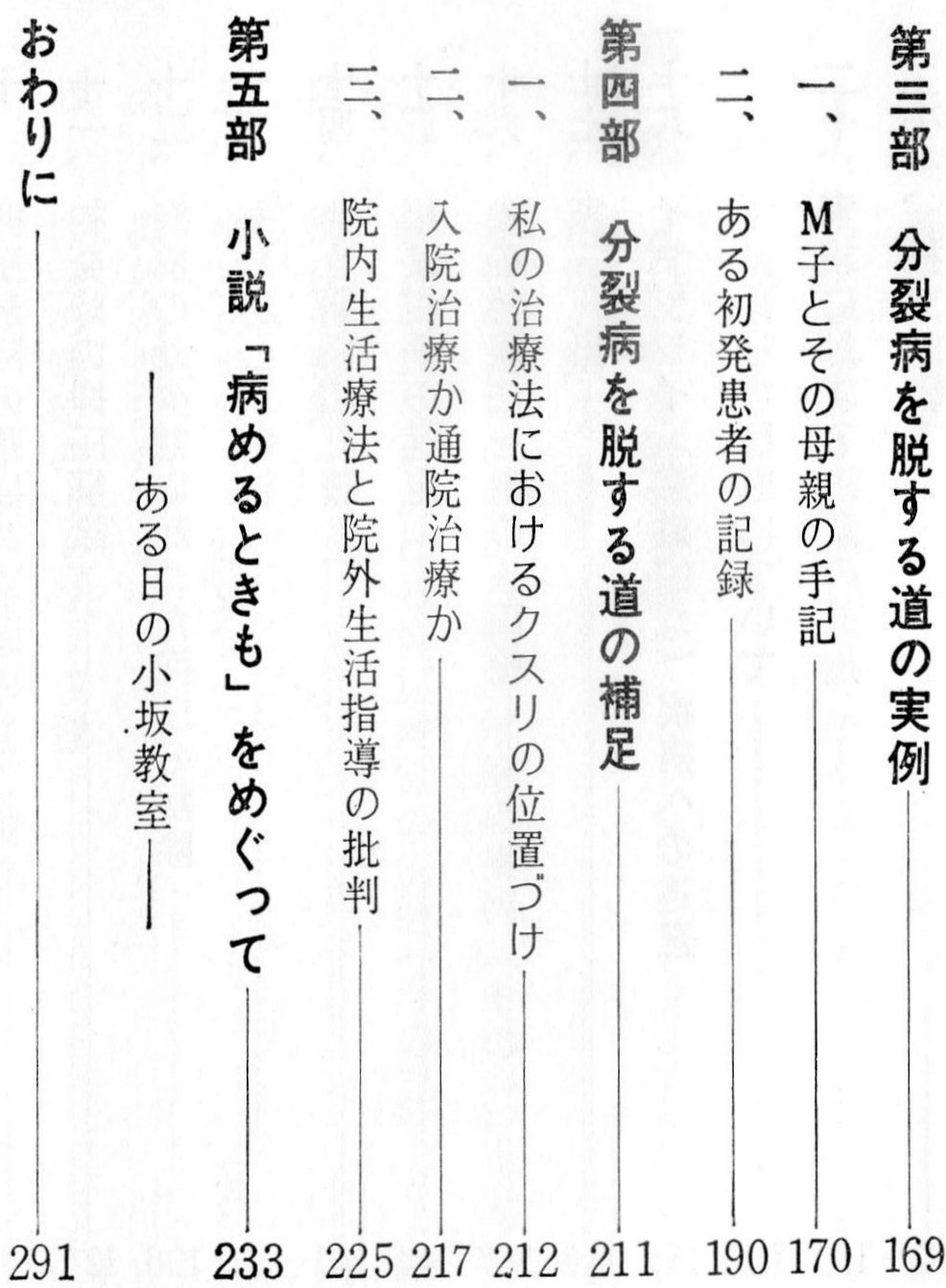 �@�Ĕ��̗}�������͍ŋ߂̂��̂���s�Ȃ��܂��B�����̏ꍇ�́A�o�������ǂ��ł��̂悤�ɐςݏd�Ȃ��Ă���̂ŁA�n�B�҂ł����̗}������������͓̂������ł��B�����ł́A��w�S�N�̏��q�w���i�j�q�j�� 28 �̖��������i�m�q�j�̗}�������̎��ۂ��ȒP�ɏЉ�܂��B
�@�Ĕ��̗}�������͍ŋ߂̂��̂���s�Ȃ��܂��B�����̏ꍇ�́A�o�������ǂ��ł��̂悤�ɐςݏd�Ȃ��Ă���̂ŁA�n�B�҂ł����̗}������������͓̂������ł��B�����ł́A��w�S�N�̏��q�w���i�j�q�j�� 28 �̖��������i�m�q�j�̗}�������̎��ۂ��ȒP�ɏЉ�܂��B
�y�j�q�̍Ĕ��̎���z�����T���́A�ӂ��Ƒ������邱�ƂɂȂ��Ă���킯�ł����A�j�q���������肵�Ă������߁A���҂͂j�q���g�ɂ����邱�Ƃɂ��܂����B����́A���̎��̍Ĕ������O�ŋN���������̂ł��邽�߁A�����ɊW����o�������{�l�ɂ����킩��Ȃ�����ł���A�j�q�����◝�_���w��ł��邽�߁A�L�����Đ��ł��邩������Ȃ��ƍl��������ł����B�Ǐo�钼�O�ɂ������o�����������čs���ƁA�w���ŊJ����Ă����u�����F�l�����ƕ����Ă������Ƃ��������܂����B���̒��Ō������ɁA�u����悭�Ƃ炦���Ă���v�Ɗ��S������ꂽ�X���C�h���������̂������ł��B�����āA���̒��ォ���Q�W�ϑz���n�܂��Ă����̂ł����B�j�q�́A���̃X���C�h�ɂ��Ď��̂悤�ɐ������܂����B�Ȃ��A���̎���́A�S�̂��j�q�ɂ���L�ō\������Ă��܂��i74�|80�y�[�W�j�B
�@�S�����ꂽ�X���C�h�͎l�A�܍˂̒j�̎q�������Ă��āA���̎q�Ɍ������ĕ��e���A�����ɂ�����ɂ��ӂꂽ�l�q�̂قق��݂��ׂȂ������܂킵�āA�قق�������Ȃ���A�h�E�V�^�m�_�C�Ɩ₢�����Ă����i�����������̂ł��������Ƃ��k���҂ɐ������܂����l�B
�@�������A�����������Ȃ���A���͂��ꂪ�����Ӗ����Ă���̂����A�����ł͂����ς蔻��܂���ł����B
�@���̂Ƃ��搶�́A�g���e�h �Ƃ����R�g�o�����Ƃ��A�p�������߂܂����B���������ꂾ�Ȃƌ����Ď��̕������܂����B�g���ꂪ�A�M���̖]��ł����������������̂��ȁh�B
�@���̐搶�̌��t����ۂ�A���̓n�b�Ƃ��̂Ƃ��̎����̐S����ԂɎv��������A�r�N�b�Ƃ��Đ����o�܂���ł����B�����ɂƂ߂ǂȂ��܂����ӂ�Ă��āA�Ƃ܂�܂���ł����B�����ė܂𗬂��Ȃ��炤�Ȃ����܂����B�܂����������������̂ł����B�i81�y�[�W�j
�@���҂̎w�E�́A�o�������v���o���������ł͕ω����N����Ȃ����ɕK�v�ȁu���߁v�ɓ�����܂��B�j�q�́A���̎��ɂ͖��䖲���ł킩��Ȃ����������ł����A�܂��Ȃ��A����܂ł̖ϑz�������Ă��邱�ƂɋC�Â��܂��i81�y�[�W�j�B���̎��̍Ĕ��̌����ɂ��āA��ɂj�q���܂Ƃ߂������̎�L����ꕔ�����p���܂��B
�@���͗c���Ƃ�����A���ɑ��ĐS�Ȃ��߂Ȃ����̂������Â��Ă��܂����B���̎v�����g�������q�W�������X���C�h�������Ƃ��ɁA�����h�����Ă��܂����̂ł���A�g���������z�h �Ȃ��܂�ɂ��̂��Ƃ�Y��Ă��܂��Ă����̂ł����B
�@���������ł́A������ �g���z�h ����ȂǂƂ�����Ԃ𑁂��E���Ȃ���A�����I�g�i�ɂȂ�Ȃ���A�Ǝ��Ȕᔻ���Ă��܂��i82�y�[�W�j
�@�j�q�́A����̎��ȗ����X�������Ȕᔻ���Ă��܂��B���̎������Ђǂ����킢��������X�����A�����a���҂ɕՂ�������傫�ȓ����ł��B���̎�����A���������X����������������̂ŁA����\�[�V�����E���[�J�[���������̂ł��B
�y�m�q�̍Ĕ��̎���z�m�q�́A�o�v�w�̉Ƃɓ������Ă��� 28�� �̖����̏����ŁA����ɂ��l�ʐڂƏ��⋳���̏o�Ȃɂ���Ď��Â�i�߂Ă��܂����B�Ō�ɍĔ������̂�1971�N�ŁA���Ƃ��̌������������Ԃ̒��Ŏn�܂������̂ł��B�m�q�́A�����̉Ƃ��\���邽���ЂƂ�̏o�Ȏ҂ł����B�m�q�̘b�ɂ��A���̂P�T�ԂقǑO����s�����n�܂����Ƃ������Ƃł������A�������̋L���͎c���Ă��邻���ł��B�Q�T�Ԍ�ɏ��⋳���ɏo�Ȃ��܂������A���̎��ɂ����ɐi�W�͂���܂���ł����B
�@���̗����A����́A�m�q����̓d�b�ŁA���ҏ͂��Ă������Ƃ���������Y��Ă����A�Ƃ������܂����B���ꂪ�������Ƃ����̂ł��B�m�q�ɂ��A�����̂��Ƃ͒m���Ă��������ł����A���ҏ���������ƂŌ����������܂�A���̖邩��s�����n�܂����Ƃ������Ƃł����B���̂��Ƃ��v���o�����疰���������Ȃ����Ƃ����i�������������߁A�{�l�̔��f�Ŗ�����ʂ����Ă��܂��B
�@�T����ɕ������o�̘b�ł́A�ω����N�������̂͂܂������Ȃ����A�܂��s�\���Ȋ���������Ƃ������Ƃł����B���̌�A�m�q����������L�ɂ��ƁA�o�̂Ƃ���ɏ��ҏ͂������Ƃ������ɂ́A���̕ω����N����Ȃ����������ł��B�Ƃ��낪�A�O�ɏZ��ł����Ƃɍs���A�����ɓ͂��Ă������ҏ���������A�u�M�N���v�Ƃ����Ƃ����̂ł��B���ҏ�́A�����������ɓ����Ă���A���̎�̕������Ă���܂����B�u�����ɂ��������̏��ҏ�炵�����h�Ȏ莆���������ɓ͂��Ă���v�B�����̖��O�Ō������̏��ҏ͂����̂́A���ꂪ���߂Ă̂��Ƃł����B
�@����́A�m�q�ɃM�N���Ƃ������R��₢�����܂������A�͂����肵�܂���ł����B�����ŁA���������I�ɂȂ����������������߂Ȃ̂��A����Ƃ��o�Ȃ������������߂Ȃ̂��������ōl����悤�Ɏw�����āA���⋳���ւ̏o�Ȃ����߂܂����B�P�T�Ԍ�A���⋳���ŁA���̂ӂ��̎w�E�����炽�߂Ă����̂ł����A�����͂���܂���ł����B�����Œ��҂��A�u�͂Ȃ₩�ȃV�[���̐F�����Ă����܂����Ƃ��������͂��Ȃ����������v�Ɛq�˂�ƁA�u�͂��߂Ĕޏ��͑傫�����Ȃ����A�w���̕\������ԃs�b�^������x�Ɠ����܂����B�����Ɋ炩��A���̂��т����Ȃ����肪�����Ă����܂����v�i83�|89�y�[�W�j�B10����Ɏ��Q������L�ɂ́A���̂悤�ɏ�����Ă��܂����B
�@�C�g�R�̂`�q����̌������̏��ҏ�����ɗ[���ȑO�Z��ł����ƂɎ��ɍs���B�N���Z��ł��Ȃ��Ƃ̒��͈Â��V���b�^�[��������Ƃ����ɏ��ҏ������B�����ɂ��������̏��ҏ�炵���������Ă��鏊�Ɏ��̐Ԃ��V�[�����\���Ă������B
�@���͂��̏��ҏ�����������M�N���Ƃ����B��̎����N�������Ă��Ȃ������́A���̉₩�ȏ��ҏ�́A�����ւ̓��Ă��̂悤�ȋC�������B�i89�|90�y�[�W�j
�@���҂��A�u���Ă����܂����v�Ƃ������߂������Ƃ���A�m�q�́u���̕\������ԃs�b�^������v�Ɠ����A����ɂ���ďǏ啝�Ɍy�������͎̂����̂悤�ł����A���ȗ����I�ȎƂ肩���͉��߂Ȃ���Ȃ�܂���B���ꂪ�ł��Ȃ��ƁA�e�Ƃ̋����W��f���Ƃ͂ł��Ȃ�����ł��B���������āA�������̌�������������A�������ׂ����������Ƃ̊Ԃɂ��ꂪ���邱�ƂɂȂ�܂��B���̖�肪���������ɂ́A���N�܂ő҂��Ȃ���Ȃ�܂���ł����B
�@�}���͉���d�˂�ɂ�āA���ȒP�ɋN����悤�ɂȂ�܂��B����́A�}�����K�������邩��ł���A��������������ɏ�������邩��ł���A����ǂ��낪����Ɏ�_�ɓ]�����A������˂����ƊȒP�ɕ����悤�ɂȂ邩��ł��B�����́A���܂��܂Ȏ��ł����ɂ�������炸�A����炪���Ƃ��Ƃ����s�������߁A�Ō�̎�i�Ƃ��� �g���a�ւ̓����h ��I���ʂƂ��ċN���������̂ł���̂ɑ��āA�Ĕ��͂����ł͂���܂���B�u�������̖������ڂ���v�ƁA�����̎��Ƃ͈قȂ�A���a�ւ̓������ȒP�ɋN�����悤�ɂȂ�̂ł��m��20�n�B����́A�u������������邽�߂ɂ��A�����W�̔j�]���܂ʂ���邽�߂ɂ��K�v�v�Ȃ��Ƃ�����ł��i65�|66�y�[�W�j�B
�@�����Œ��҂͏d�v�Ȕ��������Ă��܂��B�������a����ƁA�����a�̐��E��a�@�͎����ɂƂ��ċ��S�n�̂悢���Ƃ��킩�������߁A�����ȍ~�́A�����ɖ߂낤�Ƃ���ӎu�����������悤�ɂȂ��Ă���A����������́A�]���ʂ�̐����𑱂��邤���ŕK�v���Ƃ����̂ł��B��������ƁA�����ȍ~�̊��҂����́A�����a�Ƃ����ł��d�ǂƂ���鐸�_�����𗘗p���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B�Y�ׂ͂Ă�̉ƂɏZ�ނ��鏗���́A���҂̂��̔����𗠂Â��邩�̂悤�ɁA���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B
�@��J�̑��������̐��E�ł͎����̋��ꏊ�������A��̓I�Ȑl�Ƃ̂Ȃ��肪�����Ȃ��Ȃ�ƁA�u�����̐��E�v�́A�ǂ����������̂��������Z�ݐS�n�̂����h���ɖ������u�����v�ɂȂ�B����́A�炢�A�����o�����������ł͂����Ă��A�����̂ɂ��ウ�������A�����o���ɂ����u�����v�̐��E�������B�i�Y�ׂ͂Ă�̉ƁA2005�N�A106�y�[�W�j
�@�܂��A�ʂ̏����́A���������炢�����ɁA�u�����ɂ��猩�̂Ă�ꂽ���т����ŁA�g�̂Ƀ{�b�J���ƌ������悤�ȁv�����ɂȂ�A���́u���v�ߍ��킹�邽�߂ɃA���R�[���ɐZ��A�������ɖ����ɂȂ��������ł��i�����A97�y�[�W�j�B�e�ɖ\�͂�U����Ă�������j�����A�u�q�ǂ��̖\�͂ɂ���ĂȂ�ł��������Ƃ������z�ꉻ�����e�A���e�ɒ������p�\�R���ƃI�����C���Q�[���A������������ɓK���ĂȂ������K�ȋ�ԂƂ��Ă̐��_�a�@�A�܂������̕s���Ȃǂ̃X�g���X�ɔ����ꂽ�Ƃ��Ɉ��ދ��͂ŕ֗��ȃN�X���v�ƁA���ɗ����Ɍ���Ă��܂��i207�y�[�W�j�B�������������������ł���A����܂Ő��E���ōs�Ȃ��Ă����A���邢�͌��ݍs�Ȃ��Ă��鐸�_�Ȉ�ÂƂ́A�����������Ȃ̂ł��傤���B
�y�r�q�̏����̎���z���̎���́A1971�N�t�̏��◝�_���猩�Ă��A���ɕs�\���ȐڐG�����ł��Ȃ������B�����Ă��̎���\����̂́A�i�P�j�u���◝�_�ɊS�������Ȃ�����Ǝ��̎��Õ��@��Njy����Ă���l�c��t�ɂ���Ă����◝�_�ɂ�鐬���Ǘ�ł��邱�Ƃ��F�߂�ꂽ�v���ƁA�i�Q�j���Ì��ʂ̎w�W�ł���N�X���̌��ʂ��Z���Ԃ̂����ɍs�Ȃ�ꂽ���ƁA�i�R�j����̂���ی����ň���ꂽ����ł��邱�ƁA�Ƃ��������R����ł���B
�@1971�N�N�R��30���ɕی����ɗ���������e�ɂ��A���̂r�q�� 22 �̖����̏����ŁA�O�N���ɉ�Ђ�ސE������A�{�N�P�����ɗF�l�̏Љ�ł����Ђɋ߂����A���N�őސE���Ă���B�R�����߂���o�[�̃z�X�e�X�Ƃ��ē����n�߂����A�R�����{����y���s�����N�����Ă���B�����O����A�o�ɑ����Q�ϑz���o�����A28 ���ɂ͏f��̉Ƃɍs���A���E�������ƌ��������B
�@��e����́A���̎��������炩�ɂ��ꂽ�B�i�P�j�O�N 11 ���ɉ�Ђ�ސE�����̂́A�����̂s�ɂӂ�ꂽ���Ƃ������炵�����ƁA�i�Q�j�����O�ɁA�������Ă���P�ΈႢ�̎o�ɁA�s�Ɠ����̒j������d�b���������Ă������ƁB�o�͂��̒j���ɐS������͂Ȃ��ƌ����Ă������A���X���A�o�̗F�l�̂s�ł��邱�Ƃ��킩�����B��e�ɂ��A���̓d�b�̌��������Ĉȍ~�A�r�q�̗l�q���ڗ����Ă��������Ȃ����Ƃ����B
�@���̓��̌ߌ�A�l�c��t�̐f�@����ׂ��ی�����K�ꂽ�r�q�́A�u�\��͂������A�����ŋْ����������\��v�ł������B�l�c�ƂƂ��ɁA�s�Ƃ����j���̓d�b�̌����w�E���������₳�ꂽ�B�S���P���Ɏ����K�₵�A�����w�E�������Ƃ���A���炭���ق�����A�������b���悤�ɂȂ����B��N 10 ���A�s�̕�e�����S���A�ʖ�ɍs�����Ƃ�����s����f��ꂽ���̂́A�F�l�ɑ�������ďo�Ȃ����B���̌�A�s�̂��Ƃ֏�������d�b���������肵�����߁A�������牓���������B�s���A11 �����瓯�������Ɉٓ����Ă����̂ŁA�炭�Ȃ��đސE�����B
�@�R�� 25 ���A�s�Ƃ������O�̒j������o�ɓd�b������A�o�����炾�������ߕ�e�����B�����̒��A��e�͎o�ɂ��̘b���������A�o�͐S�����肪�Ȃ��Ƃ̂��Ƃł������B���̗����A������x�s�Ƃ����j������d�b���������B���̎��A�o�̗F�l�ł��邱�Ƃ��킩���Ă������肵���B�r�q�͂s�ɖ���������Ƃ����B����́A���ꂪ����̕s���̌����ł͂Ȃ����Ǝw�E�����Ƃ���A�r�q�́A��u�A������点�����A�₪�Ă������Ȑ��ŁA�u���ꂪ�����ł��v�Ɠ����Ċ������B
�@�����̂S���Q���A�d�b�ŘA�����Ă݂�ƁA�u���A�r�q�ł��B�ǂ������S�z�����܂����B���������܂Ō��C�ɂȂ�܂����v�Ƃ������t���Ԃ��Ă����B����܂ł̂��ׂ����Ƃ͕ʐl�̂悤�ɁA��̂��鐟���ł������B���̗����ɂ́A�H�������C�ɂ���悤�ɂȂ�A�҂ݕ���������e���r�������肷��悤�ɂ��Ȃ����B��̕���p�������Ȃ������߁A�����̗����̂���Ɍ��ʂ��Ă��炤���Ƃɂ����B�����A�l�c��t���Ή����A���̏o�����̂��߂ɓ��h���Ă����Ȃ����̂ł͂Ȃ����Ǝw�E����ƁA���������͔F�߁A�\������邭�Ȃ����B
�@�S�� 11 ���A���������r�q��f�@�����l�c�́A�u�S���݂�������悤�B���ς��Ă��ꂢ�B�o�ߗǍD�v�ƋL���Ă���B���̓��A�r�q�����Q������L�ɂ́A�u�q�̉��̎d�������Ă���Ɛ������͂͂��߂Ăł͂Ȃ����낤�v�Ɠ������猾��ꂽ���Ƃ�A�q�Ƃ̉��ɔY��ŏ��X�s����ɂȂ������Ƃ��L����Ă����B�S�� 18 ���ɗ��������ۂ̕l�c�̋L�^�ɂ́A�u���S�Ȋ����I�k�����l�ڂ�����Ă������v�Ɩ��L����Ă���B�R���_�a��́A�N�����v���}�W�� 12.5 �~���Ɍ��ʂ��ꂽ�B
�@����́A�{��̑Ή��Ȃ��āA���̂悤�ɂ܂Ƃ߂Ă��܂��B�i�P�j���Îґ������������I�Ɏ��Â�i�߂�Ƃ����]���I�ȑΉ��ɏI�n�������ƁA�i�Q�j�Ō�̓d�b�̌��݂̂��d�����A�O�N�̏H�ȗ��̈�A�̏o������{�l�̐S�̓����𖾂炩�ɂ��Ȃ��������ƁA�i�R�j���ꂼ��̏�ʂʼnƑ����ʂ������������͂����肳���Ȃ��������ƁA�i�S�j�e��ʂł̖{�l�̂����������w�E����Ȃ��������Ɓi206-209�y�[�W�j�B
�@���҂ɂ��A�����a�̏����́A����e�[�}�ɏ]���āA���N����P�N���قǂ̊ԂɈ�A�̑Ō�������Ԃ���A�Ō�Ƀ_�E������Ƃ����o�߂��Ƃ�킯�ł����A�{��ł��A���������o�߂����ڂ낰�Ȃ��畂���яオ���Ă��܂��B����́A�Ō�̓d�b�̌��ɏd����u���߂������ƂȂ��Ă��܂����A���̌��łɂ��Ă��A�S���I�Ȉ��ʊW���͂����肵�Ă���킯�ł͂���܂���B���Ă̗��l�Ɠ����̒j������o�ɓd�b�����������Ƃ��m�������Ƃ���A���̒j���ɑ��関�����v���N�����Ĕ��a�����Ƃ����o�߂̂悤�ł����A�v���N���������Ƃ��{���ɍŌ�̑Ō��ɂȂ����̂��ǂ������A���܂ЂƂ��m�ł͂Ȃ�����ł��B
�@�Ƃ͂����A�{��́A��ɒ��҂�ᔻ�������邱�ƂɂȂ�l�c�W���A����Ö@�̌��ʂ��܂̂�����ɂ��āA����𗦒��ɔF�߂Ă����Ƃ����Ӗ��ŁA�d�v�Ȏ���Ƃ������Ƃ��ł���ł��傤�B
�@�C�����V�C�Ĕ��ł̊��҂̌����ɂ́A���̂悤�ȓ���������܂��B�i�P�j���������ꂽ�����Ƃ��āA���������Ȃ��̂������o�����ƁA�i�Q�j���������������āA�����ɂ������ւ��ȗl�q�������邱�ƁA�i�R�j�����̕s��ۂ����܂������߁A�S�����W�̂��̂������Ƃ��Ă����o�����ƁA�i�S�j�Ƒ��ɂ�錴���̎w�E���������Ă��Ă��A�n�b�Ƃ��锽�����Ȃ��A���܂������Ƃ���ꍇ�����邱�ƁA�i�T�j�^�������j����ƁA�܂��܂��a�C�ɓ������ނ��ƁB���̍Ĕ��������̐ӔC�ŋN���������Ƃ�F�߂邭�炢�Ȃ�A�a�C�ł��Â���ق��������A���@�����ق��������ƌ����قǁA���������������C�������������߂ł��B�Ƃ͂����A���҂����o��������A���̏�Ԃ͊ȒP�ɏ��z�����܂��B�i155�|158�y�[�W�j
�@���̒i�K�̒��҂́A�C�����V�C�Ĕ��̌o�����܂��R�����������߂Ȃ̂ł��傤���A���̏�Ԃ��܂��܂��y�����Ă����悤�ł��B���̎�̍Ĕ��̏ꍇ�A���Â��P����ԂɊׂ��Ă��܂����Ƃ������A���̏����z����̂́A���ۂɂ͔��ɑ�ς������̂ł��B��ɁA�����ӂ���̏��肩�畷�����Ƃ���ł́A���̏�Ԃ������ł��邩�ǂ����ɂ��ẮA�ӂ���Ƃ����Ȃ�ߊϓI�ł����B
�@�l���Ă݂�A���ɂӂ����Ȃ��ƂȂ̂ł����A���Ö@����������A�����a�̊j�S�ɔ���Δ���قǁA���҂̑��ɔ��Љ�I�Ȍ������ڗ��悤�ɂȂ�A���͂̑Ή��������ԂɊׂ��Ă��܂��Ƃ������Ƃł��B���̍��̒��҂́A�C�����V�C�Ĕ��͎����̐ӔC�ŋN�������̂Ŕ����o���̂�����ƍl���Ă����킯�ł����A��ɁA�ӂ��̍Ĕ������ׂĎ����̐ӔC�ŋN���邱�Ƃ����炩�ɂȂ�܂��B��������ƁA�u�����̐ӔC�ŋN���������Ƃ�F�߂邭�炢�Ȃ�A�a�C�ł��Â���ق��������v�ƍl���邽�߂ɁA���̏�Ԃ��甲���o���Ȃ��A�Ƃ������R�́A�ʏ�̍Ĕ��̏ꍇ�͂����ł͂Ȃ��̂ŁA���ʓI�ɓ������Ă��Ȃ��������ƂɂȂ�܂��B
�@�����ɂ͂����Ƒ傫�ȗ��R������Ƃ������Ƃł��B���◝�_�́A����ȍ~�A�C�����V�C�Ĕ��̑Ή���𖾂��ł��d�v�ȉۑ�ɂȂ��čs���̂ł��B�����ɂ����A���_�����a�Ƃ������_��w�ő�̓�������d�v�Ȍ����B����Ă���̂ł��傤�B
�@�@�P�D��̈ʒu�Â�
�@�����a�Ɏg����̂́A�Ǐ��}����͂��s�\���ł����Ȃ����Í܂ł���B����ɑ��āA�}��������������A����g��Ȃ��Ă��Ǐ�͏�����B����܂Ŗ���g���Ă����ꍇ�ɂ́A����p���o�����邽�߁A���ʂȂ������~����������Ȃ��Ȃ�B�Ƃ͂����A����g�킴������Ȃ��ꍇ���Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B���Ƃ��A�c�����̗}���������������ł���B���̏ꍇ�ɂ́A�u���҂ɋ����������Ƃ��Κq�f�E�ӂ邦�E�⊾�E���_�E�����Ȃǁv�̔������N���邱�Ƃ�����̂ŁA�ꎞ�I�Ȃ��̂ł͂��邪�A�u���݂̎��̂����ł͂�͂�g�킴������Ȃ��v�B�i212�|216�y�[�W�j
�@�@�Q�D���@����
�@���@���Âɔ�����̂́A���̂悤�ȗ��R�����邽�߂ł���B���@���i�P�j���҂̐l���D���邽�߁A�i�Q�j�����a���҂̂��ǂ���A���Ȃ킿��_���h�����邽�߁A�i�R�j�����������������邽�߁A�i�S�j�z�X�s�^���Y��������o�����߁A�i�T�j���@��K�v�Ƃ��Ȃ����ËZ�p�_�҂����ɊJ�����Ă��邽�߁A�i�U�j���̎��×��_�́A�ݑ��ԂłȂ���Ί��҂ɂ��Ƒ��ɂ��g�ɒ����ɂ������߁A�i�V�j���@�ł́A��t�܂����ɂȂ��Ă��܂����߁B�Ƃ͂����A����ł����@���K�v�ɂȂ�ꍇ������B����́A�i�C�j�������s�����A���̎w�E�����҂����ꂸ�A�������Ǐ������ꍇ�A�i���j�e�̑ԓx�����������҂̏Ǐ��U������قǗL�Q�ȏꍇ�A�i�n�j�����W�̑Ŕj�̂��������Ƃ��ė��p�ł���ꍇ�B�i217�|222�y�[�W�j
�@�@�R�D�����Ö@����w��
�@�@�O�����w���Ƃ������@��ł��o���Ă����t��ی��w�����邪�A����ɂ͂������̗��h������B�ЂƂ́A���Ă̒��҂������ł��������A���҂̋���ǂ���A���Ȃ킿��_�ɋC�Â��Ȃ���A���ꂪ�h������Ȃ��悤�ɂ��邽�ߐ����K���Ƃ�����i���Ƃ���̂ł���A�����ЂƂ́A�ӖړI�ȃq���[�}�j�^���A�j�Y���Ɋ�Â��Ċ��҂ɐڂ�����@�ł���B����炪���Ȃ̂́A���҂̐l����N�Q���邱�Ƃł���A���҂��Ĕ����Ȃ������Ƃ��Ă��A���܂��܂����Ȃ����̂��A����Ƃ������K�����ۂ������ʂƂ��ĉ���ł����̂����킩��Ȃ����Ƃł���A�Ĕ������ꍇ�ɂ́A���@���Âɗ��邵���Ȃ����Ƃł���B�i229�|230�y�[�W�j
�@�ȏ�̂悤�ɁA���҂̎p���́A���݂���݂Ă����ɐ�i�I�Ȃ��̂ł����B����ɂ́A��q�̂悤�ɁA��t��M���Ƃ����ÊW�҂́A���҂�Ƒ������炷�闧��ɑނ��A���ۂ� �g�����h �ƌĂ���ł�������H���Ă����̂ł��B���̓_�ł��A�����ɐ�i�I�Ȃ��̂ł����������킩��ł��傤�B
�@�����ЂƂ̈Ⴂ�́A�ȏ�̕��@��A����ɂ���ē���ꂽ���ʂ���킩��悤�ɁA���Ȃ��Ƃ������a�Ǐ�̏o���Ƃ����_�Ɋւ��ẮA���̎����͊��S�ɐS�����̂��̂ł���A��`���̂��̂Ƃ͍l�����Ă��Ȃ����Ƃł��m��21�n�B���̂��Ƃ́A�����e�Ɉ�Ă��Ȃ��番���a�ɂȂ�Ȃ������q�ǂ��̏ꍇ�A�u�K�炸 �g�e�ᔻ�E�e�Ƃ̊ԂɐS���I������u���X���E�ʋ��h �������A�e�Ƃ̊Ԃ� �g��ꍇ���E�Ë��h ������܂���v�i163�y�[�W�j�Ƃ����L�q������킩��܂��B����ɑ��āA�I�[�v���E�_�C�A���[�O�� �g�����Ҍ����h ���A���̕����a�Ƃ���������S�����̂��̂Ƃ͍l���Ă��炸�A���̓_�ł͏]���I�ȁA�]�̋@�\�ُ�Ɋ�Â������Ƃ������������Ă��Ȃ��̂ł��B���������_���l����킩��悤�ɁA���҂��A����̏��S���т��āA�Ɨ͂ŊJ���������@���A�����Ɋv���I�Ȃ��̂����������킩�낤�Ƃ������̂ł��B
�@�{���̏o�ł��甼�N�قnj�ɁA�s�̂��ꂽ�Ō�̒����ƂȂ�w���_�����a�ǖ{�x���o�ł����̂ł����A���̍��̒��҂́A�ڊo�߂��͂��̊��҂��������Љ�I�s���� �g�C�����V�C�Ĕ��h �̑Ή��ɋꗶ����悤�ɂȂ��Ă��܂����B�������Ȃ���A�����a���̉����́A���̐�ɂ����Ȃ��̂ł��B������ɂ���A�{���́A�e�����������o�I�ɕ�����[���Ȗ��_�̎w�E���܂߁A�a�V�Ȓ��z�⏊���������Ɍ����A���Ȃ��V�N��������Ȃ��d�v�Ȓ���ł���̂͂܂���������܂���B
�m���P�n�����A���M�s�̐��_�ȕa�@�ɋΖ����Ă������́A�I�ɍ������X���M�x�X�̓X���Ɉ˗����A�X���ɖ{����������Ă�����Ă��āA�Ō��ɍŌ�Ɏc�����ɂ͂��ׂĔ����Ƃ��Ă�������̂ŁA�����ɂȂ����̂͂܂������Ȃ��B
�m���Q�n���₩��傫�ȉe�����āA�n�搸�_��Â̓��ɐi�l�c�W�ɂ��A�����A�n�搸�_�q�����������Ă����ی��w�́A�����Տ��h�Ə���h�ɕ�����Ă����Ƃ����i�l�c�A2001�N�A123�A166�y�[�W�j�B
�m���R�n�����W�Ƃ����p��́A����܂Ő����w�ł͎g���Ă������A�S���w��_��w�ł͑��݂��Ȃ������悤�Ȃ̂ŁA�����炭���҂̑���ł��낤�B
�m���S�n�c�����̃g���E�}�ƕ����a�̔��a�Ƃ̊W�������������Ƃ������Ƃł���Ώ��Ȃ��炸����i���Ƃ��ABendall et al, 2008; Bikmaz, 2007; Matheson et al, 2013; Morgan & Fisher, 2007; Popovic et al, 2019; Read, van Os, Morrison & Ross, 2005; Spence et al, 2006�j�B���́A�����a���S�����ŕs�t�I�Ȃ��̂��ǂ����Ƃ����_�ɂ���̂ł��낤�B
�m���T�n�s�q�Ȋ��o�������_��w�҂ł��������V�M�́A���̖�����ɓI�m�ɕ\�����Ă���B�u�w�����a�Ƃ͉����x���Ă����܂��ƁA���̐��_��w�̎嗬�h�́A��͂�]�̕a�C���Ǝv���Ă����ł��B�S�̒�ŁB�����a�͔]�̕a�C���ƁA�ǂ����Ŏv���Ă����ł��B�ɂ�������炸�A�ӂ����Ȃ��ƂɁA�����a�̐l�ɉ������m�Ȕ]��Q�̏��������o�����ƁA����͕����a�ł͂Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ��ł��B�k�����l�q�]�̕a�C�₯�ǁA�܂��Ȃ�ɂ�������Ȃ��A���ɂ܂��ӂ����ȕa�C�r�ɂ��Ă��������Ƃ����l�������A���_��w�̒��ɂ���v�i���V�A2010�N�A38�y�[�W�j
�m���U�n�������A�P�ɒ���Ƒ��e��Ȃ����������Ȃ��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�����ɂ͂�������͂邩�ɕ��G�Ȏ������悤�Ɏv����B���̓_�ɊS�̂�����́A�ْ��i�}���A2004�N�j��W�͂��Q�Ƃ��ꂽ���B
�m���V�n���҂́A�����̔����̏d�含���������邱�Ƃ͂Ȃ�����x���Ȃ������B���̓_���ߏ��ɕ]�����Ă����̂�������Ȃ��B
�m���W�n���҂́A���_�����a�Ɍ����Ċώ@���Ă��邪�A���̒��N�ɋy�Ԍo���ɂ��A�{�l�ɂƂ��ďd�v�ȓ_�ɂӂꂳ������A�����炭�����̗L���▯�����킸�N�ɂł��o��ƍl���Ă悳�����ł���B
�m���X�n���̂Ƃ���ł��ӂ�Ă��������A���҂Ɠ������n��Љ�ɓ��荞��Őf�Ê������s�Ȃ��Ă����l�c�W�́A��͂���ʊW�̂͂����肵�Ă���悤�Ɍ�����Ĕ����A�ꍇ�ɂ���Ă͌��I�ȍD�]������Ⴉ���Ă���B�������Ȃ���A���̂قƂ�ǂ͑���I�ȕ��@�ɂ���ē���ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�����o�ߒ��ɋC�Â��ꂽ�A���������ł���A���̌����Njy�͊Â��܂܂ɏI����Ă���i���Ƃ��A�l�c�A1979�N�j�B
�m��10�n��������ƁA��̓I�ȉ������^�������ɏǏ������̂͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃ��t�ɖ��ɂȂ�B�Ǐ���������Ƃ��ł������@�ƁA�Ǐ�o���̌��������ڂɊW���Ă��邱�Ƃɂ��Ă͋^�O��������Ă��Ȃ����A�����ł͂Ȃ��̂�������Ȃ��B���҂͂��̌������Ă��Ȃ��悤�ł��邪�A����́A�����a�̏Ǐ�������d�g�݂ƁA�Ǐ�o���̐^�̌����Ƃ̊W�͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��Ƃ����d����ɊW���Ă���B
�m��11�n���̌��I�Ȍ��ʂɂ��ẮA��ɒ��҂��������ᔻ���邱�ƂɂȂ�l�c�W���A���̂悤�ɏq�ׂĂ���B�u�m���ɂ��̗쌱���炽���ȏǗႪ���������Ƃ������ŁA���B�̊�O�Łw�悭�Ȃ��Ă��܂��Ǘ�x��������ꂽ���̂ł��v�i�l�c�A1986�N�A256�y�[�W�j�B�l�c�́A�����������ۂ��A�u�Ȃɂ��ЂƂ̗��_�̔w��ɂ́w�ƂĂ����̗��_���������ɓs���̂�������x�Ƃ������̂��A�W�܂��Ă���v�Ƃ��������ŕЂÂ��Ă��܂��Ă���i�����A256�y�[�W�j�B�����a�̏Ǐ���A�S���I���삾���ŏ��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����ƂɂȂ��Ă���̂ŁA���̔����́A���_��w�̏펯�����S�Ɉ�E���Ă���B
�m��12�n�����ɂ́A���������ڂ����Ƃ��܂܂�邪�A�e�Ɠ������Ă��Ă��A�K���������k�����肮�������ڂ����肷��킯�ł͂Ȃ��i64�y�[�W�j�B�Ƃ��낪�A�e����̎d�ł��ɂ�鏝���������Ƃ��Ă��邽�߁A�e���֗^���Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ́A���̗��_�͐������Ȃ��B��������ƁA���̎��_�ł͗��_�I���ꂪ�ł��Ă��Ȃ��������ƂɂȂ�B
�m��13�n1973�N�H�ɁA���͒��҂���A���̍��ɁA���҂̉Ƒ��Ǝv�����j�����狺���̓d�b���������������Ƃ����L��������B���̌�A����ʂ��킳���������������悤�ɂȂ�̂ł���B����́A���_�Ȉ�̊Ԃł������ł������B���̖��ɊS�̂�����́A�l�c�W�̍u���^�i�l�c�A1986�N�j���Q�Ƃ��ꂽ���B
�m��14�n���̖��ɂ��ẮA�ْ��i�}���A2004�N�j��W�͂ŏڂ��������Ă���B
�m��15�n���҂́A�����ŁA�}���ɂ���āA�u��A��`�b�N�Ȃǂ̐S�g�ǓI�ȏǏ��A�_�o�ǓI�ȏǏ�A�o���i�o�Z�j���ۂȂǂ̍s����̖��v���o�邱�ƂɌo���I�ɋC�Â��Ă���B�ɂ�������炸���҂́A�}���ɂ���ďǏo��̂́A�_�o�ǂƕ����a�������ƍl���Ă����B
�m��16�n���҂́A�ʏ�̗\���s�������҂̂��������̂��߂ɋ����o�����̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă����B���̂��߁A�}�����s���S�ł���A���o���Ă���ꍇ�������Ƃ���Ă���B���̌��ʁA�����a�Ǐ�́A�}�������S�ȏꍇ�����łȂ��A�s���S�ȏꍇ�ɂ��o��Ƃ������_�ɓ��B����������Ȃ������̂ł���B���̍l�������́A�Ō�܂ŕς��Ȃ������悤�ł���B
�m��17�n���҂́A���N��ɏo�ł��ꂽ�w���_�����a�ǖ{�x�i1972�N�A���{�Ō싦��o�ʼn�j�̒��ŁA���Z���̊��҂��A�u�ӂ����Ă��Ċ��̊p�ɘr���Ԃ��Ăق�̂T�~�T�~�����炢�́A��������o�K�[�[�ʼn���������ޒ��x�̐��������ō�����Ԃɂ͂����Ă��܂����v������Љ�Ă���i����A1972�N�A190�y�[�W�j�B���҂́A���̎�̍Ĕ����A�g�̂ɑ��邱�����A���邢�͎�_���h�����ꂽ���ʂƍl����킯�ł���B���҂́A�Ō�ɕ��Q���_�\�\�e�ɑ��镜�Q���番���a�Ƃ����a�C��I�сA����𑱂���Ƃ��������\�\��������̂ł��邪�A���̂悤�Ȏ���́A���Q���_�ł͂ނ���������ɂ����̂ł͂Ȃ��낤���B
�m��18�n������Ԃ̊��҂ɓK�p��������Ƃ��ẮA���҂����p���Ă��鎖��i����A1971�N�j���Q�Ƃ��ꂽ���B
�m��19�n�Ƃ��낪�A�����ȒP�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ��A����ɖ��炩�ɂȂ��Ă���B���̖��ɂ��ẮA�l�c����A�u�Əo�̒i�K�ŁA�������Ƃ������i�K����������ˁv�Ɲ�������Ă���B����ɑ��Ē��҂́A�u�����a�������������ǂ������Ă������Ƃ͂킩��Ȃ��B�����W�����c���Ă܂��ˁv�Ɠ����Ă���i����A1972�N�A242�y�[�W�j�B�����W�̑Ŕj�������ɓ�������̂����A�g�ɐ��݂Ă킩���Ă����Ƃ������ƂȂ̂ł��낤�B
�m��20�n�����[�����ƂɁA���_�����a�T�O������I�C�Q���E�u���C���[���A����1908�N�̎��_�Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B�u�����a���҂ɂƂ��ĕa�C�ɂȂ肽���Ƃ����Ȃ�炩�̗��R�k�����l������ƁA���ʂƂ��āA��͂�i�����Ɂj�a�C�ɂȂ�̂ł���B�Ƃ�킯�킩��₷���Ⴊ�A���ɂ�����ׂ�����ɂ���Đ��_�a�@�ɓ��@���Ă���Ĕ����҂����ł���B���鏗�����҂́A���Ɍo�߂��ǂ��މ@�������܂�Ă����B�������A����ޏ��͉ƒ�ɂ�����`�����Ăш����邱�Ƃ�Y��Ă����B����䂦�ɑމ@������ꂻ���ɂȂ�ƁA���̒���ɌJ��Ԃ��a�C�ɂȂ����̂ł���v�i�u���C���[�A1998�N�A91-92�y�[�W�j�B�l�c�W���A����Ǝ��ʂ�������J��Ԃ����Ă���i�l�c�A1976�N�A19�|22�y�[�W�G2001�N�A7�|8�y�[�W�j�B
�m��21�n���鎾������`���̂��̂��ǂ���������������@�Ƃ��ẮA�ꗑ���o�����Ɠ��o�����̔��a��v�����r������̂��̂���嗬�ɂȂ��Ă���B���̕��ʂ̌����͐������s�Ȃ��Ă���i���Ƃ��A������� 40 �N�قǑO�̂��̂ł��邪�AGottesman & Shields, 1976; Lidz, 1976; Stabenau & Pollin, 1967; Wahl, 1976�j���A��`���Ƃ����_�ł͌����҂̈ӌ��͈�v���Ă�����̂́A�ǂ��܂ł� �g���h �̉e���ɂ�邩�Ƃ����_�ł́A�ӌ��̈�v�����Ă��Ȃ��悤�ł���B


