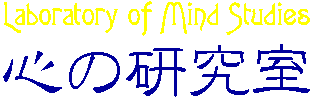
|
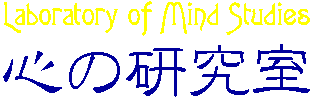
|
|
【訃報】去る2024年8月22日 笠原敏雄が他界いたしました。ここに生前のご厚誼を深謝し厚く御礼申し上げます。 笠原の他界に伴い、五反田の心の研究室は閉鎖いたしました。長きにわたり本当にお世話になりました。直近にご予約をいただいていた方や、ご連絡をくださった方にはお伝えができましたが、その他の方はご連絡先が分からずお伝えできておりません。このような形でお知らせしますことをお許しください。また、今後もこちらのサイトはご覧いただくことができます。  『新たな視点から見たサヴァン症候群』がアマゾンオンデマンドから発売されました。 『新たな視点から見たサヴァン症候群』がアマゾンオンデマンドから発売されました。笠原が書き終えていた原稿を出版できる形になんとか整えました。不十分な点もあるかもしれませんが、原稿を眠らせることなく世に出すことができました。笠原の執筆中にお世話になった方々の特定ができず、直接お礼が申し上げられないことがくやまれますが、発売に向けてご助言をくださった方々も含めまして深く御礼申し上げます。また、間違いや不備を見つけましたらメール【kasahara@h02.itscom.net】でお知らせいただけますと幸いです。(11/12/24:管理人) 追伸:『新たな視点から見たサヴァン症候群』を国会図書館に寄贈しました。国会図書館のサイトで検索すると表示されます。(12/10/24:管理人) お知らせが遅れましたが、『小坂英世著作集』全4巻、『小坂療法とは何か』その他、心の研究室で刊行した著書や編著書を、今年の春先にまとめて国会図書館に寄贈しました。国会図書館のサイトで検索すれば表示されます。これで永久保存されるので、ひと安心です。 (9/29/23)
ただいま執筆中の自閉症の本は、6章めに当たるサヴァン症候群の章を書いているところです。サヴァン症候群はやはり重要なので、それだけで3章になりそうです。文献が、1700年代から始まって大量にありすぎるのと、事実が歪めて引用されていたりなど、なぜかまちがいが非常に多いため、その確認などにかなりの時間がとられています。(2/13/23) しばらく前から自閉症の本を書き始めました。ただいまは、脳の障害についていくつかの角度から詳しく調べています。自閉症は、どう見ても脳の障害が原因ではありませんが、念のために脳障害そのものについて詳しく調べているわけです。これまでの自閉症論とは全く違うものになるはずです。刊行は来年の中頃を目途にしています。 やはりというべきか、『小坂英世著作集』も『小坂療法とは何か』もほとんど売れておりません。アマゾンでしか購入できないため、販売部数が正確に把握できるのでわかるのですが、それは想定をはるかに下まわっています。本来の目的は、物理的な形で出版し、国会図書館に所蔵してもらい、後世の専門家に託すということなので、それはそれでかまわないのですが、現在の専門家にも関心をもっていただいたほうがよいことはまちがいありません。その点では少々残念なところがあります。どこかに書評でも出れば、多少は違ってくるのかもしれませんが。(10/11/22) 一昨日、取次の学研プラスにデータを送ったばかりなのに、今朝にはもう『小坂療法とは何か――忘れ去られた精神科医・小坂英世』の予約がアマゾンで始まりました。発売予定は7月 20 日で、販売価額は 4,180 円だそうです。(7/14/22) 昨日、『小坂療法とは何か――忘れ去られた精神科医・小坂英世』のデータを学研プラスに送りました。2週間ほどで、オンデマンド版としてアマゾンから発売になるはずです。『小坂英世著作集』第4巻に収録した「小坂療法概説」を組みなおして独立させ、「『小坂英世著作集』成立の経緯」という小論を加えたものです。これは、人間のふしぎなつながりによって『小坂英世著作集』が計画、出版されるまでの経過を客観的に記述したもので、興味深く読んでいただけるはずです。付録や詳細な索引がついており、A5判横組みで 440 ページになりました。販売価額は 4,000 円を少し超えると思います。(7/13/22) 『小坂英世著作集』第3巻と第4巻の販売がアマゾンから開始されました。『小坂英世著作集』はこれで完結です。本著作集出版の第一の目的は、国会図書館など、永久保存される施設に収蔵していただき、後世の研究者に活用してもらうことですが、もちろん、現在の専門家にもお読みいただければ、編者としては望外の喜びというものです。 ところが、第4巻の巻末資料で大きなミスがありましたので、とりあえずここでお知らせしておきます。それは、「小坂療法略年表」606ページで、『小坂教室テキスト・シリーズ 第11号 私の病因論と治療法』の発行を、本文では正しく 1976 年6月としているのですが、誤って 1974 年6月の項に入れてしまったことです。他にもミスがあると思いますので、もしお読みいただいてお気づきになったら、ぜひお知らせいただきたいと思います。 ただいま、『小坂療法概説』の出版準備中ですが、その中に、「『小坂英世著作集』成立の経緯」という小文を収録する予定です。これは、まさに本著作集が成立するまでの経緯を時系列的に記述したものなのですが、お読みいただければ、人間の見えないつながりの連鎖が基盤となって、この著作集が成立していることがおわかりになるはずです。『小坂療法概説』は、予定通り来月中には出版できると思います。(6/20/22)
予定を1週間ほど遅れましたが、昨日、『小坂英世著作集』第4巻のデータを学研プラスに送りました。順調に行けば今月の 20 日前後に、やはりアマゾンから発売になる予定です。多くの方々のご協力を得ながら、著作収集から文字起こしや編集作業を経て組版まで、2年以上を要した『小坂英世著作集』の出版作業は、この4巻の刊行をもって完了です。なお、内容見本の作成には少々時間がかかりそうです。
本日、『小坂英世著作集』第1巻と第2巻が、アマゾンのオンデマンド版として同時発売されました。第1巻の解題は、わが国精神医学界の最長老、岡田靖雄先生が、第2巻の解題は、高名な比較文化精神医学者である野田正彰先生が書いてくださっています。判型はA5判、横書き 30 行、装丁は、書籍デザイナーの土屋みづほさんです。詳細な事項、人名索引がついています。 第3巻と第4巻が出たら、内容見本のようなものを作ることも考えています。 国会図書館に寄贈すれば、永久保存されるので、これでひと安心というところです。(5/29/22)
『小坂英世著作集』第3巻と第4巻のデータが、詳細な索引を含めてほぼ完成しました。ページ数はそれぞれ 516, 727 です。したがって、全4巻の総ページ数は 2300 を超え、かなりのボリュームになります。明日、編集者から念校ゲラが戻ってくるので、それを反映させて完成です。 30日に届くように学研プラスにデータを送るので、6月半ばには販売開始になるはずです。一流の書籍デザイナーによる装丁なので、かなり見栄えがします。 第1,2巻は、最終的なデータを 17 日に送っているので、そろそろアマゾンから発売になると思います。(5/26/22) 5月2日に起こった、興味深い適合行動の事例を、時間がないためとりいそぎ報告しておきます。(5/03/22) 『小坂英世著作集』全4巻のうち、第1巻と第2巻が、索引を含めて完成しました。判型はA5判、横組み 30 行で、それぞれ 582 ページと 490 ページです。装丁は、医学書を主に手がけている、知人の書籍デザイナーに依頼していて、今月末にできあがってきます。近日中にデータを、すぐ目の前の学研プラスに送りますので、5月中にはアマゾンからオンデマンド版として入手できるようになります。 第1巻の解題は、小坂先生の 60 年来の盟友であった岡田靖雄先生が、第2巻の解題は、小坂理論が成立するより前に小坂先生と対論をしたことのある野田正彰先生が執筆されています。第2巻には、浜田晋先生亡き後、長年にわたって浜田クリニックに勤務しておられた、小坂先生の東京医科歯科大学での後輩にもあたる白石弘巳先生が寄稿してくださっています。 全4巻を5月中に刊行することもできないわけではないのですが、編集者の示唆により、慎重を期して二回に分け、後半の2巻は6月に刊行することにしました。そのおかげで、1年数か月ぶりに、1日くらいですが、一息つけることになりました。本著作集の編集を依頼している、大学出版部協会にいた長年の畏友である編集者に指摘されて気づいたことですが、東京医科歯科大学の卒業生で全集や著作集を出すのは小坂先生が初めてのようです。たまたま縁があって、この重要な刊行物の編者という立場になったことを、恐縮するとともにたいへん喜んでおります。 順次、詳しい説明を加える予定ですが、今回は第一報として、大まかな紹介にとどめました。(4/27/22)
第4巻に収録予定の「小坂理論概説」もほぼ完成しました。30 ページほどの予定で書き始めたのですが、結局 270 ページにもなってしまったので、第4巻に収録するほかに、単行本としても出版することにしています。いずれも、アマゾンからのオンデマンド出版を考えており、来年の5月頃を予定しています。 「小坂英世著作目録」も更新しました。新発見の資料も盛り込まれています。
『前世を記憶する子どもたち』の文庫化の件です。先日、出版社に再校ゲラを戻し、その三校ゲラと「解説」の初校ゲラを待っているところです。1巻本で600ページほどのかなり分厚な本になります。予定通り8月下旬に発売になるはずです。
『前世を記憶する子どもたち』の文庫化の件です。角川文庫の1点として8月25日に出版される運びになりました。誤訳を正したり、わかりにくい訳文を直したりして、初校ゲラを戻したばかりです。再校ゲラは今月末に届くようなので、実際にはもっと前に出せそうですが、出版社側の判断で、8月末の刊行予定になったようです。1巻本として出るので、かなり分厚なものになるはずです。ご期待ください。 『小坂英世著作集』は、版組がほぼ完成し、あとは数名から寄せられる原稿を加えるだけになりました。小坂先生が最も注目していたクライアントを含め、当時の重要な関係者のほぼ全員から寄稿していただけることになったので、おかげさまで、後世に残すための万全の装いが整いそうです。(4/9/21)
『小坂英世著作集』は、現時点で、A5版横組み30行で1300ページほどになっています。最終的には1500ページほどになりそうなので、全3巻になるのは確定的です。神奈川県精神保健福祉センターのご協力を得て、小坂先生の超人的な活動ぶりを示す新発見の資料も掲載できる運びになりました。今回は、慎重を期して、大学出版部協会にいる友人(元TBSブリタニカ、麗澤大学出版会、各出版部長)に編集を依頼しています。ただし、販売部数がそれほど見込めないため、現在のところ、アマゾンからのオンデマンド出版を考えています。
本年4月頃に刊行できるのではないかと考えていた『前世を記憶する子どもたち』の文庫は、残念ながらいくつかの事情から、本年の9月頃の出版になりそうです。出版の予定が決まったらまたお知らせします。(2/18/21) 30年前に翻訳出版した『前世を記憶する子どもたち』が文庫化されることになりました。当時はまだ活版印刷でした。文字おこしされ、来年2月初め頃にゲラが出るそうなので、4月頃に発売されるのではないかと思います。今は生まれ変わりブームだそうですから、文庫になったらもち運びしやすくなることもあって、売れ行きも伸びるのではないかと期待しています。(12/15/20)
来年の小坂英世著作集の刊行に向けて、『精神衛生活動の手引き』『精神分裂病患者の社会生活指導』『小坂教室テキストシリーズ』の3作を、全体の分量を測るためもあって、とりあえずA5版横組みで版組みしてみました。50 年ほど前に刊行された前二者は 70 ページ前後の小冊子ですが、テキストシリーズの分量がかなりあったため、3作を合わせると 320 ページほどになりました。『精神分裂病患者の社会生活指導』を除くと、国会図書館にも収蔵されておらず、後世に残すためにはぜひとも必要なとりくみです。
合わせて、「小坂英世著作目録」を更新しました。(12/8/20) 『動物に潜む人間性――幸福否定の生物学』は、昨日、アマゾンから販売が開始されました。定価は 3907 円です。これで今西進化論シリーズの完結になります。A5版3巻を合わせて 1665ページ になりました。
『動物に潜む人間性――幸福否定の生物学』のデータを、本日、学研に送付したので、今月末にはオンデマンド版としてアマゾンから刊行が開始されるはずです。A4版横組み 30 行で、総ページ数は 449 になりました。本年の出版予定はこれで完了し、次はいよいよ、来年に出版を予定している小坂英世先生の著作集のまとめと並行して、自閉症論の執筆準備に入ります。(10/1/20)
ただいま、『人間の「つながり」と心の実在』、『今西進化論と小田柿生物社会学』に続く第3弾『動物に潜む人間性』(仮題)の出版準備中です。本文の最終チェックに入っており、10 月中の出版を目指しています。
ただいま、コロナウイルス感染防止のため、密室での長時間の面談や外出を自粛するようにとの要請が出ています。そのため、当方への来室が難しい場合、スカイプや zoom といったインターネット映像通話を使われる方が少々多くなっています。また、初回の場合には、これまで当室にお越しいただくようお願いしていましたが、このような事情のため、遠隔での心理療法をご希望であれば、当面は最初からスカイプや zoom を使う方針に切り替えました。ご希望の方はご連絡ください。(4/3/20)
心の研究室は、人間の心が脳とは別個に存在することを明らかにすることをひとつの目的として、1996年4月、東京都品川区に開設されました。当研究室では、現代科学が避けて通り続けている、さまざまな現象を直視することにより、人間の心の本質を探究しています。実際に研究の対象としているのは、〈心因性疾患の真の原因〉と〈人間の心自体が持つ力〉のふたつです。一般の科学分野では、両者とも極度に不明瞭化されており……
これまでの出版物は、私の心理療法やその基本概念である“幸福否定”に関係するものと、超常現象関係のものとに分かれます。心理療法自体について書かれたものとしては、右欄にも表示されている『本心と抵抗』があります。その理論的背景やそれが導き出されるまでの経緯については、『幸福否定の構造』に書かれています。……
◆欧文専門誌・専門書寄贈先募集

30年ほど前にアメリカの心身医学雑誌に寄稿した、心理療法の中で録音テープに繰り返し雑音が記録された事例の報告を、このたび必要があって電子化したため、「これまでの出版物」の「事典・論文」の項に pdf として掲載しました(Presumed case of spontaneous PK in psychotherapy situation)。これは、通常なら稀にしか起こらないはずの現象が、きわめて強い心理的抵抗に直面すると、それを回避しようとして頻発することを示す、非常に貴重なデータです。とはいえ、実はこの現象は、それ以降もごくふつうに、しかも録音テープばかりでなく、媒体がMDやICに変わっても、同じように起こり続けています。さらには、電話やスカイプでの心理療法でもごくふつうに起こります。ひどい場合には、声が全く聞き取れないほど大きな雑音が続いたり、接続が切れてしまったりします。そしてそれは、強い抵抗の目印として実用的に利用されているのです。こうした現象は、超常現象研究史上でも全く知られていないので、いずれ詳しく報告する予定です。また、この拙論は、現在の幸福否定という考えかたに辿り着く前の、まだ小坂療法のライバル理論をそのまま適用していた時代に書かれたものなので、その点でも興味深くお読みただけると思います。なお、この論文は、印刷前にゲラを見る機会が与えられなかったため、私の名前が誤植されています。(2/09/12)
|
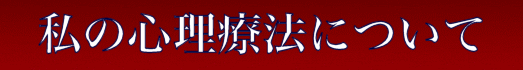
私の心理療法は、現在その存在がほとんど抹殺されている小坂英世先生の“小坂療法”から出発し、経験のみをもとにして、長い時間をかけ徐々に発展させてきたものです。最終的にはほとんどの点で全く違ったものになりましたが、小坂先生が世界に先駆けて樹立した、“反応”という客観的指標を利用する実証的方法は、そのままの形で踏襲しています。 私の心理療法の方法や理論の進展の経緯については、『幸福否定の構造』に詳しく書かれています(月刊誌に連載された「心理療法随想」には、当初の事例の一部が具体的に紹介されています)。 ちなみに、小坂先生の方法論がいかに革命的なものであったかについては、『幸福否定の構造』や『加害者と被害者の“トラウマ”』に詳述されています。なお、1973 年頃に私が録音した小坂教室の模様は、プライバシーの問題もあるため、おそらくごく一部になるでしょうが、いずれ本サイトで公開する予定です。これは、歴史的に見て、きわめて貴重な資料です。 本欄では、私の心理療法の基本概念のうち、重要なものについて手短に解説します。いずれの項目も、人間である限り、民族や時代に関係なく誰にでも当てはまるはずなのですが、いずれも根本から常識に反しており、他の心理療法やカウンセリングには全く見られない概念ばかりであるうえに、以下に述べる〈抵抗〉というものが万人にあるため、ほとんどの方にとって非常に理解しにくい――あるいは、観念的には理解できても、感情的に受け入れにくい――と思います。詳細な内容については、拙著をお読みいただければ幸甚です。なお、当サイトおよび私の心理療法で使われる用語を検索するには、右上の google サイト内検索をご利用ください。 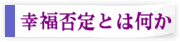
〈幸福否定〉とは,自ら望む幸福感が意識に昇るのを妨げようとする,無意識的な強力な意志のことです。この意志の強さは、まさに想像を絶するほどで、その存在を発見してから既に 25 年以上が経過しているにもかかわらず、今なお、その強さを再認識させられ続けています。 これまで集積してきた証拠を優先する限り、幸福を否定しようとする強い意志は、育てられかたなどの環境的要因とは無関係に,本来的に人間全般に内在するものと推定せざるをえません。この意志は、本能に匹敵するほどの強さを持ち、人間という存在のさまざまな側面を,特にその重要な側面を、意識に悟られないようにしながら自在に操っていると,私は考えています。心因性の症状は、ストレスなどの外部の要因によって起こるものではなく、そうした操作の結果として作りあげられるものであり、したがって、動物には見られない、非常に人間的かつ高度な産物であることになります。 わかりやすい比喩を使って表現すれば,聖書に登場する悪魔サタンのような,恐るべき力を持った存在が,生まれながらにして,ほとんど意識されることなく,各人の心の奥底に潜んでおり,黒幕のようにして絶えずその力を行使しているということです。 もちろん、現在の科学知識や常識に基づいて考えれば,そのようなことがあるはずはないでしょう。人間には、そこまでのことをする理由もなければ力もないではないか、と考えるのが世の常識なので、愚かしいにもほどがあるというものです。しかしながら、科学的根拠に乏しい現行の科学知識や常識から離れ、客観的指標のみを使って浮き彫りにしてきた事実群を尊重する限り、どの角度から見ても、そのような結論に到達せざるをえないのです。 ところで、幸福否定という意志の存在は、個人や人間全体にとってマイナスにしか見えないかもしれませんが、決してそうではありません。乗り越えるべき課題を、幸福否定という仕組みによってあえて作りあげ、自らに突きつけていると考えることができるからです。
動物には決して見られない修行という方法は、進んで自らに負荷をかけることを通じて、自らの人格的成長を目指す、まさに人間特有の方法です(したがって、精神分析のような受動的人間観ではこれを適切に説明することはできません)が、それと相同的な仕組みとして幸福否定が存在するのではないか、ということです。このことは、自分の病気や悪しき性癖を、抵抗に直面することを通じて、ある程度にせよ乗り越えた人たちを見るとはっきりします。薬により安易に症状を抑えた場合と違って、多かれ少なかれ、人格の成長を伴うからです。 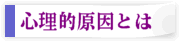
幸福否定という考えかたからすると、心理的原因は、悪いことではなく、当人にとってよいことでなければなりません。これは、客観的指標を使って経験的に導き出された結論であり、勝手な推測に基づく空論ではありません。私の考える心理的原因には、時間的近接や記憶の隠蔽など、いくつかの厳密な条件があります。 たしかに精神分析の昔から、幸福恐怖症などという“病名”は知られていました。しかしながら、これは、そのような傾向を持つ一部の人にしか当てはまらないことが大前提になっている概念です。それに対して、私の言う幸福否定は、精神分析とは視点が正反対で、民族や時代を問わず、人間であれば多かれ少なかれ誰にでも内在することを想定している、非常に普遍的な概念なのです。 反省を迫られる出来事(反省を通じて進歩するきっかけを与えてくれる出来事)を別にすれば、心因性の症状は、本人にとって悪いことが原因で出ることはないのですが、人間の意識は、症状が出た後に、その原因として悪い出来事(自分にとって負担になる、ストレスのようなもの)を探し出そうとする傾向を抜きがたく持っています。逆に言えば、好事を原因として探そうとすることは絶対にないということです。実は、これも幸福否定のひとつの現われなのです。 専門家の側も、世の常識やストレス理論という常識的原因論に忠実に従って、悪いことを心理的原因と決めつけてしまいます。それに対して、うつ病では、昇進や家の新築や結婚や出産などの好事に関係して発症することが、発病状況の研究によって知られています。虚心坦懐に観察すれば、それだけで常識とは異なる結論が導き出されることは往々にしてあるものです。
しかし、心理的原因に関係する出来事には、このように大きなものはほとんどありません。出来事としては日常的な些末事であっても、本人に大きな幸せをもたらすものが、心因性症状の原因になるのです。だからこそ、周囲にも原因がわかりにくいわけです。この問題については、『本心と抵抗』の第4章および第5章で、実際の探りかたを含めて、かなり詳しく扱っています。 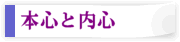
〈本心〉と〈内心〉とは、人間のいわゆる無意識の中に、半ば独立して存在するふたつの心の層のことです。本心は、自らを向上させるために内心を利用している側面があるらしいので、実際にはもっと複雑なようですが、内心は、人間の本質たる本心を否定する目的で存在していると考えるとわかりやすいでしょう。 精神分析などで想定している従来的な無意識は、あくまで西洋風に、意識を中心にして考え出された常識的概念ですから、理解しやすい半面、致命的な限界も持っています。それは、意識が許容しない概念や事柄は、意識に昇りえないため、着眼や着想に至ることすらないということです。 また、何らかの出来事を通じてその一端が表出しかかったとしても、意識がそれを“解釈”する段階で深刻な歪みが発生してしまうはずです。その結果、観察事実が、ひいては“科学知識”が大きく歪められてしまうわけです。その“歪み”が比較的少ないまま意識に到達したものが、直観と呼ばれる、従来的な知識を超えた着想になるのでしょう。 私の心理療法では、いわゆる無意識の側を主体に考えるため、視点が全く異なります。内心にしても、その下に隠されている本心にしても、非常に強い意志と能力とを合わせ持っているため、自らの心身を、特に幸福を否定する方向には自在と言ってもよいほどに、しかも間髪を入れずに操ることができます。
そして、自分の意識が望んでいたはずの幸福がいざ到来すると、あるいは到来しそうになったことを内心が察知すると、その幸福心が意識に昇る前に、幸福心を起こさせる出来事の記憶を消すなどの操作をするのと並行して、自分の心身に変調を起こさせて“不幸”を作りあげ、意識をその幸福から遠ざけようと誘導するわけです。意識側から見れば完全犯罪のようなことが、すべての人間の心の内で、ごく日常的に行なわれているようなのです。…… 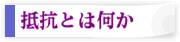
以上の説明からおわかりいただけるように、私の心理療法で言う〈抵抗〉とは、世間の常識や精神分析などの心理療法理論が想定するものとは正反対の概念で、要するに幸福に対する抵抗という意味です。これは、私の心理療法では、幸福否定と表裏一体の関係にある最重要の概念です。 人間は、特に先進諸国に住む現代人の多くは、幸福を追求する一環として、自分の人格や能力を高めたい(より正確に言えば、引き出したい)という根元的欲求を持っています。ところが、上述のように、いざそれが到来するか到来しそうになると、それが大きなものであればあるほど素直に喜ぶことができません。そうした素直な感情が意識に昇る前に、内心が止めてしまうのです。そのような抵抗の一環として――幸福に水を差すようにして――さまざまな心因性の症状や問題が作りあげられることになるわけです。 しかし、ほとんどの場合、相対的に小さな幸福は意識で許容され、それが繰り上がる結果、実際よりも大きな幸福として感じられる場合が多いようです。そのため、幸福を全否定する一部の人たちを除けば、自分がより大きな幸福を否定している事実に気づくことはまずありません。 逆の方向から眺めた場合にも、従来とはかなり違った風景が見えてきます。心底から望む幸福を避けるような生きかたを“首尾よく”続けている限り、心因性疾患を起こすこともなく、まさに“順風満帆”な人生を送りやすいことになるからです。 人類が生活に追われるだけの一生を送っていた、つい最近までのいわば動物的な時代には、平穏無事な生活こそが理想の生きかたとされていました。しかしながらそれは、現代の先進諸国に住む人間が心底から望む生きかたとは言えないのではないでしょうか。いわば雌伏的な生きかたからようやく解放され、より高度な幸福を求める余裕が生まれつつある現代では、生活を犠牲にしてまでも、冒険的な生きかたや“自己実現”のほうを優先しようとする人たちが、おそらく以前よりもはるかに多くなっているからです。
そのような側面から考えても、心因性疾患を起こすということは、決して悪いことではないことになります。動物的なもの(精神分析で言う快楽)にあらざる人間の幸福(人間的な喜び)を追求している現われでもあるからです。これは、決して慰めで言っているわけではなく、本当にそうなのではないかと私は思っているのです。…… 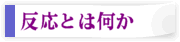
私の心理療法で言う〈反応〉とは、しばらくのあいだ持続する“症状”とは異なり、日常生活の中でも、以下に説明する“感情の演技”の中でも、ごくふつうに起こる心身の一過性の変化(眠気、あくび、心身症状)を指す言葉です。いわゆる新型うつ病などで知られるようになった、状況に応じて反応(あるいは症状)が出たり引っ込んだりする現象(以下の「対比とは何か」参照)も、反応の実例としてわかりやすいものでしょう。なお、この反応という概念は、小坂先生によるものを除けば、心理療法理論としてであれ何であれ、これまで全く存在しませんでした。 幸いなことに、最近、その格好の実例が知られるようになりました。それが、書店に入ったとたんに便意を催すとされる“青木まりこ現象”です(この現象については、『本心と抵抗』の第1章で詳細に検討しています)。これは、すぐれた美術作品に接すると心身の種々の変化を起こすとして、比較的最近、西洋で知られるようになった“スタンダール症候群”と並んで、反応自体に名前がついている珍しい例です。 “ストレス”という考えかたでは、ストレッサーにさらされ続けると、徐々に心身に影響が及び、最終的に心身症状が出ることになっていますが、実際にはそうではありません。もちろん“青木まりこ現象”もそうですが、幸福否定を起こす出来事に直面すると、それまで何ごともなかった状態から、まさに一変して下痢などの身体症状が出現するのです。ストレス理論では、こうした瞬時の変化は想定されていませんし、現行の科学知識でも、これを説明することはもちろんできません。
感情の演技の中で、たとえば鼻漏が起こることは珍しくありません。それは一般に、2分間の感情の演技を始めるとまもなく起こり、終わるとその瞬間に止まる、という経過をたどります。一見するとアレルギー反応ですが、潜伏時間がどうやら必要なさそうなことと、感情を作るのをやめた瞬間に止まるという形をとることから、別の理由を考えなければならなくなります。しかしながら、現在の科学知識や医学知識の中には、この現象を的確に説明する概念は存在しないのです。
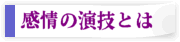
〈感情の演技〉とは、私の心理療法の中で、ほとんどの場合、喜びをはじめとする素直な感情を、なるべく実感を伴うようにしながら、演技するような形で作ろうとする方法のことです。これは、心理的原因を探ることと並んで、私の心理療法で最も重視されている方法です。 たとえば、自分の病気がよくなったり問題が解決したりすることは、誰もが望んでいるはずなのですが、実際にそうなった状況を想定して、その時に出るはずのうれしさをリハーサルのようにして作ってもらうと、驚くべきことに、誰であれ(演技を仕事にしている俳優でも)、そうした感情を作るのが非常に難しいのです。そこで抵抗が起こって、反応が出るわけです。 従来的な方法とは全く違うのでわかりにくいでしょうが、感情の演技は、感情を作る訓練ではなく、内心に抵抗のある素直な感情を意識で作ることを通じて、意識を内心の抵抗に直面させ、わずかずつでも内心の力を弱める目的で行なうものです。ところが、何回繰り返しても、あまり感情ができるようにならないため、“はりあい”といったものはほとんど感じられません。それどころか、その感情を意識に作らせないための手段として、内心が心身の反応を引き起こすため、意識にとって感情の演技は苦痛でしかないわけです。意識がそう思い込むよう仕向けることも、反応のひとつの目的になっています。 常識とは裏腹に、自分にとって悪いことは、抵抗なくいつまでも考えることができるのに対して、自分にとって幸福なことを実感を持って考えようとすると、強烈な抵抗が例外なく起こってしまうのです。ちなみに、このように誰にでも簡単な方法で確認できる普遍的現象が、これまで全く知られずに来たことは、人間にあまねく存在する強力な抵抗のためとはいえ、非常に不思議な感じがします。
感情の演技を繰り返しさえすれば、依然として感情ができなくても、それだけでさまざまな好転が起こることは、既に明確に確認されています。ただし、次に説明する〈好転の否定〉という現象があるため、ことはそう簡単ではありません。…… 
自分の病気がよくなったり、問題が解消されたりすると、そうした好転が自分の(意識の)許容範囲にあるうちは素直に喜ぶわけですが、心理療法を続けていると、それを超えてしまう時がいつか来ます。〈好転の否定〉とは、いわば過分の好転に由来する、自らの許容範囲を超えた幸福を、抵抗のため素直に喜ぶことができないため、それを意識に昇らないよう操作しながら心因性の症状を作りあげてしまう現象のことです。ふしぎに感じられるかもしれませんが、これは、幸福の否定が存在することから必然的に生ずる現象です。 この場合の特徴は、一部には意識が許容する好転もあるために、好転した部分と、好転を否定した結果としての症状とが混在することです。そのため、事情を知らない人が見ても、どこか違和感があるものです。 もうひとつの特徴は、好転の否定による症状が、時間の経過とともに自然に解消に向かうことです。しばらく“ケチ”をつけて、それで気がすめば矛を収める、という表現が実態に近いでしょう。しかし、好転が大きい場合には、それが解消されるまでにかなりの時間がかかることもあります。 一般に知られている現象で比較的これに近いのは、一流のスポーツ選手や芸術家に見られる“スランプ”でしょう。精進を重ねた結果、本当は技術や能力が向上しているのに、意識でそれを素直に認めることができないため、技術や能力が向上しなかった“証拠”を作りあげ、それを意識に突きつけるということです。
この抵抗を乗り越えれば、大きな進展が自然に浮上するわけですが、意識側からすれば、それを乗り越えるまで大変な苦しみが続くのです。その苦しみは、自分の意識を説得するためのものなので、作りあげたものとはいえ、非常に大きいわけです。…… 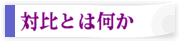
私の心理療法で言う〈対比〉とは、時間的、空間的、対人的、状況的な変化に沿って、心因性の症状が急激に変動する現象のことです。先ほどもとりあげた新型うつ病では、仕事に行こうとするとうつ状態などの心身症状が起こるのに、遊びに行く時には起こらないどころか、むしろ元気になったりするなどの変化が知られていますが、これも対比という現象に当たります。 これらは、仮病や自己暗示によるもののように見えるでしょうが、そうではありません。本当は、何らかの出来事を通じて仕事に喜びを感じるようになったのに、自分の意識にその幸福感を否定する手段として、仕事に向かう時に症状を作るだけでなく、それ以外の活動をする時には症状を消し去るという戦略を(内心が)とることによって、仕事がいかに苦痛であるかを自分の意識により強く印象づけようとしている、ということなのです。 家の中では頭痛などの症状が絶えずあるのに、玄関を一歩出ると、その瞬間にその症状が消えたり、いつも具合が悪くて自宅で寝てばかりいる人が、友人から電話がかかってくると、その瞬間から元気になってふつうに話をするのに、電話を切ると、やはりその瞬間から症状がぶり返すという経験を持つ人は少なくないでしょうが、これも、対比という現象に当たります。その場合には、世間で考えられているように、家庭生活の中に“ストレス”や“トラウマ”があるどころか、そこに、意識で認めようとしていない真の幸福が隠されているということです。 もちろん、記憶も並行して操作されます。つまり、幸福であるはずの時間や空間で過ごした記憶が消え、それ以外の記憶は消えないという形をとるわけです。そしてそれは、たとえば高校生以前の自宅内の記憶がほとんどないのに対して、玄関から一歩出た後の記憶は鮮明に残っている、などという結果になります。そしてそれは、世間でも専門家の間でも、その戦略に乗せられて、自宅でひどいことがあったためだとして、事実とはまさに正反対に解釈されてしまうのです。 子どもの不登校でも、ほとんどの場合、時間的、状況的に同じ現象が見られるはずです。また、自分から希望して大学院や専門学校、カルチャー・センター、自動車教習所などに通っている青年や成人が起こす“登校拒否”でも、同様の対比が起こるのですが、それらがあまり注目されないのは、その事実が広く知られてしまうと、不登校や登校拒否の、ひいては心因性疾患の真の原因に近づいてしまうおそれが、人間全般のいわゆる無意識に潜在しているためなのではないかと思います。
最近よく話題になる、“ペットロス症状群”も、対人的対比に関係した現象と言えるでしょう。実はこれは、対比の一方の側であり、ペットの“死による悲しみ”とは正反対の方向に、もう一方があるのですが、これは一般には全く知られていないはずです。…… |
近 刊 書
|