 �T�C�g�}�b�v�@
�T�C�g�}�b�v�@




 �@�_�o�S���w�ƐS���I�v���@�Q�D���ǂƂ����nj�Q�i�P�j
�@�_�o�S���w�ƐS���I�v���@�Q�D���ǂƂ����nj�Q�i�P�j
�@�T�b�N�X�搶�͂��̎�̖��Ɋ֘A���āA�u�ǂꂭ�炢�܂ł��펿�I�Ȍ����ɂ����̂ŁA�w���@�x�̖�肪�ǂꂭ�炢�܂ł�������Ă��邩������߂�͕̂s�\�v�i�T�b�N�X�A1992�N�A381-382�y�[�W�j�Əq�ׂĂ��܂��B����́A�������t�ɏd�x�̏�Q�������A���b�̂Ȃ��N�ɂ��Č�������̂ł����A�펿����Q�����l�����S�ʂɓ��Ă͂܂锭�����Ǝv���܂��B�����ł���Ƃ��Ă��A���Ƃ������R�Ƃ������̓I�v�������A���@�Ƃ����A�����҂̎�̐��ɊW����v�����d�������̂́A��͂�T�b�N�X�搶�̌d��ɂ����̂ł��傤�B
�@�������߂Ď��ǁi�������ǁj�����q�ǂ������ɐڂ����̂́A��w�̎��ǎ�������ɓ�����1968�N�̂��Ƃł�����A������ 50 �N�߂��O�ɂȂ�܂��B�T�b�N�X�搶�����ǂƍŏ��ɐڂ����̂�1960�N�㔼�������ł��i�T�b�N�X�A2001�N�A339�y�[�W�j����A����́A��r�I���������ɓ����邱�ƂɂȂ�悤�ł��B���̎��ǎ�������́A���Ɋ����ƂƂ��Ēm���Ă��āA��ɋ��s���ؑ�w�̊w���ƂȂ��Ћˏ[�i�������n�W���j�����S�ƂȂ��ĉ^�c����Ă��܂����m���P�n�B�����������Ȃ��������j�����o�[�́A���̌�A��w���������܂߁A�قƂ�ǂ���w�̋����E�ɂ��Ă��܂��B���ł͐����������ĕs�\�ł����A�Ћ˂���́A���̓����A���Ăŏo�Ă������NJW�̎�v�Ȓ�����_���̂قƂ�ǂɖڂ�ʂ��Ă��܂����B�܂��A��ɈǗё�w���_�ȋ����ƂȂ鎙�ʌ��T���A1970�N�܂ł̓��O�� 470 ���ɂ��̂ڂ鎩�Ǖ������W�߁A���̕����ژ^�����c�����Љ�ƒc����o�ł��Ă��܂��i���ʁA1970�N�j�B�������́A�����̉��b�ɂ������ɗ����Ă��܂����B
�@�Ћ˂��ǂ�قǎ��Ǖ����ɒʂ��Ă������́A�����̐����q��w�̏����Ȉ�A����M�`�搶�i1919-2006�N�j��1968�N�ɏo�ł����A���ǂ��������킪�����̐����w�������ǁx�́u�����v������Ƃ킩��܂��B�����ɂ́A1967�N�̏��ĂɁu�����h���� Wing �҂́w�����������ǁkEarly Childhood Autism, ed. by J.K. Wing�l�x��ЋˌN�i����S���w�Ȋw���j����q���ēǂ݁A�[�������v���A���̕Ғ����̂������ňӗ~���������Ă�ꂽ�Ə�����Ă���i����A1968�N�A�Y �y�[�W�j�̂ł��B���̕Ғ����ɂ́A�Ҏ҂̍Ȃł���A�p���̎������_�Ȉ�A���[�i�E�E�B���O�̘_�������������^����Ă��܂��B���[�i�E�E�B���O�́A��ɃJ�i�[��ӓ|�̎��nj�������ς����������҂ł�����A�������Ƃ��������ǂ�ł����Ћ˂���̎��͂̂قǂ��킩�낤�Ƃ������̂ł��B�܂��A�Ћ˂���́A�킪���̐��Ƃ̘_���Ɍf�ڂ���Ă���Q�l�������X�g�����āA��������M�������Ƃ��A���ꂼ��̕�����{���ɓǂ�ł���̂��A����Ƃ����ЂÂ��̂��߂ɍڂ��Ă��邾���Ȃ̂��𐄒f����悤�Ȃ��Ƃ����Ă��܂����B
�@���̍��́A���̂悤�ɁA���ǂƌ����J�i�[�^�̎��ǂ��w���Ă��āA���a���͂T���l�ɂЂƂ�ȂǂƐ��ԂŌ����Ă����قǒ����������ł����i���ۂɂ́A�E�B���O�i1928-2014�N�j��1964�N�ɍs�Ȃ�����������A�P���l�ɂS�A�T�l���x�Ɛ��肳��Ă����悤�ł��k�E�B���O�A1975�N�A10�y�[�W�l�B�������A����́A�J�i�[���������T�O�ɓK�����鋷�`�̎��ǂł��j�B�A�X�y���K�[�nj�Q�́A�ȉ��ɏq�ׂ闝�R����A�T�O�Ƃ��Ă͊��ɒm���Ă��āA�����͎��I���_�a���Ƃ��A�X�y���K�[�^���ǂƌĂ�Ă��܂����B���̂ӂ��̎��NJT�O���킪���ɓ������ꂽ�o�܂́A���̂悤�Ȏ����A�A�����J��p���ƈ���ď��X���ꂾ�����悤�ł��B
�@����搶�́A1962�N�ɁA�h�C�c�ŊJ�Â��ꂽ�ӂ��̊w��ɏ��҂��ꂽ�܂ɁA�E�B�[����w�̏����Ȉ�A�n���X�E�A�X�y���K�[�i1906-1980�N�j�̒m���������A�w��I����ɃE�B�[����w��K�₵�āA�A�X�y���K�[�Ƃ���ɐe����[�߂܂����B���̍ۂɃA�X�y���K�[�́A�@����݂ĖK�����邱�Ƃ���Ă��ꂽ�̂ł��B�R�N���1965�N11���A�A�X�y���K�[�́A�����ŊJ�Â��ꂽ�� 12 �ۏ����Ȋw��ɏo�Ȃ��邽�ߗ������邱�ƂɂȂ�܂����B����̕���搶�́A���������ĊJ�Â�����U����{�������_��w��i���A���{�����N���_��w��j�̉������悭���߂邱�ƂɂȂ������߁A�A�X�y���K�[�Ɉ˗����āA����œ��ʍu�������Ă�������̂ł����i����A1968�N�A�X�y�[�W�j�B����́A�uProbleme des Autismus im Kindesalter ���c�����ɉ����鎩�ǂ̏����v�Ƒ肷��u���ł����iAsperger, 1966�j�m���Q�n�B
�@����A�c����w�̎������_�Ȉ�A�q�c���u�搶�́A�W�����Y�E�z�v�L���Y��w�̐��_�Ȉ�A���I�E�J�i�[�i1894-1981�N�j�̂��Ƃ֗��w���Ă����i�q�c�A1963�N�A152�y�[�W�j���Ƃ���A���҂̊ԂŁA�u�^�̎��ǂ̓J�i�[�̂��̂��A�X�y���K�[�̂��̂��v�Ƃ����_�����N�������킯�ł��i���V�A2010�N�A130-133�y�[�W�j�B���̂悤�Ȏ����A�����A�ӂ��̊T�O�����藐��Ă������߁A�q�c�搶�́A1969 �N�R���ɋ��s�ŊJ�Â��ꂽ���nj�����c�̐ȏ�ŁA���̘_���ɏI�~����łׂ��A�u���I��������Ǐ�Ƃ��銳�������āw�����x�ƌĂԁv���Ƃ��Ă����̂ł����i���R�A�����A2002�N�A�T�y�[�W�j�B����ɂ���āu�ꉞ�̋��ʗ����ɒB�����v�i�q�c�A1969�N�A33�y�[�W�j�炵���A���ꂩ�炵�炭�̊Ԃ́A�A�X�y���K�[�̖��O�͏����Ă��܂����悤�ł��B
�@���̘_���́A���[���b�p�嗤�������A���������̂ł����B�A�X�y���K�[�́A1950�N�ɂU�T�ԂقǃA�����J�ɑ؍݂��Ă������Ƃ��������iFeinstern, 2010, p. 18�j�̂ŁA���I���_�a���Ƃ����T�O�������Ŕ��\���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł����A�����ł������Ƃ��Ă��A���ڂ��錤���҂͂��܂肢�Ȃ������Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B�����āA�A�����J��p���ł́A�p��ȊO�̘_���́A���Ƀh�C�c��̓i�`���Ƃ�������������ĂقƂ�Ǔǂ܂�Ȃ����߁A�A�X�y���K�[�̊T�O�́A���[�i�E�E�B���O��1981�N�� �g�Ĕ����h ����iWing, 1981b�j�܂ł́A�A�����J��p���ł͂قƂ�ǒm���Ă��܂���ł����iLyons & Fitzgerald, 2007�j�B���̂悤�Ȏ����A���������_���͋N����悤���Ȃ������̂ł��m���R�n�B
�@���̍��̎��Î{�݂́A�����ߕӂł͓s���~���u�a�@�═����ԏ\���a�@�i���ǂ��̑��k���B�ē��c�q�����B����M�`�ږ�j�ȂǁA���������ł����B�܂��A���{�Љ����w�́A�Έ�N�v�搶�𒆐S�ɂ��Ċ��Ɏq�ǂ���Ƒ��̎x�����n�߂Ă��܂����B��̓����s���Nj���̑O�g�ɓ����铌�����ǎ��e�̉�������ꂽ�̂́A�������߂Ď��ǂɐڂ���1968�N�̑O�N�ł����i�{�c�A1999�N�A138�y�[�W�j�B
�@���Ȃ��Ƃ������̎��ǎ��̉Ƒ��̑����́A�قڃJ�i�[�̌����ʂ�̓����iKanner, 1943, p. 217�j�������Ă��āA���e�ɂ͑�w�@�i�����̂��ƂȂ̂ŁA�����͋����j���C�������قǂ̍��w���҂������A��w�������t�A�ٌ�m�A�Ȋw�Z�p�����҂Ȃǂ��ڗ����Ă��܂����B���́A�ӂ���̎��ǎ��i����������w�Z��w�N�̒j���j�����Ă����̂ł����A���ꂼ��̕��e�́A�����鍑��w��w�@�Ƌ��s�鍑��w��w�@���o�Ă��āA�ӂ���Ƃ��Ȋw�Z�p�̗D�G�Ȍ����҂ł����B���̂����̂ЂƂ�́A�����Ȑ��w�҂̐e�F�ŁA���̌�A�傫�ȉ�Ђ̎В��ɂȂ��Ă��܂��B���̂悤�ȗ��j�I�w�i�ɏƂ炷�ƁA���݂́A�E�B���O�̍v����ʂ����c�r�l�ɂ��f�f��̕ύX�̂��߂Ȃ̂�������܂��A���������I�ɑ����iBaron-Cohen, 2008, Chap. 2�j�A���ǂƂ��������� �g�������h ���N���������������܂��B���ǘA���̂̕����傫���L�������Ƃ������Ƃł��B
�@�������́A���ꂼ��̉ƒ�ɓ����āA�O�o�����e�̑���ɖʓ|������A���o�C�g�Ƃ����`�ŁA�q�ǂ������Ɛڂ��Ă��܂����B�����āA���̊ώ@���A�T�ɂQ����x�ł͂���܂������A�Q�N�߂��ɂ킽���đ����Ă����킯�ł��B���Ԃ��������Ă���q�ǂ��₻�̐e�����Ƃ̍������h������܂����B����́A���n�ȃ��x���̂��̂ɂ͈Ⴂ�Ȃ��Ƃ��Ă��A�܂��ɏ����Ƃ��Ă͗��z�I�ȁu�֗^���Ȃ���̊ώ@�v�ł����B���̒��ŁA���ǎ������́A�{���n�ł���ƒ�ł͂ǂ̂悤�Ȑ��������Ă���̂��A�ǂ̂悤�Ȏ��ɂǂ̂悤�Ȕ���������̂��A�ǂ̂悤�ȏǏǂ̂悤�Ȏ��ɏo������̂��A�ǂ̂悤�ȓ��ٔ\�͂������Ă���̂��A���e��Z��o���Ƃ̊W�͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��Ȃǂ��A�ꏏ�ɗV��A�U��������A�H��������A���������肷�邱�Ƃ�ʂ��āA�����̊�ł����Ɋώ@���邱�Ƃ��ł����̂ł��B�U��Ԃ��čl����ƁA����́A�����v���Ă����ȏ�ɁA���ɋM�d�Ȍo���Ȃ̂ł����B
�@���ł��Y��܂��A�S�������q�ǂ��̂ЂƂ�Ə����ɎU���ɏo���������̂��Ƃł��B�U��Ԃ��čl����A��e���������ӂ��Ȃ��܂��������O�o�������̂͂ӂ����Ȃ̂ł����A���̎q�́A�����o��Ƃ����ɋ߂��̈ꌬ�Ƃɔ�э��̂ł��B�߂��Ȃ̂ŁA���͂Ă�����m�荇���̉Ƃ��Ǝv�����̂ł����A���ɂ��炸�A���̉Ƃ̒����珗���̋��ѐ������������̂ł��B�ςɂ܂܂ꂽ�v���Ō��ւ����ƁA�ڂ̑O�̕����ŁA���̎q���D�M�ɂ������^�o�R�̋z���k�����{�����̒��ɓ���悤�Ƃ��Ă���̂��A���̉Ƃ̎�w�炵���������K���ɂȂ��Ď~�߂Ă���Ƃ���ł����B�������Ȃ���A���̍b����Ȃ��A�ꕔ�͈��݂��܂�Ă��܂����悤�ł����B���́A���܂�̂��Ƃɋ�������ł����B���̎��ǎ��̌��́A�������Ďn�܂����̂ł��B
�@�����ЂƂ�ۓI�������̂́A������ԏ\���a�@���ǂ��̑��k���̃v���C���[���ŁA�����̎��ǎ����ώ@���Ă������̏o�����ł��B�����v���C���[���̓d���̕ǃX�C�b�`����ꂽ�Ƃ���A���̏u�ԂɁA���̏�ɂ����T�A�U���炢�̒j�����A�J�`�b�Ƃ������������ق��ցA��u�ł������������������̂ł��B���ǂ̎q�ǂ��́A���ɑS���������Ȃ��ꍇ�������āA���̎q���A���̂悤�Ȏ���̂��ߒ��o��Q���^���Ă����̂ł��B���̂��Ƃ����炩���ߐE�����畷���Ă����̂ŁA����������Ɖ��ɔ�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���āA���̎q�̗l�q�����������Ȃ���d���̃X�C�b�`�����Ă݂��̂ł����B���̏o��������A���̎q�͖{���͉����������Ă���炵�����Ƃ����߂Ă킩�����킯�ł��B
�@���ɂ��A�����I�Ȃ��Ƃł͂���܂����A���낢��Ȃ��Ƃ��o���I�ɒm��܂����B���Ƃ��A�ǂ̂悤�ɓw�͂��Ă��\�\��𗼎�ʼn������Ď��������킹�悤�Ƃ��Ă���\�\�K���ʂ̕��������Ă��܂��āA��Ɏ��������킹�悤�Ƃ��Ȃ����Ƃ�A�U���̃R�[�X�₻�̒��ōs�Ȃ��V���I�s�������Ȃ茵���Ɍ��܂��Ă��邱�ƁA���̏�ʂ�ɂȂ�ƃp�j�b�N���N�����ꍇ���������ƁA�������Ă��������̂ЂƂ�͓����̏�p�Ԃ̎Ԏ���i�����炭�j���ׂČ������邱�Ƃ��ł������ƁA���h�Ԃ₲�ݎ��W�Ԃ̂悤�ɍ�肪���G�Ȏ��p�ł��A�S������ꍇ�ɂ͉��������ɑ����ɕ`���邱�ƂȂǂ��A����ɂ́A�g�x������������h �� �g���ꐫ�̕ێ��h �� �g�N���[�����ہh �Ȃǂ̎��Ǔ��L�Ƃ����Ǐǂ̂悤�Ȃ��̂��Ƃ������Ƃ��A�m���Ƃ��Ăł͂Ȃ��o���Ƃ��Ă킩�����̂ł��B
�@�T�b�N�X�搶�́w�ΐ��̐l�ފw�ҁx�ɂ��A���ǂ̌����j���ȒP�ɋL����Ă��܂����A���ׂĂ݂�Ƃ��̍��́A���Ăł͊��ɓ����̃J�i�[���̊����_����]��Q���ւƁA�����_�̍��{�I�ȕύX���N��������Ȃ̂ł����B�������Ȃ���A�����̂킪���ł́A�A�����J�̐S���w�ҁA�o�[�i�[�h�E���������h�i1928-2006�N�j��1964�N�ɒ����A�_�o���B��Q�������Ƃ��鉼���iRimland, 1964�j��p���̎������_�Ȉ�A�}�C�P���E���^�[�ɂ��]��Q���iRutter, 1968�j�͒m���Ă͂������̂́A�܂������҂����Ȃ��A�J�i�[��A�����J�̐��_���͈�A�u���[�m�E�x�b�e���n�C�����句�����e�̗{��@�ɋN�����鎾���Ƃ����ʒu�Â����嗬�������悤�Ɏv���܂��B
�@���������h�́A���������̎q�ǂ������ǂ��������Ƃ���A�����̎��Ԃ������ĕ�����^���ɒ��ׂ�悤�ɂȂ�A���̌��ʂƂ��āA�S���_�����]�_�o�̔��B��Q�������ƍl�����ق������ɓK���Ă��邱�Ƃ��咣�����̂ł��B�J�i�[�́A���������h�̍l����F�߂āA�e�̗{��@�������Ƃ��Ă�������̍l��������P�A���ǂ̐e�����ɑ��ĎӍ߂��������ł��B���̂悤�Ȏ����A���������h�̂��̒����ɂ́A�J�i�[���������Ă��܂��B
�@�m���ɁA�ƒ���ł̎������̊ώ@������A�e�q�̐g�̓I�ڐG�����Ȃ��Ƃ�����ۂ͂���܂������A���a���͂����肷��܂ł̐���P�A�Q�N�Ƃ����Z���ԂɁA�{�l��Ƒ��̈ꐶ��傫�����E����قǏd�x�̎��ǂƂ����������A���ꂾ���ŋN������̂��ǂ����́A�������ɋ^��ł����B���̌�܂��Ȃ��A�킪���ł��A���������h��^�[����N�����l���������嗬�ɂȂ�A���݂ł́A�]�̊펿�I�ُ�ɂ�鎾���Ƃ����ʒu�Â����قڒ蒅���Ă���悤�ł��B
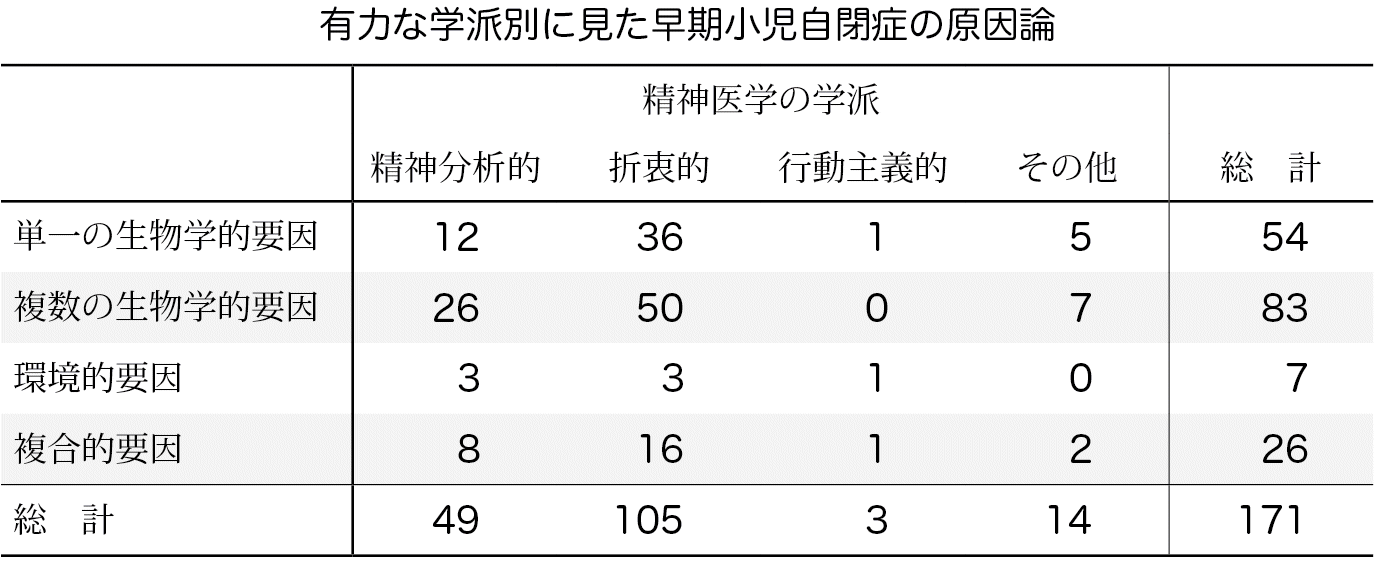
�A�����J�ōs�Ȃ�ꂽ���ǂ̌����_�Ɋւ��钲���̌��ʁB�w�h�ʂɏW�v����Ă���BGallagher, Jones & Byrne, 1990, p. 937 �̕\�Q�����Ƃɍč\���B
|
�@�������́A�����Ō��Ă���q�ǂ������������ꐬ�l�ɒB�������A���������ǂ̂悤�Ȑ���������悤�ɂȂ�̂��Ƃ������ɁA�����S�������Ă��܂����B���̎q�ǂ������́A1960�N���ɐ��܂�Ă��܂�����A���ł� 60 �ɋ߂��N��ɂȂ��Ă���͂��ł��B���̎q�ǂ������Ƃ́A���̌�܂��Ȃ��ڐG���Ȃ��Ȃ��Ă��܂�������A���݁A�ǂ̂悤�Ȑ��������Ă���̂��́A�c�O�Ȃ���킩��܂���B
�@���l�ɂȂ������NJ��҂ɂ��Ă̒��������͂܂����Ȃ��悤�ł����A�������������A��͂莩�ǂ̗\��́A���ɃJ�i�[�^�ƌ����钆�j�Q�̏ꍇ�ɂ́A�悢�ȂǂƂ͂ƂĂ������Ȃ��ɂ���܂��B�s���~���u�a�@�̒����W�搶�i1931-2013�N�j��1988�N�ɂ܂Ƃ߂��u���ǂ̒����\��v�i�����A1988�N�j�Ƃ��������_���ɂ��A�u�啔���̒����͎��ǂ̗\�オ�ɂ߂Ă��т������Ƃ��w�E���Ă���A�ꕔ�̗ǍD�Ȍo�߂����ǂ���̂͂��Ƃ��ƒm�I�����̍����Ǘ�ł��邱�Ƃň�v���Ă���v�i�����A498�y�[�W�j�Ɩ��L����Ă��܂����A�����Ɏ����ẮA�u���ǎ҂����������𑗂�悤�ɂȂ邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��ƍl�����Ă���v�i�����A612�y�[�W�j�Ə�����Ă��܂��B
�@1943�N�ɃJ�i�[�́A��ɑ����������ǂƖ��Â��邱�ƂɂȂ� 11 ��̎�����A���������a�Ƌ��ʓ_�������Ȃ���A�����̓_�ł���Ƃ͈قȂ�a�������������Ƃ��ĕ����iKanner, 1943, p. 248�j�킯�ł����A���� 30 �N�قnj�ɓ�����1972�N�ɁA���� 11 ��̒ǐՒ����̌��ʂ��A���������҂ƂƂ��ɔ��\���Ă��܂��iKanner, Rodriguez & Ashenden, 1972�j�B���ۂɒǐՂł����̂͂X�Ⴞ���ł������A���̂����̂Q��ł́A�Ă삪������悤�ɂȂ�A�c��V��̂����̂S��͎{�݂Ɏ��e����Ă��܂����B���̂悤�ɁA�X�ᒆ�U��ŗ\�オ���������̂ɑ��āA���̂R��̗\��͔�r�I�悭�A���̂����̂ЂƂ�͔_�Ƃɗa�����đ�w�𑲋Ƃ��Ă��܂��B�����ЂƂ�́A��Ə��ŐE�ƌP�����A���̋Z�p�����Ă܂��߂Ɏd�������Ă����Ƃ������Ƃł��B�������A���������҂͂ЂƂ�����Ȃ������悤�ł��B
�@�ŋ߂̒��������ł��A�����悤�Ȍ��ʂɂȂ��Ă���悤�ł��B�V���K�|�[���̌����҂炪�A ����܂Ŕ��\����Ă��� 25 ���̒����i���ǂ���уA�X�y���K�[�nj�Q�B���v 2043 ���j���܂Ƃ߂��ɂ��A�����ȏオ�ˑR�Ƃ��ĉ��炩�̎x�����Đ������Ă���A�F�l����l�̂���҂͂قƂ�ǂ��炸�A�d���ɏA���Ď����������������Ă���҂̔䗦���Ⴂ���Ƃ����炩�ɂȂ��������ł��iMagiati, Tay & Howlin, 2014, p. 83�j�B��͂�A�ΐl�I�A�Љ�I�ȏ�Q�́A�Ȃ��Ȃ���������Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤�B
�@�������A���[���b�p�̌����҂������A����Ȓm�\������ 112 ���̐��l�̎��NJ��҂�Ώۂɍs�Ȃ��������ɂ��A�Z���l�N����w�𑲋Ƃ����҂� 24 �p�[�Z���g�A��̎d���ɂ��Ă���҂� 43 �p�[�Z���g�ł���A�������A�x�����Ȃ���ł͂���܂����A�e���𗣂�Đ������Ă��܂����B�܂��A���������⓯���������ɂ킽���đ����Ă���҂� 16 �p�[�Z���g�i19 ���j�قǂ����������ł��iHofvander et al., 2009�j�B���ϓI�Ȓm�\�����A�����鍂�@�\���ǂł���A���̂悤�ȏɂ���Ƃ������Ƃł��B
�@�ł͎��ɁA���̂悤�Ȍ���������܂��������ŁA���ǃX�y�N�g�����ɓ���Ƃ���Ă��鉽�l���̎�����A��Ƃ��āA���ꂼ��̎��`�I�����ʂ��Č��Ă䂭���Ƃɂ��܂��B�����������삪����Ƃ������Ƃ́A�\�オ����߂Ă悩�����l�����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@���̒����̒��ŁA�T�b�N�X�搶�́A�O�����f�B������̕a���ɉ����āA�����Ȏ��nj����҂ł���h�C�c�o�g�̉p���̔��B�S���w�ҁA�E�^�E�t���X�̊��߂ŁA�O�����f�B��������d����⎩��ɖK�˂����̗l�q���ڂ����Љ�Ă��܂��i�O�����f�B�������E�I�ɗL���ɂȂ����̂́A�T�b�N�X�搶�̂��̒����̂������̂悤�ł��j�B������m��ɂ́A������_����ǂ����ł͂��߂ŁA��͂�X���_�o�w�̐��_�������āA�{�l�̕�炵�Ԃ�������̖ڂŌ�����A�������̒��ł����ɐڂ����肷��K�v������Ƃ������Ƃł��B
�@�O�����f�B������́A���ǂƐf�f����Ȃ�����A����̏�Q����������w�͂𑱂��A��w�ł͐S���w���w�сA����ɂ͑�w�@�ɐi�w���ē����w�̔��m�����擾���܂����B��w���ƌ�́A�q���ƒ{�����Ȃǂœ����A���݂͎����Ђ��o�c���A�傫�Ȑ��������߂Ă��邱�Ƃɉ����āA��w�̋����E�ɂ����Ă��܂��B���̂悤�ɁA�o�ϓI�ɂ��Љ�I�ɂ����S�Ɏ������Ă���̂ł��B���̓_�ŃO�����f�B������́A���E�I�Ɍ��Ă���߂Ē��������݂ƌ�����ł��傤�B���̂��Ƃ́A�ŏ��̒��� Emergence: Labeled Autistic�i�M��A�w��A���ǂɐ��܂�āx�k1994�N�A�w�K�����Њ��l�j�Ƀo�[�i�[�h�E���������h�����u�����̎��v������Ƃ͂����肵�܂��B���������h�́A���̒��ŁA�O�����f�B������̌o���ɂЂ�������Q���Ă���̂ł��B
�@���Ȃ݂ɁA��������ǂ��Ďv���̂́A���ǂƂ`�c�g�c�i���ӌ��ׁE��������Q�j��g�D���b�g�nj�Q�Ƃ̊Ԃɂ́A�Ǐ�̋��ʐ��Ƃ������ƈȏ�ɁA�A����������̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł��B���ɂ��̈�ۂ��������Ƃ����ꍇ�A���ǃX�y�N�g������Q�Ƃ������̂����݂��A���̒��̏Ǐ�Ƃ��đ�����s���ӂ�`�b�N�≘���ǂȂǂ�����ƍl����ׂ��Ȃ̂ł��傤���B����Ƃ��A�����ƍ��{�I�� �g�����P�ʁh ��ʂɖ͍����ׂ��Ȃ̂ł��傤���B���̂悤�ȍ����I�ȋ^�O��������邱�Ƃ��炵�Ă��A�O�����f�B������̈ʒu�Â��͔��ɏd�v�ł���悤�Ɏv���܂��B
�@�O�����f�B������́A���w�Z�̎��ɒm�\�w���� 137 ���������i�O�����f�B���A1994�N�A80�y�[�W�j���Ƃɉ����āA���K���邱�ƂȂ����}����������Ȃǂ́A�T���@���I�Ȕ\�͂������Ă��܂��i�T�b�N�X�A2001�N�A361�y�[�W�j�B���������āA�f�f�Ƃ����_�ł́A���ǂł���Ƃ��Ă��A�����ɍ����\�͂����������@�\���ǂ�A�X�y���K�[�nj�Q�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤���A����ɂ��Ă��A�o�ϓI�A�Љ�I�Ɏ������Ă���Ƃ����_�Ŕ��ɒ��������Ƃɕς��͂���܂���B
�@���ǂƐf�f����Ă��邱�Ƃ�����킩��悤�ɁA�O�����f�B������́A�ΐl�I�A�Љ�I�ȊW�����Ƃ��Ă��܂��B�Ƃ͂����A���ǂ̊��҂Ƃ��Ă͒������A�c�t�����ォ�玟�X�ƗF�l������Ă���݂̂Ȃ炸�A���̗F�l�����Ƌ����I�ȍs�������Ă���̂ł��B�܂��A���̎q�ǂ������ɂ��炩����ƁA�����{����o���A�����@�����艽���𓊂������肷��Ȃǂ̖\�͍s�ׂɑ����Ă����܂��B�����āA�����������Q�S�������邽�߂ɁA���l���ׂ��悤�ȉR�����o���Ȃ��畽�R�Ƃ��Ƃ����A���ǎ��Ƃ��Ă͔��ɍ��x�Ɏv���邱�Ƃ����Ă���̂ł��i�O�����f�B���A1994�N�A52-53�y�[�W�j�B���̂悤�ɁA�F�l�����l�����邱�Ƃ�A���l�Ƌ����I�ȍs�����Ƃ�邱�ƁA�{��╜�Q�S�Ȃǂ̊���������Ă��邱�ƁA�R��ړI�I�ɂ��Ă��邱�ƂȂǂ́A��������A���ǂ̓����Ƃ����X������́A���Ȃ��E���Ă��邱�ƂɂȂ�͂��ł��B
�@�܂��A������ǂތ���A�ΐl���|�ǓI�ȑ��ʂ͂������Ƃ��Ă��A���w�Z���ォ��R�~���j�P�[�V�����ɂ͂���قǕs���R���Ă��Ȃ��悤�Ɍ����܂����A��e�̏،��ɂ��A���̍��ɂ͎���ł̖��͂قƂ�ǂȂ��Ȃ��Ă��������ł��i�����A62�y�[�W�j�B�Ǐɂ���ĕω����Ă����Ƃ������Ƃł��B�����̓_�𑍍�����ƁA�{�l�̑�ςȓw�͂��������̂͂܂������Ȃ��Ƃ��Ă��A�O�����f�B������̎��ǂ́A�����Ɍy�ǂȂ��̂Ɣ��f����������Ȃ��ł��傤�B
�@�O�����f�B������́A�݊��Ő��Ԃ��ꂵ�Ă��Ȃ����߁A���Љ�ɏo������A�ŏ��̂����͂悭�l�ɂ��܂����ꂽ�藘�p���ꂽ�肵�������ł��B�������A�T�b�N�X�搶�ɂ��A���̏�Ԃ́A�u�ӂ��̗ϗ��I�������琶�܂��̂ł͂Ȃ��A���܂����₢���𗝉��ł��Ȃ��Ƃ��납�琶������̂ŁA���ǂ̐l�����ɂ͂قƂ�Ǘ�O�Ȃ��݂���v���̂ł��B�O�����f�B�����g�́A���̖��ɂ��Ď��̂悤�ɍl���Ă��邻���ł��B�w�ΐ��̐l�ފw�ҁx����̈��p�Ȃ̂ŁA�T�b�N�X�搶�̗���ŏ�����Ă��܂��B
�@���N�̂����ɁA�u���C�u�����[�v���Q�Ƃ���Ƃ����ԐړI�ȕ��@�ŁA���̒��̎d�g�݂𑽏��w�B�ޏ��͎����ʼn�Ђ�ݗ����A�܂��ƒ{�p�{�ݐ��̃R���T���^���g���v�m�Ƃ��Đ��E��Ɏd�������Ă���B���ƂƂ����_�ł͔ޏ��͑听���������߂����A�l�ԓI�Ȃ������\�\�Љ�I�A���I�ȊW�\�\�̂ق��́A�u�l���v�ł��Ȃ������B�u�d�����킽���̐l���̂��ׂĂł��v�Ɣޏ��͉��x���������B�u�ق��̂��Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���v�i�T�b�N�X�A2001�N�A353�y�[�W�j
�@���p�����́u���C�u�����[�v�Ƃ́A���G�Ȑl�Ԃ̓��@��Ӑ}�⊴��𗝉����邽�߂ɁA�O�����f�B�����S�̒��ɍ�肠���Ă���A�c��Ȍo���̋L���̌n�̂��Ƃł��B�K�v�ɉ����Ă�����Q�Ƃ��邱�ƂŁA�ǂ̂悤�Ȏ��ɂǂ̂悤�ȑΉ���������悢�̂���m��킯�ł��B�l�ԊW�̂��т��A�����Ƃ��Ē��ڂɂ킩��Ȃ��ƁA�����̐l�ԊW����łȂ��A�l�ԊW���`���ꂽ������f��Ȃǂ̃t�B�N�V�����ł����Ă��A���ꂪ���G�ł������قǗ����ł��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B�������A��������Ǔ��L�̏Ǐ�ƌ�������̂ł͂���܂���B���̎��ɒu����Ă����u���C�u�����[�v�̑傫������Ȃ���A����قǒ��������ۂł͂Ȃ�����ł��B
�@����ɑ��ăO�����f�B������́A�����O����������S�����āA���݂��܂��U�炵����F��ŎŐ����@��Ԃ����肵�āu����߂���߂���ɂ��Ă���������Ȃ��v�ƒ�Ă����̂ł��B�����āA�C�k�������悤�Ɍ���������ׂ��H�삵�Ȃ���A�ӂ���ł��̒��z�����s�Ɉڂ����Ƃ����̂ł��i�O�����f�B���A1994�N�A53-54�y�[�W�j�B���̂�������́A����̐S�̓������킩��Ȃ��Ƃł��Ȃ����Ƃł��B����ɉ����āA���̍s�ׂ́A�����ׂ����ƂɃO�����f�B�����g�̎哱�ɂ����̂Ȃ̂ł��B
�@���̈���ŁA�T�b�N�X�搶�������Ă���悤�ɁA�O�����f�B������́A����Ƃ͎��I�ɈقȂ�ԓx�������Ă��܂��B�T�b�N�X�搶�Ə��߂đΖʂ������A���H�͂��K�˂Ă����T�b�N�X�搶�̗����A��J��Ƃ�����Ԃ��v����邱�Ƃ��S���ł��Ȃ������悤�Ȃ̂ł��B�Ќ����߂�O�u�����Ȃ��A�����Ȃ�d���̘b���n�߁A�u�ւƂւƂɂȂ����v�T�b�N�X�搶�́A��ނȂ������̂ق�����R�[�q�[�����]����������Ȃ��Ȃ����̂ł����B�T�b�N�X�搶�́A�O�����f�B������Ƃ̏��Ζʂ̗l�q�����̂悤�ɏ����Ă��܂��B
�@����ɑ��āu���݂܂���A�C�Â��Ȃ��āv�Ƃ��������t���Ȃ���A�����������z���Ȃ������B�ޏ��͂����A�킽���������M���R�[�q�[�|�b�g���p�ӂ��Ă����K�̔鏑���ɘA��Ă������B�����ŁA�鏑�����ɂǂ��炩�Ƃ����ƂԂ�����ڂ��ɏЉ�ꂽ�B�킽���͂܂����A����Łu�ǂ��s�����邩�v�����������ςɊw�т͂������A�ق��̂ЂƂ̋C�����A�j���A���X������ȑΐl�W���v����銴�o�͂��܂�Ȃ��l�����������B�i�����A349�y�[�W�j
�@�T�b�N�X�搶�́A���̏�ʂł������悤�Ȍo���𗧂đ����ɂ��邱�ƂɂȂ�킯�ł��B��������ƁA�O�����f�B������́A�ɂ���āA����̐S���ǂ߂�ꍇ������Γǂ߂Ȃ��ꍇ������Ƃ������_�ɂȂ�悤�ł��B���ǃX�y�N�g������Q�����l�����͑��҂̐S��ǂނ��Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ����ӂ��ɁA�ꗥ�ɍl���Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤�B
�@��قǂ́A���Q�S��������s���ɂ��Ă��A���l�̒�ɂ������������s���ɂ��Ă��A��������点��ړI�������čs�Ȃ�����̂ł���A����ɂ���đ��肪�����邱�Ƃ���������Ă��܂��B����ɑ��āA���H�͂��K�˂ė��Ă��ꂽ�T�b�N�X�搶�����ĂȂ��ꍇ�ɂ́A�����{�ʂ̗���𗣂�āA�T�b�N�X�搶�̗���ɗ����čl����K�v������܂��B���̏ꍇ�́A�D�ӓI�ȕ����ő���̗���ɗ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯�ł����A���ꂪ�A�O�����f�B������ɂ͓���Ƃ������ƂɂȂ�悤�ł��B
�@������������鎞�ɂ��A�����̋q���A����������l���}���鎞�ɂ��A�����������{�ʂ̍s�����Ƃ����ƍl����A�Ƃ肠�������̖����͉������ꂻ���ł��B��҂̏ꍇ�A�ΐl�I�ȕs����ْ��̌��ʁA�����܂Ŏv������Ȃ������Ƃ������Ƃł���Ƃ��Ă������ł��B������ɂ���A����ł͂��Ȃ�c���I�ȑΉ��Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B���Ԉ�ʂ̎Љ�l�ł���A����Ɏ���ɂȂ�Ȃ��悤�ɂƍl���A����Ȃ�̏��������O�ɂ��Ă������̂�����ł��B�܂��Ă�A�鏑�������߂��ɂ���̂ł�����A���������ł͓����A���̋��͂�悢�̂ł��B���̎�̖��Ɋ֘A���āA�O�����f�B������́A�T�b�N�X�搶�ƑΖʂ��鉽�N���O�ɏ������ŏ��̒����i�w��A���ǂɐ��܂�āx�j�̒��ŁA���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B
�@��������x�̂킸���ɑe�\�ȍs�ׂ����ׂĂ����ƂɂȂ�B�s���ӂȂ������Ђƌ����A���������������Ēz�����M���A���h�A�M�p�𑼐l���玸�킹�Ă��܂��̂��B�i�O�����f�B���A1994�N�A166�y�[�W�j
�@���̂悤�ȏꍇ�ɁA���ƂȓI�ȑΉ������ׂ��ł��邱�Ƃ́A�O�����f�B������ɂ��o����ʂ��Ă悭�킩���Ă���킯�ł��B�ɂ�������炸�A���ۂ̏�ʂɂȂ�Ƃł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ƃ������Ƃł��B���ꂱ�����A�܂����� �g���B��Q�h �̔��B��Q����䂦��Ȃ̂ł��傤�B�ł́A����͂Ȃ��Ȃ̂ł��傤���B�����ɂ́A���Ǔ��L�̖�肪�����ł���̂ł��傤���B
�@���̂悤�ȑԓx�́A������ӂ��̐l�ł����Ă��A���Ԓm�炸�ƌ�����l�����ɂ͂悭��������̂ł��B���͂��Ȃ�ς���Ă����Ƃ͎v���܂����A��t�Ȃǂ̓���ȐE�ƂɏA���Ă���l���������̓T�^��ł��傤�B����́A���܂萢�Ԃɂ��܂�邱�Ƃ��Ȃ��A�Ⴂ�����炿��ق₳�ꑱ���A��펯�I�ȁA���Ȃ킿�c���I�ȑԓx�𒍈ӂ���Ȃ��܂ܗ��Ă��܂����߂ł��B�������Ȃ���A���ǂ̏ꍇ�́A�����ł͂���܂���B�J��Ԃ����ӂ��ꂽ���炢�ł́A���̏����̋����ŏI����Ă��܂��A���{�I�ȉ��P�͖]�߂Ȃ�����ł��B���������āA���Ă��镔��������ɂ��Ă��A����Ƃَ͈��Ȏd�g�݂��l���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ�܂��B
�@�K���ے�Ƃ����A���̂����Ȃ��拭�Ȉӎu�́A�����ɑf���ɂȂ�̂�����邱�Ƃɂ���ƌ����Ă��܂������ł͂Ȃ��قǂł����A���������p���́A�K���ے肪�d�x�ɂȂ�Ȃ�قNj����Ȃ���̂ł��B�ꍇ�ɂ���ẮA�u����Ȃ�ɓ��������邭�炢�Ȃ�A���ق����܂����v�Ƃ����قǂɂȂ��Ă��܂��̂ł��B������ӌŒn�Ƃ�����Ԃł��B
�@�f���ɂ��炴��Ή����A���̂悤�ȑ��ʂ���l����ꍇ�A���a�����̎��l�ł�������������i1907-1937�N�j�ɂ�鎩��̗c���I�s���� �g���ȕ��́h ���Q�l�ɂȂ肻���ł��B����͌�ɁA�����锽�����̐��_�a��ԂɊׂ邱�ƂɂȂ�i�}���A2004�N���A��T�A�U�́j�̂ł����A���Ɉ��p����o�����́A������R�N�قǑO��1929�N 11 ���ɋN���������̂ł��B
�@���̂R�N�O�ɑn�����ꂽ�����̐��鍂���w�Z�Ńh�C�c��̋��ڂ������Ă����A��̓����|�p��w�����A�����Z�Y�i�w�O���Y�̓��L�x�ŗL���Ȉ������Y�̒�B1904-1957�N�j�ɏЉ��āA�����̓����ł��鏬�o���O�Y�Ə��߂đΖʂ������ɋN�������o�����ł��B�����̎��l�ƌĂ�钆��́A���������ƈꏏ�Ɉ��H������A�X�ł��������S���̑��l�ɁA�����ӂ�グ�Ȃ��琳�ʂ���吺���o���Č������čs�����̂ł��B����͂Ƃ肠���܂���ł������A����́A�t�ɁA�ԂɊ����ē����������ɂ����Ă�����܂����B����͂����ɁA���Ζʂ̍ۂɏX�Ԃ����������Ƃ�l�т�莆�����o�ɑ���܂����B�����ɂ́A���̂悤�Ȃ��Ƃ�������Ă����̂ł��B
�@�����ɒ��킷�邱�Ƃ��܂�Ől�ɒ��킵�Ă�₤�Ȃӂ��ɂȂāA�ς܂Ȃ����Ƃł��B�Ȍ�ށk���l�݂܂��B�k�����l��睁k�����āl�����O�̐l�������̃t�B���X�e�B���k�����l�����̂��߂ɁA�l���������̜����z�Ƃ��ӂ��Ƃɂ��Ă��Ǝv�����ƂS���Ă���A�����珉�߂Ĉ����ɟZ�ތN�̑O�ł����X����t���悤�Ƃ��ӂ₤�ȟ������ŏ��N���B�i�������ӟ����́A�l���g�v�ӂɂ͖l�ɐ̂��炠�����̂ł͂Ȃ��I�j���������̟����ɕ��������̂ŁA���X������������܂��B�i�����A1968�N�A340�y�[�W�B���������p�ҁj
�@�ڏ�̑���ɑ��āA�������Ӎߕ��ɂ����Ă͂Ȃ�Ȃ��قǐg����Ȍ�����ɖ������ӂ�Ă��܂����A����́A���̂悤�ȈӖ��ł��傤�B�����͎�Ȃ������킯�ł͂Ȃ����A��������ꂽ���͂Ȃ��̂ŋC�����悤�Ƃ����A�ȑO�ɂ͂Ȃ������C�����N�������B�Ƃ��낪�A���������f���ȋC�������߂Ď����ɋN���������Ƃ������ŋ������Ƃ��ł����A�������̍s���ɏo�Ă��܂����Ƃ����̂ł��B�܂�A�����̐l�i�I�Ȑi���������̈ӎ��������̂��������Ƃ������Ƃł��B�S�̂Ƃ��Ē��q������ԂȂ̂��A�f���ɓ���������Ƃ����A���ƂȓI�ȑΉ�������̂�������߂Ȃ̂ł��傤�B
�@���̒���Ɠ����悤�ɁA�O�����f�B��������A�{���͂ǂ��������̂��A���邢�͂ǂ�����悢�̂����A�m���Ƃ��Ă͂悭�m���Ă���̂ɁA���������̂�������Ƃ��J��Ԃ������Ă��܂��B�ނ�����Ă���ɗ������������Ƃ���ƁA�u�S���͔j�����ɂȂ�A�ْ��ő̂��k���A�f���C�������P�����v�i�O�����f�B���A1994�N�A157�y�[�W�j�Ƃ����̂ł��B����́A���炩�Ɏ��̌��������ł��B���̂悤�Ȏ���������āA���ɂ́A�̂�����ɂ���Ƃ͐����̕����֓����Ă��܂��̂ł��傤�B
�@���_��w�ł́A���҂���̎w���Ƃ͐����̍s�����N�����Ǐ���A����� nagativism �ƌĂ�ł��܂��B���̏ꍇ�A�ӎ��I�Ɂi�Ђ˂���āj�N�������Ƃ��z�肳��Ă��邱�ƂƁA���҂̎w���ɂ����̂������̈ӎu�ɂ����̂��Ƃ����_�ł��Ⴄ�̂ŁA���ǂ̏ꍇ�Ƃَ͈��Ȃ悤�ł����A���Ȃ��Ƃ����ʂƂ��ċN�������s���͋��ʂ��Ă��܂��B���Ɏ����̂́A���ǂł͂���܂��A���̌��ۂ𗝉����邤���ŎQ�l�ɂȂ鎖��ł��B
�@����́A�H�Ȑ�V�������Ƃ����̕���nj�Q�̐f�f�����j���i�����p������j�̎���ł��B��������́A���܂���S���Ɣ]�Ɉُ킪����A�A�w�O�̒m�\�����łh�p�� 20 �������������߁A�d�x�̒m�I��Q�Ɛf�f����܂����B���������͌�����h�{���Ƃ邱�Ƃ��ł��܂���ł������A�S����̓~�L�T�[�H�ȂǁA�_�炩���H�����Ƃ��悤�ɂȂ�܂����B���e�́A��������̍D����T�������ʁA�u�Ȃ߂炩�v�����v�Ƃ������i���c�����ɐH�ׂ邱�Ƃ��킩��܂����B���̂��߁A�ߏ��̏��X�ɗ���ŁA�������̃v������z�B���Ă�����Ă��܂����B
�@18 �ɂȂ��āA��ɂ���b���ł���悤�ɂȂ�A�F�l�Ƙb���Ă��鎞�ɁA�Ȃ��v�������D���Ȃ̂��Ƃ����b��ɂȂ����̂������ł��B����ɑ��āA��������́A��e�̊�����Ȃ���A�v�����āu�v���������o�Ă��Ȃ�����v�ƌ������̂ł��B��������e�́A�v�����ȊO�͂���������o���Ă��܂��Ƃ����������w�E���܂����B����ƁA��������́A����ɋ����ׂ������������̂ł��B���Ɉ��p����̂́A���̎�ނ������W���[�i���X�g�A������������ɂ��L�q�ł��B���łȂ���ӂ�Ă����ƁA��������́A��q����x���`�B�i�e�b�j����т���ގ��̓`�B�@��ʂ��Č��t��g�ɂ����ŏd�x�̏�Q�҂����ƁA���̉Ƒ��⋳��҂������ȖڂŎ�ނ����Ă���A����߂Đ�s�I�ȃW���[�i���X�g�ł��B
�@����ɑ��鑧�q�̓����́A�u�H�ׂ����Ǝv���Əo�����Ⴄ�v�Ƃ������̂������B�p������ɂ��A�u�H�ׂ����v�Ǝv���Ύv���قǁA�����̈ӎv�ɔ����Č�����o���Ă��܂��̂��Ƃ����B���ꂪ���������������ƁA�܁A�Z���ڂł悤�₭�H�ׂ���悤�ɂȂ�B���傤�ǂ��̂�����ŁA���e�͖ڐ��ς��悤�ƃv�����������Ă��邽�߁A���܂��܃v�������ɐH�ׂ�悤�ɂȂ����Ƃ����̂��B
�@�u�������͊��S�Ɂw�v�������D���x�Ǝv������ŁA�t�ɉp���́w�v���������H�ׂ����Ă��炦�Ȃ��x�ƁA�����Ɖ䖝���Ă��āA���ꂪ�킩�������Ƃ͓�N�قǁA�v������H�ׂ邱�Ƃ͂Ȃ������ł��ˁv�i�����A2013�N�A168-169�y�[�W�j
�@����́A���ۂƂ��Ă͍K���ے�̌��ʂ̂悤�Ɍ����܂��B���́A���ꂪ�]�@�\�ُ̈�̂��߂Ȃ̂��A����Ƃ��A�{���ɐS���I�Ȏd�g�݁A���Ȃ킿�K���ے�ɂ�錋�ʂȂ̂��Ƃ������Ƃł��傤�B��������̏ꍇ�͂����ł͂Ȃ��ł��傤���A�O�����f�B������̕�e�́A���̎�̍s���̗��ɁA�{�l�̂Ђ˂���������Ă����悤�ł��B������ɂ���A�������ɃO�����f�B������̕�e�́A���̂�������悭�ώ@���Ă��āA���̂悤�Ȋώ@����L�ɏ����Ă��������ł��B����́A�܂��O�����f�B�������w�Z�ɓ��w����O�̂��Ƃł��B
�@�ދ�������A��ꂽ�肷��ƁA�e���v���͂�f������A�C��E���ŕ���ڂ����ē�������B�������Ȃ���A�������������������Ă���B���X���������s�ׂ͔ޏ��̎������z���Ă���悤�Ɍ����邪�A�ʂ̂Ƃ��ɂ́A�Z���Z�[�V�������N�������߂ɂ킴�Ƃ���Ă���B�e���v���͈���̏I��肪�߂Â��ɏ]���āA���������������Ȃ�A��ȍs�ׂ������Ƃ��Փ��I�ɂȂ�B�Ⴆ�A��f������A�܂�ň������Ƃ��������Ƃ�m���Ă���̂����A�Փ���}�����Ȃ������ƌ�������ɁA�G�Ђ������Ă��Đ@��������肷��B�k�����l
�@�e���v���͂ƂĂ��ׂ������̂Ђ��Ŕ��肠�����Ă���悤���B�{�点��ƁA�ޏ��̔����́A��J�ƃt���X�g���[�V�����̒��x�ɔ�Ⴕ�āA�ٗl����������B����ł��āA�����̊�ȍs�����l�������ꂳ���邱�Ƃ����o���Ă��āA�����ޏ����g���������낪�点����A���I�ȏ��킴�ƍ�������̂悤�ɑ����B�i�O�����f�B���A1994�N�A35-36�y�[�W�j�B
�@�����܂ŗ�Âʼns���A���邢�͐h煂Ȋώ@�������e�́A���ɒ������Ǝv���܂��B�Ƃ��������A���ǂ̎q�ǂ��̕�e�������̎q�ǂ����ώ@�����Ƃ����������āA���҂̐S�̓����������܂ʼns���ώ@�ł���l�́A���Ȃ蒿�����ƌ������ق����K�ł��傤�B���ꂪ���ǂ̕�e�ł��邱�Ƃ́A���ɂ͂ƂĂ����R�Ƃ͎v���܂���B���̊ώ@�����ɖ���T���Ƃ���A����́A�����̎q�ǂ������X�˂������ė�O�Ɋώ@�ł���Ƃ�����O�ғI�Ȏp���ł��傤���B�������A���ǂ̓�����������ŏd�v�Ȏ肪����ɂȂ邩������܂���B
�@�����ŁA���ǂɍL���ώ@�����A���҂ɑ���z���������s���l���́A���ӎ��I�Ȃ��̂ł���Ƃ��Ă��Ӑ}�I�Ȃ��̂ŁA�����̐����������̈ӎ��ɖ��炩�ɂȂ��Ă��܂��s������������ʂƂ��Đ��܂��A�Ƃ��������������яオ��܂��B�K���ے�Ƃ��������ōl����A����̐����̊�т�ے肵�悤�Ƃ��邽�߂ɁA�N����̂��̂Ǝ����i�̂����閳�ӎ��j�ōl����s�����Ƃ�̂��A�����c�������疳���o�I�Ɂi�ꍇ�ɂ���ẮA�����Ȃ�Ƃ��ӎ����Ȃ���j����������ʂƂ������ƂɂȂ�ł��傤�B���ɂƂ肠����A�����ЂƂ�̗L���Ȏ��NJ��҂ł���h�i�E�E�B���A���Y����́A���N�A���ǂ̑��k���𑱂��Ă����o������A�u���B�̐V���Ȓi�K�ɓ���ƐV������肪�����邱�Ƃ�����v�Ə����Ă��܂��i�E�B���A���Y�A2008�N�A46�y�[�W�j�B���������ώ@�������A���̉����̗L�͂ȗ��Â��ɂȂ�悤�Ɏv���܂��B
�@�Ƃ���ŁA�����a�̏ꍇ�̔��a�́A�H�ɋN����炵�����������a�ƌ�������́m���V�n�������A�v�t������N���ł��B�܂�A�Љ�ɏo�Ă䂭�O��ɋN����Ƃ������Ƃł��B���̍l���ł́A����́A��l�O�̎Љ�l�ɂȂ邱�Ƃɑ����R�̌��ʂƂ������ƂɂȂ�܂��B����ɑ��āA���ǂ̏ꍇ�ɂ́A���Љ�Ƃ����ȑO�ɁA�����̐��E�֏o�鎞�ɋN����A���̌�̐����ɂ��Ƃ��Ƃ���R����̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł��B�ȉ��A���̉�����O���ɒu���āA�O�����f�B������̍s�������Ă䂭���Ƃɂ��܂��B
�@�������A�����ŕt�����Ă����ƁA���̂悤�Ȗ��n�ȑΉ��́A���Ǔ��L�̂��̂ł͂Ȃ��A�d�x�̐��_�����͂������̂��ƁA�l�i��Q�Ƃ���邢�����̏�Ԃ̏ꍇ�Ȃǂɂ������ӂ��Ɋώ@�����A������Љ���������ΐl�I�ԓx�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B���̂悤�ɁA���ǓI�ȏǏ�Ƃ������̂̒��ɂ́A��������N�����Ȃ���A���̎����ɂ�������Ǐ���߂đ����̂ł��B���̂悤�Ȃ��̂����O���čs���A���ǂ̂���Β��j�Ǐ��̂��ƕ�������ɂ���Ă���͂��ł��B
�@���̂悤�ɃO�����f�B������́A�u���̓I���邢�͐����I�ȓ����̋�ɂ⋰�|�ɂ͋����ł��邪�A�ЂƂ̐S�〈���ɑ��鋤���͌����Ă���v�i�����A364�y�[�W�j�킯�ł����A���������ł����Ă��쒷�ނɂȂ�ƁA���Ȃ莖��ς���āA�m�I�ɂ��������ł��Ȃ��Ȃ�̂������ł��i�����A379�y�[�W�j�B�ł́A�l�Ԃ̏ꍇ�ɂ́A���ƂȂ����q�ǂ��̂ق����Ή����₷���̂��ƌ����A�����ł͂���܂���B�q�ǂ��̂ق����A���ƂȂ����͂邩�ɓ���̂������ł��i�����A365�y�[�W�j�B����́A�q�ǂ��̂ق������t�ɂ��R�~���j�P�[�V�������������ɂ������߂Ȃ̂ł��傤���B�����͈�ʂɁA�ꐫ�{�\�ƌĂ��A�q�ǂ��ɋ����Ђ��������������Ă��邱�Ƃ����Ă���ƁA���̂��Ƃɂ��Ă͂ǂ��l����ׂ��Ȃ̂ł��傤���B
�@�T�b�N�X�搶�ɂ��A�O�����f�B������͐l�ɕ������߂�ꂽ���C�����������������A����Ɠ����Ɂu�ЂƂƂ̐ڐG���|�������B�������߂���ƁA�Ƃ��ɂ��ꂪ��D���ȑ啿�Ȃ��ł������肷��ƁA����̊��G�Ɉ��|���ꂽ�B����ȂƂ��A���a�Ȋ�сkpeacefulness and pleasure�����炬�Ɗ�сl��������̂����A�����Ɉ��݂��܂��悤�ȋ��|���������v�����ł��B���̂悤�ȌX�����c�������炠�������߁A�T�ɂȂ������ɂ́A�͋����ɂ��Ă��₳�����������߂Ă���āA�����������Ŋ��S�ɃR���g���[���ł���悤�ȁu���@�̋@�B�v���Ă����̂������ł��i���̖��́A�M���������قNj������O�������āA�����ɂ킽�鎎�s����̖��A�g�������ߋ@ Hug machine�h �Ƃ��āA��Ɍ��������ꂽ�j�i�����A357�y�[�W; Sacks, 1995, p. 263�j�B
�@����Ƃ�������́A���肪����ꍇ�ɂ͑o�������̂��̂ł��B���肩�玩���ɑ��鈤��ƁA�������瑊��ɑ��鈤��̂ӂ�������Ƃ������Ƃł��B�K���ے�̈�Ƃ��Ĉ���̔ے���N�����Ă��鎞�ɂ́A���肩�玩���ɑ��鈤��̔ے�̂ق����A�������瑊��ɑ��鈤��̔ے������ʂɂ͋������̂ŁA���̋t�͂��܂肠��܂���B���̌��ʁA�����͑�����D���Ȃ̂ɁA�����͑��肩��D����Ă��Ȃ��Ƃ����A�����͋t����݂��v�����݂����܂�邱�ƂɂȂ�킯�ł��B���肩��̈����ے肷��ہA�O�����f�B������̂悤�ɋ��|�S���͂��߂Ƃ���S���I��������肠���邱�Ƃ�����A���ۂɒ�������������A�̂��d��������A���邢�͗₽���Ȃ�����A���ɂ╠�ɂ��N��������A�����т��o����A�����Ȃ�����Ȃǂ̐g�̓I�Ȕ������o�����Ƃ�����܂��B
�@�O�����f�B������́A���̎��ǎ��̏ꍇ�Ɠ������A�c���ɂ͕�e�ɕ������Ƒ̂��d�������������ł��i�T�b�N�X�A2001�N�A390�y�[�W�j�B�܂��A��h���̒��w�Z�ɓ��w�������A�Ԃő����Ă�����e�ƕʂ��ۂɁA�u��e�̗��r�ɕ����ꂽ���Ɛؖ]�����v�ɂ�������炸�A�u���ǂɂ��肪���ȋߐڊ�]�Ɠ����̖����̂�ȂɊׂ��Ă����v���߁A�_�̂悤�ɓ˂������Ă��āA�u��̃L�X�����炵���v�����ł��i�O�����f�B���A1994�N�A92�y�[�W�B���������p�ҁj�B���́u���ǂɂ��肪���ȋߐڊ�]�Ɠ����̖����v�Ƃ��������́A�K���ے肪�W���Ă��邱�Ƃ������Ă���Ă���悤�Ɍ�����̂ŁA���ǂ̓�����������ł���߂ďd�v�ł��B
�@����ɑ��āA�v�t�����߂������ɂ́A�u��D���ȁv������ɕ������߂���ƁA��q�̂悤�ɁA���|�S�ƂƂ��Ɂu���炬�Ɗ�сv���������킯�ł��B������K���ے�̖����ōl����ƁA��D���Ȃ�����̈���������Ă��ꂵ���Ƃ����f���Ȋ���Δے肷�邽�߂ɁA���|�S����肠�����Ƃ������ƂɂȂ肻���ł��B�Ƃ͂����A���ꂾ���ł͒P�Ȃ鐄��ɂ����Ȃ��̂ŁA���̐��肪�������Ă��邩�ǂ������m�F����K�v������܂��B���̂��߂ɂ́A�O�����f�B������ɁA�u���ɕ������߂��Ă��ꂵ���v�Ƃ�������̉��Z�����Ă�����āA���ۂɒ�R���N���邩�ǂ������݂邵������܂���B���̌��ʁA��R���N�����ĉ��炩�̐S�g�������o��A���̐��肪�������Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�O�����f�B�����A�K���ے�Ɋ�Â�����ے�̂��߂Ɂi���ӎ��̂����Ɂj���|�S����肠�������ŁA�ӎ��̏�ł͂�����̈���������Ă���̂������ł���A�]���I�Ȏ��NJς��炷��ƒ���������ɓ���͂��ł��B���̂��Ƃ́A����̔ے肪����قNj����Ȃ����Ƃ������Ă��邱�ƂɂȂ邩��ł��B�����玩���ɑ��鈤��̏��Ȃ��Ƃ��ꕔ���A�ӎ��̏�ł������Ă��邱�ƂɂȂ�킯�ł����A���̓_�������Ƃ��Ă��A�O�����f�B������́A�]���I�Ȏ��NJς��炷��A��͂肩�Ȃ�y�ǂ̕��ނɓ��邱�Ƃ��킩��܂��B
�@�܂��A�g�������ߋ@�h �ɓ����Ă��鎞�ɂ́A��e�̂��Ƃ�D��������������̂��Ƃ≶�t�����̂��Ƃ��l���āA�u���̐l�����������ł��ꂽ����Ǝ��������������������v�̂������ł��B�����āA�������ߋ@�ɓ����Ă��鎞�ɖ��키�A������������ɂ��ẮA�u�����ƁA�ӂ��͂ق��̂ЂƂƂ̊W�ł��̋C�����𖡂키�̂ł��傤�ˁv�ƌ���Ă���̂ł��i�T�b�N�X�A2001�N�A355�A359�y�[�W�j�B
�@����́A�l�Ԃ�ɂ������ɂ͖��킦�Ȃ��f���Ȋ���𖡂킢�����Ƃ������Ƃł���A���̊�]�́A��Ƃ��āA�������ߋ@�Ƃ����A���̒ʂ�Ȃ��@�B�ɂ��߂���ꂽ���Ɏ��������Ƃ������Ƃł��B�����ăO�����f�B��������A���̎��̊���͖{���A���ҁA���Ɉ���[���͂��̑���Ƃ̊ԂŊ�����͂��̂��̂ł��邱�Ƃ��A�����̂����ł͏��m���Ă���킯�ł��B�������ߋ@����肠���邱�ƂɎ��O��R�₵���̂́A�܂��ɂ��̂��߂Ȃ̂ł����B
�@�O�����f�B������́A���肪�l�Ԃł���A�������������N�ɑ��Ă����키���Ƃ��ł��Ȃ��̂��Ƃ����A����܂ŏq�ׂĂ����悤�ɁA�����Ă����ł͂���܂���B�`���̂�����ɕ����ꂽ���ɂ́A���|�S�̂ق��Ɂu���炬�Ɗ�сv�����ۂɊ����Ă��邩��ł��B����ɑ��āA���̍��ɂ�����e�ɕ������߂�ꂽ�Ƃ���ƁA�ǂ��������ƂɂȂ����̂ł��傤���B����ɂ��ẮA�ǂ��ɂ�������Ă��Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA��������ȊO�ɂ���܂���B
�@���̐S���Ö@�̌o�����炷��ƁA�������ɂ������̂悤�ȑf���Ȋ�����킦��ǂ��납�A�c�����⏭������Ɠ������A�������⋰�|���Ȃǂ̔ے�I�Ȋ���ӎ��ɏ����Ă��邾���Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������Ȃ���A�����ł���Ƃ��Ă��A���̂悤�ȌX�����A���ǂ�A�X�y���K�[�nj�Q�Ɍ��炸�A���̓_�Ő���Ȑl�����ɂ�����قǒ������Ȃ����̂Ȃ̂ł��B
�@�v����ɁA�O�����f�B������́A����Ƃ������̂��킩��Ȃ��킯�ł͂Ȃ��A�����A���ɉƒ{�ɑ��鈤���͂���߂ċ����̂ł��B����ɑ��āA�l�Ԃ̊���Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�ꕔ�̗�O�������āA�����̊�����܂߁A�Ƃ���ɂ킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ƃ������Ƃł��B�����{���ɂ����ł���A����́A����̌̂Ƃ̌𗬂̂ق����A�َ�̌̂Ƃ̌𗬂���������ƂɂȂ�̂ŁA�����Ƃ��Ă͔��Ɋ�ȏ�Ԃɂ��邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�O�����f�B�����������₷���̂́A�l�Ԃ����@�B�Ƃ̐ڐG�A���肪�����ł���ΐl�Ԃ��������A���������ł����Ă��A�ސl����������ȊO�̚M���ށi�ƒ{�j�A�܂��l�Ԃł����Ă��A�q�ǂ��������ƂȁA���e�Ȃǂ̋߂��ԕ��������l�A�������e�ł��߂��ԕ����������ԕ��Ƃ������ԂɂȂ��Ă���悤�ł��B�{���́A�قƂ�ǂ����̋t�̂͂��ł�����A����ł͔��ɕs���R�ł��B���̏�Ԃ́A�ӂ��̊����ے肵�����ʂƍl�����ق������ʂ�ł��傤�B�O�����f�B������̕�e�́A�{�l�Ɉ��Ă��莆�̒��ŁA�u�������������A���Ȃ��� �g�悢�h �C���̂��̂����ׂċ��ۂ������Ƃ��A�o���Ă���ł��傤�v�ƌ�肩���Ă��܂��i�O�����f�B���A1994�N�A161�y�[�W�j�B���̂��Ƃ��A��e�̉s���ώ@�͂̂������ŁA�K���ے艼���̗��Â��ɂȂ肻���ł��B���ǎ��̕�e�ł����郍�[�i�E�E�B���O�́A���̎�̖��Ɋ֘A���āA���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B
�@�k���ǂ́l�q�ǂ��������A���������̏�Q�𗝉����A���̏�Q�̕ǂ�˔j������@��m���Ă��邨�ƂȂɂ������Ă͔������������̂ł��B���̂��Ƃ���l���āA���̎q�ǂ������͔��ɖ��n�Ȃ������ł����\���Ȃ��Ƃ��Ă��A����Ȋ���̂��ׂĂ�����Ă����ƍl������̂ł��B�i�E�B���O�A1975�N�A35�y�[�W�B���������p�ҁj
�@���̐������������Ă���Ƃ���A���ǂ�A�X�y���K�[�nj�Q�Ɛf�f�����l�����́A������ӂ��̐l�Ɣ�ׂč��{�I�Ɉَ��Ȃ킯�ł͂Ȃ��Ƃ����\���������Ȃ肻���ł��B�l�ԂƂ́u�ʂ̎�v�ł��Ȃ���A�u�]�����u�Œn��ɉ��낳�ꂽ�v�i�T�b�N�X�A2001�N�A374�y�[�W�j�悤�ȁA���Ԉ�ʂ̐l�ԂƂَ͈��̑��݂ł��Ȃ��A�ӂ��̐l�ƒf�₵����Ԃɂ���킯�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���ǃX�y�N�g�����Ƃ����A���̂��l����̂ł���A���̐�́A������ӂ��̐l�ɂ܂łȂ����Ă��邱�ƂɂȂ�ł��傤�B���̐��肪��������A���@�ɂ���Ă͐S���I�Ȏ��Â��\�Ƃ������ƂɂȂ肻���ł��m���W�n�B
�@����܂Ō��Ă����悤�ɁA���ǃX�y�N�g������Q��l�ԂƂ��Ă̐�����n�̋ɓx�̔ے�̌��ʂƍl����ƁA����Ȃ�ɋ��ʂ邱�Ƃ����炩�ɂȂ����悤�Ɏv���܂��B�����ŁA���̐��肪�ǂ̒��x�܂œ������Ă����������A����ɂ������̗L���Ȏ����ʂ��Ē��ׂĂ݂邱�Ƃɂ��܂��B
�@�h�i�E�E�B���A���Y����i�ȉ��A�h�i����j�̂����鎩�ȓ��@�ɂ��ẮA�Z�����͂ł͂ƂĂ�����������Ȃ��قǏd�v�ȑ��ʂ������̂ŁA�{�e�ł͕K�v�ŏ����̋L�q�ɂƂǂ߁A���Ԃ̗]�T���ł�����A���̒i�K�ł��炽�߂ĂƂ肠�������Ǝv���܂��B
�@���Ƃ̓h�i��������ǃX�y�N�g�����̘g���ɓ���ƍl���Ă��܂��B���Ƃ��A���̒����Ɂu���́v����e�����A�h�i������݂����Ƃ̂��鎙���S���w�҂́A��O�ɂ͎��ǂƂ����f�f���^���Ă����Ƃ̂��Ƃł����A�h�i����Ǝ��ۂɑΖʂ����Ƃ���A�u������Ȃ��A���ǂł������B����������߂ėc�������炻���ł������ƁA���������v�Ə����Ă��܂����A�O��ɓo�ꂵ���������_�Ȉ�A��D���搶���A�h�i����̋����ׂ��،���ǂނƎ��ǂƂ����f�f�ɂ͋^�O������Ă��܂����A�u���̎��`��ǂތ���A�ޏ��̏��s���͎��ǂ̐f�f��ɍ��v���Ă���v�i��A2014�N�A215�y�[�W�j�Əq�ׂĂ��܂��B
�@���_�Ȃ�S�Ó��Ȃł́A�f�f�̍ۂɎQ�Ƃł���q�ϓI�w�W�����݂��Ȃ����߁A�s���┭�����܂߂��Ǐ画�f�������Ȃ���Ȃ�܂���B�c�r�l�ɋL�ڂ���鎾�����₻�ꂼ��̐f�f����A���ł���邽�тɑ啝�ɕς��̂����̂��߂ł��B�^�̌������˂��~�߂��Ȃ�����A���̂悤�ȑΉ������ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤�B������ɂ���A�h�i�����ǘA���̘̂g���Ɏ��܂�ƍl���Ă悢�̂ł���A���ǂƂ��������ɂ́A���̒��j�Ǐ�̌����͕s���ɂ��Ă��A�S���I�v�����A�܂�K���ے�Ɋ�Â��S�̓������傫���W���Ă��邱�Ƃ��A���Ȃ�̊m�x�Ŗ����ł���Ǝv���܂��B
�@�O�����f�B������́A�������A���҂̊�Œ��߂��悤�Ȍ`�ŕ`�ʂ��Ă���A����ΐ��d�ȕ����������悤�Ɋ�������̂ɑ��āA�h�i����́A�����̒��ɂ��鎋�_���玩���`�ʂ��Ă���悤�Ɍ����܂��B�Ԃɉ�݂�����̂��Ȃ��A�v����ɒ��ړI�ŗ����ȋL�q�����Ă���Ƃ������Ƃł��B������L���ŁA��������̂܂܂̌`�őf���ɕ\������Ă��܂��B����́A���@�\���ǂł���A�X�y���K�[�nj�Q�ł���A���ǃX�y�N�g�����Ɛf�f�����l�ɂ͓�����Ƃ̂悤�Ɏv���܂��B�t�Ɍ����A�����h�i�����ǘA���̘̂g���Ɏ��܂�̂ł���A��搶�����F���Ă���i��A2014�N�A215�A222�y�[�W�j�悤�ɁA����܂ł̎��Ǘ��_�◝�����܂������Ă���̂ł����āA��������{�I�Ɍ������K�v�����邱�ƂɂȂ�͂��ł��B
�@�]���̊�Ō����A�ǂ̂悤�Ȏ��ǂł����Ă��A�h�i����̂悤�ɁA���ۂɂ�������̗F�l���������A�c�t�Ȃ��̂ł���ɂ��Ă��A��������ɌJ��Ԃ��Əo�����āA���ۂɂ��炭����O�Ő��������肷�邱�ƂȂǂ͍l�����Ȃ��ł��傤�B�h�i����̉Əo�́A������Ɨ���ڎw�������̂ł����āA���ǎ���������N�����A�����̏Փ��I�Ȕ�яo���Ƃ͍��{�I�ɈႤ�̂ł��B
�@�����ẮA�i���I�Ɏ��Ƃ��痣��āA�c���I�Ή��ƍ��܂̘A���ł������Ƃ��Ă��A�o�ϓI�Ɏ������ׂ����X�ƐE�ɏA������A���ނ��Ă������Z�ɕ��w������Ɏ��͂ő�w�ɓ��w���A�����𑲋Ƃ�����A���̎��X�̗��l�Ɖ��x�����������肵�āA�ΐl�I�A�Љ�I�ɂ����Ȃ萬�����Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B�ŏI�I�ɂ͌������Q�Ă��܂��B�O�����f�B������Ƃ͂����Ɉ���Ă��邱�Ƃ��B�����ɂ��Ă͌����܂ł��Ȃ��A���l����邱�Ƃ���A�������̃O�����f�B������ɂ����ɂł��Ȃ������̂ł��B
�@�ł̓h�i����́A�T�b�N�X�搶��O�����f�B������̖ڂɂ͂ǂ̂悤�ɉf���Ă���̂ł��傤���B�T�b�N�X�搶�́A�h�i����Ɠd�b�ʼn��x���b�������Ƃ����邻���ł����A�������ׂ��͈͂ł́A���Ɋ��z�߂������Ƃ͏����c���Ă��Ȃ��悤�ł��B�������A�O�����f�B������́A�������Ɉ�a�����o�������߂Ȃ̂ł��傤���A�h�i����̈�ۂ��A���̂悤�ɖ��m�ɏ����L���Ă��܂��B
�@���ǔ��ɂ��鑽���̐l�����́A�h�i�E�E�B���A���Y�̒����i1992�N�j�k�w���ǂ������킽���ցx�l���A�s�ғI�ȉƑ��⎩��̘H�㐶�������I�Ō��z�I�ɋL�q���Ă��邱�Ƃɂ��āA���X�Ƃ܂ǂ��Ă���B�����d�b�Řb�������A�h�i�E�E�B���A���Y�́A����L���Ȋ��S�ɂӂ��ɕ�������b�������������B�ÓT�I�ȃJ�i�[�^���ǂ̕��ŒP���Șb�������ł͂Ȃ������̂ł���B�����炭�A�E�B���A���Y�̂悤�Ȏ��ǂ́A��Ƃ��āA��r�I�ӂ��̐S���A�S�ʓI�ɋ@�\�s�S�������������o�튯�ɖW�����邱�Ƃɂ����̂Ȃ̂ł��낤�B�k�����l
�@�J�i�[�^�̌ÓT�I���ǂ�������قȎЉ�I�s����d�������v�l�l���́A�����炭�v�l��F�m���^�ُ̈�������������ʂȂ̂ł��낤���A�h�i�E�E�B���A���Y�̕����Ă�����́A���o�̏����ߒ��Ɍ��ׂ������āA���ӂ��ɓx�ɕϓ����邱�Ƃɂ����̂Ȃ̂�������Ȃ��B���̉����ł́A���v�l�́A���ǃX�y�N�g�����̃J�i�[�^�A�X�y���K�[�ɂ��痣���ɏ]���Đ���ɂȂ��Ă䂭�B�h�i�E�E�B���A���Y�̒����̕��̂́A�ÓT�I�ȃJ�i�[�^���ǂɂ��A�X�̎��ۂɂƂ��ꂽ�d���������̂Ƃ͈قȂ��Ă���B�iGrandin, 1995, pp. 150 & 152�B���������p�ҁj
�@�����āA�O�����f�B������́A�h�i����̎��ǂ��A�ÓT�I�Ȏ��ǂ��Ӗ�����J�i�[�^�A�X�y���K�[�ɂ���A���t�������Ȃ���@�\���ǂ��Ӗ�����ލs�^�Ă�Ɂm���X�n�Ɏ���A���̂̒��قǂɈʒu�Â��A�u�h�i�E�E�B���A���Y�́A�J�i�[�^�̎��ǂƁA�������@�\���ǂƂ������ɂ̊Ԍ��߂Ă����d�v�ȉ˂����ɂȂ�ł��낤�v�iibid., p. 151�j�ƌ���ł���̂ł��B
�@�h�i����̏ꍇ�A���ǂƂ����f�f�́A�O�����f�B������ƈ���āA�q�ǂ��̎��ɂ���ꂽ���̂ł͂���܂���B�w���ǂ������킽���ցx�̌��e�������Ă��� 26 �̎��ɁA�����͐��_�����a�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ����^�O�ƕs���ɂƂ���A�}���قŕ����a�ɂ��Ē��ׂĂ��钆�ŁA���ǂƂ��������Ɏv�������������Ƃɒ[�������̂ł����B���̂�����́A�a�������S�Ɍ��������a�Ƃ͍��{�I�ɈقȂ�Ƃ���ł��B�����āA�����A�鏑�Ƃ��ċ߂Ă����a�@�̎������_�Ȉ�̐f�@���ɉ����������̂ł��B
�@�����b���āA���̈�t�Ɍ��e��ǂ�ł�������Ƃ���A�h�i����́u���ǂ̒��ł�������ł����݁v�Ƃ������ƂɂȂ�A�����̂��߂ɏ��������e���A���̐��_�Ȉ�̐��E�ŏo�ł���邱�ƂɂȂ����A�Ƃ����o�߂Ȃ̂ł��i�E�B���A���Y�A1993�N�A244-246�y�[�W�j�B���̌�A�h�i����ɂ́A�A�X�y���K�[�nj�Q�⍂�@�\���ǂƂ����f�f�������Ă��邻���ł��i�E�B���A���Y�A1996�N�A292�y�[�W�j�B
�@�h�i����́A��������ɁA�����ɂ킽���Ď������_�Ȉ�̐f�@���Ă����̂ł����A���̏�����t�́A�h�i����_�����a�ƌ��Ă��������ł��i�E�B���A���Y�A1993�N�A147�y�[�W�j�B����́A���̈�t�����ǂƂ���������m��Ȃ��������߂ł͂Ȃ��A�h�i����͎��ǂɌ����Ȃ������Ƃ������ƂȂ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�܂��A���ǂ̑��݂�m���Ă����Ƃ���A��������d�ǂ̎����ƌ��Ă����̂�������܂���B
�@�����ЂƂ́A���ꂩ�炩�Ȃ�Ђǂ��s�҂������Ă����ɂ�������炸�A�����̏�Q�̌����������ɋ��߂Ă��Ȃ����Ƃł��B�h�i������ȋs�҂����ꂩ��Ă������Ƃ́A���̖M�́u��҂��Ƃ����v�ɏ�����Ă���A������i�����A�������Ă����炵����e�̎o���j�̏،��i�͖�A2003�N�A286-287�y�[�W�j������m���Ȃ悤�ł��B������g���E�}�Ƃ����T�O�������o����Ă��Ȃ����Ƃ́A�S�������������l������ʂƂ͈�����悷��Ƃ���ł��傤�B���_��Q���������҂́A�قڗ�O�Ȃ��A�����̏�Ԃ⎾�������I�v���₻��ɋN������g���E�}�̂����ɂ�����̂�����ł��B�h�i����́A���̖��ɂ��āA���̂悤�ɖ������Ă��܂��B
�@�킽���͎��������̂悤�Ȑl�ԂɂȂ����̂��A�ƒ���̂������Ƃ͎v���Ă��Ȃ��B�m���ɂ����́u����v�ȉƒ�ł͂Ȃ��������A��������ނ��댴���́A�����̈ӎ��Ɩ��ӎ�����ɗh�ꓮ���Ă���悤�ȏ�Ԃ������_�ɂ���Ǝv���B�ƒ���ɍ��E���ꂽ�̂́A�킽���̍s���̈ꕔ�����ł����āA�킽���̍s�����̂��̂ł͂Ȃ��Ǝv���̂��B�����Ă܂��A�Ƒ�����\�͂������߂Ɏ���������悤�ɂȂ����킯�ł��Ȃ��A�Ǝv���̂��B�ނ���킽���́A�\�͂ɑ��ĐS������Ă����Ƃ��������������B�\�͂��܂��A�u���̒��v�̐������̗v�f�̂ЂƂ�����ł���B�i�E�B���A���Y�A1993�N�A102�y�[�W�j
�@���������h�i����̎p���́A���ꂩ�琦��ȋs�҂������Ă������ƂŗL���ȁA�f�C���E�y���U�[����i���Ƃ��A�y���U�[�A2003�N�j��f�i�����܂��B�y���U�[����̏ꍇ�́A��e�̋s�҂̂������ŁA�l�i�I�Ȑ����𐋂����ƌ�����̂ɑ��āA�h�i����́A�ŏ����玩���̏�Q�Ɩ\�͂Ƃ�ʌ̂��̂Ƃ��ĂƂ炦�Ă����̂ł��B�����āA�����͎����̒��ɂ������邱�Ƃ����Ă���킯�ł��B
�@�h�i����́A�O�����f�B������Ƃ͈���āA��e�Ɉ����������Ƃ͂Ȃ����������ł��i�E�B���A���Y�A1993�N�A29�y�[�W�j�B�����āA��e�̖\�͂��̂��̂́u�ق��Ďe��Ă����v�̂ł��B���̂悤�ɖ\�͂ɑ��Ċ�Ɏg�I�ȑԓx���Ƃ邱�Ƃ́A���ۂɗc���s�҂����l�����̑����ɋ��ʂ�����̂ł��傤�B����ǂ��납�A��������e����s�҂��Ȃ���A���̕�e�������q�ǂ�������قǂł��B����ɑ��āA������������邱�Ƃɑ����R�́A���_���������l��������łȂ��A������ӂ��̐l�����ɂ��L������������Ȃ̂ł����āA��s�Ҏ҂⎩�NJ��҂ɓ��L�̂��̂ł͂���܂���B
�k���܂������I�[�X�g�����A����p���ւ́l�o���̓��ɁA�e�B���k�ʂꂽ���l�l�͂킽���̃A�p�[�g�ɂ���ė����B��l���̒��H�������A�������悤�ȕ\��̒��ɗh��߂����Ȃ���B�ނ̎p��ڂɂ����Ƃ���A�킽���͎������ۗ��ɂ���A�߂炦���Ă��܂����悤�ȋC�����Ɋׂ����B�E�B���[�k�h�i���A�c������ΐl�I�Ղ̂��߂ɍ�肠���Ă����ʐl�i�l�́A�e�B����{������B����ł��e�B���͋C�ɂ��Ȃ������B�ނɂƂ��āA��l������Ƃ́A����قǂ܂łɑ�Ȃ��Ƃ������B
�@���킽���́A�e�B���̗E�C��S���炽���������B�E�B���[�����X�����Ȃ��Ƃ��Ԃ��Ă��A�ނ͌����ɕ����Ȃ��ӂ�����悤�Ƃ����B���Ȃɉ�����Ȃ��A�A���Ă�A�ƃE�B���[�͓{�����B�������e�B���͂킽���̎�����ƁA�킽���ɂ₳�����L�X�������̂��B�킽���͗���ŗ��\�ɔނ������̂����B�e�����͒ɂ݂Ɋ������āA�ς��邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�e�B���͗����s�������܂܁A��������Ă킽������l�Ŏ����Ɠ����Ă���̂��A���߂Ă����B�i�����A214�y�[�W�j
�@���̎��̂ӂ���̐S�̓����̋q�ϓI�`�ʂ́A��O�ғI�Ȏ��_����̃t�B�N�V�����I�`�ʂ�ʂɂ���ƁA���ǂ����l�����͂������A�ӂ��̐l�ɂ��A�����҂̗���ɗ������ꍇ�ɂ͂ł��邱�Ƃł͂���܂���B�قƂ�Ǖs�\�ƌ����Ă悢�قǂ̂��̂ł��B�h�i���A�����Ɉ���𒍂��ł���鑊��ɑ��đf���ɂȂꂸ�A�E�B���[�Ɏp��ς��ăe�B�����������₷��Ƃ����A�܂��Ɏ����̒��łЂƂ�ŋ��������Ă���̂��A�e�B���͊��S�Ɍ��ʂ��Ă��āA����ɂЂ�ނ��ƂȂ������̑f���ȋC�������h�i����ɓ`���Ă����ʂł��B�h�i����́A��������ׂď��m���Ă���ɂ�������炸�A�����̑̂́A��������̎����̌������Ƃ������䂢�قǕ����Ă���Ȃ��̂ł��B�����ăh�i����́A����̂��������S�̓������A������i�ォ��q�ϓI�Ɋώ@���Ă���킯�ł��B
�@�����āA���̂悤�ȕ`�ʂ�����킩��ł��傤���A���̒����́A�ǎ҂̖ڐ������S�Ɉӎ����Ȃ��珑����Ă��܂��B�������A�O�����f�B������̂悤�ɁA�S�̒��� �g���C�u�����[�h ���Q�Ƃ���Ƃ����ԐړI�ȕ��@�ɂ���Ăł͂Ȃ��A�ӂ��̐l�����̎v�f�␢�Ԃ̏펯��������Ƃ킫�܂��������ŏ����i�߂��Ă���Ƃ�����ۂ���̂ł��B�����Ȃ�ƁA�����猾���̂��͂�����قǂł����A�h�i����� �g�S�̗��_�h ���A���Ԉ�ʂ̐l�Ɣ�ׂĂ��A�͂邩�ɂ�����Ɣ����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B���̂��Ƃ́A���͑S�̂̒��q������͂�����킩��܂����A���ɁA���̂悤�ȋL�q������ƁA����ɖ��m�ɂȂ�ł��傤�B����́A�����̑f���Ȏv����肢�𑼎҂ɓ`����ꍇ�ɋN����S�̓������A�h�i���A���ɓI�m�Ȍ��t���g���Đ������Ă��镔���ł��B
�@�l�Ɍ������Ď����̂��Ƃ�b�����Ǝv���A���˓I�ɁA�킽���̒��ɂ͂܂����|���킫�オ���Ă���B������킽���́A��������Ď���ɕ��点�Ȃ��炵���A�����̂��Ƃ�b�����Ƃ��ł��Ȃ������B���C�Ȃ��y�����q�̂�����ׂ�����Ă���̂��ƁA�����Ɍ����������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�܂莩���̂��Ƃ�b���ɂ́A�킽���͎������g�̐S�����A���܂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł���B�k�����l
�@�l�͂悭�킽���ɁA�v�_�������悤�ɂƔ������B���ꂪ������ے肷��ςނ悤�Ȏ��́A������̂͊ȒP�������B�܂��A�킽���̗~����킽�����g�̃A�C�f���e�B�e�B�[�ɊW���Ȃ��������A�s���R�Ȃقǂ��炷��ƌ������ďo���B�k�����l
�@���ł��킽���́A�����̊��������Ƃɂ��ẮA�����ł���������E���Ă��܂����A�y�����q�̂�����ׂ�̒��ŕ\�����邱�Ƃ����ł��Ȃ��B�l�͂�����A�Q���Ƃ��Ќ��Ƃ��u���킲�Ɓv�Ƃ����B�i�����A80-81�y�[�W�j
�@�h�i�������Ō����Ă��邱�Ƃ��A����Ȑl�����ɂ������Ă͂܂�Ȃ����Ƃł͂���܂���B�ے肷��悢���̂⍱���Ȃ��Ƃ�l�ɓ`����̂͊ȒP�ł���̂ɑ��āA�����̑f���Ȏ咣���]��ɗ����ɓ`����̂́A�N�ɂƂ��Ă������ꏭ�Ȃ��������̂Ȃ̂ł��B���ɁA���肪�����ɂƂ��ďd�v�ȑ��݂ł���ꍇ�ɂ́A���x��ʂɂ���A�قƂ�ǂ̐l�����ɓ��Ă͂܂�܂��B���̏ꍇ�ɂ́A�ʂ̗��R�����邱�ƂŎ����̈ӎ��������ł���A�h�i����̌����悤�ɁA���������ł���r�I�e�Ղɂł���悤�ɂȂ�킯�ł��B
�@���̂悤�ɁA�f���Ȏ咣���]��ɗ����ɓ`����͓̂�����̂Ȃ̂ŁA�������Ȃ��悤�Ȑ��ŁA���邢�͉����Ȃ�������ׂ�Ƃ��āA�ꍇ�ɂ���Ă͂ӂ����Ă���悤�Ȓ��q�Řb���l�́A���ǂɌ��炸�������܂��B�������Ȃ���A�u�������g�̐S�����A���܂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������v�Ƃ����ӂ��ɁA���ꂪ�����̈ӎ������������H��ł��邱�Ƃm�Ɏ��o���Ă���l�́A���܂肢�Ȃ��ł��傤�B�ӂ��̐l�́A���������s�����قږ����o�I�ɍs�Ȃ��Ă���ꍇ�������̂ɑ��āA�h�i����́A�Ȃ�����������Ȃ薾�m�Ɉӎ����Ȃ���s�Ȃ��Ă����Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B���҂̊Ԃɑ��ɈႢ������Ƃ���A���ꂪ�Q����u���킲�Ɓv�ɕ�������قNjɒ[�Ȃ��̂��ǂ����Ƃ������Ƃ��炢�̂��̂ł��傤�B
�@�h�i����́A�_���I�ȃE�B���[�ƎЌ�I�ȃL�������Ƃ����l�i���A��̈��p���ɏo�Ă����悤�ɁA�c�����玩���̐S�̒��ɍ�肠���A�����̐l�i�ɊO���Ƃ̐Ղɓ����点�Ă��܂����B��e�ɖ������ꋑ�₳�ꂽ�������Ő��܂ꂽ���R���Ȃ������Ƃ�����A�u�킽���̓E�B���[�Ƃ������ʂ̐l����ʂ��Ď����̒m�\�����コ���邱�Ƃ��A�L�������Ƃ����l����ʂ��Đl�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����̕��@��g�ɂ��邱�Ƃ��A�ł��͂��Ȃ��������낤�v�i�����A260�y�[�W�j�ƁA�h�i����͏����Ă��܂��B���̓_���A�h�i�����d�l�i����Q�Ɍ����镔���ł��B���̐l�i�Ő������Ă��鎞�ɂ́A�Љ�I�ɂ���r�I�ӂ��̑Ή����ł���̂������ł��B
�@�h�i����́A��q�̎������_�Ȉ�i���A���[�j�Ƃ̖ʒk�̏�ʂ��A���̂悤�ɉ�z���Ă��܂��B
�@���낢��Ȃł����Ƃ��v���o���Ȃ���b�����A�킽���͂悭�������A�u���Ȃ��v�ƌ������B�q�ϓI�ɘb���Ă����킽���ɂƂ��ẮA�u���Ȃ��v�������A�킽���ƁA�킽�����g�ɑ���W���A�_���I�ɕ\�킵�Ă����킯�Ȃ̂��B�l�́A�u���̒��v�Ƃ̑��ݍ�p�̒��ŁA�u�킽���v�Ƃ��Ă̎��o��[�߂Ă䂭�B�����h�i���g�́A���̑��ݍ�p��m��Ȃ������B�u���̒��v�Ƃ�����荇���Ă����̂́A�����ς�L��������E�B���[�Ƃ��������ʂ̐l���������������炾�B�i�����A141�y�[�W�j
�@�k���A���[�́l�킽���̎g���u���Ȃ��v���A���̂ł����Ƃ��N���������̂킽���́A���߂��ԓx�ƋC������\�킵�Ă��邱�Ƃ����߂����Ă��܂����B�����炭�ޏ��͂�����A�킽������������낤�Ƃ��ċN�������A�܂����̐��l�ǂƌ��āA���������Ȃ���Ǝv�����̂��낤�B�������āA�\�O�N�O�ɃL�������ƃE�B���[��n��o���Ĉȗ��A�킽�����l�����ׂĂ����̂悤�ɁA�܂�����l���̂悤���A�̌����Ă����Ƃ������Ƃɂ��A�������邱�Ƃɂ���Ă̂ݐl�ƃR�~���j�P�[�V��������p��g�ɂ����Ƃ������Ƃɂ��A�C�����͂��Ȃ������̂��낤�B�i�����A144�y�[�W�B���������p�ҁj
�@����ł́A�ǂ��炪���ƂȂ̂��킩��Ȃ��قǂł��B����͂Ƃ������A���ǎ��͎�����A�Ȃ��Ȃ���l�̑㖼���ŌĂڂ��Ƃ��Ȃ����̂ł����A�͂����Ă��̋L�q���A���������X���̐����ɂȂ��Ă��邩�ǂ����ɂ��ẮA���ꂾ���ł͎c�O�Ȃ���킩��܂���B���̖��́A�܂��ʂ̋@��Ɍ������邱�Ƃɂ������Ǝv���܂��B���d�l�i����Q�̏ꍇ�ɂ́A�{���̎������ʂ̐l�i��m��Ȃ����Ƃ��قƂ�ǂł���̂ɑ��āA�h�i����̏ꍇ�͂����ł͂���܂���B�Ӑ}�I�Ɏg���Ă��邱�Ƃ����S�Ɏ��o���Ă���̂ł��B�t�Ɍ����A���d�l�i����Q�̂��炭��i�}���A1999�N���A240�y�[�W�j���A�h�i����͍ŏ����珳�m���ė��p���Ă����ƌ����邩������܂���B
�@���ǂ��܂ޔ��B��Q�̐��Ƃł������R�o�u�Y�搶�ɂ��A���ǘA���̂̒��ʼn𗣐���Q�������l�͂T�C�U�p�[�Z���g�قǂ��邻���ł��i�u�킪���̎��ǂ̌����v�T�y�[�W�j�B���d�l�i����Q�̏ꍇ�́A�ʐl�i�𗘗p���Ă���Ƃ��Ă��A���Ȃ��Ƃ���l�i����������o���Ȃ���s�Ȃ��Ă���킯�ł͂���܂���B�h�i����̏ꍇ�́A�P�Ȃ鑽�d�l�i�̂悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���̎d�g�݂����S�Ɏ��o���Ȃ���ʐl�i����肠���A���p���Ă���Ƃ����_�ŁA�ʏ�̉𗣐���Q�Ƃ͊��S�Ɉ�����悵�Ă���̂ł��B�h�i����͗�O�Ȃ̂�������܂��A�����h�i�����ǘA���̂̒��Ɏ��܂�Ƃ���A�ȏ�̓_���猩�āA���ǂ́A���̐S���������Ƃ͕ʊi�Ƃ�������ʒu�Â��ɂȂ�悤�Ɏv���܂��B
�@�ł́A���̂悤�ȓ���Ȏ��ǂ̎���͑��ɂȂ��̂��ƌ����A�ǂ���炻���ł��Ȃ������Ȃ̂ł��B�������ꋳ�猤�����i���A�������ʎx�����瑍���������j�̋���S���w�ҁA�ʈ����搶�i1923-1999�N�j�������A����߂Ēm�I�\�͂������j���̎���i�ʈ�A1975�N�A1981�N�j������ɓ�����悤�Ȃ̂ł��B
�@���̒j���́A�P�V�����̎��ɖ������܂ꂽ���߁A��e�̎��Ƃɗa�����܂����B���e�́A�R������ɂ��̎q������ɘA��߂�����A���߂ĈٕςɋC�Â��������ł��B���e��Y��Ă��܂������̂悤�Ȃӂ�܂�������悤�ɂȂ������߂ł����B�܂���^�Ƃ���ތ^�ƌ����鎖��ł��B���̏ꍇ�A�c�����Ŋ��ɔ��a���Ă����ƍl����̂���ʓI�ł��傤���A����ɖ߂��ꂽ����ɔ��a�����\�����l�����Ȃ��킯�ł͂���܂���B�����ł���A�܂��ɍK���ے�ɂ����̂̉\���������Ȃ�ł��傤�B
�@���̎q�́A�������o����̂͑����A�Q�ɂȂ�������̍��ɁA�A���t�@�x�b�g�A�Ђ炪�ȁA�J�^�J�i�A�����A�������̉p�P������X�Ɋo���������ł��B���̔��ʁA�悻�̎q�ǂ����V�тɗ���Ɠ����o���A�����߂��Ă���R�������������Ȃ��Ƃ����ΐl�I����������܂����B�܂��A�ЂƂ�V�т��D�݁A�l�ɂ͂킩��Ȃ����t�ŗ��e�ɘb���������肵�������ł��B���ǂɖڗ��Ǐ�̂ЂƂł�����A�Z�ʂ������Ȃ��Ƃ������ʂ�����܂����B
�@�c�t�������ƂƂ��ɁA�ʈ�搶�̋Ζ���̌������Ƀv���C�Z���s�[�̂��ߒʂ��悤�ɂȂ�܂����B�ʏ����J�n���Ă���P�N���قǂ���ƁA���҂Ƃ̊W���ł��n�߂��̂ł����A�l�ԊW�̂���������[�܂肩���A�L���肩���͔��ɂ������Ȃ����������ł��B���̍��ɁA���̎q�� �g�I�`���b�p�h �Ƃ����ʐl�i����肠�����̂ł��B�����āA�u��肽�������Ƃ�����K�����鎩���Ƃ��v���āA����̎������I�`���b�p�ƌĂсA�ЂƂ�Ŏ������g�Ƃ��Ƃ肷��悤�ɂȂ�܂����B�I�`���b�p�Ƃ����ʐl�i��������̂́A���������ƂƁA���Ă͂����Ȃ����ƂƂ̊W��m���Ă��āA���̑Η����������A�����𐬒������邽�߂̎�i�Ƃ��ė��p���邽�߂������̂�������܂���B�ȉ��Ɉ��p����̂́A���̉����̗��Â��ɂȂ肻���ȏo�����ł��B
�@�k���̎q�́l���鎞�A�G�ЂŊ����ӂ��Ȃ���A����̏�ɐU��グ�ăp�b�ƒ@�������Ƃ���A�������܂��Ĕނ̎肪���ɂԂ����Ă��܂����B����Ɣނ́u���߂�ˁi���ʂ̐��j�v�u�������Ƃ͂���ȁI�i�������j�v�ƌ������̂ł���B�����Ŏ����������Ă���悤�Ɏv����B�k�����l���̂悤�ɔނƃI�`���b�p�Ƃ́A�݂��ɑΗ��������������W�ɂ���B�������A����炪�S�����ĕʁX�ɊO�̐l�ɐڂ��Ă���̂ł͂Ȃ��B�Η������������k���l�Ƃ����Ƃ����`�ɂ����āA�ނ��ЂƂ�̐l�ԂƂ��āA�K���s�����Ƃ��悤�ɔނ̒��Ńo�����X���Ƃ铭�������Ă���B���������āA����͔ނ̕s����Â߂铭�������邱�Ƃ����邵�A���鎞�́A��e��Z���s�X�g���猾��ꂽ���Ƃ��u�I�`���b�p�v�ɓ��e���āA�u�I�`���b�p�v���ނɌ������������`���Ƃ��Ĕ[�����邱�Ƃ�����B�i�ʈ�A�����A�T�y�[�W�B���������p�ҁj
�@�����ł͂������Ȃ����A���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�e�Ɍ���ꂽ�Ƃ���ƁA�I�`���b�p�̌��t�Ŏ����Ɍ�����������̂������ł��i�ʈ�A1981�N�A�R�y�[�W�j�B�������Љ�I�ɐ������邽�߂ɂ́A�����̗c���ӎ���������Ă����K�v������킯�ł����A���̎���ł́A�����������m�ȖړI�������āA�ʐl�i����肠���A����𗘗p���Ă���Ƃ������ƂȂ̂�������܂���B�����������Ƃ���A�h�i����̏ꍇ�Ƃ́A�ʐl�i�̗��p�̂��������A����Ӗ��ŋt�ɂȂ��Ă���悤�ł��B������ɂ���A�ʐl�i��ΊO�I�ȓK���̂��߂ɍ�肠�����Ƃ����_�ł͋��ʂ��Ă���̂ł��傤�B
�@�����ЂƂ́A���m�����w��Q�����Ë���Z���^�[�̋���S���w�ҁA�_��i����́j�G�Y�搶�i���A���m�i����w�j�����Ă��鎖��i�����A�V�̒j���j�ł��B����́A�{���́u���g���L�v���u���g�K�L�v�ƕό`���A��e���璍�ӂ��ꂽ�莶��ꂽ�肵����ʂŁA�����́u���g�K�L�v���ƌJ��Ԃ��咣��������ł��i�_��A1984�N�j�B�����Ă���̂́A�u���g�K�L�v�ł����Ė{���̎����ł͂Ȃ��Ǝ������g�Ɍ����������Ă����Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���B�������Ƃ���A�u�K�L�v�́A�����킯���Ȃ��q�ǂ��Ƃ����Ӗ��ł̃K�L�Ȃ̂�������܂���B
�@���Ȃ݂ɁA���̎���ł́A�u�ꂳ��D���v�ƌ����ׂ��Ƃ�����A�킴�Ɓu�ꂳ��k�L�v�ƌ�������A�u���߁v�A�u��߂Ȃ����v�ƒ��ӂ����ƁA�킴�킴�u�_�����v�A�u�A���i�T�C�v�Ƃ��ꂼ�ꌾ����������A�u�����v�ƌ����ׂ��Ƃ�����u�C�u���v�ƌ������肵�������ł��i�����A262�A264�y�[�W�j�B�����́A�ӂ��̐l�� �g�Ƃ�B���h �₻��Ɋ�Â� �g���Ⴉ���h �̂悤�ɂ������܂��B���������ł���A���ǂƂӂ��̐l�̊Ԃ̋�������C�ɏk�܂肻���ł��B�h�i����̂悤�ɁA����ɂ��Ă͂����肵�����������Ă����A���̈Ӗ������ĂɂȂ�킯�ł����A�����ɂ́A�e�Ղɂ͏��z�����Ȃ��ǂ�����̂�������܂���B
�@����́A��قnj������邱�ƂȂ̂ł����A���̖����ŊȒP�ɂӂ�Ă����ƁA�ʂ����āA���S�ɐ��n�����ƌ�����l�Ԃ͑��݂�����̂Ȃ̂��Ƃ������{�I�ȋ^�₪�A�����ŕ����яオ��܂��B�s������������ÃZ���^�[�̎������_�Ȉ�A�s��G�L�搶�́A����u���̒��ŁA�u�܂��������B��Q�I�v�f�������Ȃ��l�͂���̂��v�Ƃ����^������ۂɒ悵�Ă��܂��i�s��A2012�N�A424�y�[�W�j�B�C�s��ʂ��Đl�i�̌����ڎw�����Ƃɂ��������l�������������Ƃ��炵�Ă��A���ۂɏC�s��簐i���Ă����A���̐l�����z�Ƃ���Ƃ���܂ł͓��B�����Ȃ����Ƃ��炵�Ă��A���̋^��͑Ó��Ȃ��̂ƌ�����ł��傤�B�^�̏C�s�҂ł���A�������W����̂悤�ɁA�g�ŏI��E�ҁh �ȂǂƎ��̂��邱�Ƃ͂��肦�Ȃ�����ł��B
�@���̂悤�ɁA���Ȃ��Ƃ����݂̐l�Ԃ͑S�����A�����ꏭ�Ȃ��ꔭ�B��Q�̏�Ԃɂ���ƍl����A���ǂƂ�����ӂ��̐l�Ƃ́A���S�ɘA���̂ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����ɂ͂����肵�܂��B�������A���̏ꍇ�ɔO���ɒu���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�L���X�g���������悤�ɁA�u��̎҂���ɂȂ�A��̎҂���ɂȂ�v�i�u�}�^�C�ɂ�镟�����v�� 20 �� 16 �߁j�̂�������Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�ꌩ����ƁA���B��Q�������Ă���l�����̂ق����x��Ă���悤�Ɋ�������킯�ł����A�T���@���nj�Q�̔��������ǂł��邱�Ƃ��l����ƁA���̂悤�ɊȒP�ɕЂÂ���͓̂�����Ƃ��킩��ł��傤�B���ɏЉ�铌�c�������������Ă���悤�ɁA����������܂߂��\�ʓI�ȍs���́A�l�Ԃ̖{���𑪂�肪����Ƃ��āA���܂肠�ĂɂȂ�Ȃ���������Ȃ��̂ł��B
�@�܂��A�h�i����̂悤�ɗ�O�I�Ȑl�́A�l�Ԃ̐S�̓������A�ӂ��̐l�����͂邩�ɖ��m�ɔc�����Ă���Ƃ����������炷��ƁA���̂悤�ȏ�Q�́A�ނ���A�l�Ԃ̑��݂ɂ��ĉ����d�v�Ȃ��Ƃ��ӎ��ŋC�Â������A�C�Â����������ʂƂ��ċN����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����͂Ȃ͂���O���킵���S���_�I���������܂�܂��B���̏ꍇ�A���͂Ȓ�R�̌��ʂƂ��āA�����̐l����l���Ƃ̂悤�Ɍ���`�ɂȂ�₷���̂�������܂���B
�@���ꂪ�A���܂�ɏ펯���͂��ꂽ�l���ł���̂͂܂���������܂��A���S�ɐ��n�����l�Ԃ����ڂ낰�Ȃ���ł��v���`����̂͂Ȃ����A�܂��A���̒i�K�ɓ��B�������Ɗ���l�����Ȃ��炸���݂���̂͂Ȃ��Ȃ̂��Ƃ��������l����ƁA���Ȃ����I���O��Ă���Ƃ͌����Ȃ���������܂���B
�@�{�߂łƂ肠����̂́A������f���ꂽ�m�g�j�̓��W�ԑg�u���ǂ̌N�������Ă��ꂽ�����v�i2016�N12��11�����f�j�ł��Љ�ꂽ���c�i�Ђ������j���������ł��B���c����́A1992�N�ɐ�t���ɐ��܂ꂽ�A���� 24 �̎��NJ��҂ł��B13 �̎��ɏ������w���ǂ̂ڂ������т͂˂闝�R�x�i2007�N�A�G�X�R�A�[���o�ŕ����j�́A�A�C�������h�ɏZ�ސ��E�I�x�X�g�Z���[��Ƃ̎�ʼnp���A���o�ŎЂ��� The Reason I Jump �Ƃ����^�C�g���ŏo�ł���܂����B���ꂪ�������ƂȂ��āA���̒����́A���݁A30 ������ȏ�ɖ|��A�e���v���E�O�����f�B�������h�i�E�E�B���A���Y����̒����ƕ���ŁA���E�I�ȃx�X�g�Z���[�ɂȂ��Ă��邻���ł��B���c����́A���̒����ȊO�ɂ��A�G�{�⏬�����܂߁A�������̒����𐢂ɏo���Ă��܂��B
�@�O�����f�B�������h�i����̓`�L�Ƃ��̒������r����ƁA���܂��܂ȈႢ���ڂɂ��܂��B�ł��傫���̂́A�O�҂̂悤�Ȃ���ΐ�������ł͂Ȃ��A���Ԉ�ʂ̐l���������ǂɂ��ċ^��Ɋ����邱�Ƃ��A���ꓚ�`���ŊȌ��ɓ�����Ƃ����`�ɂȂ��Ă��邱�Ƃł��B����ɂ��A���ǂ����l�ƈ�ʂ̐l�Ƃ̊Ԃ̒ʖ�̂悤�Ȗ������ʂ����Ă���킯�ł��B���̂��߁A���Ɍ��t�̂Ȃ����ǂ̎q�ǂ������Ƒ����炷��A���������̎q�ǂ��������l���Ă���̂��������ł���悤�ɂȂ��Ă���̂ł��B���Ƃ��A���ǂɓ����I�ȁA���₳�ꂽ���t�����̂܂܃I�E���Ԃ��ɂ��闝�R�ɂ��āA���c����́A���̂悤�ɉ�����Ă��܂��B
�@�l��͎�����J��Ԃ����Ƃɂ���āA����̌����Ă��邱�Ƃ���ʂƂ��Ďv���N�������Ƃ���̂ł��B����ꂽ���Ƃ͈Ӗ��Ƃ��Ă͗������Ă���̂ł����A��ʂƂ��Ă͓��ɕ����Ȃ��Ɠ������܂���B
�@���̍�Ƃ͂ƂĂ���ςŁA�܂��A���܂Ŏ������o���������Ƃ̂���S�Ă̎�������A�ł����Ă����ʂ�T���Ă݂܂��B���ꂪ�����Ă���Ɣ��f����ƁA���ɁA���̎������͂ǂ��������Ƃ����������v���o�����Ƃ��܂��B�v���o���Ă����̏�ʂɐ����̌�����������̂ł����A������炢�C�������v���o���Ęb���Ȃ��Ȃ�܂��B�ǂ����Ă��b�����Ƃ���ƕςȐ����o�����܂��A����Ŏ������p���������������A���������肵�āA�܂��܂��b���Ȃ��Ȃ�̂ł��B
�@��������Ă����b�Ȃ�A���ƃX���[�Y�Ɍ��t�̂���肪�ł��܂��B
�@�ł��A�p�^�[���Ƃ��Ċo���Ă��邾���Ȃ̂ŁA�����̋C������b�����ƂƂ͈Ⴂ�܂��B�C�����Ɛ����̂��Ƃ��A�p�^�[���ɓ��Ă͂߂Č����Ă��܂����Ƃ������̂ł��B
�@��b�͂�������ςł��B
�@�C���������Ă��炤���߂ɁA�l�́A�m��Ȃ��O����������ĉ�b���Ȃ��Ă͂����Ȃ��悤�Ȗ����Ȃ̂ł��B�i���c�A2007�N�A18-9�y�[�W�B���������p�ҁj
�@��قǂ��炽�߂ĂƂ肠���邱�Ƃɂ��܂����A�J�i�[�^�̏d�x�Ƃ���鎩�ǂł��铌�c����̏ꍇ�ɂ��A�ӂ��̊�����邱�Ƃ��͂�����Ƃ킩��܂��B�܂��A���̔����́A�u���C�u�����[�v���Q�Ƃ���Ƃ����O�����f�B������̐����Ɗ�{�I�ɂ͋��ʂ��Ă���悤�ł��B���c����̏ꍇ�A���̂悤�ɑ��̎��ǂ̐l�����Ƌ��ʂ��Ă������������̂͊m���ł����A�K���������̂悤�Ȃ��̂���ł͂���܂���B���Ƃ��A�̂ɂӂ���邱�Ƃɑ��鋰�|�ǂł��B���c����́A���ɂ���ł͂Ȃ��Ƃ����̂ł��B
�@�l�͂���ł͂���܂��A���ǂ̐l�̒��ɂ́A�������߂�ꂽ��G��ꂽ�肷��̂��ƂĂ����Ȑl�����܂��B
�@���R�͂悭������܂��A���Ԃ��C���������Ȃ�����ł��傤�B�k�����l
�@�̂ɐG����Ƃ������Ƃ́A�����ł��R���g���[���ł��Ȃ��̂𑼂̐l�������Ƃ����A�����������Ŗ����Ȃ鋰�|������܂��B�����āA�����̐S������������Ă��܂������m��Ȃ��Ƃ����s��������̂ł��B�k�����l
�@������A�l�����͎����̎���Ƀo���P�[�h���͂��āA�l���t���Ȃ��̂ł��B�i�����A44-45�y�[�W�j
�@����́A���c���������萄�������肵�Ă��邱�Ƃ𗦒��ɏq�ׂ����̂ł��傤�B�ӎ��̏�ɂ���v����l����`���Ă��邾���Ȃ̂ŁA�̂ɂӂ����̂����₪��l�̐S��킩���Ă���킯�ł͂Ȃ������ł��B�u�����C���������Ȃ��v�Ƃ����펯�I�Ȑ����͂ł��Ă��A���̗��R�́A���c����ɂ��킩��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�u�����C���������Ȃ��v���R���K���ے�̖����ōl����A���ꂪ�����ɂƂ��Ă��ꂵ�����߁A���̔ے肪�������Ƃ��鐄������͂萬�����邱�ƂɂȂ�ł��傤�B
�@�܂��A��̔����ɂ�����悤�ɁA�O�����f�B�������h�i����ƈ���āA���c����͐l�ƌ����ʼn�b���邱�Ƃ��ł��܂���B���c�����̂ӂ�������͂邩�ɏd�ǂł���J�i�[�^�ɕ��ނ����̂́A�܂��ɂ��̂��߂ł��B��b���ł��Ȃ����R�ɂ��āA���c����͎��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B
�@�l�́A���ł��A�l�Ɖ�b���ł��܂���B�����o���Ė{��ǂ�A�̂�����͂ł���̂ł����A�l�Ƙb�����悤�Ƃ���ƁA���t�������Ă��܂��̂ł��B�K���̎v���łP�`�Q��͌��ɏo���邱�Ƃ�����܂����A���̌��t�������A�����̎v���Ƃ͋t�̈Ӗ��̏ꍇ�������̂ł��B�k�����l
�@�l�́A��b�͂ł��܂��A�K���ɂ��A�͂����ݏm�̗����Ƃ��ꂳ��Ƃ̌P���ŁA�M�k�Ƃ����R�~���j�P�[�V�������@����ɓ���܂����B�����āA���ł́A�p�\�R���Ō��e��������悤�ɂȂ�܂����B�i�����A2-3�y�[�W�j
�@���ǂ̐l�́A�C���g�l�[�V��������������������A���t�̎g���������ʂ̐l�ƈ���Ă����肷�邱�Ƃ�����܂��B
�@���ʂ̐l�́A�b�����Ȃ��玩���̌����������Ƃ��܂Ƃ߂��܂����A�l�������{���Ɍ����������t�ƁA�b�����߂Ɏg���錾�t�Ƃ������łȂ��ꍇ������܂��B���̂��߂ɁA�b�����t���s���R�ɂȂ�̂��Ɩl�͎v���܂��B�k�����l
�@�݂�Ȃ͂������X�s�[�h�Řb���܂��B���ōl���āA���t��������o��܂ł��ق�̈�u�ł��B���ꂪ�A�ڂ������ɂ͂ƂĂ��s�v�c�Ȃ̂ł��B�k�����l
�@���肪�b�����Ă���āA�����������悤�Ƃ��鎞�ɁA�����̌����������Ƃ����̒���������Ă��܂��̂ł��B�k�����l
�@�������Ƃ������t�������Ă��܂�����A�����v���o���܂���B���肪�����������̂��A����������b�����Ƃ����̂��A�܂�ŕ���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ł��B���̊Ԃɂ��A����͎����玟�ւƖl�����ɂ��т����܂��B�k�����l
�@�l�����́A�܂�Ō��t�̍^���ɓM���悤�ɁA�������남�낷�����Ȃ̂ł��B�i�����A24�A26-27�y�[�W�B���������p�ҁj
�@���c����́A��̈��p���ŁA�u�m��Ȃ��O����������ĉ�b���Ȃ��Ă͂����Ȃ��悤�Ȗ����v�Ə����Ă��܂����B���c���u����Ă����Ԃ́A���ȏ��ŊO������w��ŁA�ǂݏ����������ł���悤�ɂȂ����l���A���̊O�������Ƃ���l�Ɖ�b�����Ă����ʂ�z������ƁA��r�I�킩��₷���悤�Ɏv���܂��B
�@�ǂ菑������Ȃ�A������x�͂ł���B�Ƃ��낪��b�Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�܂������Ƃ肪����B�P�ꂪ�f�ГI�ɂ��������Ă��Ȃ��B���̂悤�ȋٔ��̒��ŁA���̌��t�̈Ӗ����l���Ă��邤���ɁA�����玟�ւƕʂ̌��t�������Ă���B���̂悤�ȏł́A�������Ƃ��Ă������t�������Ă��܂��ł��傤���A���Ƃ̍^���ɓM��Ă��남�낵�Ă��܂����Ƃ��Ă��A���̂ӂ������Ȃ��ł��傤�B
�@���ꂪ�P�Ȃ��g�łȂ��A���炩�̋��ʓ_�̂��錻�ۂ��Ƃ���A���ǂ̌��t���l���鎞�A�Ȃ����̐�ɐi�݂ɂ����̂��Ƃ����A�]���Ȃ��������_�����܂��͂��ł��B���̏ꍇ�A�u�l�����͖{���Ɍ����������t�ƁA�b�����߂Ɏg���錾�t�Ƃ������łȂ��ꍇ�����v��Ƃ����،����A�傫�ȈӖ��������Ă��邩������܂���B���ɁA�������������A�ǂݏ������ł��鎩�ǂ̊��҂��A�������ăp�\�R���̃L�[�{�[�h���當�����Â�o�����Ƃ���A����܂Řb�����菑�����肵�Ă������Ƃł́A���ۂɂ͎����̋C�������\���ł��Ă��Ȃ������ƌ�������������̂ł��i�ēc�A2012�N���A80-81�y�[�W�j�B
�@���́A��قǂ������ӂꂽ�A���ǂ̐l�����ɂ͊������̂��Ƃ����A�̂���̖��ł��B�O�����f�B�������h�i����̏ꍇ�ɂ́A�L���Ȋ�������B�ꂵ�Ă��邱�Ƃ��킩��܂������A���c����̂悤�ȏd�x�̎��ǂ̏ꍇ�͂ǂ��Ȃ̂����A�ʂ̏،������Ƃɂ��炽�߂Č����Ă݂܂��傤�B
�@�����ƍ����Ă���̂́A�݂�Ȃ����Ă��鎞�ɖl�����Ȃ����Ƃł��B
�@�y�����Ǝv���邱�Ƃ₨���������Ƃ��A�݂�ȂƂ͈Ⴄ�̂��Ǝv���̂ł��B���̂����A�h�����Ƃ�ꂵ�����Ƃ���̖����ł͂ǂ����悤������܂���B
�@�ƂĂ��т����肵����A�ْ�������A�p�������������肵�������A�l�����͌ł܂邾���Ŋ����\�ɏo�����Ƃ��ł��܂���B
�@�l�̔ᔻ��������A�l�����ɂ�����A�l�����܂����肷�邱�Ƃł́A�l�����͏��Ȃ��̂ł��B
�@�l�����́A����������������A�y�����������Ƃ��v���o�����肵�����A�S����̏Ί炪�o�܂��B
�@�ł�����́A�݂�Ȃ̌��Ă��Ȃ����ł��B
�@��A�z�c�̒��ŏ���������A�N�����Ȃ������̒��ŏ��]������A�l�����̕\��́A������C�ɂ��������l���Ȃ��Ă������ɁA���R�Əo�Ă�����̂Ȃ̂ł��B�i�����A42-43�y�[�W�B���������p�ҁj
�@���c����ɂ��A�O�����f�B�������h�i����Ɠ������A�L���Ȋ������Ƃ������Ƃł��B�������A����o��Ώۂ��ʂ́A���Ԉ�ʂ̐l�����Ƃ͂��Ȃ����Ă���悤�ł��B���̏،��ŏd�v�Ȃ̂́A������z������́A�l�̌��Ă��Ȃ��Ƃ���ŕ\�o���₷���̂ɑ��āA�ӎ��̏�ɂ̂ڂ����A������́A�ǂ��ɂ��鎞�ł���\�o���ɂ����Ƃ������Ƃł��傤���B�������A�p�j�b�N���N�������ꍇ�́A���̌�����A�c���I�ȍs����ʂ��Ă��̂܂ܕ\�o������̂ł��B
�@�l�́A�������s����Ɠ��̒����^���ÂɂȂ�܂��B
�@�����Ă�߂��đ呛���A�����l�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ł��B���ꂪ�ǂ�Ȃق�̂������Ȏ��s�ł��A�l�ɂ͓V�n���Ђ�����Ԃ�قǂ̏d��ȏo�����Ȃ̂ł��B
�@�Ⴆ�A�R�b�v�ɐ��𒍂����ɁA�����ł��������ڂ�邱�Ƃ����A�l�͉䖝���ł��܂���B
�@�l���猩��A�Ȃ�����Ȃɂ��߂����̂������ł��Ȃ��Ǝv���܂��B�����ł��A�����������s�ł͂Ȃ����Ƃ��������Ă��܂��B�������A�����}���邱�Ƃ�����̂ł��B
�@���s����ƁA�܂��Ôg�̂悤�ɁA�l�̓��̒��Ŏ��s���������������ė��܂��B�k�����l
�@�Ƃɂ����������̏�Ԃ��瓦���o���Ȃ���A�l�͓M�ꎀ��ł��܂�����ł��B�����������߂ɁA�����Ȏ�i�����܂��B�����Ă�߂������ł͂Ȃ��A���𓊂�����l�������������c�c�i�����A54-55�y�[�W�B���������p�ҁj
�@����́A���ǎ��ɂ悭������p�j�b�N�̏��A�����҂���������ڂ����������Ă��镔���ł��B���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A����̕\�o��}���邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂������ł��B���̐��������������ǂ����͂Ƃ������Ƃ��Ă��B���̈�A�̌o�߂��O�����猩��ƁA�V���I�s���⓯�ꐫ�̕ێ��A���S�ȁA�����I�X���A�p�j�b�N����ȂǂɌ�����̂ł��傤�B���c����̐������������Ƃ���ƁA���̂悤�Ȏ��ɂ́A�ǂ����Ă����܂ŋ�������o��̂ł��傤���B������ɂ���A���ۂƂ��ẮA�`�c�g�c�Ƃ����q�ǂ������Ɏ����茩������̂Ɠ������Ǝv���܂��B������K���ے�̖����ōl����ƁA�Z�ʂ̂����Ȃ���Ȃȏ�Ԃ̂܂܂ł������A�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B�����ŁA���̂悤�ȃp�j�b�N�̌����́A�Z�ʂ�����������Ë������肪�܂���Ƃ����A�����̎w�W�ƂȂ�Ή�������悤�Ƃ��邱�Ƃɂ���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������������܂�܂��B
�@�����Ŏv���o���̂́A���̐S���Ö@���Ă����A�����a�� 20 ��̂��鏗���̎���ł��B���e�ɂ���ăX�L�[�ɍs���A���Ƀ��X�g�����ŐH�����Ă������̂��Ƃł��B�H�����I����Ă��A�b���D���̕��e�́A���܂��ܗׂɂȂ����X�L�[�q�Ɖ��X�Ƙb�������Ă����̂������ł��B��e�����̂��Ƃł��肵�Ă������A���̏������ˑR�ɑ吺���o���ċ������n�߂��̂ł��B�܂��̐l�����̎����́A���������ɂ��̏����ɒ�����܂����B���̎��́A�Ĕ��ɂ͎���܂���ł������A�ُ�ȋ����������̂͂܂���������܂���B���́A���̌����ł��B
�@���̎�����ɍs�Ȃ�ꂽ�S���Ö@�̃Z�b�V�����ŁA���̎��̌��������g���či�荞���ʁA�������{���́A���̂悤�ȏł��ӂ��̑Ή����Ƃ��悤�ɂȂ����Ƃ����A�������i���������Ƃɂ�邤�ꂵ���̔ے肪�A���̎��̋����̌����ł��邱�Ƃ��킩��܂����m��10�n�B���̂܂܂��܂邩�A���e�ɍÑ����邩����A�Љ�l�Ƃ��Ă̓K�ȑΉ��Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł����A���̂悤�ɎЉ�I�ɐ��n�����ԓx���Ƃ��悤�ɂȂ��Ă������Ƃ������̈ӎ��ɂ킩���Ă��܂��̂������āA���܂�ł��Ȃ��������̂悤�ɋ������n�߂��A��������Ηc���I�ȑΉ��������Ƃ������Ƃł��B��̉�������������A���̂ӂ��̎���́A����̐����̔ے�Ƃ����_�ŋ��ʂ��Ă��邱�ƂɂȂ�ł��傤�B
�@���́A�ӂ��̐l�Ƃ����ʂ���A����Ȃ��E����Ȃ��Ƃ����s�������ɂ��ẮA���c����Ȃ�̐����ł��B���Ă͂����Ȃ����Ƃł͂킩���Ă���ɂ�������炸�A�s�����~�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ������m�̌��ۂł��B���X�������p�ł����A�d�v�Ȃ̂ŒO�O�ɓǂ�ł��������B
�@���Ă͂����Ȃ��Ƃ������Ƃ͗����ł��Ă��A�Ȃ����J��Ԃ��Ă��܂��̂ł��B�k�����l
�@����Ă͂����Ȃ��Ƃ������������A���̏�ʂ��Č��������C�����̕����傫���Ȃ��āA���������Ƃ�����Ă��܂��̂ł��B
�@����ƁA���̒�����u�A�܂�Ŋ��d�����݂����ɂт���Ƃ��܂��B���̊��o�͂ƂĂ��C�����̂������̂ŁA���ł͓����悤�ȉ����͓����܂���B�k�����l
�@����ǂ��A�������Ƃ����Ă͂����Ȃ��̂ł��B����𗝐��Ƃ��āA�ǂ��Ȃ����Ă䂭�����傫�Ȗ��ł��B
�@�l�����Ƃ��Ȃ������Ƃ��Ă��܂����A���̂��߂̃G�l���M�[�͂��Ȃ�̂����ł��B�䖝���邱�Ƃ́A�ꂵ���ċꂵ���đ�ςł��B���̎��ɕK�v�Ȃ̂��A����ɂ���l�̔E�ϋ����w���ƈ���ł��傤�B
�@�l���������čD���ł���Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ł����A���Ȃ��Ƃ��Ă������Ă������Ȃ��̂ł��B
�@��������������Ă��邱�Ƃ����ƁA�����������������܂��B���������݂�Ȃɒ��ӂ��ꂽ��A��߂�����ꂽ�肷�邽�сA�l�͂ƂĂ���Ȃ��Ȃ�܂��B�������Ȃ�Ă�肽���Ȃ��̂ɁA����Ă��܂�����������Ȃ̂ł��B
�@�����A�l�ɖ��f�������邱����������Ă���̂Ȃ�A���Ƃ����Ă����ɂ�߂����ĉ������B�l�ɖ��f�������Ĉ�ԔY��ł���̂́A���ǂ̖{�l���g�Ȃ̂ł�����B
�@���Ƃ����̎��A����Ă���{�l�����Ă�����A�ӂ����Ă����肵�Ă��Ă��A�S�̒��ł͏����Ă���̂ł��B�����̑̂ł���Ȃ���A����������߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��l�����ɂ͂ǂ����悤������܂���B�k�����l
�@���̂�����肪�i���ɑ������Ƃ͂���܂���B����Ȃɂ�߂��Ȃ������̂ɂǂ����ĂƎv���قǁA������ˑR���Ȃ��Ȃ�܂��B���������͔]���I���̃T�C�����o�����炾�Ǝv���܂��B�k�����l
�@�T�C�����o��Ζl�͂����A�����������S�ĖY��Ă��܂����l�̂悤�ɁA������肩���������̂ł��B�i�����A126-129�y�[�W�B���������p�ҁj
�@�܂�ŁA�A���R�[����̈ˑ��҂��A�f���◣�E�Ɏ��s�������̌�����ł����Ă���悤�Ȋ����ł��B��̒j���̏ꍇ�ɂ́A�ʐl�i����肠���āA���̐l�i�������̈ӎ��Ɍ�����������Ƃ��������҂ݏo���Ă����킯�ł����A���c����́A��͂�d�ǂł��邽�߂��A���̂悤�ȕ��@�͎g���Ă��Ȃ��悤�ł��B
�@�����ł̃|�C���g�́A���Ă͂����Ȃ��Ɨ����ł͂킩���Ă��邵�A�D���ł��Ă���킯�ł͂Ȃ��ɂ�������炸�A���������邽�߂������Ă��܂����A���̗U�f�ɕ����Ȃ��悤�ɂ���̂́A�u�ꂵ���ċꂵ���đ�ρv���Ƃ��������ƁA���鎞�ɂ����ˑR�ɂ��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ����邪�A����́u�]���I���̃T�C�����o���v���߂��Ƃ��������̂ӂ��ł��傤�B�K���ے�̖����ōl����A�O�҂́A�����̐�����f���ɔF�߂�̂������Ď����ō�肠�����������ɂł���A�]�̏I���̃T�C���Ƃ́A���̒�R�����͂ŏ��z�������_���w���Ă���\�����������ł��B��҂ɂ��Ă����A�����܂ł̓w�͂́A�ӂ��̐l�ɂƂ��Ă��������Ă��̂��Ƃł͂���܂���B
�@���̐������������Ă��邩�ǂ������͂����肳����ɂ́A���Ƃ��A�u���Ă͂����Ȃ��Ƃ킩���Ă���̂ɂ�߂��Ȃ��̂́A�����̐�����F�߂�̂������Ă��邽�߂��v�ƁA�u���������s�������Ȃ��Ȃ�̂́A�]�̃T�C���ɂ����̂ł͂Ȃ��A��������R����蒴�������ʂ��v�Ƃ�������̉��Z�����Ă��炢�A����ɂ���Ĕ����i���C�A�����сA�g�̓I�ω��j���o�邩�ǂ������m�F����悢�ł��傤�B
�@������ɂ��Ă��A���c�����̒����Ŏ����Ă��� �g���@�h �́A13 �̏��N�ɂƂ��Ă͂������̂��ƁA�ӂ��̐��l�ł����Ă������������Ȃ��قǂ̂��̂ł��B���c���A���ɏd�x�̎��ǂɂ��āA���̂悤�ɂ��Ȃ�̂��Ƃ������Ă���Ă���͎̂����ł��傤�B�܂��A���c����̖{�́A�O�����f�B�������h�i����̖{�ƈ���āA���ꓚ�`���ł킩��₷�����Ƃ������āA���ǂ̎q�ǂ������Ƒ��ɂ͔��ɎQ�l�ɂȂ�͂��ł��B����ɑ��āA�O�����f�B�������h�i����̖{�́A�����҂�Ƒ��ɂ͋��������肷���邽�߁A���܂�Q�l�ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B�����́A�ނ�����ƂɂƂ��Ă����Ӗ����傫���悤�Ɏv���܂��B
�@�Ƃ��낪�C���̒����́C�킸�� 13 �́C�������d�x�̎��ǂ̏��N���������ɂ��ẮC���Ȃ荂�x�Ȃ��̂ł��邱�Ƃ���C����́C�O�o�̎x���`�B�iFacilitated Communication = �e�b�j�ƌĂ��Z�@��ʂ��āC�Ƒ��Ȃǂ̉�҂��i�����͖��ӎ��I�Ɂj������������ʂȂ̂ł͂Ȃ����Ƃ����^�O��������Ƃ�����̂ł��m��14�n�B�܂�C����ɂ���ĂÂ�o���ꂽ���e�́C���c���g�ɂ����̂ł͂Ȃ��C��҂̂��̂Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł��B
�@����́C���c���C���@�\���ǂ�A�X�y���K�[�nj�Q�ł͂Ȃ��C�d�x�̎��ǂƂ���Ă��邽�߂Ȃ̂ł��傤�B����ɑ��āC�T���@���̏ꍇ�ɂ́C�d�x�̃J�i�[�^�ł����Ă����̔\�͂ɋ^�`���������邱�Ƃ͂܂�����܂���B����́C�{�l������s�Ȃ��Ă���̂�ے肵�悤���Ȃ����Ƃɉ����āC�����炭���x�̎v�l�����Ă���ƍl�����ɂ��܂��邱�Ƃ��ł��邽�߂Ȃ̂ł��傤�B�����ɁA���Ƃ̋�����R�����邱�Ƃ��ł���悤�Ɏv���܂��B
�@�ΐl�W��Љ�̔��B�̏�Q�Ƃ��Ĉʒu�Â���ꎩ�ǂ́A���̌�����]�̋@�\�ُ�ɋ��߂��Ă���킯�ł����A���̂悤�ȗ���ɗ������@�������݂��Ȃ�����ɂ��ẮA�ǂ��l����ׂ��Ȃ̂ł��傤���B����������Q�������錴���ɂ��̏œ_������̂͂܂������Ȃ��̂ł����A�ŏ�����]�̏�Q�Ƃ��������Ɍ��߂��Ă��܂��ƁA�Ȋw�I�T���Ƃ����_�ł��A���ÓI���ʂƂ����_�ł��A�傫���������\��������͂��ł��B����܂Ő���ɔ��B���Ă����͂��̗c�����A���鎞������ �g���a�h �����悤�Ɍ����� �g��� regressive or set-back �^�h �����Ȃ�̔䗦�ő��݂��邱�Ɓi���Ƃ��AHansen et al., 2008�j�����āA����ɂ́A���m�ȐS���I�o�����Ɋ֘A���āA���邢�͂܂��ɂ��̒���ɔ��a�����悤�Ɍ����鎖�Ⴊ���݂���i���Ƃ��ABurd & Kerbeshian, 1988; Kobayashi & Murata, 1998, p. 297�G�_���A1994�N�j���Ƃ����āA���ǂ��V���̏�Q�ƌ��߂��A�������ɔ]�̋@�\�ُ�ɋA�������Ă悢�͂��͂���܂���B
�@�����a���܂߂����_�����S�ʂɂ��Č����邱�Ƃł����A�q�ϓI���ꂩ��W�ς��ꂽ�������ÂɌ������A�Ȋw�I�ɒ����ȗ���ɗ����A�����̉Ȋw�҂��猩�Ă��٘_�̂Ȃ��`�Ō�����i�߂Ȃ���Ȃ�܂���B���̂悤�ȕ��@���Ƃ�Ȃ�����A���ǖ��̐^�̉����͂��肦�Ȃ��悤�Ɏv���܂����A�ǂ��Ȃ̂ł��傤���B
�m���Q�n���̍u�����e�́A���N�Ɂw�������_��w�Ƃ��̋ߐڗ̈�x��V���P���Ɍf�ڂ���܂����B���łȂ���ӂ�Ă����ƁA�A�X�y���K�[�́A1944�N�Ɏ��ǂɊւ���ŏ��̘_�������������ƂɂȂ��Ă��܂����A���ۂɂ́A1938�N�ɔ��\�����_���̒��ŁA���Ɏ��I���_�a���̒j���̈�����Ă��邻���ł��iLyons & Fitzgerald, 2007�j�B���̘_���i�p���́AAsperger, 2008�j�̓��{�ꏴ��́A���˗z�q��̘_���i���ˁA2013�N�j�Ɍf�ڂ���Ă��܂��B
�@���Ȃ݂ɁA1965�N�ɗ��������ہA����搶�́A�A�X�y���K�[��q�c���u�搶�̎���ɓ��s���A��X���܂Ŋ��k���������ł��i����A1968�N�AV �y�[�W�j�B�܂��A�A�X�y���K�[�̖��ɂ��A�A�X�y���K�[�͓��{�뉀�ɁA���Ɂu�V�l�������A�Ԗ̗t�������Ƃ��āA���炵���`�ɂ������Ă���v��ʂɖ�����ꂽ�����ł��iFeinstern, 2010, p. 18�j�B11 ���ł�����A�T�U���J�������������̂ł��傤���B�q�X�e���[�̌����ŗL���� 19 ���I�t�����X�̐_�o�w�ҁA�W�����E�}���^���E�V�����R�[���A�킪���̖~�͂ɖ������Ă��������ł��B���̂悤�Ȉ�b���ƁA������������C�O�̒����Ȍ����҂������A���Ȃ�g�߂Ɋ�������ł��傤�B
�m���R�n�J�i�[�̘_���ƃA�X�y���K�[�̘_���́A���ԓI�ɋߐڂ��Ă͂��邪�S�����W�ɔ��\���ꂽ�Ɣ�r�I�ŋ߂܂ōl�����Ă����̂ł����A�����ے肷��؋�����o�����悤�ɂȂ�܂����B�h�C�c�ꌗ�o�g�̃J�i�[�́A�A�X�y���K�[��1938�N�ɔ��\�����A���Q�ɋL�����_����m���Ă����ɂ�������炸�A��������p���Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ƃ����^�O�i�ΐ�A2010�N���j�݂̂Ȃ炸�A�A�X�y���K�[�̊T�O�ނ����̂ł͂Ȃ����Ƃ����^�����������Ă���̂ł��iChown & Hughes, 2016�j�B����́A�W���[�i���X�g�̃X�e�B�[���E�V���o�[�}�����A�W�҂�W�����ɓO��I�ɓ������Ĕ��@�����؋��iSilberman, 2015�j�Ɋ�Â����̂ł��B����ɂ��ƁA�J�i�[�́A�A�X�y���K�[�̂��ƂŐf�f��S�����Ă����A���̐��_�Ȉ�ł���Q�I���O�E�t�����N�����A�W�����Y�E�z�v�L���Y��w�̊֘A�����ȕa�@�̏�Έ�t�Ƃ��Čق�����邽�߁A1937�N�ɃI�[�X�g���A����ĂъĂ����̂ł��B�t�����N�����܂߂����_���l�������i�`�̔��Q����~�o���邽�߂ł����B�����ɂ͏ڂ��������]�T������܂���̂ŁA�S�̂�����́A�����iNeuroTribes: The Legacy of Autism and the Future of Neurodiversity�j���Q�Ƃ��Ă��������B�Ȃ��A���̖{�ɂ́A�I�����@�[�E�T�b�N�X�搶���������Ă��܂��B
�m���S�n���^�[�́A���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B�u���ǂǂ����邤���� �]�����h ���ʂ����������k�S�����Ɠ������l��͂�s���Ăł��邪�A�i�ǂ�قǂ̔䗦���͂킩��Ȃ��ɂ��Ă��j�ꕔ�̏Ǘ�ł́A�]�̊펿�I�Ȉُ킪�傽�錴���ɂȂ��Ă���悤�Ɏv����B������ɂ���A�g�]�����h �Ƃ����T�O�͔��R�Ƃ������Ă��āA���ǂ̋N���𗝉����邤���ł���قǖ𗧂킯�ł͂Ȃ��B�����I�o�� physiological arousal �ُ̈킪�W���Ă��邩�ǂ����𖾂炩�ɂ���ɂ́A����̌������܂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�iRutter, 1968, p. 21�j
�m���T�n�Ƃ͂����A����܂Ő���ɔ��B���Ă����Ǝv����q�ǂ����A��▅�̒a�������ɁA����܂łł��Ă������Ƃ��}���ɂł��Ȃ��Ȃ����Ȃǂ̊ώ@�͏��Ȃ��炸���݂��܂��B���������o�߂����ǂ鎖��́A�܂���^�Ƃ���ތ^�isetback type, autistic regression�j�Ƃ��ƌĂ�A�\��̂悭�Ȃ����Ⴊ�������Ƃ��m���Ă���悤�ł��B������ɂ���A���̂悤�Ȕ��njo�߂�����ƁA���̎��_�ɐS���I�v���̊֗^���^����킯�ł��B�܂��A1973�N�Ƀm�[�x�������w�E��w�܂��A�R�����[�g�E���[�����c��Ƌ�����܂����A��r�s���w�҂̃j�R�E�e�B���x���w���́A�ƒ���Ƃ������ʂ��玩�ǂ������������i�e�B���o�[�Q���A1976�N�G�e�B���o�[�Q���A�e�B���o�[�Q���A1987�N�j���o���Ă��āA�m�[�x���܋L�O�u�����A�����͂��̌����Ɋւ�����̂ł����B
�@�܂��A�e�B���x���w���̒��z�Ƀq���g�����Ö@���g���āA���ǂƐf�f���ꂽ�q�ǂ����������Â��A�D���т��������Ƃ��錤���iZappella, 1990�j�����݂��܂��B�_�o�w�I�Ȉُ�̂Ȃ����ǎ���Ώۂɂ������̌����ł́A�e�Ɏq�ǂ���������Ď��������킹�悤�Ƃ�����ȂǁA���̌����Ӗ��Œ�R�̂��邱�Ƃ��A������x�ɂ��Ă��ނ���s�Ȃ킹��Ƃ�����@���g���Ă���悤�ł��iZappella, 1990, p. 18�j�B����Ǝ��ʂ������@�́A�A���E�z�b�W�X�̎���ł��g���Ă��܂��i�R�[�v�����h�A1975�N�j�B�U�b�y�b���̂��̌����ɂ��ẮA���ۂɂ͒ǎ����Č��ʂ����Ĕ��f���邵���Ȃ��͂��Ȃ̂ł����APlosONE �Ƃ����I�����C����厏�̊�ł́A���ʂɊւ���L�q���s�\���ł���Ƃ��āA���̘_���͏��O�̑ΏۂƂ���Ă��܂��B
�@���Ȃ݂ɁA�U�b�y�b���́A2009�N�T���ɁA�������_�E�_�o�Z���^�[�̎�ÂŊJ���ꂽ�u���B��Q�̗Տ����B���_��w�I���_����v�Ƃ������ۃZ�~�i�[�ŁA�u���ǃX�y�N�g������Q�Ɛf�f���ꂽ�q�ǂ������̗Տ��o�߂���ь��ʂ̑��l���v�Ƃ������ʍu�����s�Ȃ��Ă��܂��B���̒��ŁA�u���ǏǏ��P���锽�ʁAADHD �� Tourette �nj�Q�ւ̈ڍs�v�Ȃǂ̖����c���q�ǂ����������Ƃ���������Ă���̂ł��B���̏Ǐ�̈ڍs�i���邢�͌��j�������ł���A�����������ۂ́A���̏ꍇ�̎��ǏǏS�����̂��̂ł��邱�Ƃ̗L�͂ȗ��Â��ɂȂ�悤�Ɏv���܂��B
�m���U�n���������́A�쒷�ނ̌����҂��������T�O�ŁA���҂������Ƃ͈Ⴄ�S�������Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���\�͂̂��Ƃł��i���̎����I���ɂ��ẮA���Ƃ��A�q���w���Ȃ̋N���\�\��r�F�m�Ȋw����̃A�v���[�`�x�k1999�N�A���q���[���l��W�����A���E�L�[�i�����w���ʂڂ��]�\�\�u���̂Ȃ��̊�Ǝ��ȔF���v�k2006�N�A�m�g�j�u�b�N�X�l�x���Q�Ƃ̂��Ɓj�B���펙�ł��A�����͂T�������Ȃ��Ɩ��m�ɔ������Ȃ��Ƃ���Ă���悤�ł��B
�m���V�n�J�i�[�́A���������a�Ƃَ͈��̂��̂Ƃ��đ����������ǂƂ����������l�����킯�ł����A��ɕ����a�a�����ƍl�����鎖�Ⴊ�����Ȃ���m�F����Ă���悤�ł��i���Ƃ��APetty et al., 1984�j�B�h�i�E�E�B���A���Y������A���_�a������\���ɂӂ�Ă��܂��i�E�B���A���Y�A2008�N�A79-80�y�[�W�j���A����́A�o���̎����ɁA�H�ł���Ƃ��Ă����炩�̂Ȃ��肪���邽�߂Ȃ̂ł��傤���A����Ƃ��f�f����m������Ă��Ȃ����߂Ȃ̂ł��傤���B
�m���W�n�K���ے�̂��܂��܂ȃp�^�[���ł��ӂ�Ă����܂������A�������ǂ�������j�q���w���́A�S���Ö@�̒��Łu���w���D�����v�Ȃǂ̊���̉��Z���������Ƃ���A�����тȂǂ̔����������悤�ɂȂ�܂����B���̂��Ƃ���A�K���ے�Ƃ����l�������Ɋ�Â����̐S���Ö@���g���邱�Ƃ��킩�����킯�ł��B�����āA�ŏI�I�ɂ́A���ǎ��ɂ悭������A�Ɠ��̊�قȔ�����y�͂Ƃ��v����ԓx������A�����ł͂Ȃ��ɂ��Ă��A��r�I�ӂ��̐��ŁA�������܂��߂ȕ\��ʼn��ł���悤�ɂȂ����̂ł��B�������Ȃ���A��Q���̐e�ɂ悭���邱�ƂȂ̂ł����A��e���A���̌�܂��Ȃ����Â𒆒f�����Ă��܂������߁A����ȏ�̂��Ƃ͂ł��܂���ł����B
�m���X�n�ލs�Ƃ́A���T�Ő������Ă������悤�ɁA����܂łӂ��ɔ��炵�Ă����悤�Ɍ������q�ǂ����A���鎞����}���ɑލs���A����܂łł��Ă����n�C�n�C�┭�ꂪ�����Ă��܂����ۂ̂��Ƃł��B�ɒ[�ȏꍇ�́A����������Q�ƌĂ��H�ȏd�ǎ����i������ǎ��ǁj�ɕ��ނ����悤�ł��iVolkmar & Cohen, 1989�j�B���̌Q�́A�_�o�w�I�Ȉُ킪�m�F����邱�Ƃ������A�Ă���N�������Ⴊ�������߂ɁA���̂悤�Ȗ��̂ɂȂ����̂ł��傤�B
�m��10�n�����a�̊��҂́A���ǂƈ���Ď����̍s����������悤�Ƃ��邱�Ƃ��܂�����܂���B����́A���̂ӂ��̎����̊ӕʐf�f�Ɏg���邩������܂���B
�m��11�n���̔ے�̂������́A���팻�ۂ̏ꍇ�Ɠ����ŁA�ꕔ�̎��Ⴉ�炷�ׂĂ�ے肷��Ƃ����A�_���w�I�ɂ͌�������@���g���Ă��܂��B�Ƃ��낪�A���ۂɂ́A�����P���ɂ͂����܂���B���Ƃ��G�E�T�s�A�E�p���f�B�[�m�Ƃ����L���ȕ�����}�́A����ŕ��R�ƕs���s�ׂ��s�Ȃ����̂ł����A���̈���ŁA�^���̂��܂��܂ȕ��������ۂ��N�����Ă��܂����B���̂��Ƃ́A�A�i�t�B���L�V�[�̔����҂Ńm�[�x�������w�܂��������Ȑ����w�ҁA�V�������E���V�F��ɂ���ČJ��Ԃ��m�F����Ă��܂��i���Ƃ��ARichet, 1923, p. 461�j�B���̂悤�Ș_�@��M���闠�ɂ́A�ŏ����炠�肦�Ȃ��Ƃ����O��ŁA�ے肵�悤�Ƃ���ӎu�������Ă���\�����������ł��B
�m��12�n1986�N�ɏo�ł��ꂽ�e���v���E�O�����f�B������ɂ�� Emergence: Labeled Autistic �́A�A�����J�̃A�}�]���ł̃��r���[�� 84 ���A1992�N�ɏo�ł��ꂽ�h�i�E�E�B���A���Y����� Nobody Nowhere �͓����� 68 ���ł�����A2016�N�R���ɏo�ł��ꂽ����ł���ɂ�������炸�A���ꂪ 1668 ���ɂ��̂ڂ��Ă��铌�c����̂��̒����̃C���p�N�g�́A�����ɑ傫�Ȃ��̂ł����������킩��ł��傤�B
�m��13�n���{���B��Q�w��̋@�֎��ł���w���B��Q�����x�́A1996�N�Ɂu�R�~���j�P�[�V�����x���v�Ƒ肷����W���i��18���P���j�s���Ă��܂��B���̍��ɂ́A�e�b�����̒��S�ɂ����_�O���X�E�r�N�������_�����Ă���ق��A�킪���̂T���̌����҂��A���ꂼ��̕��삩��̍m��I�_������e���Ă��܂��B
�m��14�n���c�̃R�~���j�P�[�V�����@�ɂ��ẮA��ɂ���āA���Ƃ̊ԂɉȊw�I�����������ᔻ������܂��B���̖��ɂ��ẮA�ʍe�u�x���`�B�Ƃ����Z�@�ɑ�����Ƃ̔ᔻ�ɂ��āv���Q�Ƃ��Ă��������B


 Copyright 2008-2017 © by �}���q�Y | creatd on 2/27/17; last modified 11/25/19
Copyright 2008-2017 © by �}���q�Y | creatd on 2/27/17; last modified 11/25/19