 サイトマップ
サイトマップ




 神経心理学と心理的要因 1.サヴァン症候群という現象
神経心理学と心理的要因 1.サヴァン症候群という現象
連載が完結した段階では、参考文献を最後の回に移動する予定でいますが、連載中は、とりあえず読者の便宜を図って、その時点での最終回の末尾に置くことにします。また、文献を調べて行くにつれて、多少の添削が必要になると思います。したがって、現時点では、まだ決定稿にはなっていないことをお含みおきください。
活動中の脳の状態が画像によって把握できるようになったことから、その方面の研究が盛んになって久しいわけですが、現在の原因論の根底には、次々に開発される、こうした新しい技術を利用することで、いずれはすべてが物理的、化学的に説明できるはずだという、科学的根拠を欠いた楽観論があるように思います。それによってわかることももちろんあるでしょうが、真の意味での原因がそのような方法によって突き止められる保証は、実際にはないということです。
繰り返しになりますが、心因性疾患を対象にした心理療法に、私が本格的にとり組むようになってから、本年でもう 44 年になります。最初の数年は、精神科病院の中で、精神分裂病(昨今の名称は統合失調症。以下、分裂病)をもつ人たちとばかり接していました。その時に使ったのは、私の心理療法の恩師である小坂英世先生が開発した “小坂療法” と呼ばれる独創的な心理療法でした。小坂先生自身も小坂療法も、既に 40 年以上にわたってほとんど無視されていますが、小坂先生は、現実に分裂病という重度の精神疾患が心因性のものであることを、世界に先駆けて、実証的に明らかにしたのです。具体的に言えば、急性症状をもつ分裂病の患者に対して、その症状を出現させた心理的原因に関係する出来事を思い出させると、その瞬間にそれまでの症状がほとんど消えてしまうということです。
分裂病の患者は、その出来事の記憶を必ず意識から消しています。それを、本人の日常生活の中から “反応” を使って探り出すのです。その出来事が探り当てられた瞬間に、いわゆる正気に戻るため、その出来事(の裏にある心の動き)が分裂病症状の原因と考えられたわけです。小坂先生は、当時、既に精神分析にかなり批判的になっていたのですが、この手続きを、神経症を扱ったフロイトの方法と同じであると考え、フロイトに敬意を表して、これに “抑圧解除” という精神分析用語を当てました。
症状出現の原因が探り当てられさえすれば、このような簡単な手続きで患者が正気に戻るのは事実なのですが、分裂病は、それだけで治癒するほどなまやさしい疾患ではありません。最終的に治癒するとしても、その後が、筆舌に尽くしがたいほど大変になってゆくのです。とはいえ、これによって分裂病が心因性の疾患であることが確証されたのはまちがいありません。ショック療法や薬物療法など、これまで知られている通常の精神科的治療法では、1、2秒のうちに症状を消すことなどとうていできないので、小坂療法は、心理的原因が突き止められさえすれば、急性症状を消失させるための治療法としてはるかに効果的です。のみならず、原因論という点でも、はるかにその核心に迫っているのです。
“内因性 endogene” 精神病というあいまいな言葉で呼ばれていた昔から、脳の異常が原因であることが暗黙の裡に当然視されてきた、精神科領域で最も患者数が多いばかりか、最も難治性の疾患が、心理的原因によって起こっていることになると、理の当然として、これまで脳の異常が原因とされてきた他の疾患の少なくとも一部は、あるいはその原因の一端は、やはり心因性のものである可能性が浮上してきます。
小坂先生は、小坂療法を開発する過程で、先述の反応という客観的指標を発見していました。これは、心理的原因に近づくと、一瞬のうちに眠気やあくびや身体的変化が起こるという、それまで全く知られていなかった現象です。小坂先生は、この客観的指標を使って心理的原因を探り出すことを通じて、その理論を発展させていたのです。人間の心が、こうした客観的な目印を使って探究できるなどとは、それまで誰ひとりとして考えつきませんでした。反応の発見は、分裂病が心因性の疾患であることが確証されたことと並んで、精神医学の歴史の枠内にとどまるものではなく、人間にとってとてつもなく重要なことなのです。
ところで、反応という指標は、当初は分裂病に特有のものとされていたのですが、実際にはそうではありませんでした。心因性疾患全般に見られるものであることが、さらには人間であれば誰にでも起こるものであることが、次第に明らかになったのです。ここに至って、展望が大きく開けたと言えるでしょう。この発見に至るまでの経緯は、拙著『幸福否定の構造』(笠原、2004年)の第3章「反応を追いかける」で詳述されていますので、関心のある方はご覧ください。
この反応という目印を使うと、実際に、心理的要因が関与している場合には、それを突き止めることができるのです。このような客観的指標が利用できるとなると、当該の疾患に脳の異常が何らかの形で関係しているにしても、原因を探究するための順番としては、まずこの方法を使って、実際に症状の変化が起こるかどうかを、あるいは症状がどこまで改善されるかをはっきりさせるほうが現実的です。その結果、何の変化も起こらなければ、その疾患は心理的要因とは無縁のものということになるでしょう。しかしながら、もし何らかの変化が起こるようであれば、そこに心理的要因が関与している可能性が高くなるわけです。
また、心理的要因が関係している場合には、少数の例外を除いて、当人が置かれている状況によって症状が変化するという特性が見られます。私が “対比” と呼んでいる現象です。たとえば、自宅の中にいる時と外に出た時、学校や職場に行こうとする時と遊びに行こうとする時、特定の場所にいる時とそれ以外の時、特定の人物がいる時といない時、何かに熱中している時としていない時、時間の余裕がある時とない時、自分がしたいことを自分からしようとする時と他者からの要請によってする時など、さまざまな状況の対比的な違いがありますが、それによって症状が急速に(あるいは瞬時に)変化すれば、そこには心理的要因が関係しているということです。
従来の理論では、症状が出現する側に、何らかのストレスがあるはずだと考えられているわけですが、私は、そこに本人にとっての幸福が隠れていると考えるのです。いずれにしても、心理的要因がそこに潜在しているのはまちがいありません。
心理的要因が関係している場合には、可能な限りそれを明確にしたうえで、次の段階として、その疾患に脳の異常がどこまで関与しているかを検討するのです。脳の異常が関与していることがはっきり確認されたとすれば、今度は、そのことと心理的要因はどのように関係し合っているのかを探ってゆくわけです。この順番で研究を進めるほうがはるかに合理的であるし、早道でもあると思います。
とはいえ、それは現実には難しいでしょう。ここには、私の言う、科学者の抵抗が必ず入り込んでくるからです(笠原、2004年、第8章参照)。その中では、真理に対する抵抗(あえて中原中也の言葉を使えば、“芸術圏” 的抵抗)が最も強いでしょうが、主流科学者たちが自ら拠って立つ権威を、あるいは自らの権威を棄て去ることに対する抵抗(“生活圏” 的抵抗)もあるでしょう。
権威よりも真理の探究を優先することが科学者の本分であることは、今さらあらためて言うまでもないことなのですが、権威(定説という権威、評価の高い研究者という権威)を立てたいという誘惑に、さまざまな言い訳をしながら負けてしまう科学者が、現実には多いのです。その結果、科学は本来のありかたから完全にかけ離れたものになってしまうわけです。私の考えでは、真理に対する抵抗も、そうした権威に従属したいという、本能的とも言うべき抑えがたい欲求に由来する抵抗も、幸福否定の結果であることになります。
今回の一連の論考では、現在準備中の拙著のための資料として目を通した、神経科医のオリヴァー・サックス先生の著書『火星の人類学者』に登場する、自閉症とトゥレット症候群という、ふたつの疾患群を俎上に載せ、これらの疾患に心理的要因がどこまで関与しているかについて検討したいと思います。このふたつを選んだのは、いずれも経験的に心理的要因が絡んでいる可能性が高いとみているためです。
その検討のための基礎として、まず、脳と心理的能力の関係を、これまでにない角度から俯瞰した後、神童やサヴァン症候群をもつ人々が示す能力や技能をつぶさに眺めたいと思います。由来のはっきりしない、隠された能力というものを、最初に明確にしておくためです。
その中でも特に注目に値するのは、同大学の数学科を上位(first-class honors=おそらく、ほぼ上位3割以内)の成績で卒業した、総合知能指数が 126(言語性知能指数は 143)にもなる男子学生です。この学生は、社会的にもいたって正常だったそうですが、「脳室から大脳皮質の表面までが、通常なら4.5センチほどの厚みがあるはずなのに、1ミリ前後の薄い皮質があるだけ」だったのです。この所見は、この学生の頭が少し大きく見えたため、調べてみた結果なのでした。脳は存在しないも同然だったということです(Lewin, 1980, p. 1232)。
ローバーの研究(たとえば、Lorber, 1968; Lorber & Priestley, 1981)を紹介するこの短報は、同大学でやはり小児科教授を務めていたロジャー・ルーウィンが、アメリカ科学振興協会(AAAS)の機関誌でもある Science 誌(1980年12月12日号)の研究ニュース欄に発表したものです(本項の小見出しは、その報告のタイトルをそのまま借用しています)。ローバーが明らかにした、この瞠目すべき事実は、現行の科学知識とは根本的に相容れないので、真の科学者であれば真っ先に注目しなければならないところです。ましてや、ルーウィンの論文は、多くの科学者が目にするはずの名だたる科学雑誌に、ローバーの論文は小児神経科の専門誌に発表されたものなのです。
さらには、今から 10 年ほど前にも、Lancet という一流医学雑誌に同様の事例(Feuillet, Dufour & Pelletier, 2007)が、CTとMRIの画像データを付して報告されているのですが、ルーウィンの論文ともども、専門家からはほとんど関心が払われていないようです(Nahm, 2009, p. 102)。
加えて、2014年には、カナダのクイーンズ・カレッジ生物医学科のドナルド・フォースダイクが、記憶と脳の大きさの関係をテーマにした論文を、スイスの科学財団がオンラインで刊行する神経科学の専門誌に発表し、その中でローバーの研究成果を裏づけるブラジルの研究を紹介しています(Forsdyke, 2014, fig. 1)し、翌2015年には、ローバーの研究をもとにした肯定的論考(Forsdyke, 2015)を、シュプリンガー出版が刊行している理論生物学の雑誌に発表しているのです。にもかかわらず、これらの報告も、専門家の間ではほとんど注目されずに現在に至っているわけです。
後述するように、欧米の医学雑誌や科学雑誌の中には、わが国と違って、真理の探究を何よりも優先する伝統のおかげで、超常現象の研究を含めて、かなり先鋭的な論文を時おり掲載するものが、それも一流とされる雑誌の中にいくつかあるのですが、読者側の問題のために、その情報がほとんど共有されないまま終わっているということです。否定するにしても、その前に厳密に検証する必要があるはずです。ここにも、人の子としての科学者の強い抵抗を見ることができるでしょう。
ケーテには、生まれた時から重度の発達遅滞があって、言葉はひとことも発することができなかった。動物のようなうなり声を出すだけであったし、身体的にも、不随意な痙攣を起こす以上のことはなかったのである。周囲の出来事に注意を向けることは、一瞬たりともないように見えた。ある日、ハッピヒは、病院の精神科医であるヴィットウェーバー医師から、ケーテの病室に急行するよう求められた。ケーテは肺炎のため、死の床にあったのである。病室に入るや、ハッピヒは驚いた。
ハッピヒは次のように証言している。「私たちは、自分の目と耳が信じられませんでした。ひとことも発したことのない、生まれた時から心理的能力を完全に欠いていたケーテが、死の歌を口ずさんでいたのです。ケーテは、『たましいの、すみかはいずこ。安らぎぬ、安らぎぬ、天つ国に安らぎぬ』という歌を、はっきりした口調で何度も何度も歌っていたのです。30 分は歌っていました。それから、静かに息を引きとったのです。ケーテの顔は、その直前までいかにも愚かそうに見えていたのですが、それが神々しく、霊的なまでに変化したのです。立ち会っていた看護師や私もそうでしたが、主治医も眼に涙を浮かべていました。主治医は、次のように言いました。『このことを医学の言葉で説明することはできません。依頼があれば遺体の解剖もできますが、解剖学的な立場から言えば、〔ケーテは〕考えることなどできなかったはずなのです』」(Ringger, 1958, pp. 219-20; Nahm, 2009, p. 96)
この事例については、主治医のヴィットウェーバー医師も、別の報告の中で同様の証言をしているそうです(Nahm, 2009, p. 97)。
それまで言葉をひとことも発したことがなかった小児自閉症の子どもが、突然ふつうに話すようになったという報告は、私も時おり耳にしたことがありますし、本や論文で何度か読んだこともあります。こうした現象については、先ごろ亡くなった英国出身のアメリカの神経学者であるサックス先生(1933-2015年)も、「自閉症のひとたちによくあるように、何の練習も必要ない」(サックス、2001年、304ページ)と述べています。このきわめて重要な問題については、後ほど検討しますが、話し言葉は練習が必要なはずなのに、なぜこのようなことができるのでしょうか。それだけでも十分にふしぎですが、本例は、それと比べても格段にふしぎです。
発達心理学や言語学の常識からしても、神経心理学の知識からしても、意味のある言葉を発することができるどころか、発音すらふつうにできるはずはありません。自分の置かれている状況を完全に把握していることを教えてくれる、高度な意味をもつ歌詞を、ましてや節をつけて歌うことなどできるはずもないからです。なお、後ほどふれることになりますが、サックス先生の著書にも、それまで練習したことのない技能が突然に発揮されたという、サヴァン症候群の事例がたくさん出てきます。
このように、特に死を目前にすると、当人のそれまでの状態からは、能力的にも身体的にも想像すらできなかった状態にまで、突如として変容する事例があるのです。では、それはなぜなのでしょうか。また、どのようにすればそれが可能なのでしょうか。言うまでもないことですが、この疑問に答えることは、現段階ではできません。それだけに、この種の事例を探し出し、丹念に観察することが非常に重要な仕事になるのです。
対象は違うにしても、そうした作業を丹念に行なっていたのが、まさにサックス先生でした。サックス先生は、「レナードの朝」という映画や、『妻を帽子とまちがえた男』という著書(1992年、晶文社刊)などを通じて、わが国でもよく知られています。さまざまな神経学的所見に加えて、いわば病院神経学ではなく、「街頭神経学 street neurology」(同書、218ページ)の一環として、患者の自宅を訪ねたり、一緒に出かけたりして、現実の生活の中で細かく観察したことがらを、19 世紀の叙述の伝統にのっとって丹念に記述することにより、世界中の人たちの関心を呼び覚ます作品を数多く残したのです。
それは、神経心理学の創始者と目される著名なロシアの神経学者、アレクサンドル・ルリヤ(1902-1977年)[註1]の助言に忠実に従ったたまものでした(同書、25ページ)。サックス先生が出した本は、専門家ではなく一般読者に向けたものでしたが、専門家が読んでも非常に興味深く、実際に専門家の評価も高いものです。とはいえ、最新の研究成果はもとより、古典的な研究も重視していた、大変な碩学であったサックス先生も、先のローバーの研究には、まことに残念ながら、ひとこともふれていないようです。
ところで、わが国の専門家は、すべてを脳の機能で説明しようとする傾向が、皮肉なことに欧米の科学者よりも顕著なように思います。ひとつには、そのほうが科学的だと思い込んでいるためなのでしょう。それは、自分の側に権威があることを自任しているため、研究対象を自由に選ぶことができる欧米の科学者と違って、わが国の科学者たちは、その権威にひたすら追随する立場に(半ば無自覚的に)自らを置いていることの必然的な結果なのだと思います。先ごろ、そのことをあらためて教えてくれる、たいへん興味深い本の存在を知りました。『脳には妙なクセがある』という、ある専門家による著書です(池谷、2012年)。
これは、周知の現象を、すべては脳が原因のはずだという思い込みに基づいて演繹して引き出した結論です。その点では、養老孟司さんの “唯脳論” も同じです。こうした還元的、循環的手法が科学の作法に反していることは、今さら言うまでもありませんが、このような立場からすると、偏った、あるいは異常な行動はすべて、脳の “くせ” や障害に原因があることになります。しかし、そうした “科学的” 推断を無条件に容認するわけにいかないことは、先ほど紹介した実例を見れば明らかでしょう。
世界をリードするような科学理論がわが国からはひとつも出ていないこともそうですが、このような事例を厳密に扱った研究がわが国から出される可能性がほとんどないのも、やはり欧米の(傍流ではなく)主流の研究や理論の後を追うことしか考えていないためなのではないかと思います。
はっきりした科学的根拠もないまま、すべては脳の活動の結果にすぎないと断定的な発言をすることこそ、最も非科学的な態度なのですが、当人にはその自覚はないはずです。これは、発言者のみならず、その発言を是認する側も揃って自覚(つまり、病識)を消しているということですから、私の言葉では共同妄想ということになります。
とはいえ、わが国にも、次のような発言をする専門家もいることは、ここに明記しておかなければなりません。これは、自閉症者のカレンダー計算の能力について述べているものですが、脳の働き全般についても同じことが言えるはずです。
もし機能的MRI〔=fMRI。MRIにより、体内(この場合は脳)の血流を視覚化することで、どの部位の働きが活発になっているかを知る方法〕によって何らかの特定の知見が得られたとしても、それは数の操作に関与している脳の局所部位の活性を同定することがせいぜい可能となるだけで、脳が数の操作〔を〕どのようにするのかを解明する方法ではないからである。〔中略〕サヴァンの計算能力に関する脳の機能の研究は、いまだ一致したデータを提出できていない。さらに、もっと根本的な問題として、これらの機能的画像研究の結果からは、どのように計算能力が実行されているのかも不明である點が残る(石坂、2014年、187-189ページ)
そのことは、多少の留保条件を付しているものの、アメリカの比較心理学者であるアイリーン・ペパーバーグの研究(たとえば、Pepperberg、2003年;ペパーバーグ、2010年)を引用し、ヨウム(オウムの一種)のアレックスは「三〇〇〇語の語彙を持ち、ユーモアのセンスもあるといいます」として、数グラムの脳しかないにもかかわらず、「驚くほど優れた声と音楽と言語の能力を備えているようです」と、あるインタビューの中で率直に語っている(サックス、2012年、153ページ)ことからもわかります。
サックス先生の著書には、神童が頻繁に登場します。いまさら説明するまでもないでしょうが、神童とは、人並み外れたいわゆる天賦の才能を幼少期から発揮する子どもたちのことです。わが国で多くの人が知っているのは、オーストラリアの作曲家、アマデウス・モーツァルトや、“放浪” の貼り絵作家、山下清(1922-1971年)でしょう。
 右の表は、「執筆予定の本に関連して」で紹介しておいた、心霊研究協会の創設者のひとりである、フレデリック・マイヤーズの主著 Human Personality and Its Survival After Bodily Death から再掲したものです。100 年以上も昔の、計算を得意とする神童たちの資料ですが、これは今でも参考になります。それは、計算という領域に限られるとはいえ、複数の神童の個人名をこのように一覧表示し、能力の発現年齢や継続年数を示した資料が、他にはあまり存在しないためです。
右の表は、「執筆予定の本に関連して」で紹介しておいた、心霊研究協会の創設者のひとりである、フレデリック・マイヤーズの主著 Human Personality and Its Survival After Bodily Death から再掲したものです。100 年以上も昔の、計算を得意とする神童たちの資料ですが、これは今でも参考になります。それは、計算という領域に限られるとはいえ、複数の神童の個人名をこのように一覧表示し、能力の発現年齢や継続年数を示した資料が、他にはあまり存在しないためです。
ただし、その4年後の1907年に、コーネル大学の哲学専攻の大学院生、フランク・ミッチェルが発表した論文には、それぞれの計算神童がかなり詳しく紹介され、そのうちのやはり 13 名が文末の一覧表にまとめられています〔Mitchell, 1907, pp. 141-43〕。ミッチェルの研究が、マイヤーズの研究とは独立に行なわれたものかどうかはっきりしませんが、その表では、マイヤーズの表に列挙されているうちの4名が「小神童」として外され、別の4名が加えられています。なお、この論文も埋もれたままのようです。
マイヤーズの表には、13 名の計算神童が列挙されていますが、このデータから、いくつかの興味深いことがわかります。まず、能力が最初に表面化するのは3歳から 10 歳くらいまでの間であり、「二十歳過ぎればただの人」と昔から言い慣わされてきた通り、数年で消失してしまう事例が半数以上を占めていることです。ただし、後述するダロルド・トレッファート先生による、「どのような才能をもつにせよ、サヴァンたちは通常、生涯を通じてその才能を保ちつづける」(トレッファート、2002年、10ページ)という所見のほうが、多数例を対象にした観察であるだけに適切なのかもしれません。
したがって、ここでは、能力が途中で消失してしまう事例も少なからず存在するという点に注目しておけばよいということでしょう。また、知的水準が「傑出している」のは、フランスとドイツの著名な数学者であり物理学者であった、アンペールとガウスの2名にすぎず[註2]、「よい」と「平均的」は全体の半数ほどに当たる6名でした。
それに対して、「低い」と「きわめて悪い」は5名おり、この群がサヴァン症候群(かつてのイディオ・サヴァン)に分類されることになるわけです。このことからわかるように、サヴァン症候群は、神童全体の一部(この資料では半数弱)にすぎないということです。サックス先生も、マイヤーズのこの著書を読んでいて、表中のダーゼに関する記述を自著『妻を帽子とまちがえた男』に引用しています(サックス、1992年、345ページ)。
わが国で知られている最近のサヴァン症候群としては、自閉症の切り絵画家、上田豊治さん(上田、1999年)や、やはり自閉症の画家で鉄道風景ばかりを記憶に基づいて精密に描いている、福島尚さん(福島、2016年)、自閉症であり盲目でもあるピアニスト、磯村靖幸さんらがいます。磯村さんは、1万にものぼる楽曲を正確に記憶していてそれを演奏することができるだけでなく、初めての曲でも、一度聞くだけで完璧に再現できるそうです。のみならず、同時に演奏された3曲ものピアノ曲を、一度だけでやはりきちんと聞き分け、それらを別々に演奏するという、とてつもない能力ももっているようなのです[註3]。そこには、驚異的な感覚や記憶力が関係しています。
山下清さんは、放浪生活で有名だったわけですが、その間の出来事を、当時入所していた八幡学園に戻ってから、克明に日記に記録したそうで(池内、1996年、8ページ)、最も長い時には2年半にも及んだそうです。これも、常人ではとうてい不可能なことです。ただし、常人であっても多少なら可能な場合もあります。それは、死のまぎわを含め、生命に危険が及ぶなどの危機状況に置かれた時です。よく知られている事例としては、中国のミニヤコンカという高山で遭難し、生還した登山家の松田宏也さんや、三浦・グアム間で行なわれた外洋ヨットレースで遭難した「たか号」に乗り組んでいた唯一の生存者、佐野三治さんです。
松田さんは、その記憶について、自著の中で「幸か不幸か、僕の記憶は鮮明である。鮮明でありすぎる。すべてを、僕は思い出すことができる」(松田、1983年、275ページ)と書いていますし、佐野さんは、1991年暮れに遭難してから 27 日間も漂流を続けた間の出来事を、驚異的な精密さで記憶していて、それを「漂流二十七日の鎮魂歌」という雑誌の連載記事にまとめたのです(後に、『たった一人の生還――「たか号」漂流二十七日間の闘い』として書籍化)。
とはいえ、やはり常人では、サヴァンの能力の一端がかいま見えるとまでは言えるのかもしれませんが、記憶量という点でも期間という点でも、サヴァンに遠く及ばないのはまちがいありません。南方熊楠さんも、幼時には神童と呼ばれていたようで、近所の家で目を通した本を、自宅に帰ってからその一字一句を、記憶に基づいて再現したそうですし、後年、ロンドンの大英博物館図書館でフランス語からアラビア語に至るまで十数か国語を、その一端にしても独力で身に着け、500 巻にも及ぶ古今東西の重要書を読破したそうですが、その熊楠さんにしても、15-20 ヵ国語で読み、書き、話すことができるというクリストファーさん(スミス、ツィンプリ、1999年)や、7600 冊以上に及ぶ大冊の書籍を丸暗記しているというキム・ビークさん(トレッファート、ウォレス、2002年、6ページ)にはとうてい及びません。
サヴァン症候群の研究者として名高い、アメリカの児童精神科医、ダロルド・トレッファート先生の著書『なぜかれらは天才的能力を示すのか――サヴァン症候群の驚異』(1990年、草思社刊)の第2章に、重度の知的障害がある盲目の黒人奴隷で、やはり聞くだけでピアノを完璧に演奏したという、19世紀に活躍したトム・ビートン(1849-1908年)の事例が紹介されています。ビートンさんは、4歳の時から、誰にも教わることなく、耳にしたピアノ曲を完璧に再現できるようになっていたのです。ただし、ビートンさんが記憶していたのは7千曲ほど(ほとんどが自作の曲)だったそうなので、磯村さんは、記憶していて演奏できる曲の数という点で、ビートンさんをはるかにしのいでいることになります。
磯村さんは、以上のような点から考えて、世界的に見て非常に珍しい存在であるのはまちがいないでしょう。にもかかわらず、磯村さんを対象にして研究しようとする専門家が、少なくとも現時点でいないらしい[註4]のは、きわめて残念なことです。
トレッファート先生は、2015年に、サヴァンの研究を重視しているある医学雑誌に The savant syndrome registry: A preliminary report という報告(Treffert & Rebedew, 2015)を載せています。これは、サヴァン症候群をもつ世界中の人々の情報を登録しておこうとする試みの中間報告です。その中に、先天的なサヴァンと思われる 281 名中の 204名 について、国別に集計した表が掲載されています。その報告が発表された2015年8月の段階では、圧倒的多数(7割ほど)がアメリカのサヴァンで、わが国のサヴァンとしてはふたり(おそらく、画家の山下清、山本良比古、山村昭一郎、音楽家の大江光のうちのふたり)が登録されているのみです。
1936年に、早稲田大学心理学教室の戸川行男先生(後に同大学心理学教授。1903-1992年)が発掘、研究した先の山下清さん[註5](Lindsley, 1965)や、山本さん(Morishima, 1974)、山村さん(Morishima & Brown, 1977)、大江健三郎さんの長男、光さん(Lindsley, 1998)の4名については英文による報告が出ているおかげで、外国でも知られているのですが、この4名以外に関しては英文の報告がおそらくほとんどないため、外国ではその存在が正式に知られていないということです。特に科学的な方面では、よくも悪くも、英語で発表されないと、科学者の中で圧倒的多数を占め、現実に覇権を有する英語圏の科学者は、ほとんどが無視してしまうのです。未来を見据えたトレッファート先生の試みは、特にアメリカ以外の国から報告が続々と届くようになれば、大きな意味をもってくるでしょう。
この少年は、後に高度のピアノの演奏能力を発揮するようになるのですが、それは、有能な教師からピアノの演奏を2年ほど、非常に拒絶的な態度のまま教わり、さらにしばらくしてから後のことのようです(Minogue, 1923, p. 350)。したがって、この能力の発揮が、果たして髄膜炎に罹ったこと自体の影響によるものかどうかはわからないと見るべきでしょう。1980年にも、ある心理学者による同種の報告があるそうですが、いずれにせよ、1990年代以前の報告は少数にすぎなかったようです。
1996年に、カリフォルニア大学の神経学者、ブルース・ミラーらは、前頭側頭型痴呆(FTD)に陥った患者の中からサヴァン的な能力を示すようになった者を3名探し出しました(Miller et al., 1996)(後に探し出した事例を総計すると 12 名)。この報告は、わずか2ページの短報なのですが、Lancet という一流医学雑誌に発表されたこともあり、この研究を嚆矢として、この方面の研究がさかんに行なわれるようになりました。
そうした論文は、Google で検索するだけでたくさん見つかりますが、特に神経学や老年医学の専門誌に発表される傾向が強いようです。同様の現象は、アルツハイマー病(Chakravarty, 2011)や痴呆(最近の用語では認知症)に罹患した患者(たとえば、Gretton & ffytche, 2013; Mell, Howard & Miller, 2003; Miller et al., 2000)にも見られることがあるそうです。また、それまで芸術活動をしていた人が、やはり脳に障害を負うなどした後に、作風が変わるという現象もあります(たとえば、Annoni et al., 2005)。
最近では、わが国で行なわれた研究もあります。これは、中央大学の神経心理学者、緑川晶と昭和大学の神経内科医、河村満の共同研究で、40 代のトラック運転手が、荷台から転落して左前頭側頭葉に損傷を負い、入院治療の後、デイケアに通っている中で、それまでなかった絵画能力が開花したという事例です(Midorikawa & Kawamura, 2015)。
次に、いくつかの劇的な事例を、トレッファート先生の論文(トレッファート、2015年)から紹介します。たとえば、オーランド・セレルという 40 代の男性は、10 歳の時に野球のボールが頭の左側に当たって気を失ったのですが、それからは、それ以後に起こったことを詳しく記憶できるようになったそうです。たとえば、1983年2月7日にあった出来事について質問されれば、「月曜日。その日は雨が降ってました。ドミノでピザを買いました。ペパローニです」、1991年12月13日のことを聞かれれば、「金曜日。その日は仕事に行きませんでした」と即座に答えるのです。
セレルさんは、一塁ベースに向かって走っている時に、遊び仲間が投げたボールを左側頭部に受けたわけですが、気を失って倒れてから意識を回復して立ち上がると、頭がずきずきと痛んでいたそうです。ところが、その頭痛が治まると、自分が根本的に変化していることに徐々に気づくようになります。突然に複雑な数学の方程式がわかるようになり、記憶力も格段に向上したのです。科学者たちが何度か調べたのですが、事故後の日にちであれば、どの日であっても正確に記憶しており、まちがえることはなかったそうです。
この現象は、(1)小さい頃に、(2)脳の障害を受けたという、ふたつの条件を満たす形で起こるとは限りません。年配になってからでも、また、特に障害が残らなくても、同様の現象が起こることがあるからです。たとえば、ニューヨーク在住のアンソニー・シコリアという整形外科医の事例です。シコリアさんは、1994年、42 歳の時に雷に打たれました。街の電話ボックスで母親と通話している時に、集中豪雨に伴う雷が、その電話ボックスを直撃したのです。電話中だったため、受話器を通じて脳に電撃を受けました。幸い、外で順番待ちしていたのがたまたま看護師だったため、その救命処置のおかげで一命をとりとめました。2、3週間後には回復し、検査の結果、脳に異常はないことがわかったそうです。
それからまもなく、シコリアさんは、それまで楽器にも音楽にも関心がなかったのに、クラシックのピアノ曲を無性に聞きたくなりました。そこで、ポピュラー音楽の楽譜を買って自己流に練習を始めたのですが、進歩が遅すぎることに気づき、自分の頭の中で鳴り響いている音楽に耳を傾けることにしたのです。
すると、それが自分のオリジナルであることがわかったため、それらを走り書きしました。その結果、数十の自作曲ができたのです。事故から3ヵ月も経たないうちに、ほとんどの時間をピアノの演奏と作曲に充てるようになりました。そして、事故の前にはクラシック音楽には全く関心がなかったにもかかわらず、ソロ・リサイタルを開き、ピアニスト兼作曲家としてデビューを果たしたのです。
英国リヴァプール在住のトミー・マクヒューという建設労働者は、2001年、51 歳の時に脳の両半球に脳卒中の発作を起こしました。そのため、妻を見ても、鏡で自分の姿を見てもわからず、歩くことも食事をすることもできなくなりました。そのまま在宅で過ごしているうちに、絵を描きたいという強烈な衝動が突然に湧き上がってきたのです。労働者階級の家に 12 人兄弟のひとりとして生まれ、ヘロインを吸って刑務所に入ったこともあるマクヒューさんは、それまでは芸術的なものに対する関心など全くなかったのでした。
そのマクヒューさんが、家じゅうの壁や天井やドアを明るい鮮やかな図柄の絵で埋め尽くしたのです。マクヒューさんによれば、風船が破裂したような感じになって、「世界の美しさが見えるようになったんです。自分が誰なのかわかりました。それまでの自分はどこかへ行っちまいました。今までの自分は誰だったのか全然わかりません」と語ったそうです。とはいえ、別の人格に入れ替わったわけではなく、いわゆる目が開かれたということなのでしょう。
サヴァンというレベルではないのかもしれませんが、フロイトの愛弟子であり、アメリカで最初の精神分析医でもあったアブラハム・ブリルも、それ以前に報告された2例を紹介しています。そのうちの1例は、就学後もふつうの成長を遂げ、知的水準も高かったにもかかわらず、その後に罹った腸チフスから意識不明の状態に陥り、回復後にも以前の知的水準には戻らなかったのですが、その後2年以上が経過した 13 歳の時に、“電光石火” の計算が突然できるようになった、ザビーネという女性の事例(Brill, 1940, pp. 716-717)です。
しかしながら、それらよりもはるかに目覚ましく見えるのは、サックス先生が『火星の人類学者』の中で詳しく紹介しているフランコ・マニャーニの事例(サックス、2001年、「夢の風景」)や、自著が邦訳されているジェイソン・パジェットの事例(パジェット、2014年)です。いずれも、病気や頭部への衝撃によって、潜在的な能力(マニャーニさんの場合は、離れて久しい故郷の風景の精密な記憶とその精密な描画、パジェットさんの場合は、数学的な能力)が後天的に発揮されるようになったのでした。
それに対して、ユネスコ記憶遺産に登録された、わが国の山本作兵衛さん(1892-1984年)が、60 代半ばになってから描き始めた炭鉱の生活をテーマにした大量の絵画(たとえば、山本、2011年)があります。これらは、脳の障害とは無関係に、数十年前の絵画的記憶が鮮明に保たれ、後に発揮された実例と言えるでしょう。
後天性のサヴァンたちが作り出す作品群を見ると、こうしたとてつもない能力は、実は人間全般に隠されているという可能性が浮かび上がります。そうした観点から、脳障害のない正常人を対象にして、脳に刺激を与えることにより潜在的な能力を発揮させようとする試みも登場しています。
スティーヴンソン先生は、それまで視覚や聴覚や嗅覚などの感覚器官に多少の欠陥があり、美意識というものがほとんどなかったそうですが、メスカリンを使用したところ、視力は改善されなかったものの、世界の見えかたが劇的に変わり、特に色彩に敏感になったそうです。同時に、幼少期の体験もはっきりと蘇りました(シュローダー、2002年、151-152ページ)。
それに対してLSDでは、そのような変化はありませんでしたが、あらゆる存在や、あらゆるものとの一体感を味わったのだそうです。2回目の時には、完全に平穏な状態が3日間も続いたそうです(Stevenson, 1990, p. 10)[註7]。サヴァン的な能力というほどではありませんが、こうした薬物によっても、それまで抑えられていた能力や人格的特性が一時的に発揮されたり、場合によっては、その状態がその後も持続するということです。
最近では、このような薬物ではなく、他の方法で潜在的能力を引き出そうとする試みが行なわれるようになっています。たとえば、低周波の磁気パルスを左前頭側頭葉に送る、反復経頭蓋磁気刺激法(rTMS)という方法を通じて、健常人にこの種の脳障害を一時的に引き起こそうとする実験です。この研究は、オーストラリアの神経学者たち(Snyder et al., 2003)が行なったものです。先天性のサヴァンでも後天性のサヴァンでも、多くは左前頭側頭葉に障害があることが判明している[註8]ため、その部位をターゲットにしたということです。
サヴァンたちは、特に後天性のサヴァンたちは、驚くべき能力が誰にでも潜在している可能性を教えてくれているとしても、通常は、脳に障害を負った稀な事例でしか発現されません。この神経学者たちは、11 名の右利きの男子大学生を被験者として、サヴァン的な能力に関係していると思しきその部位を刺激する実験を行なったのです。その結果、そのうちの4名で、この磁気パルスにより絵の描きかたが、巧みな方向へと変化することが判明しました。これらの被験者の中には、文章中の誤字を発見する能力が高まった者も何人かいました。それは、注意力が高まったためなのか、それとも、ものの見えかた自体が変わったためなのかわかりませんが、いずれにせよ、何らかの変化が起こったということなのでしょう。
このように、薬物を使うことによっても、脳の特定の部位に刺激を与えることによっても、それまで抑えられていたとしか考えられない能力や、場合によっては人格的特性が、少なくとも一時的に発揮されるのはまちがいないようです。とはいえ、サヴァンが発揮する能力と比べると、天と地ほどの差があることも事実です。したがって、これらの方法で潜在的な能力や人格特性が浮上するとしても、それとサヴァンの示す能力がつながっているかどうかはわからないということです。
創造性という角度から眺めた場合、サヴァンが示す能力は、トレッファート先生によると、「使いつづけることによって能力は維持される。ときには進歩が見られる場合もある」(トレッファート、ウォレス、2002年、10ページ)そうですが、サックス先生によれば、いちおうスティーヴン・ウィルトシアという画家[註9]に限っての発言ではありますが、それには否定的なようです。サックス先生は、創造性という言葉を定義したうえで、次のように述べています。
創造性とは創りだすこと、既存のものの見方を打ち破り、想像の領域で自由に羽ばたき、心のなかで完全な世界を何度も創りかえ、しかもそれをつねに批判的な内なる目で監視することをさす。創造性は内面生活にかかわるものだ。〔中略〕この意味での創造性はたぶんスティーヴンには不可能だろう。
スティーヴンの絵は決して発展しないだろうし、深い感情や理論、あるいは世界観を表現する傑作に数えあげられることもないだろう。そして、彼もまた決して発達せず、人間として、男として十全の存在となって偉大さや惨めさを味わうこともないだろう。(サックス、2001年、329、331ページ)
マイヤーズ先生が神童としてとりあげたアンペールとガウスのような高知能の人たちは別として、また、後天的にサヴァンになった人たちの一部ももしかしたらそうではないのかもしれませんが、一般のサヴァンの場合、最初からほぼ完全なものが出てくる反面、それから大きな進歩を遂げるようなことはあまりなさそうです[註10]。これは、脳の障害などの物理的要因が関係しているためなのか、それとも幸福否定に伴う進歩の否定のようなものが関係している結果なのかはわかりませんが、非常に興味深い特性だと思います。
では、サヴァンが示す能力や技能については、どのような側面が重要なのでしょうか。それは、大きく分けてふたつあります。ひとつは、練習することなく突然に発現することであり、もうひとつは、その能力や技能の由来がはっきりしないことです。以下、その順番に簡単に検討します。
その事故の4日後、長い眠りから覚めたアマートさんは、その時の友人のひとりである音楽家の自宅を訪ねました。仮設の音楽スタジオで話をしていると、安物のキーボードが目に留まりました。そして、思わずその前に座ったのだそうです。それまではピアノを弾いたこともなければ、ピアノに関心をもったこともありませんでした。ところが、自分の指が、あたかも本能的に鍵盤を探し、自分でも驚いたことに、鍵盤の上を軽やかに行き来しながら演奏を始めたのです。それは、音楽理論をきちんと踏まえたうえで、長年ピアノを弾いてきたかのような出来ばえだったそうです。アマートさんが見上げると、その友人は、感激のあまりでしょうが、目に涙を浮かべていたということです。
その後、アマートさんは、自作の曲を、熟達したピアニストのごとくに演奏するようになりました。作曲はどのようにするのかと言えば、頭の中を黒と白のブロックが切れ目なく流れてゆくので、それを音符に置き換えるのだそうです。そのようにして作りあげた作品を収録したアルバムを発表し、現在は、作曲や演奏やレコーディングを仕事にしているということです(トレッファート、2015年、108ページ; Treffert, 2010, pp. 210-11)[註11]。
自閉症の場合もそうですが、サヴァンには女性が圧倒的に少ないという事実があります。“イディオ・サヴァン” という名称を考え出した、ダウン症の発見者でもある英国のジョン・ダウン先生(1828-1896年)は、1887年に出版した自著の中で、それまで出会ったイディオ・サヴァンは全員が男性だったと述べているほどです(Down, 1887, p. 103)。
エレンという1957年生まれの女性は、そうした少数派のひとりで、幅広い楽曲を、ピアノやギターやキーボードで正確に演奏する、やはり盲目のミュージシャンです。エレンさんが全盲であることは、生後まもなくわかったのですが、家族は、エレンさんが生後6ヵ月の時点で、歌を正確に歌う能力があることに気づきました。サークルベッドに掛けられたおもちゃが奏でるブラームスの子守歌を、エレンさんが歌っていたからです。エレンさんは、4歳になってからようやく歩き始めたそうですが、その頃になると、小さな電子オルガンでいくつかの曲を弾いて母親を驚かせました。エレンさんが7歳の時、両親が、ある教師に勧められてエレンにピアノを買い与えたのですが、エレンさんの音楽の才能が本当に開花したのは、その時からです。
4歳半の時に受けた知能検査では、エレンさんのIQは 30-50 の間だったそうです。そのため両親は、エレンさんに学校教育を受けさせることにして、カリフォルニアのサンジュアン統合学校に入学させました。そこは、子どもの学力を伸ばすには良質な親子関係を築くことが大切だという理念のもとで、そのための基盤を築き上げることを目的にして運営されている教育施設でした。この学校に入学すると、エレンさんは一連の特殊教育プログラムで好成績をあげます。また、1983年には言語療法を受けるようになり、言葉がかなり発達したそうですが、ナディアの事例(サックス、1992年、355ページ)と違って、それによって音楽の才能に悪影響が及ぶことはありませんでした。
エレンさんの驚異的な能力は、何も音楽には限られません。サヴァン症候群をもつ人たちにはよくあることのようなのですが、エレンさんも、時計が見えないにもかかわらず、時間の流れが正確にわかるという能力をもっているのです。今が何時何分かを正確に言い当てることができるということです。それは、エレンさんが8歳の時に始まりました。母親は、エレンさんに電話恐怖症を克服させようとして、現時刻を1秒単位で読み上げる「電話婦人」の声を、エレンさんに電話で 10 分間だけ聞かせてみたのです。それから自室に戻った後、エレンさんは、その読み上げの声を正確にまねていたそうです。
この時に、「どうやらエレンは自分の内部時計をセットしてしまったらし」く(トレッファート、2002年、10ページ)、その後からこの能力が現われるようになり、それが現在でも続いているのだそうです。母親がエレンさんに聞かせた 10 分の間には、59分 59 秒から次の時間の0分0秒を読み上げる箇所はなかったそうです。したがって、この事例でふしぎなのは、エレンさんが、1時 59 分 59 秒の次に「2時」と言ったことです。エレンさんは、時計というものを見たこともなければ、時間の流れについても、時計の動きかたについても説明されたことは一度もなかったにもかかわらず、そのような離れ業ができたのです[註12]。
エレンさんに関するふしぎは、もうひとつあります。エレンさんは、4歳の時に歩き始めると、すぐれた空間感覚を発揮するようになりました。大きな物体や壁や塀があることを、6フィート(1.8メートル)以上離れたところからなぜかわかっていて、その前に行ってさわってみたいと言い張るようになったのです。父親は、その頃からエレンさんが、初めて入った深い森の中でも、樹木にぶつからずに歩けることに気づいていました。エレンさんは、そのような場所でもまちがわずに歩けるようになった時には、自分なりのレーダーのように、鳥の鳴き声に似た小さな声を出し続けていたそうです(Treffert, n.d., Ellen: With a song in her heart;トレッファート、2002年、8ページも参照)。
サヴァン的な能力についてはもちろんですが、アマートさんが全く練習したこともない楽器を、事故後からいきなり、しかもかなり巧みに演奏できるようになったことも、エレンさんが現在の時刻を正確に言い当てられ、初めての場所でも物にぶつからずに歩けることも、現在の科学知識をどのように積み重ねたところで説明することはできません。では、これらの能力は、いったいどこから来たものなのでしょうか。
その検討を始める前に、はっきりさせておかなければならないことがあります。一見すると、後天性のサヴァンのほうが先天的なサヴァンよりもふしぎに見えるかもしれませんが、決してそうではないということです。先天的と言っても、マイヤーズの表で見てきたように、能力や技能が発現するのは、生後直後ではなく、幼少期かしばらく経ってからです。そうすると、後天性のサヴァンは、それがもっと後になっただけなので、それまでの能力との落差が際だつという側面はあるにしても、潜在していたものが表出するという点では全く同じことになります。したがって、このふたつを別に扱う必要はあまりなさそうです。
それに対して、これらを超常的に説明しようとする研究者もいます。そのひとりは、アメリカのキース・チャンドラーという心的実在論者です。チャンドラーさんは、サヴァン症候群が示す能力をふたつに分けて説明しています。ひとつは、A型と呼ばれるもので、読んだり聞いたりしたことを逐語的に記憶するとか、一瞬のうちに計算するとかの、現実にはきわめて難しいとしても、常人でもそれなりの訓練を重ねればできる可能性がありそうな、記憶力や処理速度が関係しているように見えるものです。もうひとつは、B型と呼ばれるもので、楽器を演奏したり、絵を描いたり、彫刻を制作したり、機械的な工作をしたりなどの技能で、常人には、長期にわたる教育や実践が必要なものです。
このふたつの区別は、ある意味で重要かもしれません。いずれも現行の科学知識体系では説明できないとしても、前者は、超常的な情報伝達現象として説明できる可能性があるのに対して、後者についてはそれは不可能だからです。この区別は、超常現象研究では、特に死後存続研究では、昔から大きな問題になってきたことでもあります。つまり、認識的な記憶や情報の場合には、ESPという概念で、あるいはそれを最大限に拡張した超ESPという概念で説明できそうに見えるのに対して、技能的な記憶の場合には、そのようなものでは明らかに説明できないからです。そのため、前世を記憶すると思しき子どもたちに、生後に習い覚えたのではない技能が見られる場合には、それがESPを通じて伝達されたのではなく、前世で身に着けた技能がそのままもち越されたと考えるわけです(スティーヴンソン、1990年、282ページ)。
少々話がそれますが、重要なことなのであらためてふれておきます。わが国の科学者は、このような話を聞くと、それだけでうさんくさいと感じてしまうようですが、英米では、このような研究が、Lancet のような有力な医学雑誌や科学雑誌に、時おりではありますが、掲載されるのです(スティーヴンソン先生の生まれ変わり型事例の研究が Lancet に掲載された経緯については、この記事に書かれています)。
また、今なお刊行が続けられている定期刊行物としては世界で最も古い、一流の精神医学雑誌でもある Journal of Nervous and Mental Disease は、数多くの超常現象関係の論文を掲載するほかに、1977年には、Ian Stevenson on Reincarnation と題したスティーヴンソン先生による生まれ変わり研究の特集号(1977年、165巻3号)まで発行しています(その特集号が発行された理由については、拙編書『サイの戦場――超心理学全史』〔1987年、平凡社刊〕、11-12 ページに編集長〔ユージン・ブローディ、メリーランド大学精神科教授〕自身の巻頭言を引用しておきました)。
話を戻すと、サヴァンたちは、例外はあるにしても、このように2種類の能力を発揮していることになるのでしょう。おおまかにいえば、前者は、認識的な記憶力や検索その他の能力が発揮されるということであるのに対して、後者は、長い間の訓練を要する技術が、何の訓練もないまま発揮されるということです。とはいえ、サックス先生が観察した一卵性双生児のサヴァンのように、マッチ箱が落ちて床に散らばった直後に、ふたりが「百十一」と同時に叫び、続いて「三十七」という素数に分解して交互に3回繰り返したという事例や、このふたりが素数をやりとりする遊びの中で、最後には 20 桁の素数を数分のうちに割り出すにまでなったという事例(サックス、1992年、337-338、341-344ページ)は、どちらにも入らない現象でしょう。いずれにせよ、現行の科学知識をいかに駆使したとしても、その由来については見当すらつきません。
先のチャンドラーさんは、そうしたサヴァンの能力や技能を説明するために、宇宙場や大脳場という仮説的概念をもち出します。記憶は、ニューロンやニューロンのネットワークに蓄えれらるのではなく、脳の大脳場レベルにあると考えるのですが、サヴァンたちは、そこに自由にアクセスすることで、その記憶を引き出しているということのようです。では、もう一方の、記憶や情報として伝達されないはずのB型の技能についてはどう考えるのかというと、次のようになるのです。
(少なくとも)B型のサヴァン状態は、まさに認知的形成原理やユング心理学の元型、思考様式のような公的な記憶に基盤を置いている。サヴァンが教えられることなく発揮する能力は、ある時に「勤勉な方法」で他者が構築した行動的記憶を求めて普遍的な大脳場レベルを走査する能力を、それぞれの脳がもっているためである。(Chandler, 2004, p. 26)
残念ながら、これでは、技能が伝達される説明にはなりそうにありません。他者が訓練した結果として身に着けた技能が、どこかに記憶として保存されていて、それにアクセスできれば、それに沿って体が自由に動くようになるという主張のようですが、そのことを裏づける証拠は、まだ存在しないからです。チャンドラーさんは、超常現象に関する著書も何冊か出版しているということですが、死後存続研究の中で行なわれてきた議論や難題については知らなかったか、知っていても重視していなかったようです。
いずれにせよ、ここであらためて明確になるのは、訓練なく言葉が話せたり、楽器が演奏できたりするということは、超常的な要因をもち出しても容易には説明できない、依然としてきわめて大きな謎だということです。では、前世で培った行動的記憶が表面化したとして説明できるかというと、これまで知られている中(たとえば、スティーヴンソン、1995年;Stevenson, 1977, p. 314)には、言葉がそこまで自由に駆使できたり、そこまで楽器が巧みに演奏できたりした事例はほとんど存在しないようなのです。稀な例外のひとつは、ビシェン・チャンド・カプールというインドの少年です。この少年は、習ったことがないどころか見たこともなかったのに、インドの伝統的な打楽器であるタブラを巧みに叩くことができたそうだからです(Stevenson, 1972; Stevenson, 1990, p. 199)。
では、サヴァンが示すB型の能力や技能が、生まれ変わりという現象で説明できるかといえば、そうではありません。インドのマハーラーシュトラ州ナーグプル在住のマラータ民族であるウッタラ・フッダルという女性の事例が、その例証になります。フッダルさんは、32 歳の時から自発的に人格変化を起こすようになり、その中でシャラーダという、本人も家族も知らないベンガル語を話す女性が出現するのですが、シャラーダは、19 世紀初頭のベンガルの農村の状況を正確に語ったうえに、「扇風機や電気のスイッチなど、現代の日常生活で用いられるものについては全く知らなかった」のだそうです。また、現代ベンガル語には、英語からの借用語が 20 パーセントほど含まれているのに対して、シャラーダの言葉には、英語の単語がひとつも混入していませんでした(パスリチャ、1994年、295-296ページ)。
このように、前世の記憶の場合には、その時代の記憶が出てくるだけであって、それ以上のものではないのです。また、サヴァンは前世の記憶を語るわけではなく、いわば今生の記憶をきわめて詳細に再現することに特徴があるのです。
船医を経て海軍軍医となっていたディキンズさんは、25 歳になる1863 年(文久3年)に長崎に上陸し、64 年 10 月に、横浜の海軍傷病兵舎の軍医に任命され、その責任者になりました。1年後に海軍の職を辞して、横浜で医師の仕事をしていたのですが、なぜか医業そのものも捨てる覚悟を決めて、1866 年にいったん帰国します。そして、その年に、『百人一首』の英語訳をロンドンで出版するのです。これは、ディキンズさんが初めて日本語に接してからわずか3年後のことでした。
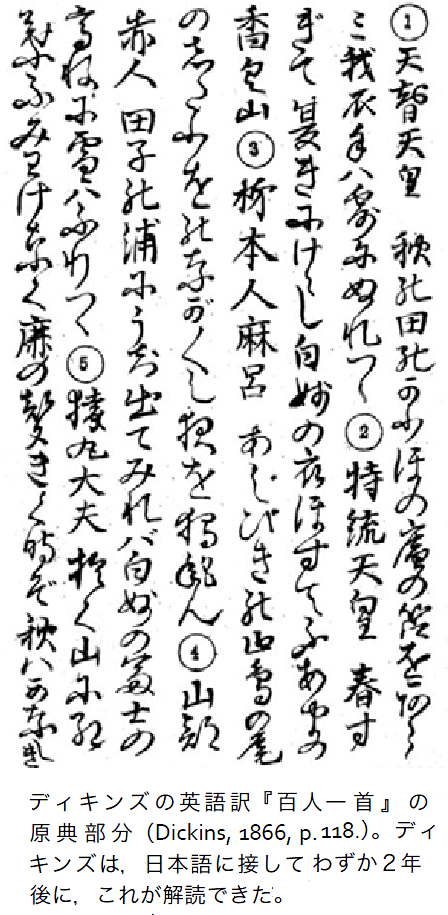 それと相前後して法学院に入学し、1870 年に法廷弁護士の資格を取得して、71 年に新妻を伴って再来日を果たします。その後、法廷弁護士となって横浜の山手に居を定め、弁護士の仕事を続けながら、4年後の 75 年に、『仮名手本忠臣蔵』の英語訳を横浜で出版するのです。また 80 年には、葛飾北斎の冨嶽百景に関する著書(Dickins, 1880b)も上梓しています。これは、北斎に関する世界で最初の学術研究書となりました(Kornicki, 2004, p. 29)。
それと相前後して法学院に入学し、1870 年に法廷弁護士の資格を取得して、71 年に新妻を伴って再来日を果たします。その後、法廷弁護士となって横浜の山手に居を定め、弁護士の仕事を続けながら、4年後の 75 年に、『仮名手本忠臣蔵』の英語訳を横浜で出版するのです。また 80 年には、葛飾北斎の冨嶽百景に関する著書(Dickins, 1880b)も上梓しています。これは、北斎に関する世界で最初の学術研究書となりました(Kornicki, 2004, p. 29)。
当時は、わが国の古典文学を英語訳しようにも、草書体と変体仮名で書かれた古文の木版本しか存在しませんでした。変体仮名というものは、明治になってから統一されるまでは、複数の異体字があって、日本人にも簡単に読めるようなものではなかったのです。ディキンズさんは、それらの書体と文章を、日本語という全く異質の外国語に接してからわずか2年後に、完全に解読できたことになります(右図参照)。ディキンズさんは、それほどの短期間に、日本人にも難しい書体と古語を、そこまで読み解くことができるようになったということです。
この偉業については、後のドナルド・キーンさんも絶賛しています(Keene, 2008)。これほどの離れ業は、どのようにすれば可能なのでしょうか。教えを受けるにしても、適切な教科書があってさえ容易なことではありません。ましてや、欧米人に役立つ基礎資料など全く存在しなかった時代背景を考え合わせると、これは、通常の能力をはるかに越えた、サヴァン的レベルのものと言わなければなりません。
ディキンズさんは、法廷弁護士としてもきわめて有能でした。特に、マリア・ルーズ号事件(日本政府とペルー政府との間に起こった訴訟事件)では、求められてペルー政府側に立ち、日本政府を震撼させるほどの敏腕を振るったそうです(秋山、2000 年、9-10 ページ)。その一方で、英国公使館の日本語書記官であったアーネスト・サトウさんという絶好の同志を得て、日本古典文学の研究と英語訳に並々ならぬ精力を注ぐのです。
ちなみに、もともとは医師であったディキンズさんは、Nature 誌などに論文も発表しています。その中に、大森貝塚に関するエドワード・モース先生の論文(Morse, 1879)に反論した論考があります(Dickins,1880a, p. 350)。モース先生は、当然のことながらその主張に再反論します。既にアメリカに帰国していたモース先生は、その原稿を何とダーウィンに送り、同誌に転送してもらうのです。それは、ダーウィンが大森貝塚に関心を寄せていたためでもあったようです。そのような事情から、モース先生の反論は、冒頭にダーウィンの添え書きが付されて、ダーウィンの名義で発表されています(Darwin, 1880, pp. 561-62)。このような逸話を見ると、わが国とは縁遠く見えるチャールズ・ダーウィンという稀代の生物学者も、ずいぶんと身近に感じられることでしょう。
ディキンズさんは、モース先生が初来日した翌年に当たる1879年1月に離日してエジプトに向かい、82 年に英国に帰国しています(岩上、2008 年、11 ページ)。それを限りに再来日することはありませんでしたが、晩年を除けば、日本文学の研究と英語圏への紹介に強い関心をもち続けていたそうです。このような事例を、単なる言語天才として片づけるのではなく、科学的な裏打ちをもって説明するには、サヴァン症候群とはまた違った難しさがあるように思います。
[註2]京都の児童精神科医、石坂好樹先生は、自著の中で、著名な数学者たちを、自閉症的サヴァンという角度からとりあげて解説しています(石坂、2014年、第3章)。関心のある方は参照してください。
[註3]磯村さんは、テレビ番組でこの能力を披露しました。この番組の詳細については、TBS系列のテレビで2013年10月18日に放映された「中居正広の金曜日のスマたちへ」 の番組概要などを参照してください。また、録画投稿サイトの YouTube にその場面が収録されています。
[註4]これは、グーグルによる検索の他に、CiNii、J-Stage、国会図書館の全資料を検索した結果です。したがって、現在進行中の未発表研究があるとすれば、それについてはもちろん不明です。それに対して、欧米では、たとえばドイツの “暗算電卓” であるリュディガー・ガムさん(Rudiger Gamm)を対象にした研究を例にとると、そのほとんどは脳の機能に結びつけようとするものではありますが、数多く存在するのです(たとえば、Pesenti et al., 2001; Butterworth, 2001, 2006; Houde & Tzourio-Mazoyer, 2003)。そのことからすると、まことに残念ながら、わが国の、特に最近の専門家は、この種の現象についても、研究の対象として真剣に考えていないらしいことがわかります。
また、テレビ番組の収録の際に磯村さんの能力の一端を目の当たりにした脳科学者の中野信子さんは、その能力について、容量の大きいハードディスクが頭の中にあるようなものと表現したそうです。それでは、磯村さんの記憶という側面のみの、しかもそのごく一部を比喩的に語ったにすぎません。このような発言は、しろうと的な思いつきの域を出ないものなので、専門家を自負するのであればすべきではありません。
[註5]一般には、精神科医の式場隆三郎先生が発掘し、その才能を伸ばしたとされているようですが、山下清さんが入園していた八幡学園のサイトの「山下清とその仲間たち」というページには、そのようには書かれていません。1936年に、特異児童の心理的特性や園児の作品が、日常生活の中でどのように変化していくかを研究するため、戸川が学生たちとともに八幡学園を訪れ、2年後の1938年に、その成果を早稲田大学の大隅小講堂で「特異児童作品展」として発表したこと、それにより、「園児たちの作品は一躍、多くの人々の関心を呼び」、画壇の重鎮であった安井曾太郎から絶賛を浴びたということが記されているだけで、顧問医を務めていたはずの式場先生の名前は、なぜか全く出てきません。戸川先生は、1936年に、その研究を「一技能に優秀な精神薄弱児の臨床例」という論文(赤松、内田、戸川、1936年)として、さらには『特異児童』(1940年、目黒書店刊)として発表しています。
それに対して、式場先生が運営する精神科病院があった千葉県市川市の「広報いちかわ」によれば、式場先生は、「山下清の絵の素晴らしさを展覧会を通して多くの人に紹介した人物」とされており、山下さんをつれて京都やヨーロッパにまで旅行しているそうです。ここには何らかの対立がありそうです。この問題に関心のある方は、石坂先生の著書(石坂、2014年、28-30ページ)や、千葉大学の大内郁さんの論文(大内、2010年)を参照してください。
[註6]スティーヴンソン先生は、一時、精神分析を研究していたことがあるのですが、結局は、幼少期の体験でその後のほとんどが決まるという主張を納得しきれなかったことや、フロイトが神格化されていることが理由になって、精神分析から離脱しています。その頃に発表した、人間の人格は、幼少期もその後も、可塑性という点で特に差はないという内容の論文(Stevenson, 1957)を読んだ精神分析学者たちから、怒りの声があがるようになりました。当時のアメリカ精神医学は、精神分析に席巻されていましたから、その後、ロンドンの精神医学研究所の教授から、「丸腰で街を歩いてだいじょうぶか」と心配されたそうです(Stevenson, 1990, p. 8)。スティーヴンソンという科学者は、権威というものの本質を、こうした経験を通じて熟知していたのです。
[註7]ここから先がスティーヴンソン先生の非凡なところなのですが、脳に働きかける微量の薬物が人間の心理的経験を変えることができるのであれば、人間の思考が単なる脳の活動の主観的反映にすぎないのかと言えば、そうではないと考えるのです。この問題については、後ほどあらためて扱うことにします。
[註8]左半球に障害を受けることで、それまで “左半球という暴君” によって抑えつけられてきた右半球の機能が高まると考えるわけです。その結果として、右半球の機能が解放されるというのです。
[註9]ウィルトシアさんに、絵の描きかたを教えた実験があります。その結果、ウィルトシアさんは、美術用語などはほかの学生と同じように覚えたそうですが、絵についてはほとんど変化しなかったそうです(Pring, Hermelin, Buhler & Walker, 1997)。
ついでながらふれておくと、ウィルトシアさんの事例は、『火星の人類学者』の「神童」という章に詳述されているのですが、邦訳では、この章の冒頭から原文で8ページ弱が削除されています。ここは、トレッファート先生が扱った盲目のピアニスト、トムの事例や、ナディアというサヴァンの少女画家の事例が自閉症との関連で書かれているところです。また、サックス先生は、全体にたくさんの註をつけているのですが、それも参考文献リストとともに完全に削除されています。これは、わが国の邦訳書によく見られる対応で、出版社の意向によるものなのでしょうが、まことに残念なことです。
[註10]大変興味深いことですが、ここにふしぎな符合がありました。アメリカ在住のサックス先生は、スティーヴン・ウィルトシアさんの存在を、サヴァンの画家として英国のある出版社から知らされたのですが、故郷であるロンドンの北西部で開業している兄を訪ねた時に、ウィルトシアさんの話をすると、「ぼくの患者だよ――彼が三つのときから知っている」という答えが返ってきたのだそうです(サックス、2001年、272ページ;Sacks, 1995, p. 196)。ちなみに、邦訳では「兄」ではなく「弟」となっていますが、サックス先生は4人兄弟の末っ子だそうですから、「兄」が正しい訳語になります。欧米では兄弟姉妹を年齢によって呼び分ける習慣がないので、特別のことがない限り、my elder brother などとは書きません。これは、翻訳者を困らせる問題のひとつではありますが、やはり注意しなければならないところです。
[註11]他のサヴァンの場合もそうですが、アマートさんについても、Derek Amato で検索すれば、YouTube でその演奏を聴くことができます。
[註12]ジョン・ダウン先生も、既に1887年の時点で、同様の事例を自著の中で紹介しています。17 歳のその少年は、いつ時間をきかれても、分単位で正確に答えることができたそうです。ダウン先生は、その現象について、その家庭は時間を厳守しながら生活していたので、少年は、その流れから時間を推定したのではないかと考えました(Down, 1887, p. 103)。通常の原因論としては、そのようなものしか考えつかないということなのでしょう。



 Copyright 2008-2017 © by 笠原敏雄 | created on 1/22/17 ; last modified and updated 2/26/17
Copyright 2008-2017 © by 笠原敏雄 | created on 1/22/17 ; last modified and updated 2/26/17