 サイトマップ
サイトマップ





 執筆予定の本に関連して
執筆予定の本に関連して
ちなみに、洋の東西を問わず、昨今の科学者は一般に、古典的文献には歴史的な意味や価値しかないと思っているようですが、実際には、抵抗の結果として注目されないまま現在に至っている重要な研究も少なからず存在しますし、倫理的な問題や時代的な背景を含め、いくつかの理由で今では得られることのない重要なデータが埋もれていることも珍しくありません。さらには、それらが新たな着想を得るための貴重なヒントになることもあるのです。
現在では、Google による構想や尽力を含めた壮大なとりくみのおかげで、英文の古典が大量に電子化され、数百万件の単位で無償で提供されているため、キーワードで検索するだけで、どの書籍に何が書かれているかが一瞬のうちにわかり、しかもそれらが即座に入手できるような状態になっています。ひと昔前までは、夢想だにできなかった状況がすでに現実のものになっているわけです[註1]。
人間は、地球上で発生した原始的な生命体から進化した産物であるのはまちがいないでしょうから、進化のひとつの頂点の最終形態は、現段階では現在の人類ということになります。したがって、生物の意識を考えた場合も、現時点では、現在の人間の意識が進化の頂点に位置することになるはずです。しかしながら、人間がさらに進化して行くとすれば、現在の人間の意識は、いまだ発展途上にあると考えなければなりません。そのことは、私の幸福否定理論からも言えるように思います。現在の人間の意識は、幸福否定という観点から見ると、発展途上どころか、まだきわめて原初的な段階にあると考えざるをえないのです。
そのような意識では、何を眺める場合でも、水面から濁った水を通して底のほうを見ようとするのと同じで、抵抗による不透明性のため、把握できる範囲は相当に限られますし、しかもひどく歪んだものになるはずです。ついでながらふれておくと、幸福否定理論が未成熟な段階ではありましたが、この問題を曲がりなりにも扱おうとしたのが、『隠された心の力――唯物論という幻想』(1995年、春秋社刊)という拙著です。
その一方で、当人の現実の能力をはるかに超える高度な能力が、意識に気づかれないような形で日常的に使われていることに加えて、当人の現実の品性をはるかに超える高い品性が、人間のいわゆる無意識に内在していることも、以下に述べる観察事実からするとまちがいなさそうです。そうした所見から推測すると、いつの日にかそれが表出し、意識に委ねられる形になる段階が来るはずです。抵抗が減少するにつれて、わずかずつではありますが、それが意識的に使えるようになり、しかも自覚できるようになることから、そのような推定ができるわけです。こうした観点からしても、ダーウィニズムをはじめとする従来の進化論の想定とは逆に、生命体は偶然による無方向性の産物ではないことがほぼ完全に推定できるように思います。これらの問題については、執筆予定の拙著で詳しく説明することにします。
したがって、ここではっきりするのは、意識がきわめて未成熟な現段階で、意識の側から無意識を眺めるという従来的な方法では、意味がないばかりか、抵抗の結果として、全くの(と言って悪ければ、壮大な)虚像が作りあげられてしまうということです。実際に、その結果として生まれたのが、現行の科学知識体系なのでしょう。したがって、そこには、脳とは独立して存在する心や、その心がもつ力といった概念が入り込むことは、木に竹を接ごうとするようなもので、最初からできないようになっているわけです。ここにも、現行の科学知識体系が隘路に入り込んでしまった謎を解くかぎがあるのです。
それに対して、従来の方法とは逆に、無意識側から意識を眺めれば、意識の実像に迫ることができるはずです。ところが、これまでのところでは、そのような試みはほとんどないようです。方法論が存在しなかったこともその理由のひとつなのかもしれませんが、それ以前に、そうした着想が生まれにくいようになったいることがその主たる理由なのでしょう。意識を主体と考える限り、あるいは意識を相当に完成されたものと見ている限り、それは最初からむりな注文と言うべきなのかもしれません。
そのきわめて稀な例外らしきものとして、 From the Unconscious to the Conscious という、まさにそのままのタイトルの古典があります。これは、著名な生理学者であったシャルル・リシェとともに物質化現象を研究したことで知られる、フランスの医師であり心霊研究者でもあったギュスターヴ・ジュレ(1860-1924年)が執筆した、進化の視点から意識を眺めようとした著作です(1920年に出版された英語版が手元にあるのですが、原典であるフランス語版の出版年は、どこにも記されていないのでわかりません。ただし、結論部には1918年という年号が見えます)。少々観念的な傾向はありますが、その視点は私の考えているものに、ある意味で多少なりとも近いようです。
この著書を含めて、たくさんの文献を読み進めようとしているのですが、その中でおそらく最も重要なもののひとつは、心霊研究協会の創設者のひとりであるフレデリック・マイヤーズ(1843-1901年)による、1903年に没後出版された Human Personality and its Survival After Bodily Death という大部の2巻本です(1巻にまとめられた要約版もあります)。これは、現代でも決して古さを感じさせないほどのもので、その点では、ダーウィンの『種の起源』にも匹敵する名著なのではないかと思います。これと比肩しうるはずがないことは言うまでもありませんが、拙著の中でこれと近い位置づけにあるのが、先の『隠された心の力――唯物論という幻想』です。『多重人格障害――その精神生理学的研究』と『偽薬効果』(1999年および2002年、いずれも春秋社刊)という拙編書も同じ趣旨から編纂されたものです[註2]。
その後に出版された同系列の著作としては、エサレン研究所の共同創設者であるマイケル・マーフィーが1992年に出版した The Future of the Body: Explorations into the Further Evolution of Human Nature (Los Angeles, CA: Jeremy P. Tarcher) があります。総計800ページに及ぶ膨大な著作で、人間の無意識に関する研究の総説が、分野別にまとめて行なわれたきわめて価値の高い歴史的な著作と言えるでしょう[註3]。ちなみに、マーフィーは、超常現象研究の文献に最も通じていたひとりであるリーア・ホワイトと共著で、『スポーツと超能力』(1984年、日本教文社刊)という興味深い本や、『王国のゴルフ』(1991年、春秋社刊)という、オイゲン・ヘリゲルの『弓と禅』に比肩しうる著書も出しています。
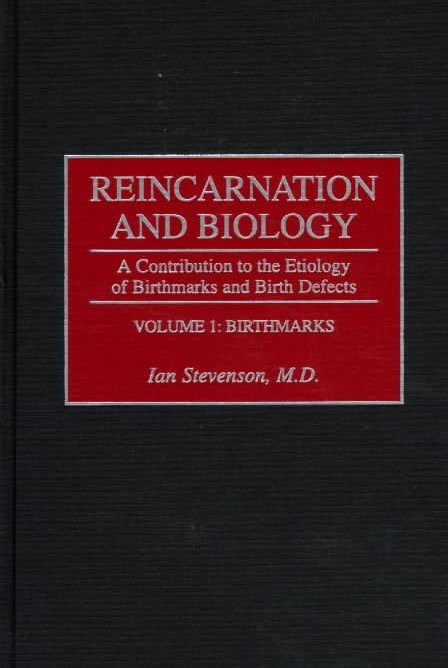 この系列の著書で比較的最近に出版されたものとしては、1997年に出版されたイアン・スティーヴンソンの Reincarnation and Biology: A Contribution to the Etiology of Birthmarks and Birth Defects (Westport, CT: Praeger Publishers)という2巻からなる、総ページ数が2300弱に及ぶ膨大なモノグラフ(一般向けの要約版は『生まれ変わりの刻印』〔1998年、春秋社刊〕)の第1巻(第2章)の他に、エドワード・ケリー、エミリー・ウィリアムズ・ケリー夫妻らによる、やはり総計830ページに及ぶ大部の著書 Irreducible Mind: Toward a Psychology for the 21st Century (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2007) があげられます(参考文献だけで101ページ、概算で1900件が掲げられています)。
この系列の著書で比較的最近に出版されたものとしては、1997年に出版されたイアン・スティーヴンソンの Reincarnation and Biology: A Contribution to the Etiology of Birthmarks and Birth Defects (Westport, CT: Praeger Publishers)という2巻からなる、総ページ数が2300弱に及ぶ膨大なモノグラフ(一般向けの要約版は『生まれ変わりの刻印』〔1998年、春秋社刊〕)の第1巻(第2章)の他に、エドワード・ケリー、エミリー・ウィリアムズ・ケリー夫妻らによる、やはり総計830ページに及ぶ大部の著書 Irreducible Mind: Toward a Psychology for the 21st Century (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2007) があげられます(参考文献だけで101ページ、概算で1900件が掲げられています)。
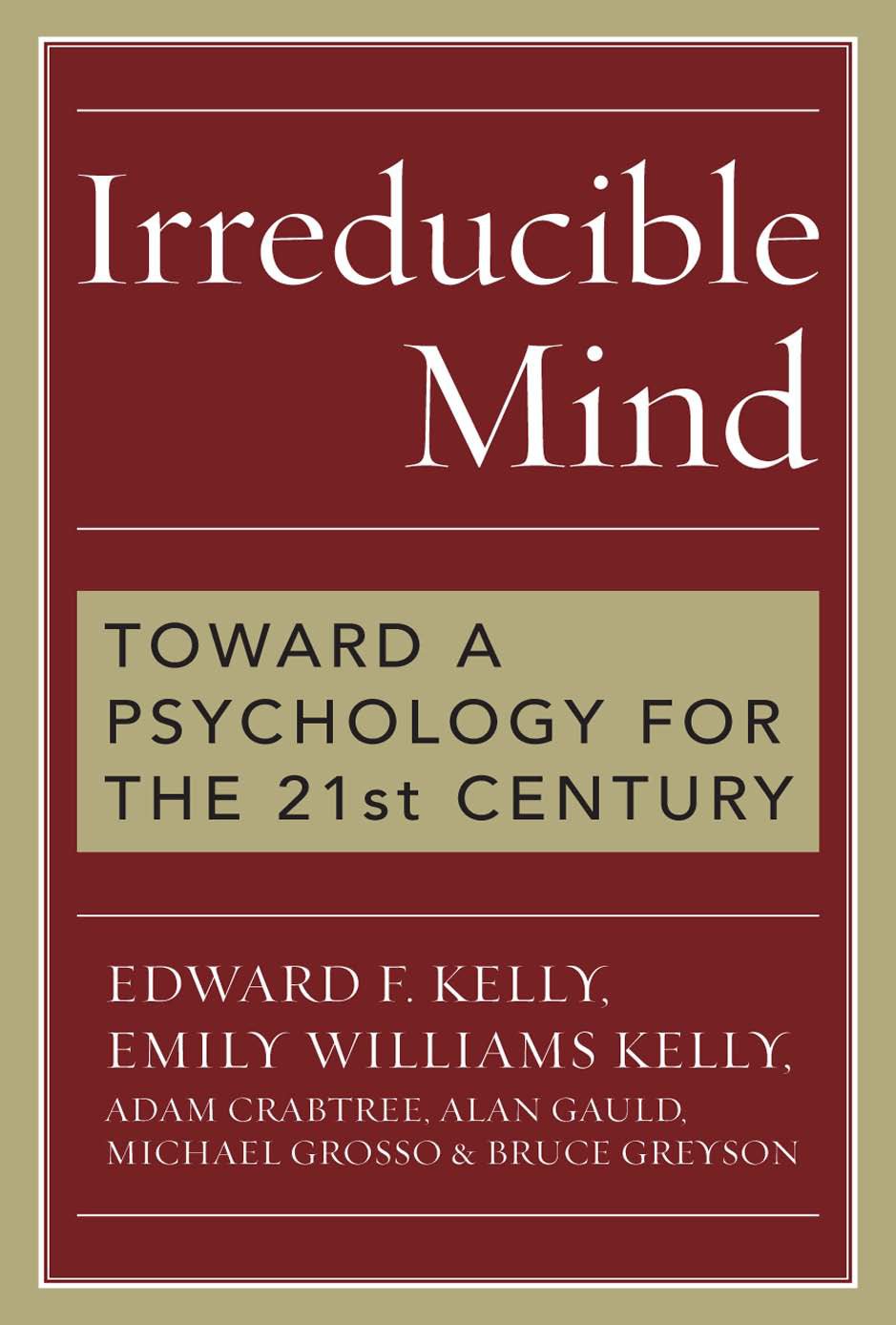 ここで注目しなければならないのは、「還元不能な心」という主タイトルとともに、副タイトルが「21世紀の超心理学に向けて」ではなく、「21世紀の心理学に向けて」となっていることです。今世紀の心理学は、超常現象研究やその成果など、これまで無視ないし軽視されてきた事柄をむしろその中核とすべきだという主張だからです。本来は、超常的な現象という、主流科学者から相手にされていない領域の研究に従事してきた自分たちにこそ正統性があるという立場を堂々と打ち出しているところに、著者たちのおおいなる意気を感ずることができるでしょう。
ここで注目しなければならないのは、「還元不能な心」という主タイトルとともに、副タイトルが「21世紀の超心理学に向けて」ではなく、「21世紀の心理学に向けて」となっていることです。今世紀の心理学は、超常現象研究やその成果など、これまで無視ないし軽視されてきた事柄をむしろその中核とすべきだという主張だからです。本来は、超常的な現象という、主流科学者から相手にされていない領域の研究に従事してきた自分たちにこそ正統性があるという立場を堂々と打ち出しているところに、著者たちのおおいなる意気を感ずることができるでしょう。
主著者のふたりはいずれも、スティーヴンソンが開設したヴァージニア大学医学部人格研究科(現、知覚研究科)に所属しており、エミリー・ウィリアムズ・ケリーは、長年にわたってスティーヴンソンの研究助手を務めていました。1980年に私が会った時にはまだ30歳前後で、クックという研究者と結婚していたため、エミリー・ウィリアムズ・クックとして論文を発表していました。また、エドワード・ケリーは、当初は言語の研究をしていて、その後、超常現象の研究に転じた心理学者ですが、拙編書『サイの戦場――超心理学論争全史』(1987年、平凡社刊)に、超常現象の実在をめぐる論争に関する論文を寄稿していただいたことがあります。当時はデューク大学工学部に所属していましたが、その後、ヴァージニア大学医学部知覚研究科に移って現在に至っています。
この著書には、長文の書評がたくさん出ており、超常現象研究の専門誌以外にも、Journal of Nervous and Mental Disease (2008, April issue) や、少々否定的なものではありますが American Journal of Psychology (2010, summer issue) のような有力な精神医学雑誌や心理学雑誌にも掲載されています。それはやはり、この著書が重要なものであることの有力な裏づけになるでしょう。
この著書の構成は次のようになっています。
序文(エドワード・ケリー)当時は、手術自体が非常に珍しかったわけですが、それなりの大きな手術の場合には、感染や出血のため死亡率が異常に高かった(たとえば、四肢の切断で40パーセント〔Perry & Laurence, 1983, p. 357〕)そうです。それに加えて、痛みも尋常なものではなかったため、手術を受ける患者の両手足を4人の助手がそれぞれ押さえつけながら行なったのです[註4]。
それに対して、患者を深いトランス状態に導入できる場合には、全くと言ってよいほどの無痛で手術を行なうことができたのです。1845年から54年にかけて、インドのベンガルで手術を行なっていたエスデイルは、そのような手術例を自著の中でたくさん報告していますが、そのうちの160件ほどは、四肢や乳房、最大で36キロにもなる陰嚢水腫の切除などの大手術でした。にもかかわらず、患者は手術が終わるまで痛みをほとんど訴えず、まさに死体のように不動の状態を保っていたというのです[註5]。
ところが、セオドア・バーバーをはじめとする昨今の著名な催眠研究者たちは、それを、患者の注意が催眠によって逸らされた結果と説明してすませようとしたのです。こうした説明について、皮肉を交えながら、ウィリアムズ・ケリーは次のように述べています。
この種の変化が、催眠や非催眠暗示によって誘発されたものかどうかはともかくとしても、本書でこれまで何度か提示してきた、「どのようにして起こったのか」という疑問は依然として残る。この現象を、自発的に、あるいは非自発的に注意が逸らされた結果にすぎないと主張した(たとえば、Barber, 1961; McPeake, 1968 参照)のでは、ふつうに見られる現象にしか通用しない説明をこの場合に適用することがいかに不適切かがむしろはっきりしてしまう。〔中略〕注意を逸らせるという点でここで重要な現象があるとすれば、それは、患者(や被験者)が(激痛などの)関連刺激から注意を逸らせたことではなく、理論的研究者たちが関連現象から注意を逸らせたことのほうであろう。(Kelly, 2007, p. 184。説明を補いながら拙訳)
科学者たちは、重要な現象を、意識でそれと気づかないようにしている――私の言葉では、「ことの重大性」に気づかないようにしている――ということです。ここでは、科学者に見られる抵抗という現象が浮き彫りにされています。この種の指摘は、超常現象の実在やその研究を否定する側には、当然のことながらできません。とはいえ、これは現象の指摘としてはまさに適切なのですが、問題は、ケリーの考えている抵抗が、意識的なものにせよ無意識的なものにせよ、私の言う抵抗と同じものかどうかという点です。このことが、執筆予定にしている拙著の大きなテーマに関係してくるのです。聖痕や、絶えず変動する多様なヒステリー症状を誘導、創成するもので、催眠によって水泡が作られる場合、その背後にある炎症過程を開始させたり停止させたりする方法を知っており、われわれの通常の意識にはわからないような形で、「K」という文字や十字架を肉体〔皮膚〕に表出させるという目標を実現する、隠された、より高度な知性のようなものである。(Kelly, 2007, p. 214)
人間の心が超常的な力を自分の肉体に対して行使する場合、その裏にあるはずの生理的過程を最初から知っており、しかもそれを、ある程度にせよ自在に操作できるということです。人間の意識の下に、そうした層が実在することを想定する必要があることを、マイヤーズは他に先駆けて主張していたのです。聖痕などの現象は、霊媒やヒステリーのような特殊な人たちに限って見られるものではありますが、マイヤーズは、それらを孤立した現象と考えていたわけではありません。この点について、ウィリアムズ・ケリーは、上の引用文に続いて次のように述べています。マイヤーズが主としてとり組んだ事柄のひとつは、意志という問題であった。心を、われわれが自覚している部分と同じものと考えるのはまちがいであったが、意志を、意識連続体全体の中では比較的小さな閾上部のものと同一視することも、同じくまちがいなのかもしれない。それどころか、意志は、個人の心全体の働きと考えなければならない。閾下にあるとともに閾上にもあり、個人が意識的かつ自発的に始めたことが自覚されているたぐいの行為に限定すべきではない(Myers, 1886, p. 448)。その「担当者 Person in charge」が、それをどのよう行なっているのかがよくわからないのは言うまでもないが、それを、脳の働きに置き換えたところで同じようなものであろう。しかしながら、その過程は、脳の自動的な反射というよりは、意図的で目標指向的なもののように見える。〔中略〕ここでまた、ほとんどの心理学者がとり組みたがらない根本問題に直面せざるをえない。それは、意志という問題であって、故意に腕を上にあげるという行動から、故意に水泡を発生させるという現象に至るまでの、あらゆる意図的現象が、意識の本質について教えてくれるはずのことである。(ibid., pp. 214-15)
このようにマイヤーズは、意志というものを、意識で把握できるものはもちろん、把握できないものも含めて、全体としてとらえようとしていたのです。この考えかたがすぐれているのは、通常の意識観や人間観とは違って、必ずしも閾上の意識を主体と見ているわけではないことでしょう。したがって、意識するかしないかは別として、閾下にあるものも、主体的にコントロールされると考えることになります。マイヤーズのような視点に立つと、人間の心というものを、このようにより広い視野から眺めることができるのです。
とはいえ、そのマイヤーズにしても、暗示によって身体的変化が起こるという現象を明確に説明できていたわけではありません。この問題については、将来の研究に期すとしていたのです。したがって、後世の研究者は、このマイヤーズの期待に応える責務があるのではないでしょうか。
たとえば、全身に難治性の皮膚病をもつ被験者を対象にして催眠暗示の効果を検証しようとした場合、右腕の肘から下だけが、次には左腕の肘から上だけが好転するように暗示をかけて、その通りのことがその順番で起こった(たとえば、Mason, 1952)とすると、言葉を介した暗示が、その言葉に従って肉体を変化させたことになるわけですから、これは、現在の生理学がいかに進展しても、説明できる見通しが全く立たない現象なのです。暗示という言葉は、そのような現象を命名したものにすぎず、何の説明にもなっていないということです。ウィリアムズ・ケリーは、このことから逆に、われわれが腕を上にあげようと思うだけでそれが実現されることに関する従来の説明にかえって疑問が起こると述べています(Kelly, 2007, p. 215)[註7]。
ここで興味深いのは、暗示の本質という問題を真剣に研究する者がほとんどいないことです。このこと自体も、非常に不思議な現象と言わなければならないでしょう。暗示は、念力と違って、現象としては実在が認められているのですが、そこから先の探究がほとんど行なわれることのないまま現在に至っているのです。そこには、共同歩調のようなものの存在が感じられるため、もちろん無意識的なものではありますが、研究者の間に暗黙の了解が存在する可能性すら疑われます。私はこのことを、“共同妄想”と呼んでいます(『幸福否定の構造』第7章参照)。ベルクソンは、この種の広く見られる現象を、心と物質の一元論(心身一元論)以外のものを本能的に拒絶する傾向の現われと考えました(ベルクソン、1992年、88ページ)。 「本能」と感じられるほど強固なのは、ベルクソンの指摘を待つまでもなく確かなので、ことはそう簡単ではないのですが、そこに抵抗があると考えると、新た展望が開けてくるのです。 ところで、超常現象の統計的実験法を創始したことで有名な、デューク大学のジョゼフ・B・ラインは、「超心理学と生物学」と題した1950年の論文で、次のような着想を提示しています。この頃のラインは、そもそもが生物学者であったためかもしれませんが、動物に見られる超常的現象や医学的研究との関係などを含めて、幅広い領域の研究に強い関心を示していたのです[註8]。火傷による水泡のようなものを“暗示”で作り出すことができるのであれば、あるいは“暗示”に従って皮膚に文字を浮かび上がらせることができるのであれば、心身症の症状も、念力によって起こる可能性があるのではないか。(Rhine, 1950, pp. 91-92)
この引用文でラインは、暗示によって起こるそうした現象が念力によって起こる可能性を示したうえで、心身症の症状も同じく念力によって起こる可能性を示唆しています。これは、非常に大胆かつ卓抜な着想と言えますが、現実には、ほとんど無視されたまま現在に至っているのです。私は、心身症的な症状が目の前で一瞬のうちに発生し、状況の変化に伴ってやはり一瞬のうちに消失するという現象を40年以上にわたって日常的に観察してきた経験から、ラインのこの主張に心から同意するものです[註9]。 暗示によって起こる精神生理学的変化が超常現象と違うとすれば、それは、ほとんどが形式的な側面に限られると思います。そのことは、たとえば、いぼを念力で消すという試みと、いぼを暗示によって消すという試みを比較してみればわかるでしょう。両者の違いは、言葉の違いという形式だけで、両者を本質的な点で区別することは不可能なのです。 ただし現実には、同じいぼでも、念力によって――つまり、念力を使うという条件で――消すことのほうがはるかに難しいと思います。それは、おそらくは、施術者と被術者の一方ないし双方が、念力のほうが難しいと思い込んでいるためであって、それ以上のものではないでしょう。暗示という条件であれば、あくまで被験者ないし被術者の体内で起こることになるので、仮に念力が働いていたとしても、それがはっきりすることはありませんが、念力という条件になると、施術者が被術者という他者の肉体を変化させたことになってしまい、念力が働いたとする説明以外が成立しにくくなるわけです。 しかしながら、心身症的な症状が念力によって起こるという着想は、私のように特殊な経験を積んでいる場合は別として、簡単に出てくるものではありません。その最大の理由は、心因性疾患の原因が一律に“ストレス”と断定されて片づけられているため、他の可能性を考える必要がない状態になっていることでしょう[註10]。逆に、抵抗という現象を基盤にして考えると、ほぼ全員が暗黙の了解のもとに、その可能性を考えなくてもすむように、ストレスを原因と決めつけていることになります。このような視座が、これから書こうとしている拙著のテーマに深く関係しているわけです。 ラインのような着想が出てきにくいもうひとつの理由は、身体的変化をもたらす暗示を念力によるものと考えることに、催眠現象の研究者を含めた科学者が、ほぼ例外なく抵抗しているように思われることです[註11]。念力という概念が、現行の科学知識体系には存在しない(現実には、最初から参入できないようになっている)ことに思いをいたすと、こうした主張は常軌を逸しているように感じられるかもしれません。とはいえ、暗示という現象は、ウイルス性の皮膚疾患であるはずのいぼが高率に消えたり、重度のやけどが跡形もなく治癒したりするという事実を考えてもわかりますが、その本質は未だに不明なだけでなく、それを生理学の知識体系やその延長で説明することはできないのです。その点は、主流科学者たちから実在自体が否定ないし無視されている超常現象の場合と全く同じです。 そのような状況を勘案すると、ここでは、従来の枠組みから大幅にはずれた概念を導入する以外になさそうです。問題は、その概念や説明が常識を逸脱しているかどうかではなく、それによって目の前の隘路を抜け出せるかどうかにしかないはずです。 少々話を戻すと、マイヤーズの遺産を生かしながらこの先に進むには、実際にはどうすればよいのでしょうか。そのためには、ひとつには、これまで発表されてきた観察や実験の報告の中から、ほとんど注目されないまま、あるいは重視されないまま来てしまった所見にあらためて注目することです。暗示の場合には、たとえば、先に紹介してきた事例などの他に、次のような観察事実があげられるでしょう。コロンビア大学の著名な精神科医であったハーバート・スピーゲル(スタンフォード大学精神科のデヴィッド・スピーゲルの父親)が、偽薬効果のひとつである“反偽薬 nocebo”に関する論文の中で紹介している事例です。想像力を制御する実験で、私は、陸軍のある下士官に催眠をかけ、前腕部に熱した鉄片を押し当てるという暗示を与えた。鉛筆の先端を前腕部に当てると、この下士官は、痛みを訴え、2,3分のうちに水泡を発生させた。数日後、傷口を覆っていた痂皮が剥落した。この実験は、その翌月に4回繰り返され、いずれも同じ反応が得られている。しかしながら、5回目の実験では、立ち会っていた高級将校が、実験の真正性に疑念を表明した。権威ある人物にけなされ、面目を失って以降、この被験者は、催眠暗示に二度と反応しなくなった。(スピーゲル、2003年、223ページ)
ここで重要なのは、水泡が暗示を与えてから2,3分のうちに発生したという瞠目すべき事実もさることながら、権威の存在と暗示効果が密接に関係していることを示す実例になっていることです。被験者が、それまで素直に従っていたコロンビア大学の精神科教授という権威よりも上と見なす上官が、催眠現象に疑念を表明しただけで、この被験者は、二度と催眠状態に導入されなくなったというのです。これは、単なる逸話を超えて、催眠や暗示という現象の謎を解くうえできわめて有力な手がかりになるはずです。 ところが、ここで興味深いことがあります。催眠や暗示が権威という要因と大きくかかわっている可能性は昔から指摘されてきたのですが、そのことに焦点を当てた研究がほとんど存在しないということです。魔術的手順では,そう望むだけで降って湧いたように所定の結果が得られ,その間に介在するはずの段階がすべて省略されるのである。魔術の本質的特徴は,目に見えない知的存在が働いたと考えると一番簡単に説明のつきやすい形で現象が起こることである。科学の本質はメカニズムであるのに対して,魔術の本質はアニミズムである」(プライス,1987 年a,34 ページ)。
プライス自身は、それがありえないことの理由として、超常現象を魔術と同一視したのでしょう[註13]。このあたりは実際には同意反復になっているだけなのですが、魔術的な現象が現実の中で起こるはずはないと考えたプライスは、この論文で、ラインをはじめとする超常現象の研究者が不正を働いたことを疑ったのです。 同じく、福来友吉の念写実験の信憑性を疑った、前東京帝国大学総長の山川健次郎は、「『ラヂューム』が丸龜にありと云ふことと、念寫が出來ると云ふことと、何方れがより不思議なるや」と述べたそうです(藤、藤原、1911年、90ページ)。被験者がラジウムを使って乾板を感光させ、念写に見せかけたと考えたわけです。ところが、『キュリー夫人伝』(1988年、白水社刊)によると、当時のラジウムは、とてつもなく高価なものでしたし、実際にも、わが国にはごくわずかしか輸入されていなかったのです。庶民が気軽に入手できるようなものではなかったのです。 逆に考えると、そのようなラジウムをもち出さなければならないほど、念写という現象はとてつもなくありそうにないことであること――つまり、ことはきわめて重大であること――を、物理学者たちは昔からよく知っていたということです。 しかしながら実際には、プライスの言う通りで、超常現象の仕組みは、まさに魔術的なものなのです。超常現象の本質は魔術と同じく、目標を念ずるだけで、途中の経過を知らずとも自然に実現されてしまうことにあるわけです。ただし、そのことは、繰り返しになりますが、先の暗示の場合にも言えますし、さらには、私たちの日常的な身体的動作の場合にも言えるかもしれません。後者の場合、誰も疑問に思わないだけで、実際には全く同じかもしれないのです。 この論文を発表した後、プライスは、その問題についてラインとやりとりを続けます。その結果、最終的に自らの非を認め、同じ Science 誌に、ラインとソウルに対する謝罪文を掲載することになるのです(プライス、1987年b、153ページ)。そうすると、その後の超常現象の位置づけは、プライス自身の中ではどうなっていたのでしょうか[註14]。魔術的なものであることを認めたのか、それともそれ以上考えずにすませてしまったのかのどちらなのか、ということです。その後、プライスは超常現象に関する発言はしていないようですから、現実には後者の対応を選択したということなのでしょう。 目標指向性という特性は、このようにさまざまな領域で観察されるわけですが、その裏には、マイヤーズが考えたように、閾下の実在がそれに必要な知識をもっており、それをある程度にせよ自在に使うことができると想定しなければならないのです。とてつもなく考えにくいことのように思われるかもしれませんが、実際にはその推定の裏づけとなるもっと明確な証拠が存在するのです。- 人間は、自らの進歩の指標となる幸福心が意識にのぼることのないように、絶えず万全の注意を払っている
- 人間は、自らのもつ能力や品性が、意識に気づかれることのないように、絶えず万全の注意を払っている
- そのため人間は、意識をその方向に自在にコントロールしている
[註2]続いて、催眠と暗示、神童、超常的現象などのシリーズを出す計画があったのですが、翻訳著作権料が高騰したため、断念せざるをえなくなりました。。
[註3]かつてニューエイジ・ムーヴメントの旗手として知られたマイケル・マーフィーは、研究者というよりは行動の人のようですが、同書は各方面で高く評価され、最も有力な医学雑誌のひとつとされる New England Journal of Medicine にも、ブルース・グレイソン(現、ヴァージニア大学知覚研究科部長)による書評が出ています。なお、同書は、800ページのうち、註や86ページに及ぶ参考文献(1000件ほどの註と3000件ほど参考文献)を含め、本文以外の資料で200ページ弱を割いています。それだけでも、資料集としての価値が高いことがわかるでしょう。
[註4]ついでながら、ダーウィンが医学の道に進むのをやめたのは、エジンバラの病院で2件の手術を見学した際、直視に耐え切れず逃げ出して以降、手術に立ち会うことができなくなったためでもあるようです。その後もしばらくは、手術の光景が頭から離れなかったそうです(Darwin, 1893, p. 12)。
[註5]当時の手術は、現在では夢想だにできないほど迅速かつ手際のよいものでした。たとえば、1846年にロンドンで行なわれたエーテル麻酔を使った最初の手術では、手指の切断が、結紮を含めてわずか29秒で終わったそうですし、それより前に、つまり麻酔を使わずに1824年に行なわれた、脚を股関節から切断するという大手術でも、わずか20分しかかからなかったそうです(Perry & Laurence, 1983, p. 356)。
[註6]ただし、同書には、スティーヴンソンが高く評価した、飼い犬を対象にした実験が中心になったルパート・シェルドレイクの著書(シェルドレイク、2003年)や、レオニード・ワシリエフの師でもあるロシアの著名な生理学者ウラジーミル・ベヒテレフが行なった、やはりイヌを対象にした一連の実験(Bechterev,1949)などがとりあげられていません。また、科学的探検学会の現在の会長でもあるウィリアム・ベングストンが共同研究者とともに行なった、マウスのがんを退縮させる一連の劇的な実験(Bengston,2012; Bengston & Krinsley,2000)もまったくとりあげられていないのです。いずれも有名なものであることから、何らかの理由で意図的にふれなかったものと思われます。
[註7]1970年代の終わりころだったと思いますが、私は、これと同じ疑いを、東京工業大学の教授を務めていた吉田夏彦さんからじかに聞いたことがあります。吉田さんは、誰も疑問に感じていないようだが、右手を上げようと思うだけでそうなるのは、実は非常に不思議なことなのではないかと言っていました。
[註8]ラインは、それまでアカデミズムの中で受け入れられていなかった超常現象研究を、心理学実験法に似た方法で行なうことで、専門家に広く受け入れてもらうことを構想したわけですが、それから80年以上が経過した現在、残念ながらそれは失敗に終わったとみてよさそうです。それどころか、この領域の研究は、全体としてますます狭く小さなものになってしまっています。この問題に関心のある方は、ジョン・ベロフ『超心理学史』(1998年、日本教文社刊)の第5章「ライン革命」を参照してください。
[註9]この段落とその上の引用文は、先ごろ出版した拙著『幸せを拒む病』の第2章に書かれたものなのですが、このような主張は読者には受け入れられにくいので、同書からは外したほうがよいのではないかという助言を受けて削除したものです。そうしても大勢には影響しないと考えましたが、同書の出版を実験と考えたため、その示唆に従うことにしたわけです。
[註10]ところが、ストレスが心因性疾患の原因と考えてよい科学的根拠は、あるはずだと誰もが思い込んでいるだけであって、実際には存在しないのです。にもかかわらず、心因性疾患の原因を、外部からのストレスと見る以外の着想は、これまでどこにもなかったようなのです(例外は、ここでもイアン・スティーヴンソンです。心身医学の確立にも寄与しているスティーヴンソンは、1950年と1970年に、本人が喜んでいるはずの状況の中で身体症状が出現した、あるいはそのまま死に至った事例を、周囲の反対を押し切って医学雑誌に発表しているのです〔Stevenson, 1950, 1970, 1989〕)。この問題については、拙著『加害者と被害者の“トラウマ”――PTSD理論は正しいか』(2011年、国書刊行会刊)で厳密に検討しているので、関心のある方は同書をご覧ください。
[註11]この問題については、拙著『隠された心の力――唯物論という幻想』(1995年、春秋社刊)の第3章で厳密に検討しておきましたので、関心のある方は同書を参照してください。当該の一部は、当ホームページの「催眠状態の中で起こる不思議な現象」に再掲されています。
[註12]この問題に関心のある方は、拙編書『超常現象のとらえにくさ』(1993年、春秋社刊)をご覧ください。
[註13]ちなみに、後にプライスは,血縁淘汰説を唱えた理論生物学者ウィリアム・ハミルトンと共同で研究を行なうようになり,著名な生物学者ジョージ・メイナード=スミスとも共著論文を発表しています。にもかかわらず、最後は、ホームレスのようになって孤独死するのです。
[註14]ただし、皮肉なことに、超常現象の研究者たちは、後に、ソウルが行なった実験の信憑性を疑うようになります。このような側面も、超常現象がとらえにくい結果の一因になっています。
[註15]そう言うと、主流科学者たちからは相手にされなくなる可能性が高いはずです。それは、宇宙はすべて偶然に支配されているという大原則が現行の科学知識体系の根底にあるからです。そのため、宇宙に方向や意志や目的のようなものはあるはずがない、あったらそれは宗教的な信仰にすぎないと断定するのです。ところが、宇宙が偶然に支配されているという着想は、科学的方法を使って証明されたものではありません。それも単なる信仰にすぎないのです。ここには、とてつもなく大きな抵抗が見え隠れしています。
