 サイトマップ
サイトマップ



 書評 自閉症当事者――1.『ぼくたちが見た世界』
書評 自閉症当事者――1.『ぼくたちが見た世界』


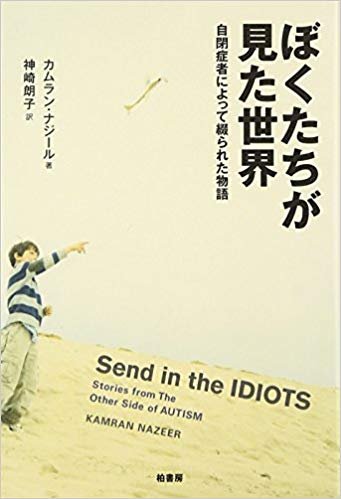
『ぼくたちが見た世界――自閉症者によって綴られた物語』(柏書房、2011/10/1 刊行)
カムラン・ナジール (著)、神崎朗子 (翻訳)
四六判、270ページ
![]()
著者のカムラン・ナジールさんは、本名をエムラン・ミアンさんという 1978 年生まれのパキスタン系イギリス人で、ケンブリッジで博士号を取得しています。本書執筆当時は、政策顧問という役職にある国家公務員でした(現在も同じ立場にあるそうです)。驚いたことに本書は、著者が弱冠 27 歳の時の著作なのです。これほどまでの作品をこれほどの若年で書きあげることができたのは、やはり著者の能力と努力のたまものなのでしょう。著者による自閉症を扱った出版物は、他の多くの当事者たちと違って本書のみのようですが、これほどの力作であれば、それだけでもう十分かもしれません。
本書でとりあげられているのは、20 年ぶりに著者が再対面した時点で、ボストンで姉と同居していたコンピュータ科学者のアンドレ、シカゴにあるトランスジェンダー・パートナーの大邸宅に同居し、自転車便の仕事をしていたランダル、ニューヨークで民主党大物議員のスピーチライターをしていたクレイグ、そして、2006 年に本書の原著が刊行される3年ほど前に入水自殺を遂げていたエリザベス(両親との面談をもとに執筆)の4人です。さらに、当時の担任と校長(ともに女性)のふたりにもインタビューしています。ついでながら、著者はたくさんのコンピュータ科学者を知っているそうですが、奇人変人が多いにもかかわらず、ランダル以外には、自閉症者はひとりもいなかったそうです(18-19 ページ)。
本レビューでは、本書で具体的な形で詳細に記述されている事柄のうち、主として、自閉症の中核症状とされるものは実際にはどのような構造になっているのかという問題と、自閉症はどこまで好転しうるのかという問題のふたつをとりあげることにします。
では、そうした中核症状には、いわば下部構造はないものでしょうか。仮にあるとすれば、それはどのようなものでしょうか。他者との会話を筆頭とする社会性の障害その他の、自閉症特有とも言うべき症状は、どのような仕組みで表出しているのか、つまり真の中核症状は “自閉” なのか、それとも別のことなのかということです。この点が詮索されることはまずありませんが、そのようなものがあるとすれば、そこにこそ、自閉症の謎を解く糸口があるはずです。幸いなことに、本書には、その疑問を解くヒントになりそうな実例がたくさん紹介されています。そのひとつは、コンピュータ科学者であるアンドレが見せた、非常に興味深い行動でしょう。
アンドレは 10 歳になるまであまり会話ができず、できたとしても、広げたクリップの先で自分の爪の裏をかきながらでなければ難しかったそうです。そして、伝えたいことがうまく伝えられない時には大きなうなり声をあげていたのですが、著者が再会した二十代半ばの時点では、比較的ふつうに会話ができるようになっていました。こうした改善は、さほど珍しいことではないとはいえ、本人にとっては大きな進歩です。ところがアンドレは、口頭で話すことの他にも、よくできた何体かの自作の操り人形を使って、本来の本人とはまったく違う声で話すということも、必要に応じてしていたのです。
それはどういう場面かというと、誰かが言ったことの意味がわからない時や、自分の言いたいことがうまく伝えられない時、きちんと伝えるにはどうすればいいかを考えるのに時間がかかりそうな時などです。要するに、何らかの理由で、やりとりがもう少し必要な場合や、判断に手間どりそうな場合ということでしょう。そのような時には、“自分” であることをやめて、別の役になり切るというのです(29 ページ)。そして、いざ人形を登場させると、アンドレは「とたんにリラックスした様子」になり、人形を介して姉に質問する余裕すら見せる(49 ページ)ほどになるばかりか、初対面の人とも、かなり自然に対話することができるのです。
また、人形を使えば皮肉を言うことさえできるそうです。つまり、多少の条件はあるにしても、人形を介してであれば、かなりふつうの対応ができるということです。このことからわかるのは、少なくともアンドレの会話障害は、技術そのもののためではないということです。
ドナ・ウィリアムズさんをはじめ、少なからざる自閉症者が別人格を作り、多くの場合、それらを自覚的に利用して対社会的な接触をしていますが、より演技的で作為的なアンドレの戦略も、それと同じ位置づけにあるようです。この点はきわめて重要です。ここにこそ、自閉症者の社会性障害の本質を解明する糸口がひそんでいるからです、この戦略に対して、著者は、次のように実に的確な解説をしています。これは、同一性の保持とされる症状の仕組みも、ともに明確にしてくれる、まことに瞠目すべき説明にもなっているわけですが、当事者の立場からでなければ、推定はできるとしても、ここまで断定的な態度を自信をもってとることはできないでしょう。
ぼくが一緒に出かけたときもそうだったが、アンドレはまず、自分なりに同一性を保って身を守ろうとする――ややこしいことは意識の外に置き、かわりにテーブルの表面をペンでこつこつ叩いたり、空っぽのグラスを一列に並べたりすることに意識を集中させる。それでもうまくいかないとき、次なる戦略として人形が登場するのだ。そして、ついにこの人形作戦までが失敗してしまうと、つまり、誰かが人形の言葉を遮り、必死に保っていた同一性があえなく崩れ去ると、キレてしまうのだ。突然、衝動のままに、思いとどまることもなく。(59-60 ページ)
著者は、同一性の保持そのものについて、さらに鋭い観察をしています。次の通りです。アンドレはバーに行った時、グラスの氷をいじる。バーカウンターを指でなぞり続けるなどの同一性保持行動をするが、そういうことをしていると、まわりのことはあまり気にならなくなる。そして、赤い服を着ている人にもおちついて話しかけられるようになる。こういうのを同一性保持というのだ。(48 ページ)
これは、ご覧のように、目的的な説明になっています。意識的な自分では対応できないと感じると、目の前のその現実から気持ちをそらせる手段として、何か別のことに注意を集中するため、単調な行為を強迫的に繰り返すようになります。それが、外から見ると “同一性の保持” とされる行動になるわけです。これは、いわゆる定型発達をしている人たちに見られる “癖” と質的には同じ位置づけにあるものでしょう。違うとすれば、場面や状況をわきまえず、度を外れて極端な形で出現することくらいのものです。ところが、そうした戦略でも対応しきれない(と意識の上で感ずる)段階になると、次の手を繰り出すことになるわけです。アンドレの場合は、それが人形を通じた対話や独白なのでした。
最初に同一性の保持が破られたとき、ほんとうは採るべき方法はもうひとつあるだろう。意識の外に隠してしまおうとした問題を表面化させるのだ。ほかのみんなと同じように、素直に負けを認め、人生のドロ沼でもがくのだ。でも、アンドレはそうしようとはしない。むしろ、激情に駆られたり不愉快な目に遭ったりすると人形を取り出す。バックアップのテクニックだ。(60 ページ)
“定型発達者” がごくふつうにしている、浦河べてるでも推奨されているところの “当たり前の苦労 ”を、何とかして避ける目的でアンドレがとっていた手段が、人形を介した対話や独白だったということです。著名な神経学者であったオリヴァー・サックス先生は、ある自閉症サヴァンの男性について、「人間として、男として十全の存在となって偉大さや惨めさを味わうこともないだろう」(サックス、2001年、331ページ)と、客観的な立場から述べています。ウジェーヌ・ミンコフスキーのことばを借りれば、この自閉症者は、「生ける現実との接触」を避けているということでしょう。著者と同じくサックス先生も、それぞれが見た自閉症の個人を、実生活の中で味わうべき苦しみを避けて通っていると考えたのです。アンドレの姉によると、アンドレがこのテクニックを身につけたのは、ある「少年の頭を道路に死ぬほど打ち付けて施設に入れられたとき」だったのだそうです。その少年にはかなりの後遺症が残ったそうですから、ことと次第によっては傷害致死事件に発展しても不思議ではない状況だったのです。
それはともかく、「気まずい状況を切り抜けるにしても、もっと無難な方法がいくらでもありそう」なものです(49-50 ページ)。しかしながらアンドレは、世間一般のふつうの人たちのように「素直に負けを認め、人生のドロ沼でもがく」のを嫌って、意識的なものではなかったにしても、この方法を選んだということなのでしょう。これはアンドレ個人の問題ではありますが、自閉症者全般についても同じことが言えるのかどうかが、ここで大きな問題として浮かび上がってくるのです。
自分の姉ではあっても、アンドレにとっては心理的距離が遠いらしく、そのため、姉が難しいことを言い始めたり、アンドレに意見を求めたりすると、必ず人形が割り込んできたそうです。そして、誰であれ、人形が話している間に口を挟むことは許されません。誰かが少しでも口を挟もうものなら、アンドレは間髪を入れずその場をとび出してどこかへ行ってしまい、しばらく戻ってこなくなるのです。
この場合、ふたつのポイントが考えられるでしょう。ひとつは、自分の代理になるものを利用すると、つまり自分が他人と直接に応対しているのではないというふうに自分の意識を説得できさえすれば、おおむねふつうに対話することが可能になるということです。もうひとつは、その代理作戦が不調に終わると、そのとたんにアンドレは現実に背を向け、その場から物理的に逃げ出すという幼児的対応をとることです。つまり、自閉症者一般に見られる、他者との対話や社会性の障害と言われるものの本質は、このようなもの――自らの意識の説得という問題に関係している――かもしれないということです。
したがって、脳機能の異常を自閉症の原因として考えるにしても、意識的な自分の説得が極度に難しいという事実の説明ができなければならないことになりそうです。換言すれば、“偽りの自分” ではなく、本来の自分として他者と対話するのが難しいのはなぜなのか、その理由が脳の機能として説明できなければならないということです。
次は、もうひとつの長期予後という問題です。自閉症児は長ずるにつれて、多かれ少なかれ障害が改善することが経験的にわかっているわけですが、では、実際にはどれほどよくなるものなのでしょうか。これは、もちろん個人差が大きく、予後調査の結果の悪い側を見れば、かなり悪いのはまちがいないので、簡単にかたづけることはできません。しかしながら、本書の枠内で言えば、結局は自殺してしまったエリザベスを含め、全員がかなり好転していることがわかるのです。
たとえば、特別支援クラス時代に Send in the idiots(「おバカさんたちを連れといで」)ということば(“反響言語”)をことあるごとに発していたクレイグは、民主党大物議員のスピーチライターになっていました。ちなみに、本書の原著は、クレイグのこのことばがそのままタイトルになっています。クレイグは、専門のそうしたスピーチライターだけあって、すばらしい文章を書くそうです。ただしそれは、「本人が苦労して身につけたものであり、生まれつきの能力ではない」のです(252 ページ)。
クレイグは、上院議員の「助手の話に耳を傾けつつ」、「なにやらずっとメモを書いて」いました。そして、最初のページを破り取り、それを見ながら、その秘書に、驚くほど詳細かつ的確な助言を与えていったのです。これは、「いち時には単機能しか働かない」とされる自閉症の人たちが、並行してふたつの、しかも高度な作業ができることをはっきり教えてくれる出来事です(113 ページ)。またクレイグは、初対面の相手に次々とジョークを言って笑わせるほどの芸当も演じています。ただし、その時には、「足元を見つめたまま一本調子の声」で言っているそうなので、この点はやはり “自閉症的” なのかもしれません(140 ページ)。とはいえ、ここまでくれば、もはや自閉症をもち出さなくても、十分に説明できるように思います。
自転車便の仕事をしていたランダルにも、大きな改善が見られていました。たとえば、トランスジェンダーのパートナーが、家の中で起こるさまざまな小事にまつわるぐちを著者に向かってこぼしている時、目を閉じて黙って聞いていたランダルは、「自閉症の人間と暮らすのは大変だって認めたくないんだろ」と、パートナーに向かって言ったのです。それに対してパートナーは、「そんなんじゃんないんだよ」とあわてて否定したそうです(89 ページ)。これも、当人すら意識の上ではわからないかもしれない、言葉の裏にある相手の真意を見抜くという、自閉症にとっては難しいとされることができていることになるでしょう。
自閉症は、他人の気持ちを察するのが苦手と言われているわけですが、この問題について教えてくれる事柄としてさらに適切なのは、やはり著者が関係している次の出来事でしょう。その特別支援クラスは、その後、ある事情から閉校を余儀なくされたのですが、失職したレベッカ先生は、次の勤め先を探すのに苦労したそうです。先生はこうした教職を、単なる仕事ではなく天職と考えており、プロとして十分な技術と熱意とを兼ね備えていたのですが、不幸なことに「きちんとした資格」をもっていなかったのでした。
この問題について、校長だったアイラ先生をまじえた3人で話していた時のことです。著者はうっかり、当時のレベッカ先生には熱意しかなかった、と口をすべらせてしまったのです。
ぼくがそんなことを口走ると、レベッカより先に、すかさずアイラが言った。
「経験だって必要よ』ぼくをたしなめたのだ。「大学じゃ現場のスキルなんて身に着かないんだから」
「あ」しまった、とぼくは思った。レベッカは気を悪くしたに違いない。きっとそうだ。どう言い直すべきか、ぼくは必死に頭をひねった。
「だけど、とてつもなく並外れた熱意だったってわかってるわけ?」
だんまりをやめて、レベッカがぼくをからかった。そして、一瞬、ぼくの手にそっと手を重ねた。ぼくはうなずいた。(216 ページ)
ぼくらは自閉症のおかげで、他人との関わりや自分のふるまいについて、ふつうのティーンエイジャーよりもよっぽど真剣に考えていた。自閉症の場合、おのずとそういう問題にじっくり向き合わざるをえない。ぼくはよく心理士を相手に話をしながら、ほんとうに面倒くさいと思っていた。まず見知らぬ相手に自分がいま思っていることを伝えなければならない。そして、こんどは心理士が手探りで答えを探していくのを見守っていなければならない。答えなんて、自分でとっくに見つけているのに、だ。(176 ページ)
このように、その苦労は、私たちが推定しているものとはかなり違っているらしいのですが、こうした自閉症児たちは、やはり当事者なりの大変な苦労を、おそらく延々と重ねてきたのです。「ぼくらが進歩したのは、自分自身の外にある世界とふれあったおかげなのだ」(251 ページ)と著者は書いていますが、自閉症療育という側面について言えば、この課題をこそ、その中心に据えなければならないということなのでしょう。べてるの家流に言えば、療育に当たる側は、狭義の“受容”ではなく、当事者が自分本来の「苦労をとり戻す」手助けをする、ということになります。本書には、「心の理論」に対する、著者なりの反論も明記されています(82-83 ページ)し、93-96 ページにある著者の “天才” 論も一読に値するものでしょう。さらには、自閉症的行動の仕組みについての著者なりの説明も、非常に興味深いと思います。それは、たとえば次のようなものです。
自閉症の子どもはいらいらすると自分の殻に閉じこもる傾向にある。そして、ほかのひとの手を借りずにすみ、リラックスできるような簡単なことをしようとする。たとえば、どこかに隠れたり、身体を揺すったり。〔中略〕
自閉症の子どもは大きくなっていく過程で、思うようにいかないことが重なって怒りを募らせることがある。その怒りは自分自身に向けられることもあるが、ほかのひとたちに向けられることもある。ふつうは両親だ。(173 ページ)


