 サイトマップ
サイトマップ



 書評 自閉症当事者――7.『私の障害、私の個性。』
書評 自閉症当事者――7.『私の障害、私の個性。』


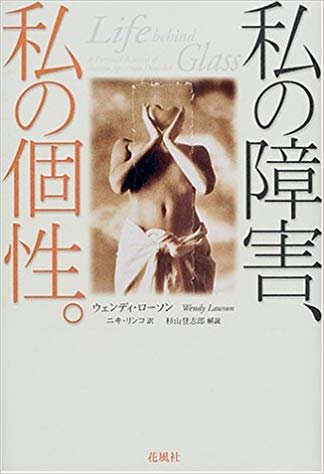
『私の障害、私の個性。』(花風社、2001/5 刊行)
ウェンディ・ローソン(著)
四六判、219 ページ
![]()
2歳の時に知的障害、17 歳の時には精神分裂病(昨今の名称は統合失調症)と誤診されたこともあるそうですが、42 歳になってようやくアスペルガー症候群の確定診断を受けています。本書は、著者が本格的にその頭角を現わす前に書かれた最初の著書です。本書を一読して驚かされるのは、何ごとにもへこたれず、何ごとにも前向きにとり組もうと絶えず努力する著者の強靭な姿勢です。
その後、著者は英国で心理学の博士号を取得し、専門家として自閉症の相談業務に携わってきたそうです。60 代半ばの今は、母国のクイーンズランド大学自閉症共同研究センター(ACRC)の顧問をしています。また、性同一性障害もあって、女性同士のカップルとして長らく同居生活を送っていたそうですが、20 年後に性転換をして、現在は、同じパートナーを妻として、ウェン・ローソン Wenn Lawson という名前の男性として暮しています。ドナさんや、わが国の Lobin H. さん(『無限振子――精神科医となった自閉症者の声無き叫び』協同医書出版社)の場合をしのぐ、まさしく波乱万丈の半生です。著者の場合も、やはりこれまでの生涯全体がひとつの作品のようになっています。
専門家としての著者は、その後に 14 点の著書を出版していることに加えて、“心の理論” 仮説では自閉症の中核症状群を適切に説明できないとして、ピアジェが提唱した発達心理学の概念である “対象の永続性 object permanence” の理解を根幹とした仮説を提唱しています(Lawson & Dombroski, 2017)。
その経歴を見ただけで、著者は、テンプル・グランディンさんらと並んで、一般の自閉症スペクトラム障害の人たちとは一線を画するほど抜きん出た存在であることがただちにわかります。これは、障害が軽いためであるのはまちがいないとしても、本書に目を通せば納得できるように、また、著者も繰り返し強調している通り、大変な努力を続けたたまものでもあるわけです。
本邦訳書の解説を書いている杉山登志郎先生によれば、本書は、ドナ・ウィリアムズさんのような “積極奇異 active but odd 型” の自閉症者が書いたものではなく、“受動 passive 型” の自閉症者が世に出した初めての自伝なのだそうです(“孤立 aloof 型” を加えた3群からなるこの下位分類は、ローナ・ウィングによるもの〔Wing & Gould, 1979〕です)。そして、本書の文章を見ると、「他者配慮に乏しい積極奇異型に対して、他者配慮が可能な受動型」の特徴がはっきりわかるというのです(217ページ)。そうなのかもしれません。
その点については、「他者配慮に乏しい」はずのドナさんの場合も同じです。ちなみに、ドナさんの文章がわかりにくいとすれば、それは、「他者配慮に乏しい」ためというよりは、自閉症はもとより人間の心の動き一般について、ドナさんが専門家もあまり知らないほどのことにまで踏み込んで発言しているため、その内容や重要性が読みとれないことによるのだと思います。そのことは、欧米の専門家が書いたいくつかの書評を読んでみるとわかります(ついでながらふれておくと、ドナさんの自伝4部作〔刊行順に、『自閉症だったわたしへ』、『こころという名の贈り物』、『ドナの結婚』〔以上、新潮社〕、『毎日が天国』〔明石書店〕〕は、後半になるにつれて専門家の理解をも越えるようになったらしく、専門家からも一般読者からもほとんど相手にされなくなっているようです)。それと比べると、著者は、特に高度なことや未知(あるいは想定外)のことを言っているわけではないので、わかりやすいという印象を受けるのではないでしょうか。
本書も、他の当事者による数多くの半生記と同じく、自閉症の特性を具体的に教えてくれる貴重な資料です。ここでは、その一端をとりあげてその説明をすることにします。
ひとつは、第2章の次のパラグラフにあります。この文章は、ふつうの子どもがこわがるものを自閉症児はこわがらないことがあるという脈絡で出てきます(危険を避けるという本能的な感性や行動が欠落しているということです。これまで軽視されてきましたが、この点も自閉症の重要な特性です。その結果なのでしょうが、ふつうの子どもと比べて、不慮の事故に遭う比率が高いことが知られています〔Jain et al., 2014; Lee et al., 2008; Guan & Li, 2017 参照〕)[註1]。
商店街や遊園地、学校や動物園などを怖がる一方で(うるさくて、無秩序で、人が多く、見慣れない物でいっぱいだから)、大通りや海、屋根の上、崖などを怖がらなかったりする。道路も海も、心の静まる、落ちつく場所だったりするのだ。いつ見ても変化がないし、こちらに向かってこない。(29ページ)
これは、自閉症の特性として周知の現象です。著者はここで、ふたつの状況を対比的に並べて説明しています。そのおかげで、従来の知覚過敏や入力情報過多という角度からの解釈とは違った着想が浮かび上がるのです。たとえば、当該の状況に対人的、社会的要素が関係しているかどうかで、対象に関与するしかたが異なってくるとする考えかたです。
引用文の前半は、ドナさんが「曝露不安」とその延長線上にある「広場恐怖」として語っている症状のことです。ドナさんの言葉を借りると、恐怖の対象はもちろん広場という場所や場面そのものではなく、「外で人々に見られるのがこわい」(『毎日が天国』207ページ)ということなのです。
ここで重要なのは、言うまでもなく状況という要因です。先日(2017年10月12日)のNHKのウェブサイトに、「ヘッドホンを外せない子どもたち」という表題で、自閉症児の聴覚過敏に関する記事が掲載されていました。そこには、次のようなことが書かれていました。ある自閉症児は、
幼い頃から音に敏感で、歩き始めるようになっても音を怖がって外を歩きたがらなかったそうです。そして大きな音が怖いのに加え、たくさんの人がいる場所では、話し声や空調の音、物がぶつかる音など一般には気にならない音も耳が拾ってしまい、音の波が体に押し寄せてくるような圧迫感で、いつも耳を押さえていたそうです。
ここで注目しなければならないのは、もちろん、「たくさんの人がいる場所」という状況に置かれている(あるいは、そこに自ら進んで入り込んでいる)時に、聴覚がより過敏になるとともに、大小さまざまな音を区別なく拾ってしまうという現象が見られる(あるいは強まる)ことです。聴覚が過敏だとしても、他の状況ではそれほどの問題は起こっていないことになります。自閉症と同じく脳の機能異常がその原因として想定されているトゥレット症候群でも、状況によって症状の出現が(ほぼ)完全にコントロールされること(オリヴァー・サックス『火星の人類学者』所収の「トゥレット症候群の外科医」参照)を考えれば、この着想はそれほど奇妙なものではないことがわかるでしょう。本書は、そのような着想を抱かせてくれるという点でも、貴重な参考資料になっているのです。
「そうかもしれないけど、先生はウェンディ〔著者のこと〕を当てているのよ」
「そうですか。でも私は、答えを知りません」
これも本当のことだから、私はまだ、自信いっぱいだった。
「今日は罰として、居残ってもらいます。放課後、答えを書いて提出しなさい。それから、これからはもっと集中してもらわないと困りますよ」
先生の言うことはさっぱり筋が通ってないわ。私はちゃんと集中してたもの。ちゃんと、窓の外の木に集中してたもの。葉っぱは陽の光を浴びて、一枚残らず、きらきらと輝いていたのだもの……。
別の先生は、確か、「集中する」というのは、頭も時間も、何かを見聞きすることだけに使うことだと言っていた。これは、私の側に状況を把握する能力がなかったというより、ほかの人たちの説明が不完全だったのではないだろうか?
私にとっては、数字や図形はまったくつかみどころのない存在で、理解しようとしても、頭が痛くなってくるのだった。だから算数の時間は、いつも以上に集中するのが大変だった。(71-72ページ)
著者は、何に対してであっても集中していれば同じだとして、集中していたのはまちがいないのだから、自分には非がなかったと(心の中で)主張しています。しかしながら、この一連の経過を、自閉症という背景から離れて率直に眺めれば、著者は、授業に集中していなかったことを意識の上でも半ば承知していたのに、担任の問いかけに対して話をそらせ、自分が叱られたのを人のせいにしていることになるでしょう。残る半分が意識の上でわかっていなかったとすれば、その分については、いわゆる自己欺瞞ということになるはずです。
自閉症の謎を解く鍵は、今やほぼ定説になっている “心の理論の乏しさ” にあるのではなく、もしかすると “状況性”(の背後にある要因)をはじめとする別の要因にあるのかもしれません(ちなみに、トゥレット症候については、この要因に着目している研究者が何人かいるようです。たとえば、Scahill, Sukhodolsky & King, 2007, p. 39 参照)。
この場合、脳が先だと考えることこそ科学的な態度なのであって、そこに疑問を差し挟むこと自体がおかしいとされるわけですが、本当にそう考えてよいのでしょうか。しかしながら、それでは自己矛盾に陥ってしまいそうなので、心理的要因のほうが先だと考えると、当然のことながら、現行の科学知識体系の基盤となっている唯物論仮説と完全に衝突してしまいます。したがって、どちらかがまちがっていることになるわけですが、それはどちらなのでしょうか。
今は亡き小澤勲は、1984 年に行なわれた講演で自閉症の原因論にまつわる自説を展開しています。そして、その質疑応答の中で、「自閉症の子どもに脳障害がある」ということと、「脳障害があるから自閉症になる」ことの区別が、専門家の間でいまひとつできていないことを指摘しています(小澤、2010年、100ページ)。ふたつの事象のあいだに高い相関があったとしても、一方がもう一方の原因になるとは限らないという、あたりまえのことを言っているのです。真の意味での科学的立場に立って考えれば、こうした疑問が当然のことながら出てくるはずなのですが、主流研究者は、分裂病の場合と同じく、どうもそうは考えたがらないようなのです。どうやらこの問題の根源は、ひとつには心の実在に関する、いちばんの基本たる、いわゆる心身問題を無視して議論が進められてきたことにありそうです。
自閉症は、要するに対人関係や社会性の発達の障害として位置づけられ、その原因はこのように脳の機能異常に求められているわけですが、そのような立場からの研究法は、本当に適切と考えてよいのでしょうか。なぜそうした障害が生ずるのかという点にこそその核心があることは言うまでもありません(とはいえ、かつての “冷蔵庫マザー” 仮説といういわば俗説に立ち戻ることが不毛であるのはもちろんです)が、最初から脳の障害というもっともらしい原因論に自らを縛りつけて研究を進めてしまうと、本来進むべき道が他にあったとした場合、科学的探究という点から見ても、治療的側面という点から見ても、非常に不適切な結末になるはずです。
それまで正常に発達してきたはずの幼児が、ある時を境に “発病” したように見える “後退 regressive or set-back 型” がかなりの比率で存在すること(たとえば、Hansen et al., 2008)や、明確な心理的出来事が起こったことに関連して、あるいはまさにその直後に発病したように見える事例が存在する(たとえば、Burd & Kerbeshian, 1988; Kobayashi & Murata, 1998, p. 297;神園、1994年)という事実を無視して、それを、先天性の障害と決めつけ、無条件に脳の機能異常に帰着させてよいものなのかどうか[註3]。
そう考えてゆくと、自閉症問題の根底にあるのは、やはりと言うべきか、心を脳の活動の副産物とする唯物論的立場の理非なのではないかという疑問に帰着するように思います。そのような着想を抱かせてくれるという点でも、本書は非常に貴重な資料になっているのです。
[註1]その一方で、危険な行為をしても、なぜか事故に遭いにくい子どもがいることも知られています(たとえば、ウィング、1980年、20ページ)。
[註2]東海大学の小林隆児(現、西南学院大学)は、「自閉症の基本障害は言語認知面の障害が一次的であって、対人関係障害(自閉性)はあくまで二次的なもの」とする従来の着想に異を唱え、対人的な側面の障害にこそその基本があると考えて、「自閉症の人々の心の中を解明」することに主眼を置いています(小林、1999年、153ページ)。
[註3]この問題については、琉球大学の神園幸郎の論文(神園、1994年)を参照されたい。


