 サイトマップ
サイトマップ



 書評 自閉症研究――3.『自閉症』
書評 自閉症研究――3.『自閉症』


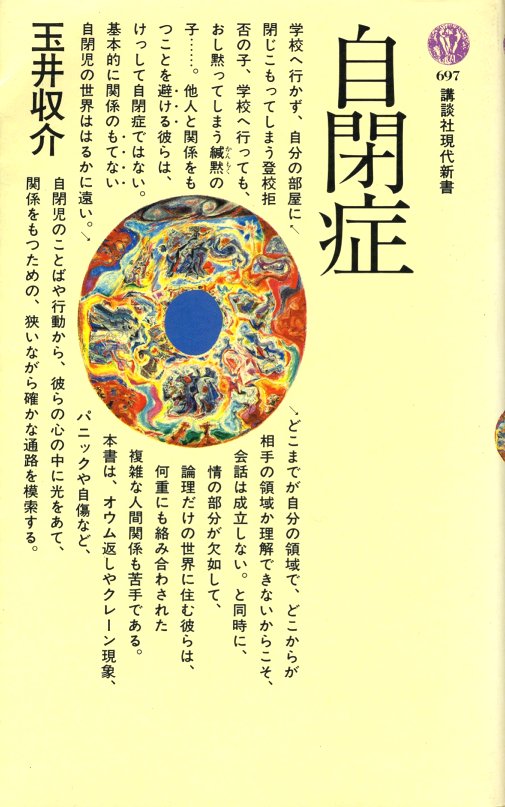
『自閉症』(講談社現代新書、1983/7 刊行)
玉井収介(著)
新書判、186 ページ
![]()
わが国の研究者の書いたものは特にそうなのですが、欧米の研究者の考えかたにふりまわされるばかりで、肝心の自閉症の実像が見えないことが多いように思います。大学や研究所で、外来の “症例” を細切れに観察したり、その子どもたちを対象にして実験を行なったりしただけでは、自閉症という実在のごく一面しかわからないことに加えて、生の実像がとらえられないためなのでしょう。それに対して、著者の玉井収介先生は、国立の研究施設で長い時間をかけて地道な観察を積み重ね、その中で直接間接に得られた所見を、本書の中で具体的な形でたくさん提示しているのです。
その中でも重要なのは、いわゆることばがない自閉症児でも、いざ話し始めると、いきなりおとなのような話しかたをする事例をいくつか紹介していることでしょう。喃語期(赤ちゃんことば)が存在しないということです。こうした現象自体は、数多くの専門家が認めていることなのですが、著者のユニークな点は、「内面にはことばの体系をもっているのではないか」と明言していることです。そのうちの一例が、13 歳までに一度しかことばを話したことがないという事例です。
彼はあるとき、風呂にとびこんだ。わかしてはあったのだが、かきまぜていなかったので、熱い部分と冷たい部分が、わかれていて火傷をしてしまった。そして、救急車で病院に運ばれた。そのときだけ医者に、
「痛いよ。早くして」
といったそうである。この例のように、非常に切迫した場面で、その場にふさわしいことをいい、また沈黙の世界に戻った、という報告はほかにもある。こういうことは、内面に言語をもっていなければ、できない相談である。〔中略〕
他の人との会話がむずかしいから、表に出ることばがないと考えるべきではなかろうか。(69、78 ページ)
この脈絡でついでながらふれておくと、外国人力士をみると誰でもわかるように、20歳前後で初めて日本語に接した者でも、おそらく外国語としてではなく、現実の場面の中に身を置いて、乳幼児のように自然言語として習得した場合には、発音も含めて日本人にきわめて近い日本語話者になるという事実があります(宮崎、参照)。いわゆる臨界期は存在しないということでしょう。ドナルド・キーンさんのように、既に日本語を話して70年以上になる人でも、おそらく外国語として習得したためなのでしょうが、発音はいつまで経ってもアメリカ人のままです。経験の長さではなく、習得の方法によって、方言や外国語のいわゆる習得臨界期を乗り越えることができる(母語になる?)ということです。
ことばに関する重要な問題にもうひとつふれておくと、自閉症児のことばの習得は、いわゆる健常児(“定型発達”の子ども)とは、順序が逆になっている場合が多いことです。人間のことばは、ボノボ(サベージ=ランボー『カンジ』〔NHK出版〕参照)やヨウム(ペッパーバーグ『アレックスと私』【幻冬舎刊〕参照)の子どもにも教えることができる[註1]という事実からすると、人間が勝手に作りあげたものではなく、進化の過程で徐々に準備されてきたものと考えるべきなのでしょう。そして、母語ということばがあるように、初めは母親を筆頭とする養育者たちの発音を聞いて、話しことばを少しずつ身につけるのです。それに対して、書き言葉は、歴史的に見てもそうですが、個人的にも、かなり後になってから、教育を通じて覚えるものなのです。
これは、生物として非常に不自然な経過であるのみならず、人間にしか駆使できないきわめて高度の技術に基づくものでもあります。これを、母親との、つまりは人間との対人関係に障害があるためというふうに平面的に考えたのでは、適切な説明にならないように思います。それよりも、ふつうの対人関係を、何らかの理由により、乳幼児期から徹底的に回避していると、主体性を基盤に考えたほうが実態に近いのではないでしょうか。ただし、そうすると、従来の自閉症観とは根本から違ったものになってしまうことは言うまでもありません。
次は、実に興味深いやりとりです。ことばが使える高知能の自閉症児でも、このようなやりとりになってしまうことが少なくないということです。
「君は、数学が得意だったね」
「得意というのではありません。興味をもっているといいなおしてください」
「君、中学のころの先生、覚えている?」
「当時、二九歳でしたから、いま三二歳のはずです」(84 ページ)
彼はあっという間に、A君が読んでいた本を取りあげた。A君はどうしたか。彼からすれば、今読んでいた本が突然なくなったのである。身をよじらせてもだえている。顔がくしゃくしゃになっている。誰がみても、本がなくなってやるせなくて、もがいているのである。だが、それだけである。イライラは彼の中にだけあるのであって、取り返しにいくという行動にはならない。(136 ページ)
これに対して著者は、自分が読んでいた本がなくなったことがわかってイライラするものの、A君は、誰が本を取ったかがわからないため、取り返しに行くことも相手を攻撃することもない、と解説しています。そして、自我の境界があいまいで、「私」と「あなた」の関係が成立していないために、そのような現象が起こるとして、従来の理論に則って解釈しているのです。しかし、その本は目の前に見えているので、取り返すことができるはずです。この解釈では、その点を適切に説明することができません。それについて著書は、「ここのところはよくわからない」と率直に認めています(136 ページ)。このように、不鮮明な自我境界という従来的な仮説では、こうした行動の説明がかえって難しくなるわけです。それよりも、自分のほうから人にものを頼むことができないのと同じで、「返してほしい」と相手に頼むことや、取り返すという、強引ではあっても正当な行動を避けていると考えたほうが、この場合も理にかなっているように思います(実際に、テンプル・グランディンさんのように、そうした行動を果敢に起こす人たちもいます。ウイングは、このようなタイプを積極奇異型 active but odd type と呼んだのでしょう)。このように、主体性を基盤にして考えると筋が通りやすい実例が、本書には他にもたくさん紹介されています。
自閉症という状態像を、脳の機能異常で説明するにしても、心理的要因によって説明するにしても、これらの現象がきちんと説明できなければなりません。本書のように、著者自身によるさまざまな観察事実が紹介されている資料は、こうした問題を考えるヒントや手がかりをたくさん与えてくれるという点で、きわめて重要な位置づけが与えられてしかるべきだと思います。
[註1]ボノボの場合、ことばを通じて偽薬効果を起こすことまでできるようです(Savage-Rumbaugh & Fields, 2013, p. 219)。


