 サイトマップ
サイトマップ



 書評 当事者研究――2.『べてるの家の「当事者研究」』
書評 当事者研究――2.『べてるの家の「当事者研究」』


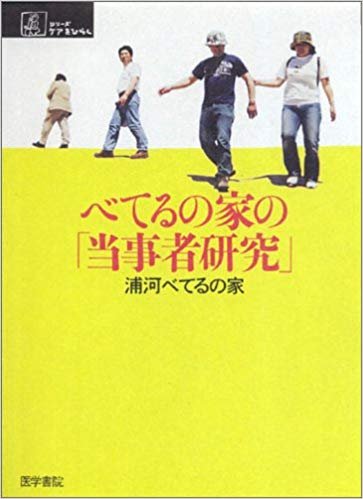
『べてるの家の「当事者研究」』(医学書院、2005/2/1 刊行)
浦河べてるの家(著)
A5版、297 ページ

こうした状況を鑑みれば、このことは快挙と考えてよいのではないでしょうか(とはいえ、この方法論の中心にいるケースワーカーの向谷地生良〔むかいやち いくよし〕さんは、そのようには考えていないようです〔290 ページ〕)。しかしながら、わが国の精神科医療も、今から110年ほど前には、アメリカの専門家から、その先進性を高く評価されたこともあったのです。
1909 年の夏のことです。ジョンズ・ホプキンズ大学精神科のアドルフ・マイヤーらとともに、由緒ある Journal of Nervous and Mental Disease の編集顧問を務めていたコロンビア大学の精神科教授、フレデリック・ピーターソンが、わが国の精神科医療の実態を調査するために来日しました。後に呉秀三らが明らかにすることになる悲惨な実態とは裏腹に、アメリカでは、わが国の精神科医療の “先進性” が、わが国からの留学生(松原三郎ら)を通じてなのでしょうが、既にそれなりの注目を受けていたらしいのです(たとえば、Mabon, 1907-1908, p. 27 参照)。ベヒテレフの弟子である、ロシアの精神科医、ウィルヘルム・スチーダの来訪から3年後のことでした。
そして、呉秀三(精神科医療の旧弊を打ち破った東京帝国大学精神科第三代教授)、三浦謹之助(シャルコーの弟子で、わが国の神経内科の開祖)、今村新吉(京都帝国大学精神科教授)という時の大御所たちの協力を得て、わが国の精神科医療の歴史を調べたうえで、各地の精神科病院を訪ね歩いたのです。
ピーターソンは、まず、わが国に 11 ヵ所もの精神科が存在していることに驚嘆します。信じがたいことに、当時の合衆国にはそれほどの数はなかったのだそうです。また、わが国の精神科病院が、清潔でゆったりしており、患者たちがおとなしいことにも強い印象を受けています。言うまでもなく、当時は、抗精神病薬はもとより電撃療法もありませんでした。さらには、ニューヨークと比べると、医師ひとり当たりの患者数がはるかに少ないことや、他のどの国にも見られないほど、看護者が優しく親切で辛抱強いこと、無断離院しようとする患者がいないことにも驚いています。
次いで、今村新吉とともに洛北の岩倉村も訪ねています。美しい自然環境の中で、精神病患者たちが、明るく清潔な村の家庭に引きとられ、そこで軽作業に従事している様子を目の当たりにしたピーターソンは、深い感銘を受けたのです。帰国するとピーターソンは、翌年5月にセントルイスで開催された全国社会福祉協議会の総会で、その経験を発表するのです(Peterson, 1910)。
そして、パリの著名な精神科医たちが、近郊のヴァンヴに作りあげたメゾン・ドゥ・ファルレという治療共同体を引き合いに出しながら、「日本とフランスでは、既に一定の標準が達成、実現されている。〔中略〕治癒しうる精神病患者の看護に必要不可欠なものが、今やここにある」(Peterson, 1910, p. 7)と絶賛します(先のスチーダは、岩倉を、ベルギーのゲールという治療共同体に比肩しうると述べていたようです)。皮肉な意味ではなく、べてるは、それに次ぐ快挙なのではないでしょうか。
たとえば、べてるの家のもうひとりの中心人物である精神科医の川村敏明先生の言葉を借りれば、「暴れたら誰かが助けてくれる、抑えてくれる、そういう関係性でやってると、遠慮なく、思いっきり激しく暴れてしまう」ことになるわけです(266 ページ)。本当の因果関係がどのようになっているかはともかく、現象的な経過としてはその通りなのでしょう。ついでながらふれておけば、ここに、しばらく前に気づかれるようになった、統合失調症の軽症化という現象の謎を解くヒントがあるように思います。
べてるでは、それとは正反対の、当事者を一人前の人間として扱おうとする、徹底した非免責および “非援助” という方針を貫いています。具体的には、いわば肩透かしを食わせるような方策(たとえば、220 ページ)などを通じて、問題行動が自らのひとり芝居であることを当事者自身の意識に浮かび上がらせることで、そうした依存傾向が自然に弱まる方向へともってゆくわけです。言うまでもないことですが、それらの方針は、経験的に導き出されたもの(266 ページ)であって、既存の理論に基づくものではありません。これこそが、べてるの対応法を次第に進化させてきた最も重要な創造的特性なのです。
当事者研究は、とりあえず、「問題と人を切り離す」ことから始まります(4ページ)。その中では責任をあえて不問に付し、第三者的な立場から自らの問題について、他者の協力を得ながらできる限り客観的に検討を進めてゆくわけです。そうすると、「苦労する権利、悩む権利、失敗する権利を獲得し、人間が本来するべき当然の苦労を取り戻す」(91 ページ)ことにより、当事者が目の前の現実に少しずつ直面するようになるのです。
その結果として、幻覚妄想の重症度や頻度が小さくなり(たとえば、105、124 ページ)、暴力的傾向が弱まるなど、統合失調症の症状が軽減されるとともに、多少なりとも責任を自覚するに至り、薬が場合によっては大幅に(10分の1程度にまで)減るそうです(たとえば、124 ページ)。結果を見てもわかる通り、これは、統合失調症への対応法として適切なものと言えるのはもちろんですが、そればかりではありません。心理的な対応によって症状が大幅に軽くなるわけですから、そのことが、統合失調症の、少なくとも症状悪化の心理的要因を、場合によっては症状出現の原因を探り出すうえで大きな手がかりになることも、まちがいないのです。
統合失調症は、病因論的に見るときわめてふしぎな位置づけにある精神病で、小澤勲先生の言葉を借用すれば、現在の精神医学の主流派は、「分裂病は脳の病気だと、どっかで思っているんです。にもかかわらず、ふしぎなことに、分裂病の人に何か明確な脳障害の所見が見出されると、それは分裂病でないということになる。〔中略〕〈脳の病気やけど、まだなんにも見つかっていない、非常にまかふしぎな病気〉にしておきたいという考え方が、精神医学の中にある」(小澤、2010年、38 ページ)のです。これは、事実関係を的確に見抜いた、にもかかわらず他にはたぶん誰も指摘していない、まさに卓見だと思います。
ただし、向谷地さんや川村先生は、そうした精神病理学的な側面にはなぜか関心がないようです。のみならず、べてるをとり巻く研究者たちも、そこにはなぜか注目していないらしいのです。べてるでのとり組みに対する評価が、必要以上に悪化していた症状を軽減ないし消失させることができるという点にほぼ限られるように見えるのは、そのためなのでしょう。しかしながら、そうした見かたに終始してしまうと、後ほど説明するように、大きな損失が起こってしまうのです。
〔急性期の〕危機状況を患者と共同して向精神薬なしで切り抜ける諸前提は次の通りである。患者の落ち着きのなさにできるだけ早く気づくこと。患者が時間の経過とともに自分の不快感を表現することを学ぶこと。そうすれば、解決策を探しだすことができるのだ。それにもかかわらず問題が生じたとき、看護者を受け入れられるように、患者が十分に信頼をもてるようにする。(シュミット、2005 年、101 ページ)
これは、1980 年代からフィンランドで実践されてきた “オープンダイアローグ” という方法(セイックラ、アーンキル、2016 年)や、後に(2001 年2月から始まって)べてるの家が経験的に編み出すに到る対応法と、理念的基盤はほとんど共通しているように思います。現に、筑波大学精神保健学教授の斎藤環先生は、オープンダイアローグとべてるの方法論との「親近性」を指摘しています(斎藤、2015 年、61-63 ページ)。
この関連でふれておくと、専門家の間では、薬物療法は必須だという大前提がまずあって、ドーパミン仮説の存在を考えればわかるように、薬物療法を続けてゆきさえすれば、再発を多少なりとも防ぐことができると、金科玉条のごとくに考えられています。しかしながら、このように薬を使わなくても治療は可能な場合も少なからずあることに加えて、長期的に見ると、薬物療法を続けることで、深刻な副作用(長嶺、2006 年)が起こることの他に、実際には精神症状がかえって増大することを示す調査結果(たとえば、Jobe & Faull, 2014)も存在します。さらには、抗精神病薬は、急性症状に対しても、偽薬と比較して、想定されているほど目覚ましい効果は実際には確認できなかったことを示す、60年の間に行なわれてきた 167 件の二重盲検法研究(総計で28102名)の総説すらあるのです(Leucht et al., 2017)。
方法論について言えば、この種のものはこれまで知られていなかったようなので、その点では、精神医療史上の大きな快挙であり進歩であると言わなければなりません。このようにして生み出されたこれらの発言は、統合失調症の本質を知るうえで、このうえなく重要な資料になるはずです。そして、このようなデータこそが、統合失調(精神分裂病 schizophrenia)と呼ばれる疾患の精神病理学の礎石になるのではないかと思います。
当事者研究で得られた発言の中から、この疾患に際立って見られる重要なものを、より本質的なものと思われる項目順にとりあげると、次のようになるでしょう。なお、ここであえて当事者たちの実名を明記しているのは、この人びとの心意気に敬意を表してのことであって、当事者たちを非難するためではないことは、言うまでもありません。
【成熟に向かう自然な過程を拒絶する】
河崎さんは、それとは別に、次のような発言もしています。
〔爆発した後〕ぼくは、自責と後悔の念に襲われて、反省も人一倍する。「またやってしまった」「おまえは、何をやってもだめなんだ……」という〈お客さん〉〔幻聴〕が勝ち誇ったように騒ぎ立てる。そして、爆発を防ぐために対人接触を断ち、引きこもりに入る。(195 ページ)
この発言では、“反省” した結果として、失敗を恐れて対人的な接触を断つという形の因果関係が示されています。その “解釈” が正しいかどうかはともかく、真の反省とは、自分を責めたり、相手に謝罪したりすることとは無関係のもので、二度と同じ失敗は繰り返さない覚悟をすることだという点を、まず明確にしておく必要があります。そのことは、同じ失敗を繰り返した場合、「反省が足りない」と言われてしまうことからもわかるでしょう。そうすると、その後に引きこもってしまうようでは、単に目の前の現実から逃げているだけで、真の反省になっていないことになるはずです。現に、河崎さんは、その後も、新車の高級乗用車にきずをつけてしまうという “大爆発” を起こしているそうです(199 ページ)。誰であっても本当の反省は難しいものですが、いわゆるふつうの人は、その “失敗” の規模が大きければ大きいほど、同じ失敗は繰り返さないものです。そこが、ふつうの人と、精神病を筆頭にした異常とされる人とを分ける、かなり決定的な分水嶺になっているのです。「善悪の判断」ができないわけではありません。後述するように、知識としてはよく知っているのです。
常識を越える行動をするかどうか、ということです。わかりやすい例をあげれば、アルコール依存症の人たちは、出勤する前に飲酒するほどまでになる(その結果、解雇されたりする)わけですが、では、ふつうの社会人に、同じ行動をとるように言ったとしたら、どうなるでしょうか。「そんなことしたら、もう世間から相手にされなくなってしまう」という答えが返ってくるはずです。世の中で経済的に自立しながら生きてゆくことが大前提になっているからです。これは、アルコールを好きかどうかという次元をはるかに越えたところにある、最も重要というべき要因なのです。
本当に反省を「人一倍」するとすれば、ひたすら自分を責め、現実に背を向けるのとは正反対の方向に向かうはずです。それは、難しいことではあるにせよ、統合失調症の人たちにも決して不可能なことではありません。ただし、そのためには絶対的に必要な条件があります。それは、自分がどのようなことをしたのかを、心底から実感することです。
河崎さんは、向谷地さんとの対談の中で、「親に文句なんかほんとうに言っていいんだろうか。親は爆発しても警察に届けないし、もし警察に届けられたら、ぼくは即、刑務所か何かです」(182 ページ)とも語っています。これは、非常に興味深い発言と言わなければなりません。この前半は、不当な主張は容易なのに対して正当な主張は難しいという、万人に共通して見られる、これも非常に重要な行動特性が明瞭に現われた発言ですが、ここでとりあげるのは、後半の部分です。
世間体を重んじ、子どもに強く出ることが難しい親は、何としてでも穏便にすませようとするわけです。それが逆効果にしかならないことは、先に見てきた通りです。しかしながら、事件をおおっぴらにされたら自分が困ることになるのは、当事者も実はよくわかっているのです。入院中に傷害事件を起こしたある男性から、「俺は分裂病だから、刑事責任は問われないはずだ」と堂々と主張するのを聞いたことがあります。本来なら刑事責任を問われる事態になっていることを、知識としてはよくわかっているということです。しかしながら、知識や自覚は、そのままでは現実の行動を根本から変える力にはなりにくいのです。
もちろん治療効果という側面から見れば、河崎さんの爆発は少しずつ収まっているようなので、当事者研究の有効性が、それによって証明されたことになります。それがまだ不十分だとすれば、今後の課題とすればよいのです。ただし、科学的な立場から見ると、それだけでは重要な点を見落とすことになってしまうわけで、そのことは、先ほど説明した通りです。
まず、幻聴という現象の一般的特性です。どのような内容でも幻聴として聞こえるのかと言えば、そうではありません。専門家が共有する知識にはなっていませんが、幻聴は、(1)被害的なもの、(2)命令的なもの、(3)慰撫的なものと、大きく3種類に分けることができるのです。それ以外のものはまずないと言っていいでしょう。そして、それぞれが順に、被害関係妄想、させられ体験、誇大妄想という強い思い込みと補完的な関係にあるわけです。
幻聴については、既に 1920 年頃に、フランスのある精神病理学者が、幻聴が起こっている時に声帯の筋肉がわずかに活動することを観察しているそうです(荻野、1980年、36 ページ)。この所見を裏づける実験や観察は、他にもいくつか報告されています(たとえば、Bick & Kinsbourne, 1987; Gould, 1949; McGuigan, 1966)。わが国でも、同趣旨の実験的研究(志水、1975 年、91-92 ページ。Inouye & Shimizu, 1970)が、既に50年近く前に行なわれています。
統合失調症と診断されたある女性は、現実に、この所見と符合する発言をしています。これは、この精神病の本質を解明するうえで、とてつもなく貴重な証言と言わなければなりません。
自分がいけないと思って、自分で自分を責めていることが、他人の声を使って、私の耳に入ってくるのです。つまり幻聴とは、自分の心で起こる現象なのです。それが、 実際に自分のことを噂されていると思いこんでいる。 だから、 自分の考えもしないことが、幻聴で聞こえてきたとしても、それは、どこかで潜在的に思っていることだけ。だから、自分で自分に問いかけていることに関して、いつも聞こえてくる。〔中略〕幻聴は自分の意見を押さえて言わなくなると、よけいに聞こえてくる。自分を自然にだし、主張するときには、幻聴はほとんど聞こえなくなる。(古川、2001年、70 ページ)
このような仕組みで幻聴が起こるとすれば、幻聴そのものは二次的な症状ということになるでしょう。そうすると、自分を責める意志は、どのような状況の中で、どこから湧いてくるのか、その意図はどこにあるのかという疑問が、次の課題になるはずです。このようにしてゆけば、より根源にまで遡ることができそうです。林園子さんは、幻聴がやわらいだ時に、「幻聴にすら見捨てられたさびしさで、身体にボッカリと穴が空いたような」感じになり、その「空虚さ」を埋め合わせるためにアルコールに浸り、買い物に夢中になったそうです。そうなると、林さんの場合、幻聴と被害妄想は、飲酒や買い物という行動と、ある意味で同等の位置づけになりそうです。続けて林さんは、「それが被害妄想であると気づくこと自体が、わたしにとってはこわいことだった」と述べている(97-98 ページ)のですが、これは、その幻聴が被害的なものであり、現実ではないのを認めることに強い抵抗が働いたということでしょう。そのことは、清水里香さんの次の発言を見てもわかります。清水さんは、被害妄想が起こる理由はわからないとしたうえで、次のように述べているのです。
苦労の多い現実の世界では自分の居場所を失い、具体的な人とのつながりが見えなくなると、「幻聴の世界」は、どこよりも実感のこもった住み心地のいい刺激に満ちた「現実」になる。それは、つらい、抜け出したい現実ではあっても、何ものにも代えがたく、抜け出しにくい「事実」の世界だった。(106 ページ)
このような発言を見 ると、ある時点で浮上した何らかの理由から、現実に背を向けるようになり、そのための手段として、自分を、責めたり、自傷的、自滅的行動に走らせたり、慰めたりすることによって、目の前の現実から遠ざからせるという仕組みになっているらしいことが推定できるでしょう。このようなことを考えさせてくれるという点で、べてるの家の実践は、精神病理学にとって大きな意味をもっているのです。

